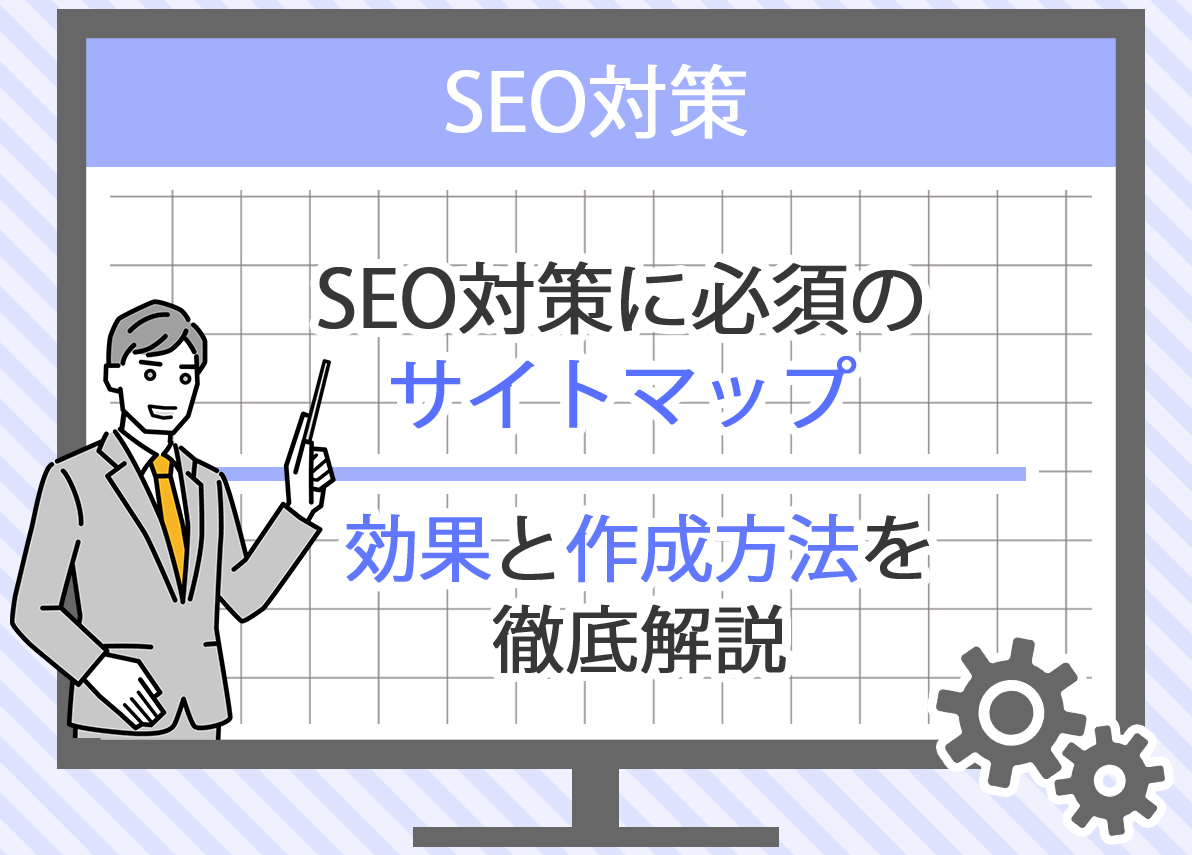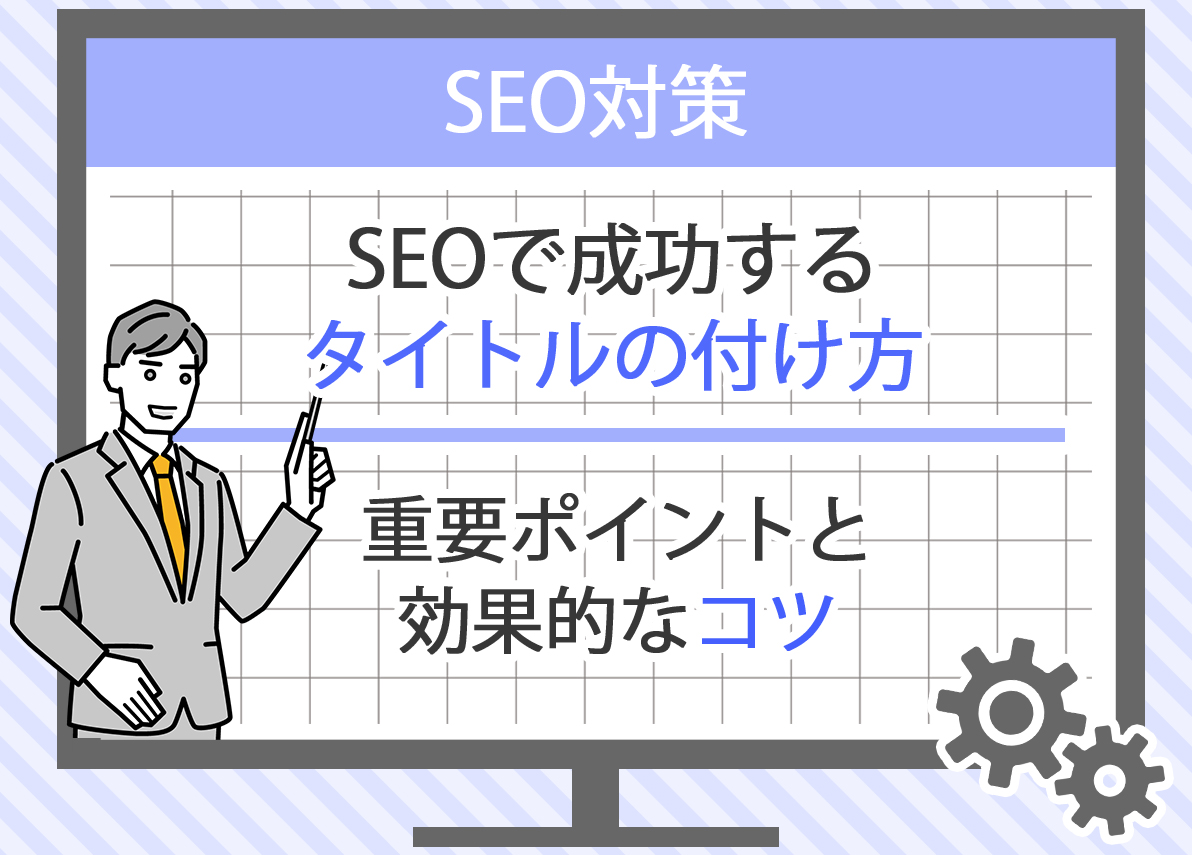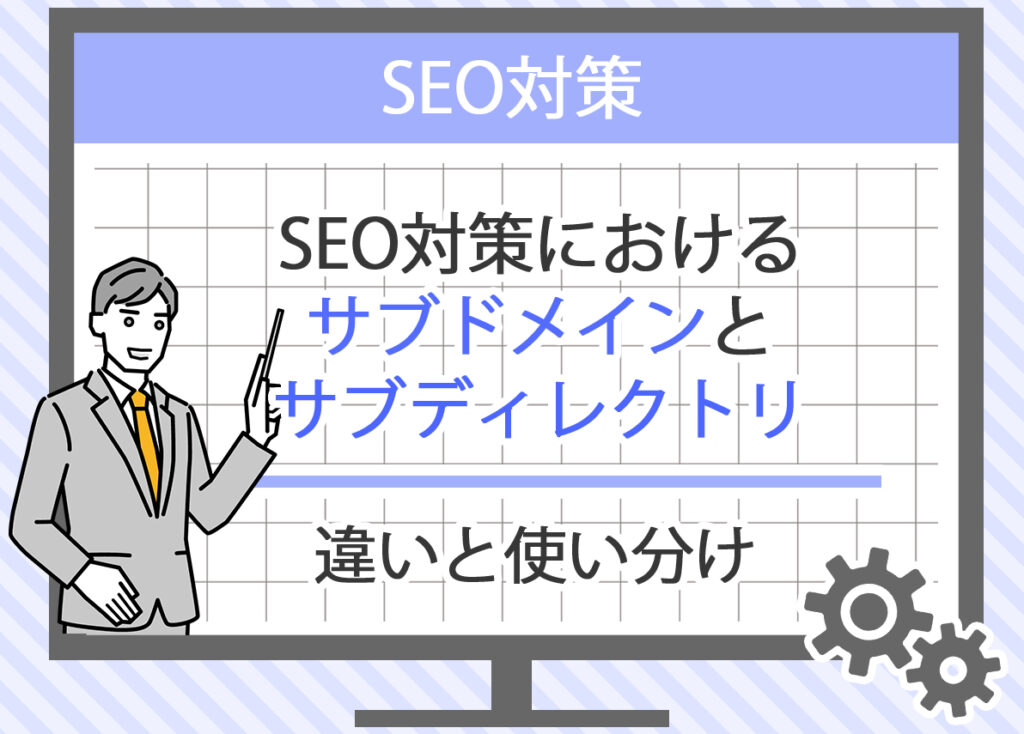
SEOを考えるときによく登場するのが「サブドメイン」と「サブディレクトリ」という用語です。
どちらもインターネット上のサイト構造を示す仕組みですが、意味や使い分けの観点を正しく認識している方は意外と少ないかもしれません。
たとえばshop.example.co.jpのように企業の運営会社や事業ごとに独立したサブドメインを設定するケースもあれば、example.com/blogのように同一ドメイン内でカテゴリを分けるサブディレクトリを採用する場合もあります。
本記事では両者の違いを整理し、それぞれのメリットやデメリット、SEOにおける有効性やドメイン取得時の理由まで最新情報を交えて解説します。
初心者でも理解しやすい概要を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
サブドメインとサブディレクトリの違い
サブドメインとは?
サブドメインとは、メインのドメイン名の前に追加される文字列のことで、インターネット上では独立したサイトとして認識されます。
たとえば、example.comがメインドメインなら、sub.example.comのような形になります。
co.jpやincなどの拡張子と組み合わせることで、事業ごとに分けた運営会社サイトを構築するケースも多く見られます。
サブドメインを使うことで、同じドメイン取得の枠内でありながら、異なるテーマやジャンルに特化したサイトを作り分けられるのが特徴です。
AI関連サービス、動画配信、採用情報など用途別に分けると管理しやすく、検索上位を狙う観点からも有効な場合があります。
サブドメインの特徴
- 独立したサイトとして扱われる
- 別々のコンテンツを管理できる
- メインのドメインと異なるデザインや機能を持つことが可能
サブディレクトリとは?
サブディレクトリは、メインドメインの後にスラッシュを付けて続くフォルダ構造のことで、同じドメイン内に存在します。
たとえば、example.com/subのような形式です。
サブディレクトリを利用すると、1つのドメイン内でカテゴリやサービスを分けつつ、全体のSEO評価を共有できます。
yahoo.co.jpのようにトップページ配下にニュースやショッピングといったセクションを展開するのは代表的な例です。
サブディレクトリの特徴
- メインのドメイン内の一部として扱われる
- サイト全体の統一感を保ちながらコンテンツを管理できる
- 同じドメイン内でカテゴリやセクションを分けられる
サブドメインとサブディレクトリの具体例
実際のURLで両者の違いを見てみましょう。
| 例 | URL | 説明 |
| サブドメインの例 | blog.example.com | ブログ専用のサブドメイン |
| サブディレクトリの例 | example.com/blog | メインサイト内のブログセクション |
| サブドメインの例 | shop.example.com | ショップ専用のサブドメイン |
| サブディレクトリの例 | example.com/shop | メインサイト内のショップセクション |
どちらを選ぶべきか?
サブドメインとサブディレクトリのどちらを選ぶかは、サイトの目的や運営方針によっ
て異なります。以下は選定のポイントです。
サブドメインが適している場合
- 独立したサイトとして扱いたい場合
- 異なるテーマや機能を持つサイトを運営する場合
- メインのドメインとは異なるデザインや機能を持つ必要がある場合
サブディレクトリが適している場合
- メインドメイン内でカテゴリやセクションを分けたい場合
- サイト全体の統一感を保ちながらコンテンツを管理したい場合
- 同じドメイン内でSEOの効果を高めたい場合
以下に、選択する際のメリットとデメリットを表にまとめました。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| サブドメイン | 独立したサイトとして扱える異なるテーマや機能を持てる | SEO効果がメインのドメインに直接影響しない |
| サブディレクトリ | サイト全体の統一感を保てるSEO効果をメインのドメインと共有できる | カテゴリやセクションが複雑化する可能性がある |
運営会社の事業規模や提供サービスの数、ユーザーにとって役立ちやすい構造かどうかといった観点を踏まえ、適切に選ぶことが大切です。
どちらを選んでも、SEOやユーザーエクスペリエンスに影響するため、詳細を検討しながら進めることが望ましいでしょう。
サブドメインのメリットとデメリット
サブドメインの利点
サブドメインには複数の重要な利点があります。
特に、異なる事業やサービスを展開している企業にとっては有効に働くケースが多いです。
- 独立性
サブドメインはメインのドメインから独立したサイトとして扱われるため、まるで別のサイトを運営しているかのように見せられます。
たとえば、企業の公式サイトがexample.co.jpの場合、採用情報専用のrecruit.example.co.jpを立ち上げることで、訪問者にわかりやすい構造を提供できます。 - SEO戦略の多様化
サブドメインごとに異なるキーワードやSEO戦略を選定できるため、トピックごとに特化した最適化が可能です。
AI、動画配信、ECなどジャンルの異なるサービスを展開する際に役立ちます。
テーマ別に検索上位を狙う戦略をとるときも有利な手段といえます。 - ブランド認知
特定のサブドメインを利用すると、ブランドの一部を強調しやすくなります。
たとえば、blog.example.comで専門的な記事や詳細な解説を継続的に発信すれば、業界内での認識が広がりやすくなります。
これはデジタルマーケティングにおいても効果的です。 - アクセス制限や管理の柔軟性
サブドメイン単位でアクセス制御を設けられるため、開発・テスト環境を安全に切り分ける観点からも便利です。
ユーザーエクスペリエンスを損なわず、本番環境に影響を与えずに検証作業を進められる点は大きな利点です。
サブドメインの欠点
一方で、サブドメインにはデメリットも存在します。
両者を比較した上で検討することが重要です。
- SEO効果の分散
サブドメインはメインドメインとは別に評価されるため、SEO効果が分散してしまうリスクがあります。
良好な評価がメインサイトに直接つながらないケースもあるため、上位表示を狙う際には注意が必要です。 - 管理の負担
複数のサブドメインを運用する場合、設定や更新作業がそれぞれに発生します。
サーバー設定やセキュリティ対応も分散されるため、事業規模が拡大すると管理の手間が増えることがあります。 - ユーザーの混乱
サブドメインとメインドメインの見た目が大きく異なると、利用者が別サイトと認識してしまう可能性があります。
特にブランドの一貫性を重視する場合はマイナス要素となりかねません。 - 技術的な課題
一部の古いシステムやツールではサブドメインの扱いに制限があることもあります。
そのため、CMSや解析ツールの導入時には事前に対応状況を確認しておく必要があります。
サブドメインが適しているサイト
サブドメインが特に役立つケースを以下にまとめます。
- 多言語サイト
言語ごとに独立運営できるため、en.example.comやjp.example.comのように切り分けるとSEO上も有利に働く場合があります。 - 異なるサービスや製品ライン
EC事業や情報発信サイトを分けたい場合、shop.example.comやblog.example.comなどで明確に区別できます。 - 開発・テスト環境
dev.example.comやtest.example.comを利用することで、ユーザーに公開せず安全に検証作業を行えます。
このように、サブドメインは管理やSEO戦略の観点でメリットとデメリットが両立するため、詳細を比較しながら自社の目的に合った選び方をすることが大切です。
新規ドメイン vs. 既存ドメイン
ドメインを選ぶときには、新規ドメインを取得するか、既存のドメインを購入するかを比較する必要があります。
両者には次のような違いがあります。
新規ドメインのメリットとデメリット
メリット
- コストが低く、ドメイン取得にかかる費用を抑えられる
- 完全に新しいブランド名でスタートでき、自由に選べる
- クリーンな状態から始められるため、過去のペナルティがない。
デメリット
- 信頼性が低く、上位表示まで時間がかかる
- トラフィックがゼロからのスタートで集客に時間が必要
既存ドメインのメリットとデメリット
メリット
- 検索エンジンに信頼されやすく、早期に上位表示が狙える
- 既存の訪問者や外部リンクを引き継げるため、SEO的に有利
デメリット
- 人気ドメインは高額で購入コストが大きい
- 過去のペナルティや悪評を抱えている場合、逆に不利になる
ドメイン選びのポイント
適切なドメインを選定するための基本的な観点を整理します。
- 覚えやすく短い文字列にすること
- ブランドや事業内容に合った名称にすること
- 関連するキーワードを含めることが有効
- co.jp、.com、.netなど信頼性の高い拡張子を選ぶこと
ドメイン変更のリスク
既存ドメインを変更する場合、SEOに影響が出るリスクがあります。
- 検索順位が一時的に下がる
- トラフィックが減少する
- 外部リンクが切れてしまいSEOにマイナスの影響を与える
対策:
- 古いドメインから新しいドメインへの301リダイレクトを設定する
- サイトマップを更新し、Google Search Consoleに再インデックスを依頼する
- 関連するサイトやユーザーに告知し、リンク更新を依頼する
ドメイン選定はSEOの土台であり、新規と既存を比較した上で、自社の目的や理由に合った選択を行うことが大切です。
適切なドメインを選ぶことで、検索エンジン上で有利な評価を得やすくなり、長期的なトラフィック拡大につながります。
サブドメイン、サブディレクトリがSEOに与える影響
サブドメインのSEO効果
サブドメインはインターネット上で独立したサイトとして扱われるため、SEOに特有の影響をもたらします。
企業が新たな事業やサービスを展開する際にサブドメインを利用すると、検索順位を上げる観点で役立つケースがあります。
- 独立した評価
メインのドメインとは別サイトとして認識されるため、AIや動画など異なるテーマに特化したSEO戦略を選んで展開できます。 - キーワードの集中
サブドメインごとに専用のキーワードを設定することで、ニッチ市場での上位表示を狙いやすくなります。 - リンクビルディング
サブドメインとメインドメイン間のリンクを適切に構築すれば、SEO効果が共有され、比較的早い段階で評価を高められる可能性があります。
サブディレクトリのSEO効果
サブディレクトリはメインドメインの一部として扱われるため、SEO効果を共有できるのが大きな特徴です。
たとえばexample.co.jp/blogのようにフォルダを追加する形で文字列を組み込むと、メインサイトの評価を直接引き継ぎやすくなります。
- 内部リンクの強化
サブディレクトリ内のページ同士で内部リンクを張ると、検索エンジンがサイト全体を効率的にクロールし、SEOに役立ちます。 - SEO効果の共有
メインサイトの評価が高い場合、その効果をサブディレクトリにも反映でき、上位表示につながりやすくなります。 - 一貫性の維持
サイト全体のデザインやトーンを統一しやすく、ユーザーエクスペリエンスを高めます。
Googleの評価基準
Googleは特に以下の項目が重視されます。
- コンテンツの質:詳細で有益な情報を提供しているか
- ユーザーエクスペリエンス:表示速度、モバイル対応、使いやすさ
- バックリンクの質:信頼性の高い外部サイトからのリンクの有無
- 技術的な最適化:メタタグ、サイト構造、内部リンク整理などの基本的施策
サブドメイン、サブディレクトリのSEOリスク
活用にはデメリットも存在します。
- 評価の分散
メインドメインと直接共有されないため、SEO効果が分散するリスクがあります。 - 重複コンテンツ
同じ記事を複数のサブドメインに掲載すると、検索順位にマイナスの影響を与えることがあります。 - 管理の複雑さ
複数のサブドメインを運用する場合、更新やセキュリティ対策に時間がかかるのが理由の一つです。
重複コンテンツについては下記で詳しく紹介しています。

注意点
リスクを回避し、SEO効果を最大化するためには以下の点が有効です。
- 高品質なコンテンツを提供すること
- ページ速度やモバイル対応など、技術的な最適化を行うこと
- サブドメインとメインドメイン間で適切にバックリンクを構築すること
- 重複コンテンツを避け、オリジナリティのある情報を発信すること
- ブランドデザインやトーンを統一してユーザーが混乱しないようにすること
サブドメイン、サブディレクトリはデジタルマーケティングの中でも柔軟な手法であり、詳細な検討と比較を行ったうえで導入すれば、自社のSEO戦略にとって有効な選択肢となります。
サブドメインとサブディレクトリの設定方法
サブドメインの設定手順
サブドメインの設定は、インターネット上で新たにサイトを展開する際の重要なステップです。
手順の概要は次のとおりです。
- ドメイン管理サービス(例:お名前.comや海外のGoDaddyなど)の管理画面にログインし、対象ドメインを選びます
- DNS設定画面を開き、新しいレコードを追加します。一般的にはAレコードまたはCNAMEレコードを選定し、サブドメイン名(例:blog)や値(IPアドレスや別のドメイン名)を入力します
- 入力した情報を保存して変更を反映させます
- ウェブホスティング側(cPanelやPleskなど)にログインし、サブドメイン用のディレクトリを作成します。このとき生成されるフォルダにHTMLやCSS、JavaScriptファイルをアップロードできるようになります
この手順を行うと、たとえばsupport.example.co.jpのように事業やサービスごとに分けたサブドメインを運営会社単位で有効に活用できます。
サブディレクトリの設定手順
サブディレクトリの設定は、既存のドメイン配下に新しいセクションを追加する方法です。
詳細は以下の流れになります。
- ウェブホスティングの管理画面にログインします
- ファイルマネージャーを開き、ドキュメントルート(public_htmlなど)の下に新しいフォルダを作成します。このフォルダがサブディレクトリとなります(例:public_html/blog)
- 作成したフォルダにウェブサイトのコンテンツ(HTMLやCSS、JavaScriptファイルなど)をアップロードします
- ブラウザでURL(例:example.com/blog)にアクセスし、正しく表示されるか確認します
ディレクトリ構造をどう設計するかはSEOの観点でとても重要です。
カテゴリを比較・検討しながら選定すれば、上位表示につながりやすい強い設計になります。
設定時の注意事項
サブドメインやサブディレクトリを設定する際には、以下の点を守ることが重要です。
- SSL証明書を必ず設定し、HTTPS化して安全に通信できる環境を整えること
- 重複コンテンツを避け、同じ内容を複数のURLに使わないこと
- 内部リンクを適切に整備し、ユーザーが迷わず移動できるようにすること
- 各ページのメタタグ(タイトル、ディスクリプションなど)を適切に設定し、SEO効果を高めること
設定後の確認方法
設定が完了したら、以下の確認を行うと安心です。
- ブラウザで新しいURLにアクセスし、正しく表示されるかチェックする
- Google Search Consoleに登録し、インデックス状況やパフォーマンスを監視する
- SSL証明書が適用され、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されるか確認する
- Google PageSpeed Insightsなどのツールを使い、ページ速度を測定し改善点を検討する
こうした基本的な確認を怠らなければ、SEOの観点で有効に作用し、ユーザーにとって役立つサイト構造を維持できます。
サブドメインとサブディレクトリの運用時の注意点
運用開始前のチェックポイント
サブドメインやサブディレクトリを導入する前に、目的や構成を明確にしておくことが重要です。
特に事業を拡大する際には、どの形態が役立つかを比較・検討してから選定する必要があります。
- 目的の明確化
ブログやオンラインショップ、サポートサイトなど、どのような理由で運用するのかをはっきりさせましょう。
多くの企業は目的を知ったうえで構造を選んでいます。 - 技術的な設定の確認
サブドメインの場合はDNS設定、サブディレクトリの場合はディレクトリ構造を整備し、リンク切れや権限の不具合がないかを確認します。 - コンテンツの準備
詳細で独自性のあるコンテンツを用意し、ユーザーにとって有効な情報を提供できる状態にしておきます。 - セキュリティの確認
SSL証明書によるHTTPS対応やファイアウォールの導入など、安全な環境を整えることが求められます。 - SEO対策の実施
タイトルやディスクリプションの設定、サイトマップの作成など、基本的なSEO施策を事前に行いましょう。
運用中のトラブル対応
実際に運用を始めると、さまざまなケースでトラブルが発生することがあります。
その際の対応策を知っておくと安心です。
- リンク切れのチェック
定期的に全ページを確認し、リンク切れがないか監視します。自動検出ツールを使えば効率的です。 - サーバーの監視
稼働状況をチェックし、ダウンタイムが発生した場合は迅速に復旧作業を行います。 - セキュリティの維持
不正アクセスやマルウェア対策を続け、CMSやサーバーの更新を怠らないようにします。
これらの作業は一見手間に思えるかもしれませんが、検索順位の維持やユーザーエクスペリエンスの向上に直結する有効な取り組みです。
まとめ
SEOにおけるドメイン戦略では、サブドメインとサブディレクトリのどちらを選ぶかが重要な観点になります。
両者には明確な優劣があるわけではなく、事業の目的や運営方針によって適した選択肢は異なります。
サブドメインは、新たなサービスを独立して展開したいケースや、AIや動画などテーマごとに差別化を図りたい場合に役立ちます。
一方、サブディレクトリは、既存のSEO効果を共有して効率的に上位表示を狙いたいときに有効です。
どちらを使わないかではなく、状況に応じて柔軟に選び分けることが大切です。
詳細な設計や最新のSEO施策を取り入れることで、多くのサイトがより効率的に成果を得られるでしょう。