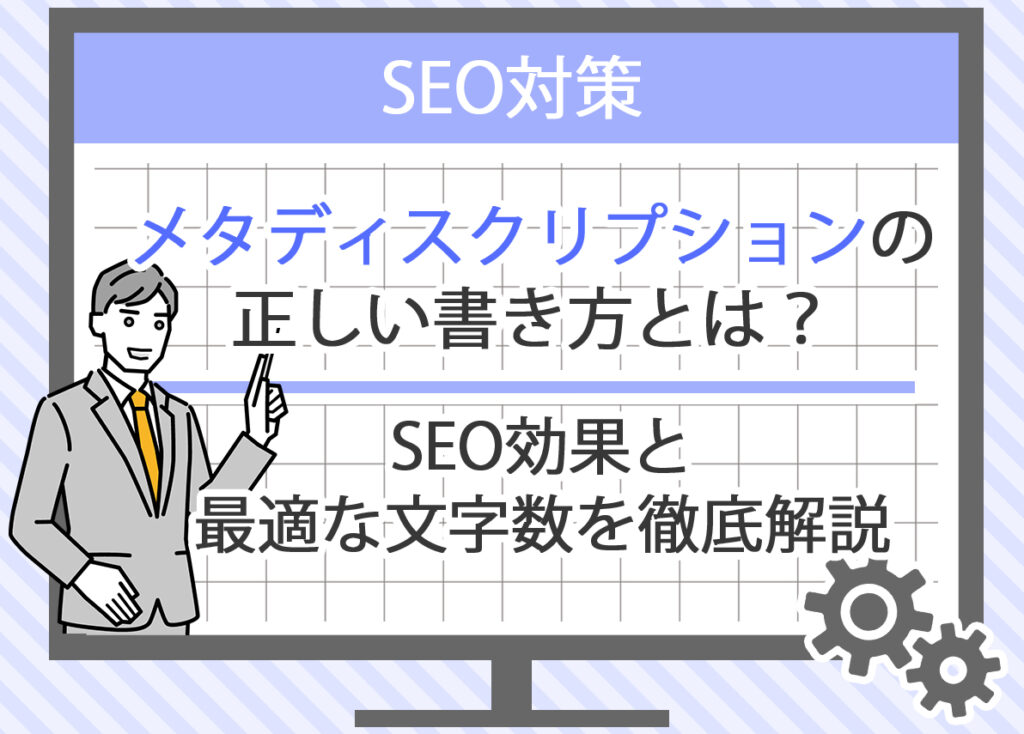
Webサイトを作ったあと、みなさん「もっと多くの人に見てもらいたい」「検索で上の方に表示されたい」と思いますよね。
そんなときに大切なのが「メタディスクリプション」です。
これは、検索結果に出てくるページの説明文のようなものです。
この文章がわかりやすく魅力的だと、ユーザーが思わずクリックしてくれる可能性が高まります。
しかし、書き方を間違えると、せっかくの内容が伝わらなかったり、表示されなかったりすることもあります。
このページでは、初心者の方でもすぐに実践できるメタディスクリプションの書き方や設定方法をご紹介していきます。
メタディスクリプションとは?基本の役割と重要性を解説

検索結果に出てくる「説明文」のこと
GoogleやYahoo!などの検索エンジンでキーワードを入力したとき、ページタイトルの下に2〜3行程度の文章が表示されることがあります。
この文章が、メタディスクリプションです。
ページの内容を短くまとめた説明文で、そのページに何が書いてあるかを検索ユーザーに伝える大切な情報です。
表示される内容は、ページ制作者が設定することもできますが、何も設定されていない場合は検索エンジン側が自動でページ内の文章を抜き出して表示することもあります。
ただし、自動生成された説明文は必ずしも意図した内容が表示されるとは限りません。
ユーザーにページの魅力や内容をしっかりと伝えるためには、自分で説明文を設定することが大切です。
なぜメタディスクリプションが必要なのか
メタディスクリプションが重要な理由は、検索結果の中で目を引く情報になるからです。
ページの内容に興味を持ってもらえるかどうか、クリックしてもらえるかどうかは、説明文にかかっていると言っても過言ではありません。
特に、同じようなテーマのページが複数ある場合、内容が似ていても説明文が魅力的な方が選ばれる可能性が高くなります。
そのため、以下のような点を意識してメタディスクリプションを書くと、クリックされやすくなります。
- ページの内容がひと目で伝わるようにする
- ユーザーが知りたい情報に触れている
- 興味を引く言葉や問いかけを含める
検索順位が同じでも、説明文の印象でアクセス数が変わってくることもあるため、設定を省略するのはとてももったいないです。
SEO対策とのつながり
メタディスクリプションは、検索順位に直接的な影響を与えるものではありません。
しかし、間接的に検索エンジン対策(SEO)に影響する要素のひとつとして考えることができます。
その理由は、次のような点にあります。
- クリック率の向上
説明文が魅力的だと、検索結果でクリックされやすくなり、ページの評価が高まります - ユーザーエクスペリエンスの改善
説明文から内容がわかると、訪問者の満足度が高まり、サイトの滞在時間や再訪率にもつながります - ロングテールキーワードとの親和性
ページの内容が具体的なテーマや検索意図に対応しているとき、それが説明文に反映されていれば、よりマッチ度が高くなります
どこに設定されているの?
メタディスクリプションは、Webページの「head」と呼ばれる部分に書かれているHTMLの中に設定されます。
実際の記述方法は以下のようになります。
<meta name="description" content="このページでは、○○についてわかりやすく解説しています。初心者にもおすすめです。">
このように、name="description"というタグに、実際に表示される文章をcontentに記述します。
CMS(コンテンツ管理システム)を使っている場合は、管理画面から入力することも可能です。
たとえば、WordPressでは以下のような方法で設定できます。
- SEO系プラグイン(例:All in One SEOやYoast SEO)を使う
- 投稿や固定ページの編集画面で、説明文入力欄に記入する
特別な知識がなくても、プラグインを活用すれば初心者でも設定が可能です。
ひと言で伝えるとどうなる?
メタディスクリプションは、検索結果の「広告文」のようなものと考えるとわかりやすいです。
短い文章の中に、どれだけ魅力と情報を込められるかがポイントになります。
書くときには、次のような要素を意識すると良いでしょう。
- ページのテーマをしっかり伝える
- ユーザーの関心に寄り添った言葉を使う
- 専門用語はできるだけ避けて、わかりやすく書く
特に、Web初心者を対象にしたページの場合は、「わかりやすさ」や「親しみやすさ」を大事にすることで、検索結果で選ばれやすくなります。
また、説明文は見た目ではなく内容の伝わりやすさが大切なので、「短くても濃い情報」を意識するのがおすすめです。
短文でいかに印象を残すかが、クリックされるかどうかを左右する大きなポイントになります。
SEOにおけるdescriptionタグの効果とは?
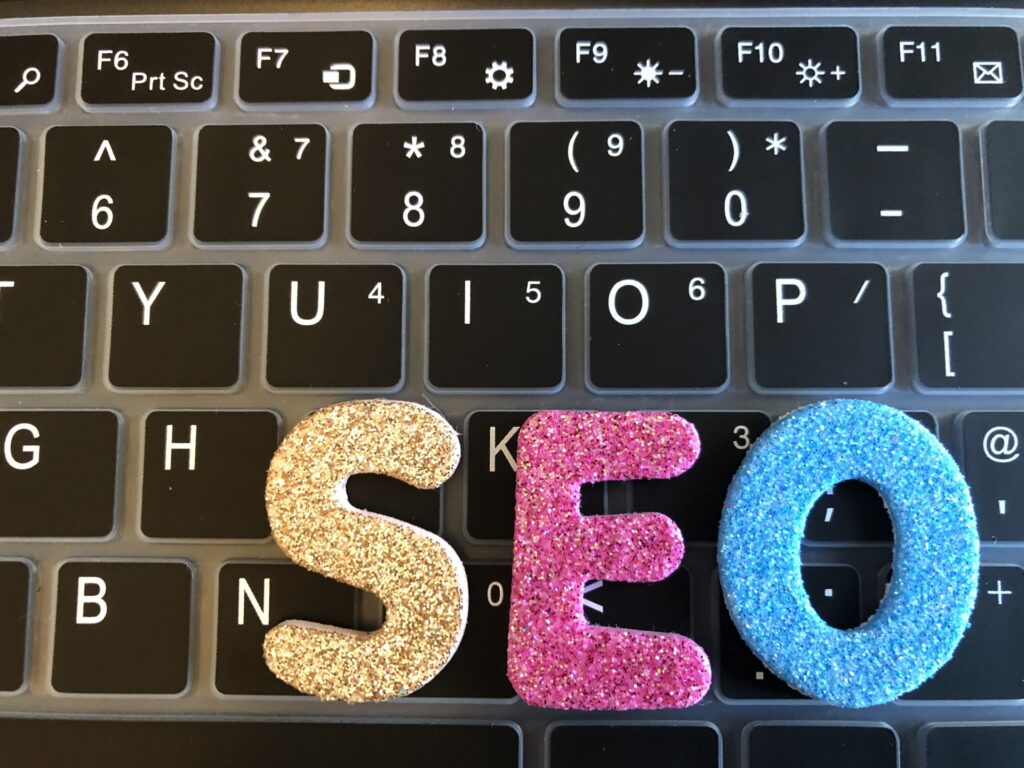
descriptionタグってどんなもの?
descriptionタグは、Webページに関する簡単な説明文を指定するためのHTMLタグです。
このタグに書いた文章は、検索結果に表示されることがあり、検索ユーザーにとってはそのページがどんな内容かを知る手がかりになります。
検索したときにタイトルの下に表示されている2〜3行の文章、それがdescriptionタグで設定された内容です。
HTMLの中では次のように記述します。
<meta name="description" content="この記事では○○についてわかりやすく解説します。初心者にもおすすめの内容です。">
このタグはWebページの中には表示されず、ブラウザや検索結果で表示される役割を持ちます。
ユーザーにクリックしてもらえるかどうかを左右する、とても大事なポイントです。
検索順位に直接影響するの?
descriptionタグは、Googleの公式見解によれば検索順位には直接的には影響しないとされています。
しかし、だからといって不要というわけではありません。
descriptionタグが果たす役割は、主に間接的なSEO効果にあります。
つまり、説明文がわかりやすく、魅力的であることでクリック率が上がり、その結果として検索エンジンからの評価も高まりやすくなるということです。
Googleは実際のユーザー行動も判断材料にしているため、クリックされやすいページは評価が高くなる傾向があるというのが現実です。
以下のような要素が評価に影響すると考えられています。
- ページがクリックされた回数や割合(クリック率)
- サイトに訪れた後の滞在時間
- 他のページへの移動などの行動
descriptionタグが魅力的であればあるほど、これらの指標にプラスの影響を与えることができます。
クリックされやすくなる理由
descriptionタグの最大の目的は、検索結果でユーザーにクリックしてもらうことです。
ページの中身がどれだけ良くても、クリックされなければ見てもらえません。
検索結果に並んだとき、タイトルと同じくらい説明文が重要になります。
クリックされやすいdescriptionには次のような特徴があります。
- ユーザーの疑問に直接答えている
- 数字や具体的な言葉が使われている
- ページのメリットが伝わるように書かれている
- ロングテールキーワードを自然に含んでいる
以下は、クリックを誘いやすくするための書き方のコツです。
- ページ内容を一言でまとめる
- やさしく具体的な言葉を使う
- 最初の30〜40文字にインパクトのある文を入れる
- 60文字以上になる場合は途中で切れても伝わる構成にする
文章の冒頭にユーザーの関心に近いキーワードがあると、検索結果で太字になりやすく目に入りやすくなります。
Googleがどこを見ているのか
Googleは、ページのdescriptionタグを参考に検索結果を表示しますが、必ずしも設定された内容をそのまま使うとは限りません。
以下のような場合、Googleはページ内の別の文章を自動で抜き出して説明文として表示します。
- descriptionタグが設定されていない
- 設定された内容が検索キーワードと一致していない
- 説明文があいまいでユーザーの検索意図に合っていない
つまり、Googleが重視しているのはユーザーの検索意図にマッチしているかどうかです。
ページの内容と検索キーワードがうまく一致するような文章がdescriptionに入っていれば、それがそのまま使われる可能性が高まります。
また、Googleは説明文が重複している場合にも独自の判断で差し替えることがあります。
ページごとに異なる内容を丁寧に書いておくことが信頼性につながります。
使わないとどうなる?
descriptionタグを設定しなかった場合、検索エンジンがページ内の文章から自動的に抜粋して説明文を作成します。
このときに表示される内容は、ページ内で検索キーワードが出てくる前後の文章が中心になることが多いです。
しかし、自動で選ばれる説明文は、以下のようなリスクを含みます。
- 意図していない文言が表示される
見出しやメニューなどがそのまま表示されてしまうこともあります - 内容があいまいに見える
伝えたいポイントがぼやけることがあります - ページの魅力が伝わらない
ユーザーの関心を引く言葉になっていないことが多いです
検索結果に表示されたとき、見た目に魅力がなく他と比べて目立たないとクリックされづらくなってしまいます。
Webサイトのアクセス数を増やしたいなら、説明文を自分でコントロールできるdescriptionタグを積極的に使う方が有利です。
メタディスクリプションを書くときの最適な文字数と目安
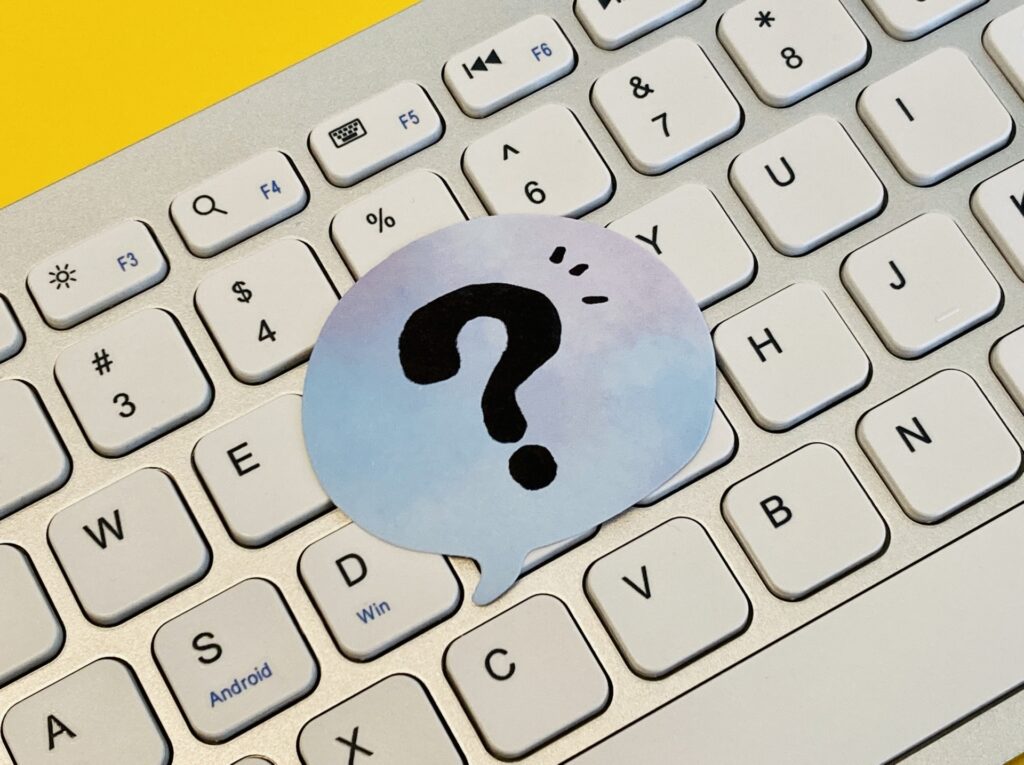
文字数が多すぎても少なすぎてもダメ?
メタディスクリプションは、ページの内容を検索結果で伝えるための文章です。
そのため、短すぎると情報が足りず、長すぎると途中で切れてしまい、伝えたいことが伝わらなくなる可能性があります。
検索エンジンに表示される文字数には限りがあります。その範囲を超えてしまうと、文章の途中で省略され「…」と表示されることがあり、文章の魅力が伝わりにくくなります。
一方で、文字数が少なすぎると、そのページがどんなテーマを扱っているのかを把握するのが難しくなり、クリックされにくくなることがあります。
適切な長さで要点を伝えることが、クリック率の向上に効果的です。
スマホとパソコンで見える長さは違う
検索結果に表示される説明文の長さは、スマホとパソコンで異なることがあります。
デバイスごとに表示される幅が違うため、同じ文章でも切られて表示される場所が変わることがあるのです。
次のような違いがあります。
- パソコン:約110〜130文字前後が表示される傾向
- スマホ:約70〜90文字前後が上限になりやすい
最近はスマホでの検索が多くなっているため、70〜90文字で内容の中心が伝わるように構成することが重要です。
そのうえで、パソコンでも読みやすいように、120文字以内で文章を収めると安心です。
一文で伝わる長さの目安
メタディスクリプションは、1〜2文でページの内容や魅力が伝わる文章が理想的です。
長い説明文を詰め込むより、シンプルな表現で伝えるほうが印象に残りやすく、読みやすさも向上します。
以下のような構成が効果的です。
- 最初の1文でページの概要を伝える
- 2文目で読むメリットや行動を促す言葉を入れる
ページ内容の要点とユーザーにとっての価値を、一目で理解できるよう意識すると良いでしょう。
何文字くらいがベスト?
一般的に、メタディスクリプションの文字数は全角で80〜120文字以内が推奨されています。
中でも、90〜110文字程度を目安にすると、スマホでもパソコンでも切られずに表示される可能性が高くなります。
実際にGoogleが公式に文字数を発表しているわけではありませんが、検索結果の表示例から逆算すると、以下のような基準が参考になります。
- 70文字以下:情報量が少なく、クリックされにくい傾向
- 80〜110文字:読みやすさと情報のバランスが良い
- 120文字を超える:表示が途中で切れる可能性が高い
文章を作るときは、文字数の調整だけでなく、伝えたいポイントを1文に凝縮できるかどうかも意識することが大切です。
はみ出したときの見え方
メタディスクリプションが指定された上限を超えた場合、Googleは自動的に文章を省略して「…」を表示します。
これによって、文章の途中が切れてしまい、伝えたい情報が最後まで表示されないことがあります。
たとえば、以下のような見え方になることがあります。
【設定された文章】
このページでは、初心者向けにdescriptionタグの効果や設定方法についてわかりやすく解説しています。
【検索結果での表示例(はみ出し)】
このページでは、初心者向けにdescriptionタグの効果や設定方法についてわかりやすく…
文章が途中で切れると、情報が中途半端になり、クリックするかどうかの判断がつきにくくなる場合もあります。
そのため、文章の後半に重要な情報を詰め込みすぎるのではなく、最初の60文字程度で要点を伝えるようにするのがポイントです。
また、はみ出しによって内容が伝わらないとGoogleが判断した場合、ページ内の別の文章を勝手に抜き出して表示するケースもあります。
自分で設定した説明文が必ず表示されるわけではないため、簡潔かつ的確に内容を伝える工夫が求められます。
ユーザーのクリック率を上げるための書き方と構成のコツ

思わず読みたくなる言葉選び
検索結果に表示される文章は限られています。その中でクリックされやすい説明文を書くためには、ユーザーの関心を引く言葉選びがとても重要です。
ただ情報を並べるだけでなく、読み手の気持ちに寄り添うような言葉を使うと、文章に惹きつけられやすくなります。
以下のような言葉は、関心を持ってもらいやすくなります。
- よくある悩みや不安を反映した言葉
知らないと損、間違いやすい、失敗しがち - 簡単さや手軽さを感じさせる言葉
初心者でもできる、今すぐできる、かんたん - 行動を促す言葉
チェックしておきたい、今すぐ確認、まず読んでみて - 読んだあとのイメージが浮かぶ言葉
○○がわかる、○○を理解できる、○○ができるようになる
ただし、必要以上に煽る表現や誇張は逆効果になります。
自然な言い回しの中に価値を感じさせることが大切です。
ユーザーの「知りたい」を先回りする
検索をする人は、何かしらの疑問や悩みを持っています。
クリックされる説明文を作るには、その疑問にいち早く答えることが効果的です。
ユーザーの「知りたい」が何なのかを考えて、それに直接こたえる一文を入れましょう。
検索されやすいテーマには、以下のようなパターンがあります。
- ○○とは何か知りたい:定義や概要を求めている
- ○○の方法が知りたい:やり方や使い方を知りたい
- ○○の違いを知りたい:比較や特徴を理解したい
- ○○の効果を知りたい:結果やメリットを期待している
こうした検索意図を読み取って、「このページにはその答えが書いてある」と伝わる内容にすると、検索結果の中で選ばれやすくなります。
強調したい言葉の置き方
クリックされやすい説明文は、文章の構成にも工夫が必要です。
とくに、どの言葉を文頭に置くかは、読まれやすさに大きく影響します。検索結果で表示されたときに、一番目に入る場所に大切なキーワードや伝えたい内容を置くと、目を引きやすくなります。
効果的な構成には次のようなものがあります。
- 最初の30文字で結論を伝える
このページで何がわかるのかを最初に示す - 重要なキーワードは前半に配置
検索に使われやすい言葉を早めに使う - 文章の後半で安心感や行動喚起を伝える
初心者にも安心、今すぐチェック
検索結果では、検索キーワードに一致した部分が太字で表示されることが多いため、関連キーワードを前の方に置くことで目に留まりやすくなるという利点もあります。
避けたいNGワード
メタディスクリプションでは、不自然な言葉選びや読みにくい構成を避けることが大切です。
以下のような表現は、クリック率の低下を招く可能性があります。
- キーワードの詰め込みすぎ
SEO対策のために無理に言葉を連ねると読みにくくなる - あいまいで印象に残らない言葉
効果的、最適、適切などが並ぶだけでは意味が伝わりにくい - 抽象的すぎる表現
内容のイメージが湧かないため興味を持ちにくい - 不安をあおるだけの文章
根拠なく不安を強調すると信頼を損ねる - 専門用語の多用
Web初心者には伝わりにくくなる
検索ユーザーが求めているのは、自分の悩みや目的にこたえてくれるページかどうかです。
表現はやさしく、そして具体的にすることで、安心感と信頼感を持ってもらいやすくなります。
実際にクリックされた例を見てみよう
クリック率が高かった実際の説明文には、読み手が行動したくなる要素がしっかりと含まれています。
ここでは、効果的なパターンをいくつか紹介します。
- Web初心者でもすぐに実践できる、descriptionタグの書き方をわかりやすく解説
- クリックされる説明文の作り方とは?SEO対策にもつながるメタディスクリプション活用術
- 記事タイトルだけでは伝わらない魅力を伝える、設定すべき理由と具体的なコツを紹介
これらに共通しているのは次のポイントです。
- ページを読むことで得られる内容やメリットが明確
- 具体的な言葉を使ってイメージしやすくしている
- ユーザーの不安や疑問にそっと寄り添っている
こうした表現は、ユーザーエクスペリエンスを高めるうえでもとても重要です。
クリックされた後にページを読んでもらうことが前提となるため、過剰な煽りではなく、信頼感を持たせる内容にするのがポイントです。
少ない文字数の中でも、言葉の選び方や配置を工夫することで、メタディスクリプションは大きな効果を発揮します。
しっかりとユーザーの目線を意識して、検索結果で「読んでみたい」と思ってもらえる文章を作っていきましょう。
メタタグの設定方法とページごとの最適化ポイント

WordPressでの設定は簡単?
WordPressを使っている場合、メタディスクリプションを設定する方法はとてもシンプルです。
基本的には、SEO系のプラグインを活用すれば、専門的な知識がなくても説明文を設定できます。
有名なプラグインには、以下のようなものがあります。
- All in One SEO
- Yoast SEO
- The SEO Framework
これらのプラグインでは、投稿ページや固定ページの編集画面に「メタディスクリプション入力欄」が用意されています。
そこに、そのページの要点を簡潔にまとめた説明文を入力するだけでOKです。
プラグインによっては、検索結果での見え方をリアルタイムでプレビューできる機能もあるため、スマホやパソコンでどう表示されるかを事前に確認しながら調整できるのも便利です。
注意点として、テーマによってはmetaタグの出力方式が異なる場合がありますので、テーマがSEO対応しているかも確認しておくと安心です。
HTMLで設定するときの書き方
WordPressを使っていない場合や、自分でHTMLファイルを編集している場合は、HTMLのheadタグの中にdescriptionタグを直接書くことで設定ができます。
書き方の基本は次のようになります。
<meta name="description" content="○○について初心者向けにわかりやすく紹介します。今すぐチェックしてみてください。">
このコードを、<head>〜</head>の間に記述することで、検索エンジンに向けてそのページの要約情報を伝えることができます。
metaタグの内容は検索エンジンだけでなく、SNSなどでページがシェアされたときの表示内容にも影響する場合があるため、内容を丁寧に書いておくとWeb上での印象も良くなります。
記述する際は、以下の点に気をつけましょう。
- 全角で80〜120文字程度に収める
- ページごとに固有の内容にする
- 同じ内容の繰り返しやキーワードの詰め込みは避ける
metaタグは目に見えない部分の設定ですが、ユーザーエクスペリエンスに直接影響する要素のひとつです。
各ページに別々の説明文を書く理由
すべてのページに同じメタディスクリプションを設定してしまうと、検索エンジンから「内容の重複が多い」と判断される可能性があり、評価が下がる原因になります。
また、検索ユーザーにとっても、「どのページをクリックすれば自分の知りたいことがわかるのか」が判断しづらくなるため、クリック率の低下につながります。
ページごとに異なる説明文を書くことで、以下のようなメリットがあります。
- ページの目的や内容がはっきり伝わる
- ロングテールキーワードにも対応しやすくなる
- SNSや検索結果で目立ちやすくなる
Webサイト内に複数のページがある場合、それぞれのページがどのような役割を果たしているのかを、メタディスクリプションを通じて説明するように意識することが大切です。
まとめて自動で設定することもできる?
ページが多いサイトでは、1つ1つ手動で設定するのが手間になる場合もあります。
その場合は、プラグインやCMSの機能で、自動生成のテンプレートを使う方法もあります。
たとえば、WordPressのAll in One SEOでは、テンプレート機能を使って以下のような形式で自動生成できます。
- 【投稿タイトル】|【サイト名】
- 【投稿の抜粋】+固定の説明文
ただし、自動生成された内容はユーザーの検索意図に十分に対応できていないことが多いため、できるだけ手動での調整をおすすめします。
以下のようなパターンでは、自動生成よりも手動設定の方が効果的です。
- ビッグキーワードを狙っているページ
- ページ内容が専門的でターゲットが絞られているとき
- コンバージョン(問い合わせや資料請求など)を重視しているとき
自動生成をベースにしつつ、重要なページだけ手動でカスタマイズするのもひとつの方法です。
サイト全体の印象を整える方法
メタディスクリプションは、Webサイト全体のイメージにも影響します。
すべてのページで一貫性のある文章構成やトーンで設定しておくと、ユーザーからの印象が良くなりやすくなります。
以下のようなポイントを意識すると、サイト全体の印象がまとまりやすくなります。
- 説明文の語尾や口調を統一する
敬語、断定口調、やさしい表現などスタイルをそろえる - 書き出しのパターンを決めておく
○○を紹介します、○○について解説していますなど - 企業やサービス名の入れ方を統一する
どの位置に入れるか、略称か正式名かなど
また、ターゲットユーザーに合わせた言葉選びも大切です。
専門用語を避けるのか、業界用語を取り入れるのかといったスタンスを決めておくと、読みやすさと親しみやすさが高まります。
メタディスクリプション作成時の注意点とよくある間違い

他のページと同じ文章になっていない?
Webサイトを運営していると、ページ数が増えるにつれて説明文を書くのが面倒になることがあります。
そうしたときに、すべてのページで同じメタディスクリプションを使い回すと、検索エンジンから「重複コンテンツ」と判断されてしまうことがあります。
Googleは、内容が似ているページが複数ある場合、どれを優先して表示すべきか迷ってしまい、どのページも順位が上がらないといった状態に陥る可能性があるとされています。
同じ説明文を使わないための工夫として、次のようなポイントを意識してみてください。
- ページのテーマや目的が異なる場合は、それぞれの内容をしっかり反映する
- 決まり文句やテンプレートを使うとしても、一部はページごとにカスタマイズする
- 同じキーワードを使う場合でも、その見せ方や伝え方を変える
複数のページがあるサイトでは、それぞれのページが独立して価値を持っていることをメタディスクリプションでもしっかり伝えることが大切です。
キーワードを詰め込みすぎてない?
SEO対策として、検索されやすい言葉を説明文に入れたいと考えるのは自然なことです。
しかし、必要以上にキーワードを詰め込むと逆効果になることがあります。
ユーザーから見ても、文章が不自然だったり、読みづらかったりすると、クリックされにくくなってしまいます。
また、検索エンジンも過剰なキーワードの使用はスパムとみなす可能性があります。
避けたいキーワードの使い方には次のようなパターンがあります。
- 同じ単語を繰り返している
- 意味が通じにくい文章になっている
- 無理にキーワードを詰め込んで文の流れが崩れている
以下のような書き方を心がけることで、キーワードを自然に取り入れることができます。
- 文章の中に違和感なくキーワードを入れる
- ビッグキーワードとロングテールキーワードをバランスよく使う
- 読み手が「自分のための情報だ」と思えるような言い回しを選ぶ
自然な表現でユーザーに伝わる文章こそが、検索結果でクリックされるきっかけになります。
まとめ
メタディスクリプションは、検索結果でページの内容を短く伝える大切な説明文です。
うまく書けていると、ユーザーの目にとまりやすくなり、クリックされる可能性が高まります。
ただし、文字数が長すぎたり短すぎたり、同じ文章をいろんなページで使いまわしたりすると、検索エンジンに正しく評価されなかったり、ユーザーに伝わりにくくなったりすることもあります。
説明文を書くときは、そのページの内容が一目で伝わることと、読み手が「知りたい」と思っていることに寄りそうことがポイントです。
また、クリックしたくなるような言葉選びや、見やすい文章構成も効果的です。
WordPressやHTMLでも設定は簡単にでき、ページごとにきちんと書き分けることで、検索順位やアクセス数にも良い影響が期待できます。
小さなパーツですが、しっかりと丁寧に作ることが、わかりやすく伝わるサイト作りの第一歩になります。
検索結果で目を引くために、ぜひ活用してみてください。




