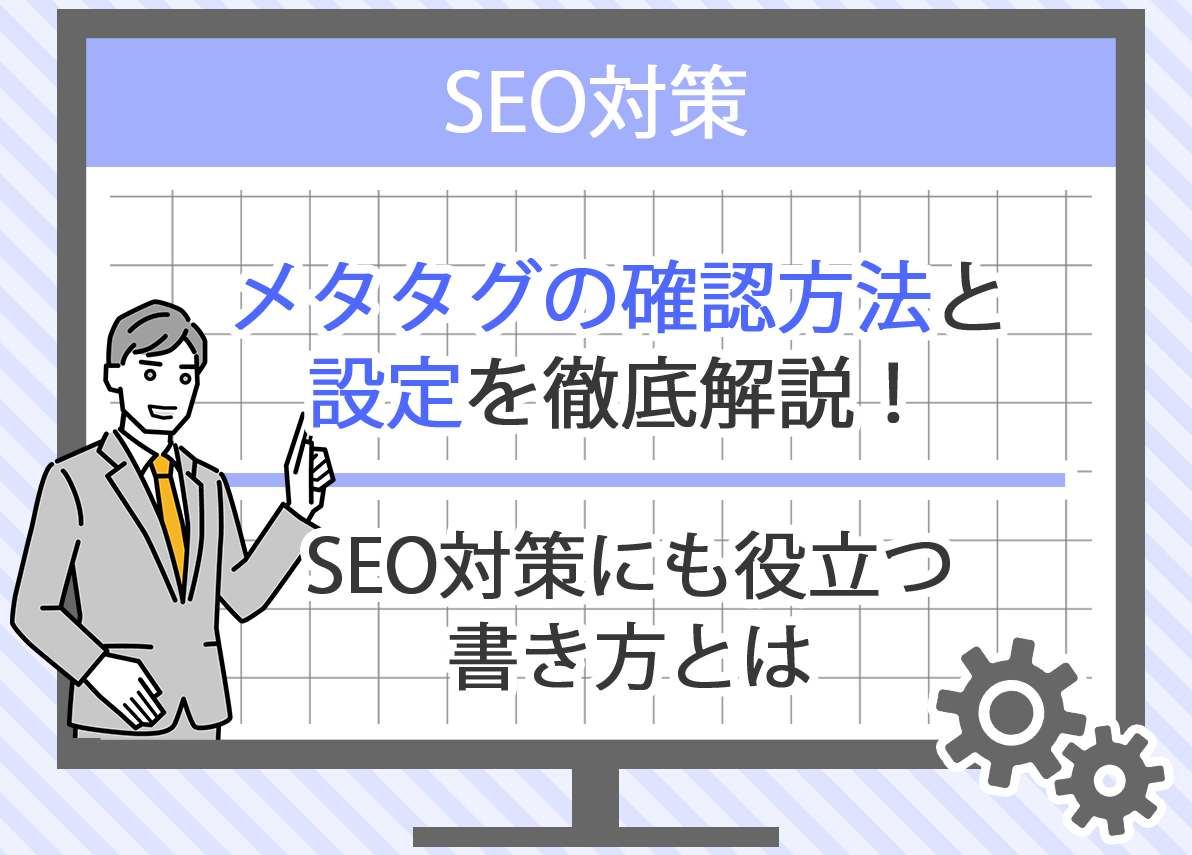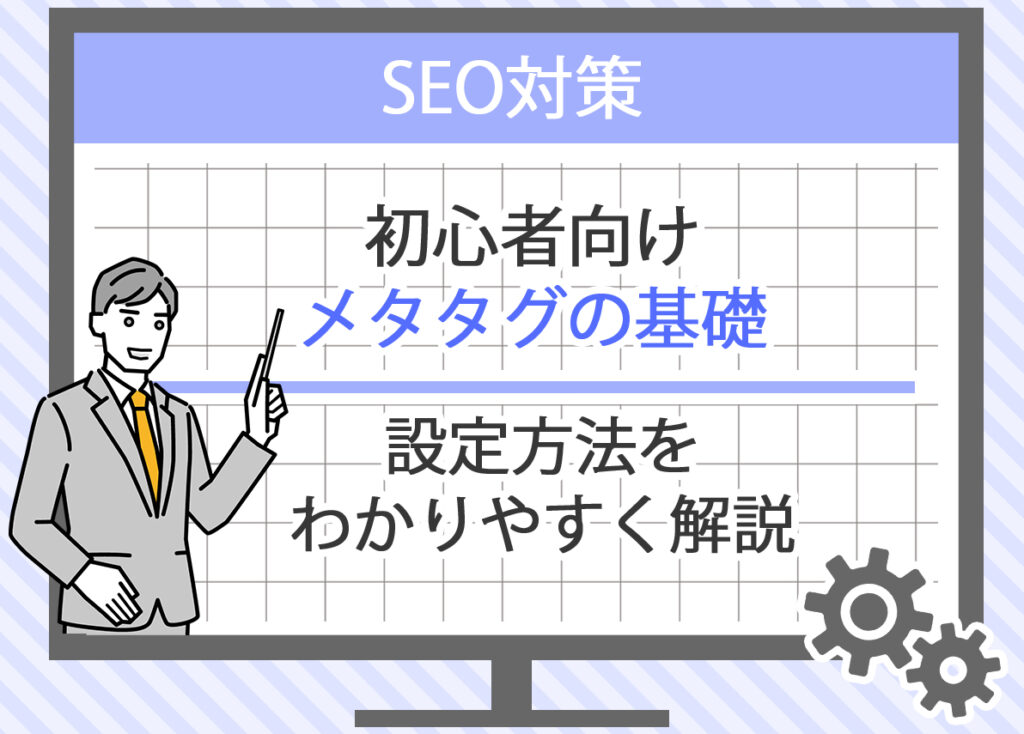
Webサイトを作成したり運営したりするときに、「メタタグ」という言葉を目にすることがあるかもしれません。
けれども、その意味や役割を正しく理解している人は意外と少ないものです。
メタタグは、検索エンジンやブラウザにページの情報を伝えるための重要な要素で、SEO対策にも欠かせない仕組みです。
検索結果での見え方や、SNSでの共有時の表示内容にも関わるため、正しく設定することでアクセス数やクリック率の向上にもつながります。
この記事では、初心者の方にもわかりやすい言葉でメタタグの基本的な意味から種類、設定の手順、そして注意すべきポイントまでをやさしく解説します。
これからWebサイトを作る方も、すでに運営中の方も、ぜひメタタグの理解を深めて効果的に活用してください。
メタタグとは?基礎からわかる重要な役割を解説

メタタグとは?基礎からわかる重要な役割を解説
メタタグれはWebページの裏側にある情報を整理して伝えるためのタグで、見た目には表示されませんが検索エンジンやSNSにとってとても重要な情報源です。
メタタグには、ページの説明文や文字コード、検索エンジンに知らせたい内容などを記述します。
たとえばGoogleで検索したときに表示される説明文は、多くの場合メタタグの「description(ディスクリプション)」をもとに作られています。
つまり、メタタグはWebページの概要を知らせる「裏側のメモ」のような役割を持っています。
なぜメタタグがあると検索に強くなるのか?
メタタグを正しく設定すると、検索エンジンがページの内容をより正確に理解しやすくなります。
検索エンジンは「クローラー」というプログラムを使ってサイトの情報を読み取りますが、メタタグがあると効率的に内容を把握できるため、検索結果で表示されやすくなる傾向があります。
また、メタディスクリプション(meta description)に書かれた内容は検索結果でクリックされるかどうかにも関係します。
検索した人が「自分の知りたいことが書かれていそう」と感じる説明文であれば、クリック率が上がりアクセスも増えます。
このように、メタタグは検索順位だけでなくページの評価やアクセス数にも影響します。
検索エンジンに好まれるメタタグの特徴は次の通りです。
- 説明が簡潔で内容が伝わりやすい
余計な言葉を使わずに要点をまとめると効果的です - キーワードが自然に含まれている
無理に詰め込むのではなく、文の流れに沿って使います - ページごとに内容を変えている
すべて同じ説明だと検索エンジンの評価が下がることがあります
メタタグが使われる場所とその働き
メタタグはHTMLファイルのhead内に記述します。
この部分はWebページの見た目を作るbody部分とは異なり、ページ設定や外部との連携を定義する役割を持っています。
代表的なメタタグと役割は次の通りです。
- meta charset 文字コードの指定(例:UTF-8)
- meta description ページの説明文を設定
- meta keywords ページに関連するキーワード(※現在は多くの検索エンジンで無視される傾向あり)
- meta robots 検索エンジンに対するページの扱い方を指示(例:index, follow など)
- meta viewport スマートフォンなどでの表示方法を調整
これらのメタタグは、検索エンジン対策だけでなくユーザーエクスペリエンスの向上にもつながります。
たとえばmeta viewportを設定することで、スマートフォン表示時に画面サイズを自動で最適化できます。
さらに、SNSでページをシェアしたときの見え方を調整する「OGP(Open Graph Protocol)」もメタタグの一種です。
X(旧Twitter)やFacebookに合ったタイトルや画像を指定でき、クリックされやすくなります。
HTMLにどのように記述されるか
実際のHTMLでは、メタタグは以下のように記述されます。
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="初心者向けにメタタグの役割や書き方を解説します。">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>metaタグは開閉タグが不要で、nameやcontentなどの属性を組み合わせて使います。
初心者の方でもこの形を参考にすれば簡単に設定できます。
自分のサイトでどのように記述されているかを確認したいときは、ブラウザで右クリックして「ページのソースを表示」を選ぶとHTMLの中身を見ることができます。
WordPressを利用している場合は、プラグインを使ってコードを書かずに管理できます。
現在では「Yoast SEO」や「All in One SEO」などが定番で、どちらも日本語対応が進んでおり初心者でも扱いやすい構成です。
設定画面でdescriptionやtitleを入力するだけで、自動的にメタタグが生成される仕組みになっています。
このように、メタタグはWebページの見えない部分にありながら、検索結果やSNS表示、モバイル対応など多方面に影響を与える大切な要素です。
SEOにおけるメタタグの効果と検索エンジンへの影響
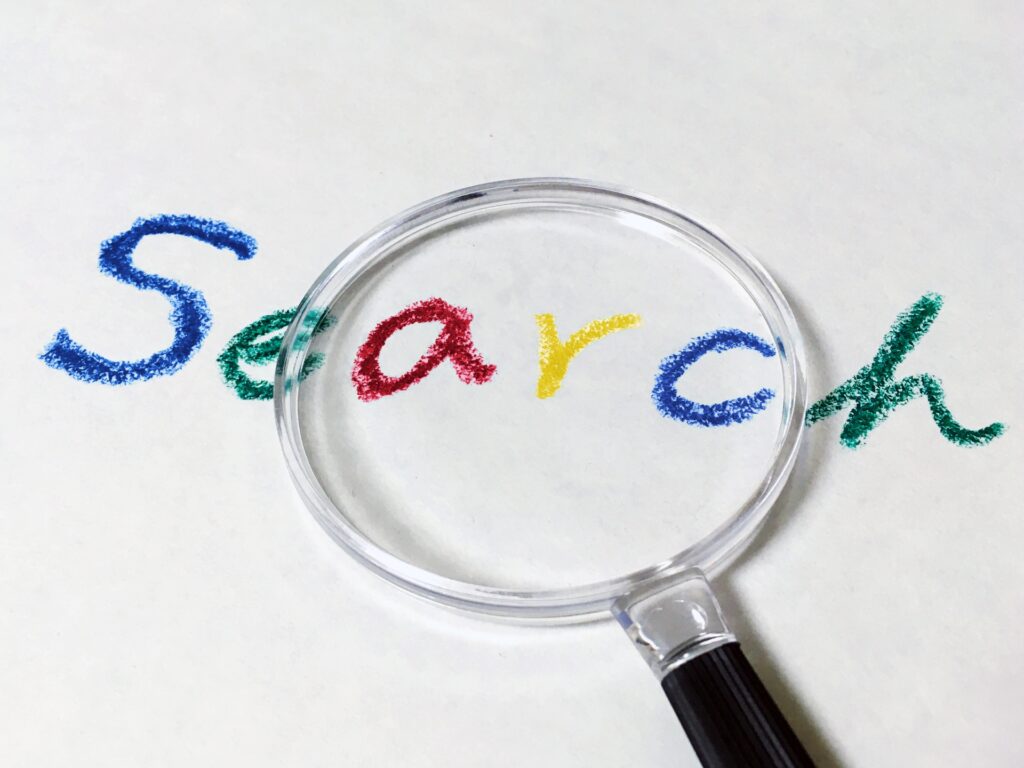
検索エンジンはWebページの内容を理解する際、メタタグに記載された情報も重要な手がかりとして利用します。
ページ全体を解析するだけでなく、メタタグを通して概要を把握することで内容を効率的に判断できるため、検索順位や表示内容にも影響を与えることがあります。
特にdescription、robots、viewportの3つは検索エンジンにとって重要なメタタグです。
descriptionはページの説明を伝え、robotsはページを検索結果に載せるかどうかを制御し、viewportはモバイル端末での見やすさを調整します。
descriptionに書かれた内容は検索結果の画面に表示されることも多く、クリック率を左右する大きなポイントになります。
検索順位への影響と注意点
メタタグには直接順位に関わるものと、間接的に影響するものがあります。descriptionタグはGoogleのアルゴリズム上、順位決定の要因には含まれないとされていますが、クリック率を上げることで結果的に評価を高める可能性があります。一方、robotsタグはより直接的に影響します。たとえば次のような記述がある場合、そのページは検索結果に表示されません。
<meta name="robots" content="noindex">
この指定は「検索結果に載せないでください」という指示を意味します。もし誤って設定すると、意図したページが検索に出なくなることがあるため、公開前に必ず確認することが大切です。またviewportタグはモバイル対応を検索エンジンに伝える役割を持ち、スマートフォンでの閲覧が主流となった現在では、モバイル対応が評価基準の一部となっています。Googleのモバイルファーストインデックスが導入された現在、スマホで見やすい設計をしているかどうかはSEOにおいて欠かせない要素です。め、クリックされるかどうかに関わるポイントにもなります。
上位表示にどれくらい影響するの?
メタタグには直接順位に関わるものと、間接的に影響するものがあります。
descriptionタグはGoogleのアルゴリズム上、順位決定の要因には含まれないとされていますが、クリック率を上げることで結果的に評価を高める可能性があります。
一方、robotsタグはより直接的に影響します。
たとえば次のような記述がある場合、そのページは検索結果に表示されません。
<meta name="robots" content="noindex">この指定は「検索結果に載せないでください」という指示を意味します。
もし誤って設定すると意図したページが検索に出なくなることがあるため、公開前に必ず確認することが大切です。
またviewportタグはモバイル対応を検索エンジンに伝える役割を持ち、スマートフォンでの閲覧が主流となった現在ではモバイル対応が評価基準の一部となっています。
Googleのモバイルファーストインデックスが導入された現在、スマホで見やすい設計をしているかどうかはSEOにおいて欠かせない要素です。
クリックされやすいdescriptionの作り方
検索結果では、見た目や説明文の分かりやすさも重要です。
特にdescriptionの内容は、ユーザーがクリックするかどうかを判断する決め手になります。
クリックされやすいdescriptionには次のような特徴があります。
- タイトルと内容に一貫性がある
- 100文字前後で簡潔にまとまっている
- キーワードが自然に含まれている
descriptionを作成する際は、検索ユーザーの意図に合わせて自然な文章にすることが大切です。
ロングテールキーワード(複数の単語を組み合わせた検索語句)を意識すると、より具体的な悩みや目的を持つユーザーに届きやすくなります。
スニペットとの関係
SEOにおけるメタタグの効果と検索エンジンへの影響
検索エンジンはWebページの内容を理解する際、メタタグに記載された情報も重要な手がかりとして利用します。ページ全体を解析するだけでなく、メタタグを通して概要を把握することで内容を効率的に判断できるため、検索順位や表示内容にも影響を与えることがあります。特にdescription、robots、viewportの3つは検索エンジンにとって重要なメタタグです。descriptionはページの説明を伝え、robotsはページを検索結果に載せるかどうかを制御し、viewportはモバイル端末での見やすさを調整します。descriptionに書かれた内容は検索結果の画面に表示されることも多く、クリック率を左右する大きなポイントになります。
検索順位への影響と注意点
メタタグには直接順位に関わるものと、間接的に影響するものがあります。descriptionタグはGoogleのアルゴリズム上、順位決定の要因には含まれないとされていますが、クリック率を上げることで結果的に評価を高める可能性があります。一方、robotsタグはより直接的に影響します。たとえば次のような記述がある場合、そのページは検索結果に表示されません。
<meta name="robots" content="noindex">
この指定は「検索結果に載せないでください」という指示を意味します。もし誤って設定すると、意図したページが検索に出なくなることがあるため、公開前に必ず確認することが大切です。またviewportタグはモバイル対応を検索エンジンに伝える役割を持ち、スマートフォンでの閲覧が主流となった現在では、モバイル対応が評価基準の一部となっています。Googleのモバイルファーストインデックスが導入された現在、スマホで見やすい設計をしているかどうかはSEOにおいて欠かせない要素です。
クリックされやすいdescriptionの作り方
検索結果では、見た目や説明文の分かりやすさも重要です。特にdescriptionの内容は、ユーザーがクリックするかどうかを判断する決め手になります。クリックされやすいdescriptionには次のような特徴があります。
- タイトルと内容に一貫性がある
- 100文字前後で簡潔にまとまっている
- キーワードが自然に含まれている
descriptionを作成する際は、検索ユーザーの意図に合わせて自然な文章にすることが大切です。ロングテールキーワード(複数の単語を組み合わせた検索語句)を意識すると、より具体的な悩みや目的を持つユーザーに届きやすくなります。
スニペットとの関係
Googleの検索結果では、タイトルの下に表示される文章を「スニペット」と呼びます。
スニペットは、ページの本文から自動的に抜き出される場合もありますが、descriptionメタタグに書かれた内容がそのまま使用されることもあります。
上手に設定されたスニペットは、ユーザーに「このページで自分の疑問が解決しそう」と感じさせる大きな要因になります。
一方で、descriptionが設定されていない場合や空欄の場合、Googleが本文の一部を自動で抜き出して表示します。
そのため文脈が伝わりにくかったり、意図しない情報が出たりすることがあります。
自分で内容をコントロールできるように、必ずdescriptionを設定しておくことが重要です。
descriptionの最適な文字数は90〜120文字程度が目安です。
パソコンとスマートフォンでは表示される文字数が異なるため、一文で伝わるわかりやすい文章にまとめましょう。
読みやすさと情報の的確さを両立することがクリック率の向上につながります。
メタタグの種類とmeta属性の正しい記述ルール

ここでは代表的なメタタグの種類と、正しい記述方法について解説します。
よく使う代表的なメタタグを紹介
Webページの見た目には現れませんが、メタタグにはたくさんの種類があり、それぞれに異なる役割があります。
中でもよく使われている代表的なメタタグを紹介します。
- meta charset
ページの文字コードを指定します。日本語サイトではUTF-8が一般的で、文字化け防止に欠かせません。 - meta name=”description”
ページの説明文を設定します。検索結果に表示され、クリック率に影響します。 - meta name=”keywords”
ページの内容に関連するキーワードを設定します。ただし、現在はGoogleなどの主要検索エンジンでは無視されています。 - meta name=”viewport”
スマートフォンやタブレットでの表示を最適化します。モバイル対応が評価される現代では必須です。 - meta name=”robots”
検索エンジンに対して、ページをインデックスしてよいか、リンクをたどってよいかを指示します。
これらのタグは、SEO対策だけでなくユーザーエクスペリエンスを高めるためにも重要です。
特にviewportの設定はモバイル閲覧時のレイアウト崩れを防ぐ役割を持ちます。
「description」や「keywords」って何のこと?
descriptionは、ページの要約として検索結果に表示されることが多く、クリック率に大きく関係します。
keywordsは、かつてはSEOに利用されていましたが、現在は評価対象外です。
それでも他の検索エンジンやサイト内検索機能で利用される場合があるため、適切に記述しておくとよいでしょう。
【記述例】
<meta name="description" content="Web初心者向けにメタタグの意味や正しい書き方をやさしく解説します。">content属性には、ページの内容を100文字前後で簡潔にまとめます。
長すぎると検索結果で途中が省略されることがあるため注意が必要です。
書き方の基本ルール(コピペで使える形式紹介)
メタタグはHTMLのheadタグ内に記述します。
headはページの設定情報をまとめる場所で、外部CSSやスクリプトの読み込みもこの中で行われます。
基本構成は次のようになります。
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="このページはWeb初心者向けにメタタグを解説しています。">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="robots" content="index, follow">
</head>
metaタグは開閉タグが不要で、<meta ...>の形で記述します。
テンプレートとして保存しておくと、複数ページの制作時に便利です。
robotsタグには以下のような指示を設定できます。
- index ページを検索エンジンに載せる
- noindex 検索結果に表示しない
- follow ページ内のリンクをたどる
- nofollow リンクをたどらない
たとえば、「noindex, nofollow」を設定するとそのページは検索結果に出ず、リンクも評価対象外になります。
非公開ページや会員限定ページで使われることが多い設定です。
必ず使いたいメタタグと、あまり使わないもの
初心者でも必ず設定しておきたいメタタグは次の3つです。
- meta charset 文字化けを防ぐために必須です
- meta description 検索結果でのクリック率に関係します
- meta viewport スマホやタブレットでの見やすさを調整します
逆に、現在は使われなくなったり、効果が限定的なものもあります。
- meta keywords 主要な検索エンジンでは無視されます
- meta author 作成者情報を記載しますが、SEO効果はありません
- meta refresh 自動でページを切り替えますが、ユーザーが混乱しやすいため避けられています
メタタグを正しく使うためには、「何を伝えるのか」「誰に見せたいのか」を意識することが大切です。
各ページごとに内容を変え、適切な文字数を守り、不必要なタグを省くことで、検索エンジンにもユーザーにもわかりやすいWebページを作ることができます。
メタタグの書き方と設定方法を初心者向けに紹介

メタタグを設置する場所はどこ?
メタタグはHTMLファイルの中でもhead(ヘッド)部分に記述します。
このhead部分はページタイトルや文字コード、外部ファイルの読み込みなど、Webページの基本情報をまとめる場所です。
headの外に書くと正しく認識されないため、必ずheadタグの中に記述しましょう。
基本構成は以下のようになります。
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<!-- メタタグはこの中に記述 -->
</head>
<body>
<!-- ページの見た目を作る部分 -->
</body>
</html>headタグ内にメタタグを入れることでWebページが読み込まれる前に設定情報が反映され、より正確で安定した表示が可能になります。
コピペで使える基本の書き方
メタタグは1行で完結する記述が多く、閉じタグを必要としません。
次のように、nameとcontentをセットで使うのが基本形です。
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="このページはWeb初心者の方向けにメタタグについてわかりやすく紹介しています。">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="robots" content="index, follow">
それぞれの意味は次の通りです。
- charset 文字のエンコードを指定します
- description ページの説明を設定します
- viewport スマートフォンなどの画面幅に合わせて表示を最適化します
- robots 検索エンジンにインデックスの可否を伝えます
迷ったときはこのテンプレートをベースにすれば、基本的なSEO対策として十分機能します。
WordPressでの設定方法(初心者にもおすすめ)
HTMLファイルを直接編集しなくても、WordPressを使っていれば管理画面からメタタグを設定できます。
プラグインを利用すれば、コードを書かずに簡単に設定が可能です。
代表的なプラグインは次の3つです。
- All in One SEO 多機能で、細かい設定がしやすい
- Yoast SEO 視覚的にわかりやすく、初心者に人気
- SEO SIMPLE PACK 日本語対応でシンプルな構成
設定の流れは次の通りです。
- 管理画面の「プラグイン」から該当のSEOプラグインをインストールして有効化します
- 各投稿や固定ページの編集画面に、descriptionやtitleの入力欄が追加されます
- テキストを入力するだけで、HTMLのmetaタグが自動で挿入されます
どのプラグインも入力した内容がリアルタイムでプレビューされるため、初心者の方でも安心して使えます。
無料ツールを使ってメタタグを作成する方法
WordPressを使用していない場合でも、Web上の無料ツールを使えば簡単にメタタグを作成できます。必要項目を入力すると、自動的にHTMLコードが生成されます。
【便利なツールの例】
- Metatags.io
OGP(SNS共有時の設定)もまとめて作成可能 - SEOptimer Meta Tag Generator
英語だがシンプルな操作で直感的に使える
生成されたコードをHTMLのhead内にコピーして貼り付ければ、設定は完了です。
また、Chrome拡張機能を使えば、他サイトのメタタグを調べたり自分のページの設定を確認したりすることもできます。
- META SEO inspector
ページのメタ情報をまとめて確認できる - SEO META in 1 CLICK
SNSでの見え方や文字数をチェック可能
いずれも無料で利用でき、確認作業にも役立ちます。
Google検索で上位を狙うためのキーワード対策のポイント

メタタグに入れるキーワードはどう選ぶ?
キーワードは、検索エンジンにページの内容を伝えるための重要な要素です。
特にmeta descriptionやtitleタグに含めることで、検索エンジンにページの主題を明確に伝えることができます。
キーワードを選ぶときは、次の3つの視点が大切です。
- 検索されている回数が多いか
- ページ内容と一致しているか
- 読み手が自然に使う言葉か
より具体的な検索意図を持つユーザーに届きやすくするには、ロングテールキーワードの活用が効果的です。
たとえば「メタタグ 記述方法 初心者」のように複数語を組み合わせると、検索数は少なくても意図の合致率が高くなります。
キーワードを見つけるには次の方法があります。
- Google検索のサジェスト(予測表示)を確認する
- 関連キーワード取得ツール(例:ラッコキーワード)を使う
- 他の上位表示ページで使われているキーワードを参考にする
どんな人がどんな悩みで検索しているかを意識し、読者の検索行動に沿ったキーワードを選ぶことが重要です。
「詰め込みすぎ」はNG!自然な書き方とは
キーワードを多く入れれば上位に表示されるわけではありません。
不自然な詰め込みは検索エンジンに読みづらいと判断され、評価を下げる原因になります。
たとえば次のような文章は避けましょう。
「メタタグ 記述方法 メタタグ SEO メタタグ キーワード 書き方 メタタグとは」
このような羅列は読者にも伝わりにくく、検索エンジンにもスパムとみなされるおそれがあります。
自然な文脈の中でキーワードを使うことで、読みやすく内容も正確に伝わります。
検索エンジンは文全体の意味を理解できるようになっているため、「伝わりやすい文章」を意識することが大切です。
自然に見える文章にするためのポイントは次の通りです。
- タイトルにキーワードを1回だけ入れる
- descriptionにキーワードを自然に2回程度含める
- 1〜2文で内容をまとめる
キーワードの多さよりも、読みやすさや内容の整合性が評価につながります。
SEOで失敗しないための考え方
キーワード対策は単なる「言葉の挿入」ではなく、ユーザーエクスペリエンスを高めるための工夫と考えることが重要です。
SEOで成果を出すためには、次の考え方を意識しましょう。
- ユーザーが何を知りたいかを最優先にする
- メタタグは「読み手への案内文」として考える
- 検索順位よりも内容の正確さとわかりやすさを重視する
- 無理にキーワードを押し込まず、自然な流れを保つ
Googleは近年、キーワードよりも「読者にとって有益かどうか」を重視しています。
検索意図に合った内容を丁寧に書くことで、結果的に上位表示につながります。
また、長期間更新されていないページは評価が下がる傾向があるためdescriptionやタイトルを定期的に見直すことも大切です。
内容の鮮度を保つことが、今のSEOでは欠かせない要素になっています。
メタタグ設定時に確認すべき注意点と避けたいミス

タグを重複して使っていないか?
メタタグはページの情報を正しく伝えるための仕組みですが、同じ種類のタグを複数書くと検索エンジンが混乱し、正しい情報を読み取れなくなるおそれがあります。
たとえばdescriptionタグを2つ以上記述すると、Googleがどちらを採用するか判断できず意図しない文が検索結果に表示される場合があります。
次のような点を確認して、重複記述を防ぎましょう。
- meta name=”description”が複数行入っていないか
- meta name=”robots”が別の設定で2回以上記載されていないか
- OGP(SNS表示用タグ)と混同して、同じ内容が繰り返されていないか
特にWordPressなどのCMSでは、テーマやプラグインが自動でメタタグを出力する場合があります。
自分で追加したタグと重複していないか、公開前にページのHTMLソースを確認することが重要です。
文字数が長すぎる・短すぎるとどうなる?
meta descriptionやtitleは、文字数によって見え方が変わります。
長すぎると途中で省略され、短すぎると検索エンジンに十分な情報が伝わりません。
推奨文字数は以下の通りです。
- titleタグ:30〜40文字程度(全角換算)
- descriptionタグ:90〜120文字程度(全角換算)
文字数が多いとスニペット表示で末尾が「…」に置き換わり、内容が伝わりづらくなります。
逆に短い場合は、検索エンジンが本文の一部を自動で抜き出して表示することがあり、意図しない文章が表示される可能性があります。
文字数を確認する際は、次のツールが便利です。
- Serposcope Meta Description Checker
文字数や表示幅のシミュレーションが可能 - Google Search Console
実際の表示履歴やクリック率を確認できる
実際の検索結果をシミュレーションして確認すると、より最適な調整がしやすくなります。
「noindex」「nofollow」の設定に注意
robotsタグは、検索エンジンにページの扱い方を伝えるタグです。
中でも「noindex」や「nofollow」は慎重に使う必要があります。
次のような記述をすると、そのページは検索結果に表示されなくなります。
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">この設定は限定公開の資料や社内専用ページには有効ですが、通常公開するページに誤って使うと検索から完全に除外されます。
次の点を必ずチェックしてください。
- テーマやテンプレートで自動的に「noindex」が入っていないか
- WordPressの「検索エンジンに表示しない」設定が有効になっていないか
- 会員制ページやパスワード保護設定と併用して意味が変わっていないか
一度noindexを設定すると、検索結果への再掲載には時間がかかります。
公開前に念入りに確認しましょう。
Googleがメタタグを無視する場合もある
設定したメタタグが必ずしもそのまま表示されるとは限りません。
Googleはユーザーに最も適した情報を表示するため、descriptionやtitleを自動的に書き換えることがあります。
たとえば、検索キーワードと本文の一部が一致している場合、Googleが本文から抜き出した文をスニペットとして使うことがあります。
また、titleタグに同じ言葉を繰り返し使っていると、自動で短縮・修正されることがあります。
【避けるべき例】
- 「メタタグとは|メタタグとは|SEOに強いメタタグとは」など、同じ単語の繰り返し
- 内容が薄い誇張表現だけのタイトル
- 単語だけの羅列で文章になっていないもの
Googleは「自然で読みやすい日本語」を重視しており、過度な装飾よりも明確で簡潔な表現が評価されます。
設定後は必ずプレビューやチェックをしよう
メタタグは設定して終わりではなく、実際にどのように表示されているかを定期的に確認することが大切です。
以下の方法でチェックできます。
- Googleで実際に検索して表示を確認する(ただし反映には時間がかかる)
- Googleリッチリザルトテストでdescriptionや構造化データを同時に確認
- SNSカードチェック(XやFacebookの開発者ツール)でOGP表示を確認
- Chromeの開発者ツールでhead内のmetaタグを直接確認
ページ数が多い場合は、Google Search Consoleを使って全体の状態を管理しましょう。
エラーが出た際には通知が届くため、迅速に修正できます。
メタタグは一度設定して終わりではなく、検索エンジンの仕様やページ内容の変化に応じて定期的に更新することが大切です!
特にdescriptionやtitleは、最新のキーワードやページ内容に合わせて調整することで、クリック率やユーザーエクスペリエンスの向上につながります。
まとめ
メタタグはWebページ上では直接見えませんが、検索エンジンやSNSにページの情報を正確に伝えるための大切な要素です。
特にdescriptionやtitleなどのタグは、検索結果の表示内容やクリック率に大きく関係します。
文字数の適正やキーワードの自然な使い方を意識することで、より読みやすく伝わるページを作ることができます。
一方で、同じタグを重複して記述したり、誤って「noindex」などを設定してしまったりすると、ページが検索に表示されなくなることがあります。
設定後は必ず検索結果やHTMLソースを確認し、内容が意図どおりに反映されているかをチェックすることが大切です。
HTMLに慣れていない方でも、WordPressのプラグインや無料のメタタグ生成ツールを使えば、専門的なコードを書かずに設定できます。
最初は基本のタグだけでも十分効果があり、正しく使うことでWebサイト全体の信頼性や検索評価の向上につながります。
難しく考えすぎず、一つずつ理解しながら実践していくことで、メタタグを活かしたサイト運営ができるようになります。
小さな工夫の積み重ねが、長期的に見て大きな成果を生み出すポイントです。
メタタグの確認方法と設定については下記で詳しく紹介しています。