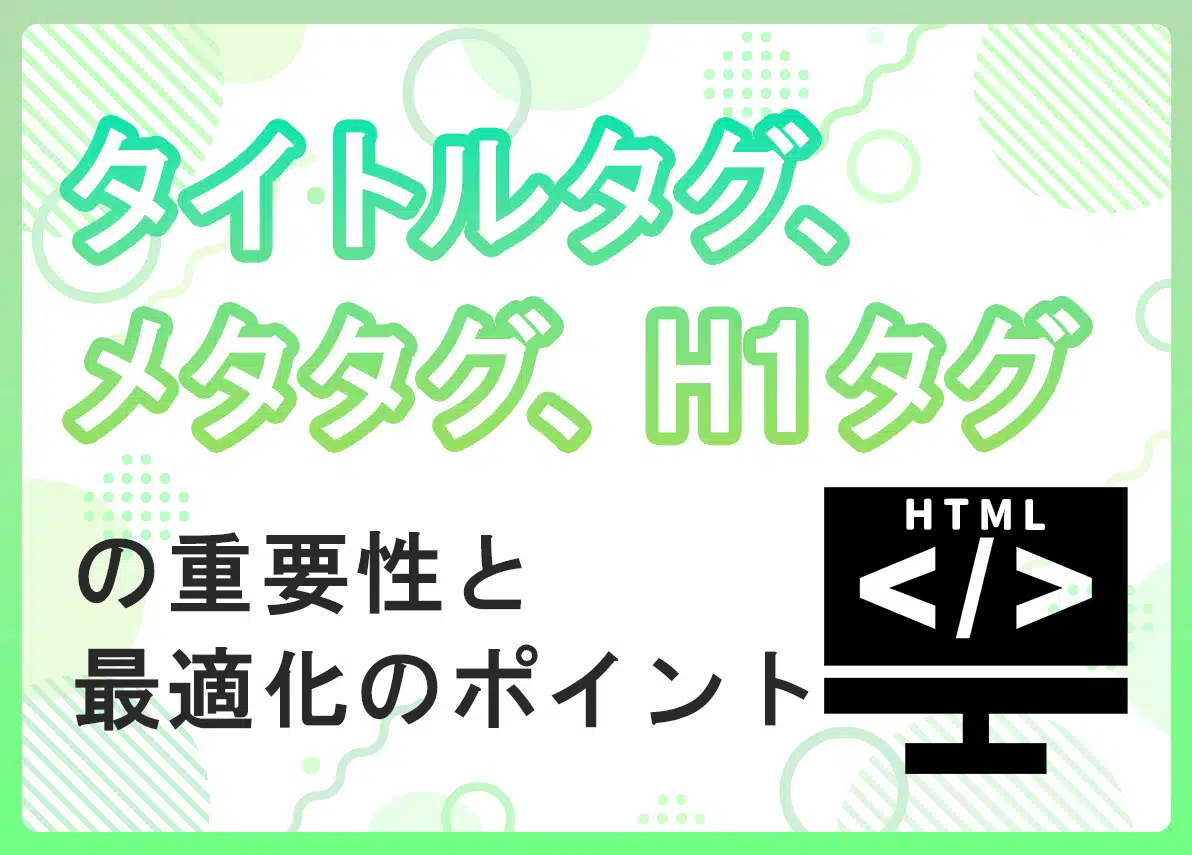Webサイトを公開したあと、「どうすれば検索結果で自分のページが上位に表示されるのか」と疑問に思ったことはありませんか。
そんなときに関係してくるのがメタタグという小さなタグです。
メタタグはページの情報を検索エンジンへ正確に伝えるための仕組みで、設定内容によって検索順位やクリック率が変わることもあります。
初めて耳にする方には少し難しく感じるかもしれませんが、実際には基本を理解すれば簡単に扱うことができます。
この記事では、Web初心者の方にもわかりやすいように専門用語をやさしく解説し、SEO対策としてのメタタグの役割や設定の考え方を丁寧に紹介します。
メタタグとは?SEOとの関係をわかりやすく解説

メタタグってなに?初心者にもやさしく解説
メタタグとは、Webページの表面には見えない情報を記述するためのタグで、検索エンジンやブラウザにそのページの内容や性質を伝える役割を持っています。
ページの説明文や使用している文字コード、検索エンジンに掲載するかどうかなどの情報が含まれます。
これらはWebページのHTML構造の中でも、特に<head>部分に記述されるのが一般的です。
たとえば、次のようなタグでページの概要を示すことができます。
<meta name="description" content="Webマーケティングの基本を初心者にもわかりやすく紹介します。">このように「description」属性にページの説明文を設定することで、検索エンジンにそのページがどんな内容なのかを正確に伝えることができます。
2025年現在もこの仕組みは変わらず、Googleをはじめとした主要検索エンジンが情報を理解するうえで重要な要素のひとつです。
SEO対策とのつながりとは?
SEO(検索エンジン最適化)は、Webページを検索結果で上位に表示させるための取り組みを指します。
メタタグはその中で、ページ内容を正確に伝えるための基礎となる存在です。
検索エンジンはコンテンツ本文だけでなく、メタタグの情報もあわせて読み取り、評価を行います。
特に次のような要素が評価に影響すると考えられています。
- ページの説明がユーザーの検索意図と合っているか
- 不要なページを検索結果に含めていないか
- 文字コードが正しく設定され、情報が正確に読み取れるか
つまり、メタタグは検索エンジンにとって案内板のような役割を果たします。
正確でわかりやすい設定がされていればページ全体の評価が高まり、クリック率向上にもつながります。
「検索結果に表示される情報」の仕組み
検索結果で表示される「タイトル」や「説明文」は、多くの場合メタタグの内容をもとに作られています。
特によく使われるのが次の2つです。
- titleタグ
ページタイトルを表示 - descriptionタグ
ページの説明文を表示
ただし、Googleなどの検索エンジンは、ページの内容や検索キーワードとの関連性を考慮し、自動で別の文章を抜粋することもあります。
そのため、descriptionタグの内容が常にそのまま反映されるとは限りません。
それでも、メタタグに適切な説明を記述しておくことで、検索エンジンとユーザーの双方にページ内容を正確に伝えられる可能性が高まります。
特にdescription文が読みやすく魅力的であれば、検索結果からクリックされる確率も上がります。
メタタグはなぜWebサイトに必要なの?
メタタグはサイトの裏側にある情報ですが、Webサイト運営において欠かせない要素です。
メタタグがない、あるいは誤った内容が書かれていると次のようなトラブルを招くことがあります。
- ページの内容が正しく検索エンジンに伝わらない
- 検索結果に誤った説明が表示される
- 不適切な文字コード設定により文字化けが発生する
- クロール(検索エンジンの巡回)が正常に行われない
特に以下のようなケースでは、メタタグの設定が重要になります。
- 新しくWebサイトを公開したとき
- ページ数が多く、インデックス対象を整理する必要があるとき
- 他社と差別化できる説明文を設定したいとき
さらに、SNSでページをシェアした際の見え方にも影響します。
OGPタグ(Open Graph Protocol)などと組み合わせることで、SNS上での表示内容もコントロールでき、ユーザーエクスペリエンスの向上にもつながります。
メタタグは一度設定して終わりではなく、ページ内容の変化に応じて定期的に見直すことが大切です。
正確で最新の情報を保つことで、SEO対策の効果を持続させることができます。
メタタグの代表的な種類と役割を知ろう

meta name=”description”ってどんなタグ?
descriptionタグは、ページ内容を短くまとめて説明するためのタグです。
検索結果では説明文として使われることが多く、ユーザーにページの概要を伝える重要な役割を持っています。
検索キーワードと一致する部分が太字になることもあり、クリック率に影響を与えることがあります。
ページの魅力を的確に伝えることで、訪問してもらえる可能性が高まります。
記述の基本形式は次の通りです。
<meta name="description" content="このページではメタタグの基本と使い方を初心者向けに解説しています。">descriptionに書く内容はページごとに異なるため、すべてのページで個別に考えて作成することが重要です。
文字数はおおよそ80〜120文字が目安ですが、2025年現在ではスマートフォンの検索結果で表示幅が異なるため要点を簡潔にまとめることが推奨されています。
特にGoogle検索では、説明文の内容がユーザーの検索意図と一致している場合に優先的に表示されやすい傾向があります。
titleタグとの違いとは?
titleタグはページのタイトルを指定するタグで、ブラウザのタブや検索結果の見出し部分に表示されます。
訪問者がページ内容を判断する目印となり、SEO評価にも大きく影響します。
検索結果では、titleとdescriptionが並んで表示されることが多く、どちらもクリック率に関係します。
meta descriptionとの主な違いは次の通りです。
- 表示場所
titleは見出し、descriptionは説明文 - 役割
titleは検索エンジンへの強いアピール要素、descriptionはユーザーへの説明 - 書き方
titleはシンプルに、descriptionは補足的に
どちらのタグもページ内容と一致していることが前提です。
関係のない言葉を詰め込みすぎると、検索エンジンの評価が下がる場合があります。
keywordsタグの今の役割
かつてはSEO対策の定番だったkeywordsタグですが、現在GoogleやBingなど主要検索エンジンはこの情報をランキング要因として評価していません。
そのため、無理に設定する必要はありません。
ただし、企業内検索システムやCMSの内部検索など、限られた環境では参考情報として役立つ場合があります。
また、WordPressやMovable Typeなど一部のCMSでは入力欄が残っているテーマもありますが、空欄のままでも問題ありません。
整理目的で利用する場合は、次のように記述します。
<meta name="keywords" content="メタタグ, SEO, 記述, タグ, 初心者向け">現在はkeywordsよりもtitleやdescriptionを重視し、これらを最適化することが効果的なSEO対策につながります。
robotsタグでやること・やらないことを決める
robotsタグは、検索エンジンに対してページをどのように扱うかを伝えるタグです。
「このページは検索結果に表示してよい」「このリンクはたどらないでほしい」といった指示を与えることができます。
よく使われる指定は次の通りです。
- index 検索結果に掲載してOK
- noindex 検索結果に表示しない
- follow ページ内のリンクをたどる
- nofollow リンクをたどらないよう指示
これらは組み合わせて使うことができます。
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">特に、会員専用ページやテストページなど、検索に出したくないページではnoindexを設定します。
robots.txtでサイト全体を制御する方法もありますが、robotsタグを使うことでページ単位で細かく指定できるため、柔軟性があります。
各タグが果たす役割をわかりやすく整理
メタタグは種類ごとに明確な目的を持ち、SEOとユーザーエクスペリエンスの両面に関係しています。
主な役割は次の通りです。
- descriptionタグ
ページの魅力を簡潔に伝える - titleタグ
検索結果での第一印象を作る - robotsタグ
不要なページを非表示にしてクローラビリティを最適化する - keywordsタグ
現在はSEOに影響しない補助的な情報
検索エンジンはページ内容や構造だけでなく、メタタグの使い方も評価対象としています。
正確で整ったメタタグを設定することで検索エンジンに正しく理解され、より多くのユーザーに見つけてもらいやすいWebサイトを作ることができます。
検索エンジンに伝えるためのmetaタグ設定方法

どこに書く?metaタグの設置場所(head内)
metaタグは、WebページのHTML内にある<head>部分に記述します。
この部分には、ページタイトルやスタイル情報、JavaScriptの読み込み、文字コードの指定など、ページ全体を説明するための重要な情報がまとめられています。
metaタグがheadの中に置かれる理由は、ページが表示される前に検索エンジンやブラウザが必要な情報を取得するためです。
もしmetaタグを<body>内に書いてしまうと検索エンジンが認識せず、SEO効果が反映されないため注意が必要です。
以下は、head部分に記述するmetaタグの例です。
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="SEO対策に必要なメタタグの設定方法を初心者向けに解説します。">
<title>メタタグの基本と設定手順【2025年最新版】</title>
</head>このようにhead内に配置することで、検索エンジンが正確に内容を理解できるようになります。
HTMLの基本構造を守ることが、SEOの第一歩です。
HTMLでの書き方の基本ルール
metaタグはHTMLタグの一種で、自己完結型のタグです。
開始タグと終了タグを分けずに、1行で完結して書くのが正しい形式です。基本構造は次の通りです。
<meta name="〇〇" content="△△">それぞれの意味は次のようになります。
- name メタ情報の種類(descriptionやkeywordsなど)
- content 実際に検索エンジンへ伝える情報
HTML5では、文字コードを指定する場合は以下のように記述します。
<meta charset="UTF-8">metaタグのスペルミスや記号の抜けは、検索エンジンが内容を正しく読み取れない原因となります。
特にdescriptionやrobotsなどは間違えやすいため、入力時には注意しましょう。
サイト全体とページごとの使い分け
metaタグはページ単位で設定するのが基本です。
すべてのページで同じdescriptionやtitleを使い回すと、検索エンジンが「重複コンテンツ」と判断し、SEO評価が下がる可能性があります。
ページごとにmetaタグを設定することで、次のようなメリットがあります。
- 検索結果で各ページの説明文が内容に合ったものになる
- クリック率が上がる可能性が高まる
- ロングテールキーワードにも対応できる
たとえば、同じサイト内でも「サービス紹介ページ」と「ブログ記事」では目的が異なります。
それぞれに合った説明文を設定することでユーザーが求める情報にたどり着きやすくなり、ユーザーエクスペリエンスも向上します。
WordPressでの設定方法
WordPressを利用している場合、HTMLを直接編集しなくてもmetaタグを設定できます。
代表的なプラグインには「All in One SEO Pack」や「Yoast SEO」などがあります。
たとえばYoast SEOでは投稿画面の下部にmeta descriptionの入力欄があり、そこに説明文を入力するだけでHTMLのhead内に自動反映されます。
また現在は日本語対応も改善され、プレビュー機能で検索結果の見え方を確認できるようになっています。
テーマによっては、管理画面の「SEO設定」項目からdescriptionやkeywordsを入力できるものもあります。
テーマやプラグインの説明書を確認し、自分の環境に合った方法を選びましょう。
設定後はブラウザで該当ページを開き、右クリックから「ページのソースを表示」を選んで確認します。
head内にmetaタグが正しく挿入されていれば設定完了です。
metaタグを設定するときのチェックポイント
metaタグを効果的に活用するためには、次のポイントを意識しましょう。
- ページ内容とmeta descriptionの内容が一致しているか
- 文字数が80〜120文字程度で収まっているか
- キーワードを自然に含めているか
- 無理な詰め込みや同じ文の使い回しをしていないか
- head内に正しい構文で記述されているか
現在ではモバイル検索の表示が主流のため、スマートフォンでも読みやすい文構成を意識することが大切です。
metaタグは検索エンジンだけでなく、ユーザーにとってもページ内容を判断する重要な情報源です。
正しい位置に、適切な内容を記述することがSEO対策の基本となります。
SEO対策として有効なメタタグの書き方とポイント

ユーザーが読みたくなる説明文の作り方
meta descriptionは、検索結果でタイトルの下に表示される短い文章で、クリック率を左右する重要な要素です。
検索結果を見ている人が「このページに自分の探している情報がある」と感じるかどうかで、アクセス数が変わります。
効果的な説明文の特徴は次の通りです。
- ページの内容を簡潔に要約している
- 興味を引く自然な表現を使っている
- 検索キーワードが自然に含まれている
- 読み終わると行動を促すように構成されている
たとえば「SEOの基本をやさしく解説。初めての方でも実践できる設定方法を紹介します」といった文は、初心者にもわかりやすく効果的です。
現在ではGoogleがAIによって検索意図をより正確に理解するようになったため、説明文の自然さと関連性がより重視されています。
ページ内容に合ったメタタグを書くコツ
メタタグは単なる文章ではなく、そのページだけの情報を検索エンジンへ伝える役割を持ちます。
どんなに魅力的な文章でも、ページ内容と一致していなければ離脱されてしまう可能性があります。
以下の点を意識して作成しましょう。
- ページ内容とmeta descriptionの整合性を保つ
- 実際のページで使用されているキーワードを自然に含める
- 同一サイト内で文面を使い回さない
検索エンジンは本文とメタタグを照らし合わせて整合性を評価します。
意図しないキーワードの過剰使用は逆効果になるため、自然な日本語で伝えることを意識することが大切です。
文字数の目安と改行に注意
meta descriptionは80〜120文字前後が目安です。
長すぎると検索結果で途中で切れてしまい、内容が伝わりにくくなります。
また、HTML上で改行しても検索結果では1行で表示されるため、読みやすい語順と文構成を意識してください。
ポイントは次の通りです。
- ひとつの文で完結させるようにする
- 「、」や「。」などで区切りを入れて読みやすくする
- 無理に情報を詰め込みすぎない
Google検索ではPCとスマホで表示文字数が異なるため、主要情報を文の前半に入れると読みやすくなります。
よくあるNG例とその対処法
metaタグでよくあるミスには、検索エンジンの評価を下げる原因が含まれています。
次の行為は避けましょう。
- 関係のないキーワードを羅列している
- すべてのページで同じdescriptionを使用している
- 内容があいまいで何を伝えたいのかわからない
これらを防ぐには、ページごとに固有の説明文を作成することが基本です。
設定内容はブラウザの「ページのソースを表示」で確認でき、Google Search Consoleの「検索での見え方」レポートでも確認可能です。
最新仕様では、AIが自動で生成した説明文を採用することもあるため、metaタグの内容が正確であることがより重要になっています。
サイト全体のメタタグを一貫させるメリット
Webサイト全体でmetaタグの方針を統一すると、検索結果での印象が整い、ユーザーエクスペリエンスも向上します。
統一のポイントは次の通りです。
- タイトルと説明文の構成をテンプレート化する(例:「〇〇|サービス名」)
- 文体やトーンをそろえる(です・ます調で統一)
- キーワードの優先順位を決める(ビッグキーワードとロングテールキーワードの使い分け)
このように共通ルールを決めておくことで、改善や更新の際にも効率よく進められます。
サイトの目的や読者層が変化した場合は、定期的にルールを見直すことが大切です。
見落としがちなタグの効果も知っておこう
metaタグにはdescriptionやrobots以外にも、SEOや表示品質を支える重要なタグがあります。
- charsetタグ 文字コードを指定し、文字化けを防ぐ
- viewportタグ スマートフォンやタブレットでの表示幅を調整する
- refreshタグ 指定した時間後にページを自動更新・リダイレクトする
これらは直接SEOスコアに影響しない場合もありますが、サイトの快適さや見やすさを整えることで、結果的に検索評価に良い影響を与えます。
特にモバイルユーザーが中心の現在では、viewportタグの設定が欠かせません。
未設定のままだとページ全体が縮小表示され、ユーザーが離脱する原因になるため、必ず確認しておきましょう。
Googleに適切に伝えるための設置時の注意点

Googleが読み取るmeta情報の優先順位
GoogleはWebページを評価する際、metaタグの情報を重要な判断材料として確認します。
ただし、すべてのタグを同じ重みで評価しているわけではなく、特に重視する項目には一定の優先順位があります。
現在、Googleが注目する主な順序は次の通りです。
- titleタグ
検索結果の見出しに表示されるため、最も重要 - meta description
検索結果の説明文として使用されるが、内容が不適切だと自動生成される場合もある - robotsタグ
検索エンジンの巡回やインデックスの制御に直接関わる - charsetタグ
文字コードを読み取ることで、ページの文字化けを防止 - viewportタグ
スマホ表示での見やすさを決める
特にtitleとdescriptionは、検索結果でユーザーがクリックするかどうかを左右するため、正確でわかりやすい内容にしておくことが大切です。
タイトルにはキーワードを自然に含め、説明文ではページ内容を簡潔に伝えることが効果的です。
noindexやnofollowの正しい使い方
robotsタグに設定する「noindex」「nofollow」は、Googleに対してページの扱い方を伝えるための命令文です。
設定を誤ると、重要なページがインデックスされず非表示になってしまうことがあります。
よく使われる場面は次の通りです。
- noindex
検索結果に掲載させたくないページに使用します。
会員限定ページや仮ページ、テストページなどが該当します - nofollow
そのページ内のリンクをGoogleにたどらせたくないときに使用します。
広告リンクや信頼できない外部リンクなどが対象になることがあります
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">これらを同時に使うこともできますが、すべてのページに設定するとサイト全体が検索結果から除外される可能性があるため注意が必要です。
大切なのは、インデックスさせるべきページとそうでないページを明確に分けることです。
タグの書き間違いが招くトラブル
metaタグはHTMLに直接記述するため、わずかな入力ミスでも正しく読み取られないことがあります。
特に次のようなミスに注意が必要です。
- スペルミス(例:descriptionをdescriptonと書いてしまう)
- 属性の指定ミス(例:nameではなくcontentを2回書いてしまう)
- ダブルクオーテーションの閉じ忘れ(content=”説明文が途中で終わる)
- 不要なスペースの挿入(例:
<meta name="robots" content="noindex , nofollow">)
こうしたエラーは、Googleに正しく認識されずSEO効果が得られない原因になります。
記述後はチェックツールを使って確認するのが確実です。
確認に便利なツールは次の通りです。
- Google Search Console
インデックス状況やエラーの有無を確認できる - W3C Markup Validation Service
HTML構文エラーを検出できる
すでにあるメタタグの確認方法
CMS(WordPressなど)を利用している場合、metaタグは自動的に生成されることがあります。
意図した内容になっているかを確認するには、次の方法が有効です。
- ブラウザの右クリックメニューから「ページのソースを表示」を選び、head内を確認する
- Google Chromeの開発者ツール(右クリック→「検証」→「Elements」タブ)を使って、metaタグの内容を見る
- Chrome拡張機能「META SEO inspector」などを利用して、meta情報を一覧表示で確認する
特にdescriptionやOGPタグは、実際にどんな文が出力されているかを目視でチェックすることが重要です。
ツールを併用すれば、出力の抜け漏れや重複を防ぐことができます。
検索結果に反映されるまでの時間感覚
metaタグを修正しても、変更が検索結果に反映されるまでには時間がかかります。
Googleのクロールとインデックス更新が完了して初めて内容が反映されます。
反映までの一般的な目安は次の通りです。
- 数時間〜数日
更新頻度の高いサイトやトップページ - 1週間〜2週間程度
一般的な更新頻度のページ - それ以上かかる
新しく公開されたページ、低頻度のページ
反映を早めたい場合は、Google Search Consoleの「URL検査」ツールから「インデックス登録をリクエスト」する方法が有効です。
また、古い情報が表示され続ける場合は、ブラウザやGoogleのキャッシュが影響している可能性があります。
シークレットモードや別のデバイスで確認すると、最新の情報を確認できます。
metaタグは表には見えませんが、検索結果での見え方を大きく左右します。
正確に設定し、定期的に確認・更新を行うことが、SEO対策の基本です。
まとめ
メタタグは、Webページの見えない部分にありながら、検索エンジンにもユーザーにも重要な情報を伝える役割を持っています。検索エンジンにページ内容を正しく理解させたり、検索結果でどんな説明文を表示するかを指定したりすることで、サイトの見え方やクリック率に大きく影響します。
特にdescriptionタグやtitleタグは検索結果に直接反映されるため、ページの第一印象を決める重要な要素です。また、OGPタグを活用すればSNSでシェアされた際の見た目も整い、より多くのユーザーにページ内容を伝えやすくなります。
metaタグを設定するときは、内容がページと一致しているか、文字数が適切か、記述ミスがないかを必ず確認しましょう。
WordPressを使用している場合は、All in One SEOやYoast SEOなどのプラグインを使えば、専門知識がなくても簡単に設定できます。
2025年現在、GoogleはAIによる検索意図の解析をより重視しているため、メタタグにも自然でわかりやすい表現が求められています。
難しく感じるかもしれませんが、基本を理解して丁寧に設定すれば、検索エンジンにもユーザーにも伝わる質の高いWebサイトを作ることができます。
メタタグは、検索結果で選ばれるサイトへと導く最初の一歩です。
タイトルタグ、メタタグ、H1タグの重要性と最適化のポイントについては下記で詳しく紹介しています。