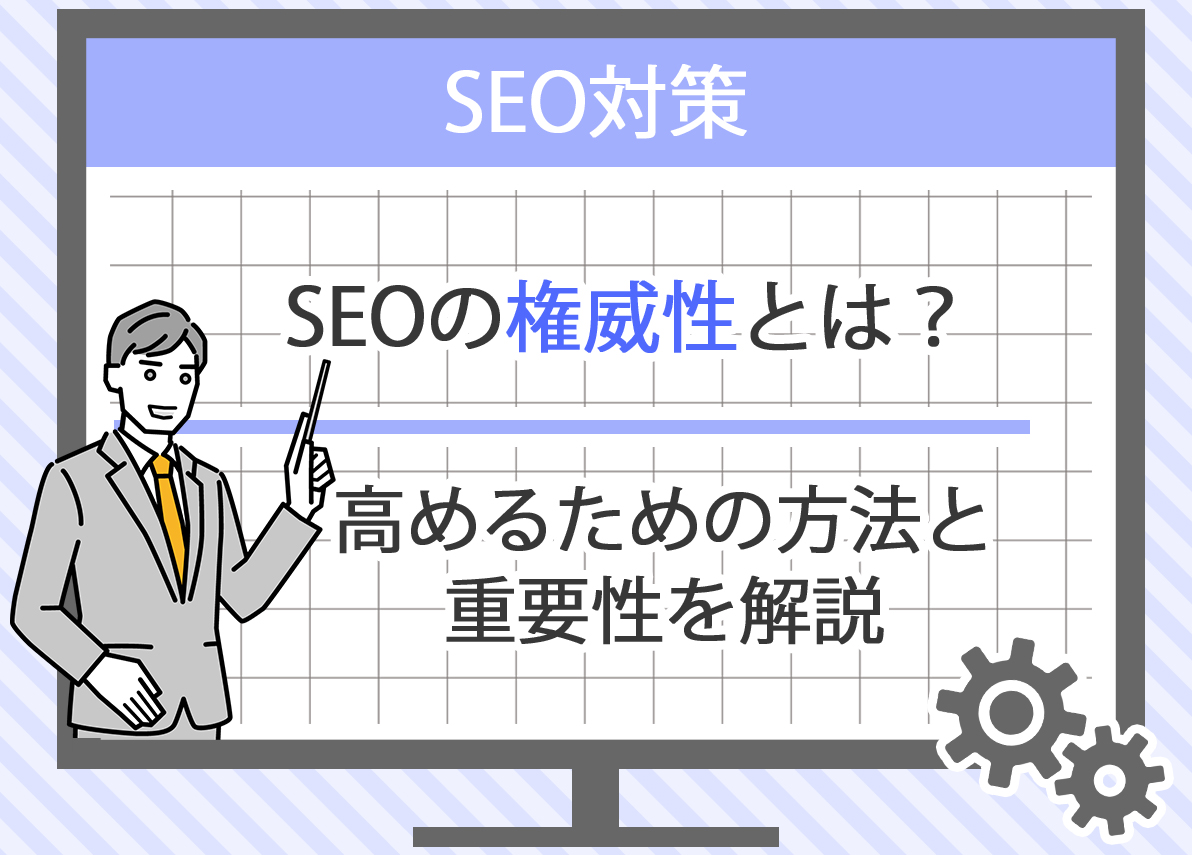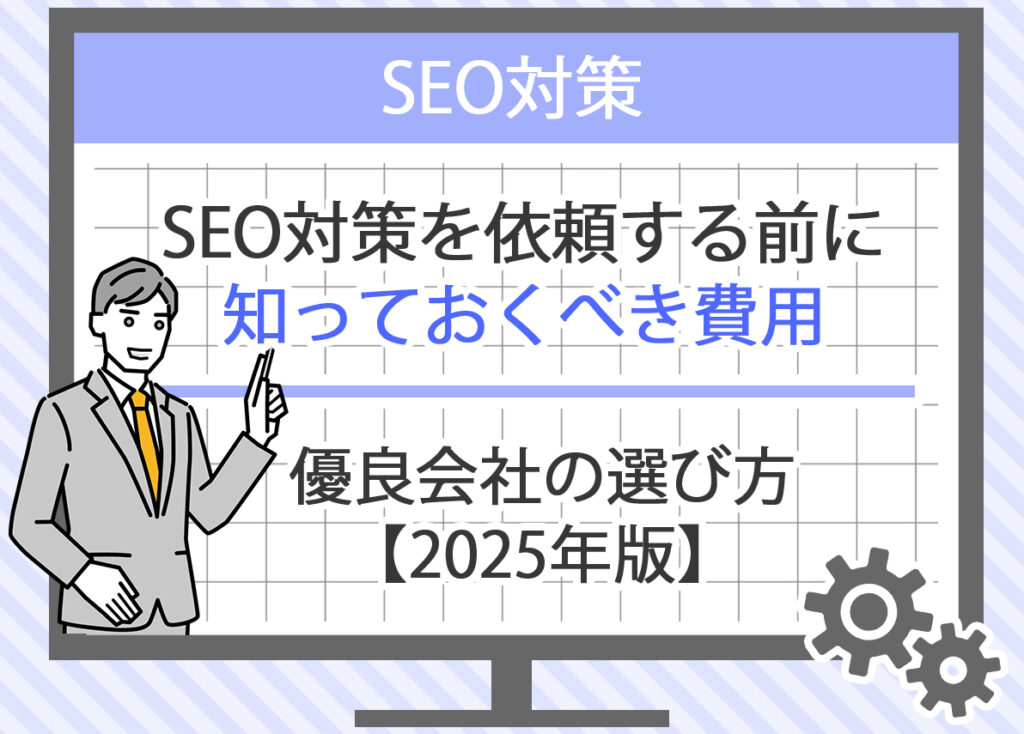
「ホームページを作ったのにアクセスが伸びない」
「Google検索で自社サイトが出てこない」
そんな悩みを抱えていませんか。
サイト運営で成果を上げるには、search engine optimization、つまりSEO対策が欠かせません。
とはいえ仕組みが複雑で、どの会社に依頼すれば良いのか判断が難しいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、SEOコンサル会社へ依頼する際の流れや費用、成果につながる選び方を2025年の最新情報を交えて解説します。
AIを活用した分析や現状分析のポイントも紹介しており、初心者でも安心して理解できる構成です。
外注を検討している方やインハウスでSEOを始めたい方にも役立つ内容になっています。
SEOを外注するメリットとデメリットを解説

プロに任せることで得られるメリット
SEOの外注とは、検索結果で上位表示を目指すための施策を専門の会社やコンサル業者に任せることを指します。
AIやデータ分析技術が進化した2025年現在では、外注の質や手法も大きく向上しています。
自社では難しい分析や改善を、専門家が一貫した流れでサポートしてくれる点が魅力です。
主なメリットは以下の通りです。
- 専門的な知識と経験がある
Google アナリティクスやサーチコンソール、検索エンジンのアルゴリズム、内部・外部施策など、SEOは複雑です。
外注先の専門家はKPI設定やUX設計も踏まえて、正確で高品質な対策を実施します。 - 最新の検索ルールに対応できる
Google検索の仕組みはAI導入により変化が速く、2025年も継続的なアップデートが行われています。
信頼できるSEO会社は、最新情報をもとに最適な対応を提案します。 - 社内の時間とコストを削減できる
自社でSEOを内製化するには、専門人材の採用や教育やツール導入費などが必要で、少なくとも月間数十時間の作業負担が発生します。
外注すれば人的コストを削減し、他業務に集中できます。 - 客観的な視点から改善提案をもらえる
自社サイトに慣れていると気づきにくい課題も、第三者の専門家による現状分析で新たな改善点が見つかります。 - コンテンツ制作やライティングも任せられる
SEO会社では、ロングテールキーワードを盛り込み、ユーザーエクスペリエンスを意識した構成で記事を作成します。
特にオウンドメディアの運営やLP制作、動画活用を含む提案も増えています。
これらにより、自社にSEO担当が在籍していなくても外注によって効率的かつ短期間でCVを高めることが可能です。
外注のデメリットとは?失敗を避けるために
一方で、SEOを外注する際には注意点もあります。
契約形態や方針を誤ると、成果が出ないどころか検索評価を下げる危険もあります。
主なデメリットは以下の通りです。
- 社内にノウハウが蓄積されにくい
外注に任せきりだと、知識やスキルが社内に残らず、将来的なインハウス化が難しくなります。 - 成果が出るまで時間がかかる
SEOは即効性が低く、最低でも3〜6ヶ月は継続が必要です。
AI分析による支援で短縮されつつあるものの、短期間で順位を上げる保証はありません。 - 契約内容が不透明な業者もある
作業項目が曖昧なまま高額契約を結ばせる業者も存在します。
作業範囲、期間、費用、成果基準を明示することが重要です。 - ブラックハットSEOのリスク
自動生成リンクや過剰な被リンクなど、ガイドライン違反の手法で順位を一時的に上げる業者もいます。
これによりペナルティを受けると、順位回復に数ヶ月以上かかるケースもあります。
こうした失敗を防ぐには、実績の提示や説明のわかりやすさ、品質管理体制の有無を必ず確認してください。
特に契約前には、レポート例や作業表を見て透明性をチェックすることが大切です。
自社でやるより費用対効果が高い理由
外注費用は10万〜100万円前後まで幅広く、契約形態も月額制や成果報酬制など多様です。
高く感じるかもしれませんが、トータルで見ると費用対効果が高いケースも少なくありません。
自社でSEOを始める場合は、以下の準備が必要です。
- 専門人材の採用または育成
- ツール導入(Google アナリティクス、Search Console、AI分析ツールなど)
- コンテンツ制作体制の構築
- 定期的な現状分析と改善サイクルの実施
これらには時間とコストがかかりますが、外注であればすでに整ったシステムを活用し、短期間で成果を出すことが可能です。
さらに、CV向上やKPI達成を目的とした具体的な施策を提案してもらえる点も強みです。
外注すべきか判断するためのチェックポイント
SEOの外注が向いているかどうかは、社内のリソースと目標達成までの体制で判断します。
- Web担当者が1人、または兼任している
- SEOやコンテンツ設計の知識が不足している
- 既存の広告費が高く、費用削減を検討している
- オウンドメディアの更新や記事作成が追いつかない
- 競合他社が上位に表示されている
これらの項目に複数当てはまる場合は、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
複数のSEO会社を比較し、相性や提案内容を見極めてから契約することで、確実に効果を高めやすくなります。
SEO会社へ依頼する際の流れと準備しておくこと

依頼前に整理すべき「目的」と「目標」
SEO対策を外部のコンサル会社へ依頼する際は、まず自社の「目的」と「目標」を明確にすることが大切です。
ここが曖昧だと、相手がどれだけ専門家でも正確な提案ができず、費用や作業内容が合わない可能性があります。
目的は方向性を示す指標、目標は成果を測るための数値です。
- 目的
なぜSEOを行うのか(アクセスを上げたい、問い合わせやCVを増やしたいなど) - 目標
どのくらいの成果を目指すのか(例:月間訪問者数を1.5倍、CV数を月20件に達成など)
このように具体的な数値を設定することでKPIが明確になり、SEO会社も施策の優先順位を立てやすくなります。
目標はGoogle アナリティクスやサーチコンソールなどのデータを使い、定量的に測定できるものを選ぶとよいでしょう。
目的と目標を整理しておくことは、施策を一貫した方向で進めるための基盤となります。
打ち合わせ前に準備しておきたい情報
初回打ち合わせの前に以下の項目を社内でまとめておくと、相談がスムーズに進みます。
SEO会社側も精度の高い提案を出しやすくなります。
- 現在のサイトURLや構成
サイトマップや主要ページの一覧を共有 - 更新の頻度や体制
誰が更新を担当しているか、外注か社内対応か - 過去の対策歴
過去にSEO施策やWeb広告を行った履歴、使用したツールや外注内容 - 狙いたいキーワード
検索でどの言葉に表示されたいか(短期と長期の両方を設定) - 現在の課題
CV率が低い、アクセスが伸びない、特定の層に届いていないなど
CMS(WordPressなど)を使用している場合は、そのシステム名も必ず共有しましょう。
SEO会社は、CMSや契約形態、管理権限の範囲によって作業可能な内容を判断します。
現状分析や改善提案を依頼する際にも、これらの情報が揃っていると短期間で的確な診断が可能です。
どんな資料があるとスムーズ?
相談時に提出できる資料があると、提案の品質が大きく上がります。
以下のような資料をPDFやスプレッドシート形式でまとめておくのが理想です。
- 現状のアクセスデータ
Google アナリティクスやサーチコンソールのデータ - 過去に発注したWeb制作会社の仕様書やレポート
- 自社の商品・サービス内容が分かるパンフレットや説明資料
- 競合サイトの情報
よく検索で見かける上位企業や同業他社のURL
特に、競合分析の観点からは「どの企業を目標にするか」「どの層を狙いたいか」を明示できると効果的です。
もし資料が不足していても、最低限ホームページURLと現状の希望を伝えるだけで相談は可能です。
資料提出時はデジタル形式で渡すと、SEO会社側でAIツールを活用して解析がしやすくなります。
初回相談でよく聞かれる内容とは
初回の相談では、SEO会社の担当者から以下のような質問をされることが一般的です。
事前に整理しておくと、より具体的な提案を受けられます。
- 自社の事業内容と提供している商品・サービス
- 想定しているターゲット層や地域
- 現在のWebサイトの課題や悩み
- SEO以外に行っている集客施策(Web広告、SNS、紙媒体など)
- 上位表示を狙いたいキーワード
- 社内で修正・更新ができる担当者の有無
- SEO対策に充てられる予算の目安
これらの質問は、SEO会社が提案内容を具体化するための重要な項目です。
まだ予算や施策内容が決まっていない場合でも、そのまま率直に伝えて問題ありません。
信頼できる会社であれば、契約を急がせたり高額なプランを押しつけたりすることはありません。
むしろ、長期的に伴走できる形を一緒に探してくれます。
依頼先を選ぶポイントとは?信頼できる業者の特徴

信頼できるSEO会社の見分け方
SEO会社を選ぶときに最も重要なのは、信頼できる業者かどうかを見極めることです。
見た目の印象や料金だけで判断すると、契約後に「思っていた結果と違う」と感じるケースもあります。
2025年現在ではAI分析や自動レポート生成を導入する企業も増えており、技術力の差が成果に直結します。
そのため、担当者の専門性や説明の丁寧さを確認することが欠かせません。
信頼できる会社かどうかを判断する主なポイントは以下の通りです。
- 実際の施策内容を丁寧に説明してくれる
専門用語を避け、作業項目を具体的に説明してくれる業者は信頼性が高いです。
内容を理解させる姿勢があるかどうかも重要です。 - 「短期間で順位が上がる」と断言しない
SEOは短期間で結果が出る施策ではありません。
AIを活用した分析でも上位表示までには一定の時間がかかります。
「すぐ上がります」と言い切る業者は注意が必要です。 - 継続的な改善提案がある
単発の対策で終わらず、定期的に現状分析と改善を行う体制があるかを確認しましょう。
月間レポートやKPI報告がある会社は信頼度が高いです。 - 透明性のある報告体制
作業内容・実施日・効果測定を明示したレポートを提出しているかどうかを確認します。
数字や表を活用して説明する企業は信頼できます。 - 契約内容が明確で柔軟
契約形態が月単位か、途中解約ができるか、成果報酬型かどうかを確認しましょう。
契約条件の説明が丁寧な会社ほど安心です。
初回のヒアリングでの対応や、資料の品質、説明のわかりやすさも重要な判断基準になります。
担当者とのコミュニケーションの相性も見極める要素の一つです。
実績があるかどうかのチェック方法
SEO会社の信頼性を測るうえで、過去の実績をどのように公開しているかは重要な判断材料です。
特に成果事例の具体性や透明性を確認しましょう。
単なる「実績多数」という記載だけでは、効果を判断することはできません。
実績のチェックポイントは次の通りです。
- 成果事例の公開があるか
どの業種のクライアントとどのような施策を実施したのか、CV率やアクセス増加率などを具体的に示しているかを確認します。 - 数値データや表で改善内容を示しているか
数値の変化が明確なほど信頼性が高く、分析力のレベルを判断できます。 - 第三者メディアや公的資料で紹介されているか
メディア掲載や認証を受けた企業は、一定の品質基準を満たしていることが多いです。 - クライアントの声や評判を公開しているか
実名または企業名付きでコメントを掲載している場合、信ぴょう性が高いといえます。
また、信頼できるSEO会社は単なる成功事例だけでなく、どのように課題を解決したのか、要因分析を具体例として説明してくれることが多いです。
BTB・BTCなど、企業規模や業界ごとに異なるケースを複数紹介している会社は応用力も期待できます。
提案内容で見る「プロらしさ」
見積もりと一緒に出される提案書には、その会社の技術力や理解度が表れます。
単なるテンプレート資料ではなく、自社の課題や運営状況に合わせた提案ができているかを確認しましょう。
プロらしい提案の特徴には以下のような項目があります。
- 自社の課題に合わせた内容になっている
競合との比較分析や現状診断を踏まえた提案であること。
サイト規模や更新頻度などを考慮しているかも重要です。 - キーワード選定の根拠が明確
検索ボリュームや競合度を表にまとめ、ビッグキーワードとロングテールキーワードをどう使い分けるかの説明があるかを確認します。 - ユーザーエクスペリエンスを重視している
コンテンツの構成やデザイン面など、UX改善を重視した提案が含まれているかがポイントです。 - Googleガイドラインに準拠している
ブラックハットSEOのようなリスクのある手法を避け、AI分析や自然な被リンク獲得を中心とした正攻法であるかを確認します。
また、提案書に動画やサイトマップや改善イメージ図などを盛り込む企業は、施策の全体像を視覚的に伝える工夫をしています。
これもプロ意識の高さの表れです。
契約前に確認したい5つのこと
契約を結ぶ前には、トラブルを防ぐために次の5点を必ず確認してください。
- 契約期間と解約条件
長期契約の縛りがないか、途中解約が可能かを確認します。 - レポート提出の頻度と内容
月間レポートに順位・アクセス・CV・KPIが含まれているかをチェックします。 - 作業内容の具体性
内部リンク設置やタイトル修正など、どの作業を誰が行うのか明示されているか確認しましょう。 - 費用に含まれる範囲
初期費用・月額・成果報酬の明細を明示してもらいましょう。
特に15万円前後のプランにはオプションが含まれるか確認が必要です。 - 対応体制と連絡の速さ
質問へのレスポンスが早いか、担当者の配置が明確かをチェックします。
契約形態や金額だけで判断せず、担当コンサルとのコミュニケーションの取りやすさ、対応品質、運営体制を重視してください。
不明点をそのままにせず、すべて確認してから契約することが、後悔しない依頼につながります。
SEO対策会社の費用相場と見積もりの考え方

SEOにかかる費用はどのくらい?
SEO対策を外部のコンサル会社に依頼する際、最初に気になるのが費用です。
金額は会社の規模や施策内容によって大きく異なりますが、2025年現在の一般的な相場を知っておくことで適切な判断がしやすくなります。
最近ではAIを活用した分析や自動化ツールの導入により、コスト効率を高める企業も増えています。
主な価格帯の目安は次の通りです。
- 月額5万円〜10万円
中小企業や個人事業向け。基本的な内部対策やキーワード選定、月1回のレポート提出などが中心。
初期SEO診断を含むプランもあります。 - 月額10万円〜30万円
中規模〜大規模サイトに多く、コンテンツ制作、内部リンク設計、アクセス解析、UX改善など総合的な施策が実施されます。 - 月額30万円以上
競合の多い業界(BtoBやIT、教育など)や全国展開を狙う場合に多く、AI解析ツールによる現状分析や戦略的なKPI設計が含まれます。
また、単発施策(サイトリニューアル時のSEO設計や構造改善など)は30万円〜50万円程度が一般的です。
記事制作やサイトマップ最適化、動画コンテンツの追加などを含むと、別途オプション費用が発生します。
重要なのは「費用の総額」ではなく、「どんな作業が含まれているか」「成果測定をどこまでしてくれるか」を確認することです。
安すぎる会社には注意が必要
SEO業界では、相場より極端に安い価格を提示する業者も少なくありません。
しかし、こうした業者にはリスクがあるため、注意が必要です。
価格が安すぎる場合に起こりやすいトラブルは以下の通りです。
- 作業内容が不明確で、契約後に実際の対策が行われない
- 自動ツールやAI任せの対策のみで、人的分析や改善提案が行われない
- ブラックハットSEO(自動リンク生成など)を使い、ペナルティを受けて順位が下がる
- 成果レポートがなく、効果検証ができないまま契約が終了する
特に「初期費用0円」「月額1万円未満」などの広告は要注意です。
短期間で順位を上げても、Googleのアルゴリズム更新で一気に下落する可能性があります。
SEOは継続的な運営と品質管理が必要な分野です。
価格と内容のバランスを見極め、担当者の説明が明確かどうかを確認することが大切です。
月額制・成果報酬制の違いとは
SEO対策の費用形態は主に「月額制」と「成果報酬制」に分かれます。
それぞれにメリットと注意点があります。
月額制の特徴
- 毎月一定額を支払い、継続的な運用支援を受けられる
- 内部改善やアクセス解析、レポート提出などが含まれる
- 長期的な戦略設計やブランド構築に向いている
- KPIやCVなどを定期的にチェックしながら改善を続けられる
成果報酬制の特徴
- 「特定のキーワードで順位上昇」「CV達成」などの成果に応じて支払う方式
- 初期費用を抑えやすいが、成果条件や範囲が不明確な場合もある
- 短期成果を優先する傾向があり、長期的なSEO設計が後回しになるケースもある
最近では、月額制と成果報酬制を組み合わせた「ハイブリッド型」も増えています。
例えば、基本運用費を月15万円、成果達成時に追加報酬を支払うといった方式です。
自社の目的(短期間での成果か、安定した運営か)に合わせて、契約形態を選ぶことがポイントです。
見積書でチェックするべきポイント
見積書を受け取った際は、金額よりも「中身」を重視しましょう。
見積書には作業内容と費用配分が明確に記載されている必要があります。
チェックすべき項目は次の通りです。
- 施策ごとの作業内容が記載されているか
タイトル修正、内部リンク設計、構成案の提出など具体的に書かれているかを確認。 - キーワード選定や記事制作の範囲が明確か
対象キーワード数や月間記事数、品質基準を明示してもらうと安心です。 - 成果レポートの頻度と内容
順位変動だけでなく、CV・KPI・アクセス数などを表形式で報告してくれるかを確認。 - オプション費用の有無
サイト修正やフォーム最適化などが基本料金に含まれるかをチェック。 - 契約期間と解約条件
契約更新のタイミングや、途中解約時の費用発生有無を確認します。
SEO対策では、最初の3〜6ヶ月で基礎を固め、その後の分析・改善が成果に直結します。
見積書を確認するときは「どこまでが初期対応」「どこからが運用フェーズか」を明確にすることが、費用の無駄を防ぐポイントです。
価格だけでなく、担当者の説明の丁寧さ、対応の早さ、提案内容の具体性を基準に判断することで、信頼できるSEO会社を見つけやすくなります。
SEO施策の主な内容と成果が出るまでの期間

SEO施策にはどんな種類がある?
SEO施策とは、Google検索などで自社サイトの評価を上げるために行う一連の最適化作業のことです。
検索エンジンに「このページは信頼でき、ユーザーにとって有益だ」と認識させるための工夫を行います。
施策は大きく分けて内部施策と外部施策の2種類があり、どちらも欠かせません。
さらに2025年現在では、AI分析を活用したキーワード抽出やUX(ユーザーエクスペリエンス)の改善など、より精密な対策が求められています。
主なSEO施策の種類は次のとおりです。
- 内部施策
HTML構造やタイトルタグ、メタ情報、サイトマップなどを最適化し、検索エンジンが正しく情報を理解できるように整備する。 - 外部施策
他サイトからの自然な被リンク獲得を通じて信頼性を高める。 - コンテンツSEO
検索ユーザーの疑問や課題を解決する高品質な記事を作成し、滞在時間やCV率を上げる。 - テクニカルSEO
サイト表示速度、モバイル対応、構造化データなど技術面の改善を行う。
これらはどれか一つで完結するものではなく、複数を一貫して行うことが成果への近道です。
特にGoogle検索のアルゴリズムはUXやサイト品質の指標を重視する傾向が強まっており、内部・外部・技術的要素を総合的に高めることが重要です。
コンテンツ作成・リンク対策とは?
SEOの中核を担うのがコンテンツ作成とリンク対策です。
コンテンツは検索ユーザーの意図に合致したテーマを扱い、信頼できる情報を提供することで評価を得ます。
コンテンツSEOで意識すべきポイントは以下です。
- ロングテールキーワードを活用し、特定層のニーズにも応える
- 構成を整理し、読みやすく理解しやすい文章にする
- 専門家の意見や統計データを引用し、信頼性を高める
- UX(ユーザーエクスペリエンス)を重視し、直帰率を下げる
一方のリンク対策は、外部サイトからの推薦を得るような形で評価を高める施策です。
信頼性の高いサイトからのリンクは「このページは価値がある」と判断される重要な要因になります。
リンク対策で注意すべき点
- 自然な形でリンクを得ることを意識する
- 有料リンクや自動生成ツールの使用は避ける
- コンテンツの品質を上げることで自然な被リンクを増やす
Googleのガイドラインに反する行為(ブラックハットSEO)は、短期的に順位が上がっても最終的に評価を下げる要因になります。
継続的に有益な情報を発信することが、最も確実なリンク対策といえます。
結果が出るまでの目安期間
SEOは広告のように即効性がある施策ではありません。
検索エンジンの評価が定着するまでには時間がかかり、結果が出るまでには数ヶ月単位の運用が必要です。
成果が出るまでの目安
- 内部施策を行った場合
2〜3ヶ月で順位に小さな変化が見られる - コンテンツを新規で追加した場合
3〜6ヶ月でアクセスが安定的に増加 - 競合が多いビッグキーワードを狙う場合
6ヶ月〜1年を想定するのが現実的
特にBtoBや全国規模の競争が激しい業界では、成果を出すまでに時間がかかる傾向があります。
ただし、正しい方向性で運営を続ければ、CVや問い合わせ数の増加といった具体的な効果が徐々に見えてきます。
効果が出るかを判断する方法
SEOの成果を判断するには、感覚ではなくデータに基づいた分析が不可欠です。
AI解析ツールやGoogle アナリティクスを活用し、複数の指標を総合的に確認します。
効果測定で見るべき指標
- 検索順位の変化
主要キーワードでの順位変動を継続的に追う - アクセス数の増加
月間訪問者数や流入経路を分析 - コンバージョン数
問い合わせや購入などの成果指標を数値で確認 - ページの滞在時間や直帰率
ユーザーがどれだけコンテンツに関心を持っているかを測定
外注している場合は、月1回のレポートでこれらを確認できることが多く、KPIの進捗や施策の改善提案が含まれています。
表やグラフで視覚化されたレポートを提出してくれる会社は、進行状況を把握しやすく安心です。
「効果が出ない」と感じたときの見直し方法
3ヶ月経過しても成果が見えない場合は、いくつかの要因を見直す必要があります。
特に検索意図とのズレやコンテンツの品質不足が原因となっているケースが多いです。
見直しのポイントは以下です。
- 月間順位やアクセスの推移をデータで再確認
- 想定ターゲット層やキーワード設定が適切か見直す
- 内部施策と外部施策のバランスが取れているかチェック
- 分析・改善が定期的に行われているか確認
- コンサル担当者に質問した際の対応の早さ・説明の正確さを評価
SEOは長期戦ですが、3〜6ヶ月の間に小さな改善兆候が現れ始めるのが一般的です。
その変化がまったく見られない場合、業者の施策や分析手法、契約内容を見直すことも検討すべきです。
現状分析を正確に行い、KPIを再設定することが、再浮上への第一歩になります。
まとめ
SEO対策を外注するか自社で行うかを判断する際に重要なのは、「自社の目的や体制、そして目指す成果と相性が合っているか」を明確にすることです。
単に価格が安い、短期間で順位が上がると聞いた、という理由だけで契約してしまうと期待した結果が得られず、かえって費用や時間を無駄にしてしまうことがあります。
信頼できるSEO会社は、専門用語を避けて分かりやすく説明し、作業内容・費用の内訳・契約形態を明示してくれる傾向があります。
また、成果を判断するための数値(CV、KPI、アクセス推移など)を定期的に共有してくれる会社は、運営体制が透明で安心です。
反対に「すぐに順位が上がる」「AI分析ですべて自動化できる」といった根拠の薄い説明をする業者には注意が必要です。
外注を選ぶ場合でも、自社内で一定の理解を持ち、担当者がレポート内容や提案の妥当性を判断できるようにしておくことが大切です。
社内にSEO担当者を配置できない場合でも、最低限の知識を共有しておくと、業者とのコミュニケーションが円滑になります。
SEOは一度実施して終わる施策ではなく、検索アルゴリズムの変化や市場の動向、競合の動きに合わせて定期的な見直しが必要です。
月間単位で現状分析を行い、コンテンツや内部施策を更新し続けることが成果を上げる近道です。
焦らず、一歩ずつ品質を高めながら、信頼できるパートナーと継続的に取り組むことが確実に価値を生み出すSEO運用の基本といえます。
SEOの権威性とは?高めるための方法と重要性については下記で詳しく紹介しています。