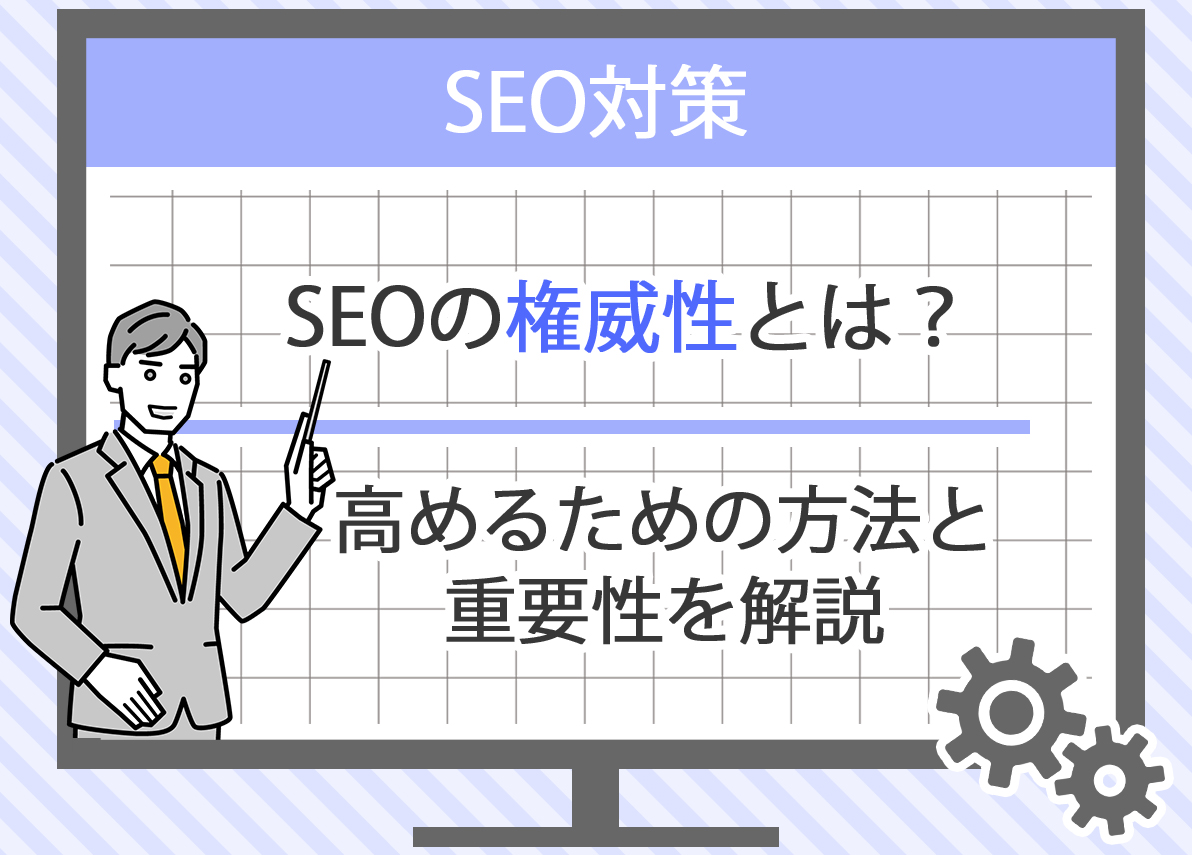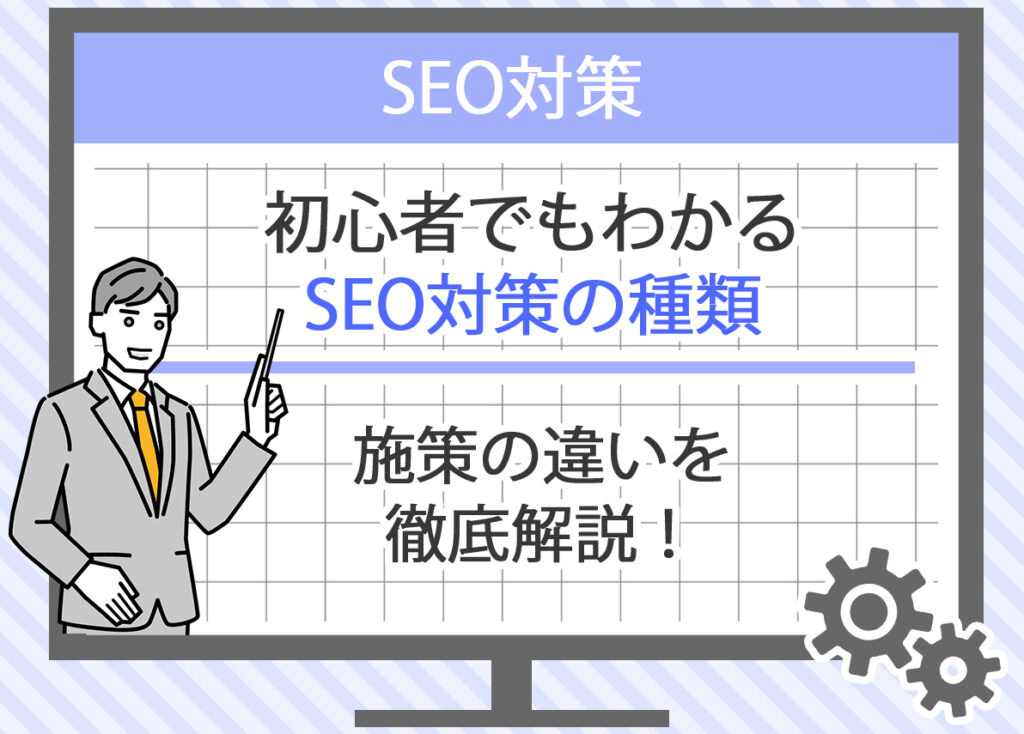
検索エンジンで上位を目指すためには、SEO対策(検索エンジン最適化/Search Engine Optimization)が欠かせません。
自社サイトへの自然流入を増やすうえで、適切な施策を行うことが重要です。
本記事では、SEOの基本である「内部対策」「外部対策」「テクニカル対策」の3種類について、初心者の方にも理解しやすいよう解説します。
これからWebサイト運営やWebマーケティングを始めたい企業の担当者や個人の方にとって、実践的で役立つ内容となっています。
SEO施策は大きく分けて3つ!内部・外部・テクニカル対策の種類を紹介

SEO対策(検索エンジン最適化/Search Engine Optimization)は、Webサイトへの自然流入を増やすために欠かせない取り組みです。
検索エンジンで上位に表示されやすくするためには、主に「内部対策」「外部対策」「テクニカル対策」という3つの方向から最適化を行う必要があります。
それぞれの対策には異なる目的とアプローチがあり、分類を理解することで、自社サイトのどの部分を優先的に改善すべきか判断しやすくなります。
近年では、Googleのアルゴリズムがよりユーザーエクスペリエンスを重視する傾向にあるため、3つの対策を適切に組み合わせていくことが重要です。
内部対策・外部対策・テクニカル対策の違い
3つの施策には目的や方法の違いがあります。
以下の表で概要を整理します。
| 対策の種類 | 対象 | 主な内容 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 内部対策 | 自社のWebページ | キーワード設計、見出し構成、画像のalt属性、HTMLのマークアップ、meta descriptionの設定など | 自社で管理・改善しやすく、効果を確認しやすい |
| 外部対策 | 外部サイトとの関係 | 被リンク獲得、サイテーション、SNSシェア、企業名の露出など | 第三者からの信頼を得ることが中心 |
| テクニカル対策 | サイトの技術的側面 | 表示速度、スマートフォン対応、構造化データ、クロール最適化 | 専門的な知識や技術が必要なことが多い |
内部対策は、Webページの中身を改善して検索エンジンに正しく内容を伝えるための施策です。
外部対策は、他サイトやメディアからの信頼を得て、サイト全体の評価を高めるための取り組みです。
テクニカル対策は、クローラーが効率的にサイトを巡回できるように整える「基礎工事」のようなものです。
これらをバランスよく実践することがSEOの効果を最大化するポイントです。
それぞれの施策が目指している効果とは
3つのSEO施策は、検索エンジンとユーザー双方に価値を提供するための仕組みを作ることを目的としています。
- 内部対策
ページ内容を正確に伝え、検索意図との関連性を高める。
たとえば、タイトルや見出しにキーワードを入れたり、alt属性を設定して画像の内容を補足したりすることで、検索エンジンが理解しやすい構造になります。 - 外部対策
他のWebサイトやSNSで紹介・共有されることで、信頼性・話題性を高める。
被リンクが多く、かつ質の高いサイトから評価されるほど検索順位が上がりやすくなります。 - テクニカル対策
ページ速度やモバイル最適化を行い、クロール効率を高めます。
スマートフォンで閲覧したときに読み込みが遅い場合、Googleの評価が下がる要因になるため注意が必要です。
これらの施策は互いに影響し合いながら、検索順位の安定と流入の増加を支えています。
初心者でも取り組みやすい施策はどれ?
SEO初心者でも始めやすいのは内部対策です。
自社で直接コントロールできるため、コストをかけずに改善できる項目が多く存在します。
- タイトルにキーワードを入れる
検索クエリに近い言葉をタイトルへ入れると、検索エンジンとユーザーの両方にページ内容を伝えやすくなります。 - 見出し(h1・h2など)を整理する
HTMLの階層構造を意識して見出しを設定することで、テキスト全体の構成が明確になります。 - alt属性を設定する
画像の内容を文字で説明することで、クローラーが理解できるようになります。
視覚的情報を補完し、アクセシビリティ向上にもつながります。 - 内部リンクを設置する
関連ページをつなげることで、クローラーの巡回効率が高まり、ユーザーの滞在時間も増えます。
外部対策やテクニカル対策は専門的な知識や時間を要することがありますが、内部対策はHTMLの基礎理解があればすぐに始められます。
特に、Google Search Console(サーチコンソール)やPageSpeed Insightsなどの無料ツールを活用すると、改善すべき点を具体的に把握できます。
- Google サーチコンソール
インデックス状況や検索クエリごとの表示順位を確認できる。 - PageSpeed Insights
ページの読み込み速度を測定し、改善提案を数値で把握できる。
まずは内部対策から取り組み、成果を確認しながら外部・テクニカル対策へと段階的に広げていくことが、SEO運用を継続的に改善していくうえで効果的です。
内部対策のポイントと主な項目一覧【初心者向け】

内部対策とは、自社サイト内部の情報や構造を整理し、検索エンジンとユーザーの双方にとってわかりやすく最適化する施策を指します。
SEOの基礎であり、サイト全体の品質を高めるうえで欠かせない要素です。
検索エンジンは構造が整っていて内容が明確なサイトを高く評価する傾向があるため、内部対策を行うことで良質な流入を増やしユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。
内部対策ってどんなことをするの?
内部対策では、Webページの情報を「正確・効率的・適切」に伝えることが重要です。
2025年現在、GoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視しており、コンテンツの品質と構造の両方を高めることが求められています。
主なポイントは以下の通りです。
- コンテンツの内容
ユーザーが求める情報を的確に掲載しているか - キーワードの使い方
関連性の高い検索クエリを自然に盛り込めているか - ページ構造
情報を階層構造で整理し、重要度に応じて見出し(h1〜h3)を設定しているか - URLの設計
短く、意味の分かる単語で構築されているか(英単語推奨) - 内部リンク
関連ページ同士が論理的に繋がっているか
これらを整備することで、検索エンジンのクロール効率が高まり、ページの存在を正しく認識させることができます。
内部対策は、SEOの中でも比較的コストを抑えて実践できる有効な施策です。
サイト内の文章や構成を整える
ユーザーが快適に読み進められる文章構成は、SEOにおいても高く評価されます。
特に低品質なテキストや曖昧な表現は、検索エンジンからの評価を下げる要因になります。
文章作成の際は以下の点を意識すると良いでしょう。
- 一文を短く区切る
読みやすさを優先し、句読点の位置に注意する - 難しい専門用語は言い換える
初心者にも理解しやすい言葉にする - 段落を適度に分ける
覚的な読みやすさを意識する - 適切に装飾を使う
箇条書きや見出しで情報を整理する
このように文章を整えることでユーザーエクスペリエンス(UX)が向上し、滞在時間や回遊率の増加といった好影響が期待できます。
検索エンジンはユーザーの行動データを評価指標としているため、結果的にSEO全体にも良い効果をもたらします。
タイトルや見出しを工夫する意味
タイトルや見出しは、SEO内部対策の中でも最も重要な要素のひとつです。
Googleはタイトルタグや見出しタグ(h1・h2・h3)を通じてページの主題を理解します。
- タイトルタグには狙いたいキーワードを入れる
- h1はページ内で1つだけ設定する
- h2・h3で階層を整理し、関連情報を構造的にまとめる
- キーワードの詰め込みすぎは避ける(不自然な文言は評価が下がる可能性あり)
また、meta description(メタディスクリプション)も重要です。
検索結果に表示されるこのテキストがクリック率に大きく影響するため、ページ内容を120文字前後で簡潔にまとめることが推奨されます。
内部対策では「見出し・構造・文言の整備」を通して、ユーザーと検索エンジン双方にとって理解しやすいサイトを作ることが基本です。
スマホ対応や表示スピードも重要
近年、スマートフォンからのアクセスが全体の約7割を占めており、モバイル対応はSEO内部対策における必須条件になっています。
Googleはモバイルファーストインデックスを採用しており、スマホでの表示を基準に評価を行います。以下を確認しましょう。
- スマホでの表示崩れがないか(レスポンシブデザイン対応)
- フォントサイズやボタン配置は指で押しやすいか
- 画像・動画の容量を最適化して読み込み速度を高める
- 不要なスクリプトを削除し、HTMLやCSSを効率的に読み込む
表示速度はユーザー離脱率にも直結します。
PageSpeed Insightsを活用して、スコアや改善点を定期的にチェックすることが効果的です。
クローラーが巡回しやすいサイトにするには
検索エンジンのクローラー(Googlebotなど)は、Web上を自動的に巡回しながら情報を収集・インデックス化します。
サイトの内部構造が不明確だったりリンク切れが多いとクロール効率が下がり、インデックスされにくくなることがあります。
以下の設定を行うと効果的です。
- XMLサイトマップを作成・送信する(Google Search Console経由)
- robots.txtでアクセス制御を設定し、不要なページのクロールを制限する
- 内部リンクを最適化してページ同士の関連性を高める
- リダイレクト設定を整理し、重複ページや削除済みURLを正規化する
これらを整えることで、検索エンジンはサイト全体を正しく把握でき、重要なページを優先的に評価してくれるようになります。
また、構造化データをHTML内に記載しておくと、検索結果でリッチリザルト(レビュー・FAQなど)が表示される可能性も高まります。
内部対策はSEOの中でも最も基礎的でありながら、検索順位を安定させるうえで最も重要な領域です。
定期的に内部構造を見直し最新情報やコンテンツ更新を続けることが、長期的な成果へと繋がります。
外部対策とは?被リンクやサイテーションの基本を解説

外部対策とは、自分のWebサイト以外の場所で得られる「信頼」と「評価」を高めるためのSEO施策です。検索エンジンは、サイト単体の内容だけでなく「他のサイトからどう扱われているか」をもとに順位を決定します。
特に被リンクとサイテーションは、Googleがページの信頼性を判断するうえで重要なシグナルです。
これらを正しく理解し、自然に増やしていくことが、SEOの成果を高めるための鍵となります。
外部対策は「信頼されているか」がカギ
Googleをはじめとする検索エンジンは、たくさんの人や企業に信頼されているサイトを上位に表示させたいと考えています。
そのため、「どんなサイトから紹介されているか」「どのような文脈で言及されているか」など、サイト外での評価を継続的に分析しています。
- 被リンクが多い
他サイトからリンクされているページは、情報が役立つと判断されやすい - 質の高いサイトからの評価がある
信頼性や権威性のあるサイトからのリンクは大きな評価につながる - SNSやニュースサイトでも話題になっている
ェアや引用が増えると、トレンド性や影響力が高いとみなされる
つまり、外部対策では「多くの人が自然に紹介したくなるサイトを作ること」が重要です。
単なる被リンク数よりも、どのような立場・文脈でリンクされているかが評価に直結します。
被リンクって何?どうやって得るの?
被リンクとは、他のWebサイトから自社のページへ向けて設置されたリンクのことです。
検索エンジンはこれを「推薦」や「信用の証」として捉えます。
ただし人工的にリンクを増やす行為(自作自演)はペナルティの対象になるため、自然な形でリンクを得ることが大切です。
- 自然な被リンク
他社メディアやブログが、価値ある情報として自発的に紹介してくれる - 自作自演のリンク
自分で複数のサイトを作りリンクを貼る行為(ペナルティの要因になる)
質の高い被リンクを増やすためには、検索ユーザーや業界関係者にとって役立つ情報を発信し続けることが基本です。
そのうえで、次のような手段も効果的です。
- オウンドメディアで専門的な記事や資料を発信する
- 業界ポータルサイトやデータベースに登録して露出を増やす
- プレスリリース(例:PR TIMESなど)でニュース性のある情報を配信する
- 他社サイトや専門コラムへ寄稿して、信頼性のある形で紹介してもらう
短期間で大量の被リンクを狙うのではなく、「紹介したくなるような価値」を積み重ねていくことが外部対策の本質です。
サイテーションとは?リンクがなくても効果あり
サイテーション(Citation)とは、リンクが貼られていなくてもWeb上で自社名・サービス名などが言及されることを指します。
たとえば「株式会社トモシビが新しいSEO資料を公開」などの記事が他メディアに掲載されていれば、それも評価対象になります。
- 社名や商品名が取り上げられている
ブランド認知の広がりとして評価される - ブログ・SNSで紹介されている
口コミとしてユーザー信頼を高める - レビューサイトや比較記事で触れられている
客観的評価として価値が高い
サイテーションは被リンクのように明示的ではありませんが、Googleは文脈解析によって認知情報を把握します。
特に地域名や店舗名を含むサイテーションは、ローカルSEOに強く影響します。
信頼されるサイトを作るためにできること
外部から信頼されるためには、単にリンクを増やすのではなく「信頼して引用される価値」を作ることが大切です。
以下のポイントを意識することで、自然な評価を得られやすくなります。
- 正確でわかりやすい情報を発信する
事実に基づいた説明を心がけ、誤解を招く表現を避ける。 - サイト全体のユーザーエクスペリエンスを高める
レイアウトやフォント、ナビゲーション構造を整えて利便性を向上させる。 - 運営者情報や監修者を明記する
どの企業・担当者が発信しているかを明示することで信頼性が高まる。 - 更新頻度を維持する
定期的な情報更新で「生きているサイト」であることを示す。 - 口コミやレビュー対応を丁寧に行う
ネガティブな意見にも誠実に対応することで、ブランドイメージが安定する。
外部対策には即効性はありませんが、時間をかけて評価が積み上がっていきます。
Googleのガイドラインに沿いながら、ペナルティを避けつつ「紹介される理由のあるサイト」を育てることがSEOにおける最重要ポイントです。
SEOコンテンツの作り方とは?ユーザーに評価される記事構成のコツ

SEOコンテンツとは、検索エンジンに見つけてもらいやすく、同時にユーザーが読みやすいように設計された記事のことです。
どれだけ検索上位に表示されても、読まれなければ意味がありません。
検索されるための工夫と、読者の役に立つ内容の両方を意識して、評価されやすい構成を作ることが重要です。
ユーザーが求める情報を考える
検索される記事を作るためにまず必要なのは、ユーザーの疑問や悩みに答えることです。
SEOでは、単にキーワードを使うだけでなく、そのキーワードで検索する人が「何を知りたいか」を考えることが重要になります。
- 検索意図を読み取る
キーワードの背景にある「知りたいこと」「解決したいこと」を想像する - 読者のレベルに合わせる
初心者向けか、実務経験者向けかによって説明の深さを変える - 過去の自分を想像する
同じ悩みを持っていたときに読みたかった内容を思い出す - 検索キーワードを調査する
ラッコキーワードや[Googleサジェスト]で関連語を確認する
コンテンツの「中身」を考える段階で、検索キーワードに合わせてテーマや構成を決めることがポイントです。
読みやすい見出しの付け方
ユーザーはページをすべて読むとは限らず、見出しだけを追って内容を判断していることも多いです。
そのため、見出しは「どこに何が書いてあるか」をわかりやすく伝える役割があります。
- h2は大見出し、h3はその補足という構成にする
階層がわかりやすいと読みやすくなる - 見出しにはキーワードを含める
検索エンジンにも「この記事の主題」が伝わりやすくなる - 疑問形の見出しはユーザーの関心を引きやすい
「◯◯とは?」「どうすればいいの?」など - 曖昧な言葉を避ける
「これ」「それ」など指示語は見出しでは使わない
ページ内の見出しだけ読んでも内容の概要がわかるように設計することで、ユーザーエクスペリエンスが高まります。
キーワードの使いすぎに注意!
キーワードを意識するあまり、不自然に同じ言葉を繰り返してしまうと、検索エンジンからスパムと判断されることもあります。
また、ユーザーにとっても読みにくい文章になってしまいます。
- 自然な文脈でキーワードを使う
あくまでも文章の流れを優先する - キーワードの言い換えや関連語も使う
Googleは「意味の近い言葉」も理解できる - ビッグキーワードとロングテールキーワードをバランスよく使う
一語の強いワードだけでなく、複数語で具体性のあるワードも活用する - ページ全体でのキーワード比率を意識する
目安としては全体の3〜5%程度に留める
検索順位を上げたいキーワードがあっても、読み手を置き去りにした文章では意味がありません。
あくまで自然な文章の中で伝えることが大切です。
長すぎず、短すぎない文章を意識する
1つ1つの文章が長すぎると理解しづらく、短すぎると情報が足りなくなってしまいます。
文の長さには適度なリズムが必要です。
- 1文の目安は60〜80文字前後:読みやすさを意識する
- 句読点の位置にも注意する:息継ぎのような間があると読みやすくなる
- 文章の構造を意識する:結論→理由→補足の順がわかりやすい
- 表現の繰り返しを避ける:同じ表現ばかりだと読み疲れてしまう
また、一段落ごとにテーマを切り替えることで、情報が整理されて伝わりやすくなります。
役に立つ記事とは?内容の質がポイント
検索エンジンは、「実際に読んだ人にとって役立つかどうか」を非常に重視しています。
そのため、ただ情報を並べるだけではなく、読者にとって意味のある情報かどうかが判断されます。
- 一次情報や体験談を盛り込む
ネットに溢れている情報のコピーにならないようにする - 具体的なデータや引用を使う
信頼性が上がり、内容に深みが出る - 図解や画像で補足する
視覚的に理解を助ける工夫をする - 悩みに対して明確な回答を示す
答えが曖昧なままだと満足度が下がる
質の高いコンテンツとは、読者の疑問に対して「納得できる情報」が提供されているかどうかで評価されます。
検索エンジンの評価も、ユーザーの行動(滞在時間、直帰率、共有数など)を参考にしているため、読んだ人が「読んでよかった」と感じられる構成と内容が最も重要です。
記事の中身こそがSEOの核となります。
テクニカルSEOの施策内容とおすすめ無料ツール

テクニカルSEOとは、検索エンジンがWebページを正しく読み取り適切に評価できるようにサイトの内部構造や技術的な要素を整えるための施策を指します。
デザインや文章内容のような表面的な部分ではなく、Webサイトの仕組みそのものを最適化する工程であり、SEOの「基盤づくり」と言える部分です。
検索結果で上位に表示されるには、表面の見やすさだけでなく裏側の構造が整っていることが欠かせません。
テクニカルSEOとは?初心者にもできる対策
テクニカルSEOは専門的な印象がありますが、基本的な部分は初心者でも十分に対応できます。
以下の項目を確認するだけでも、サイト全体のパフォーマンスと信頼性が向上します。
- サイトの読み込みスピードを改善する
- モバイル対応(スマートフォン表示)を最適化する
- SSL化(https化)を実施し、安全な通信を確保する
- リンクエラーや重複コンテンツを修正する
- クローラーが巡回しやすいサイト構造を整備する
これらの施策は、ユーザーエクスペリエンスの向上と検索エンジン評価の両方に直結します。
特にスマートフォン利用が主流となった現在では、モバイル最適化と高速表示がSEOの基本指標として重要視されています。
サイトの構造を整える意味
検索エンジンは、見た目のデザインではなく、サイト内部のHTML構造や階層設計をもとに情報を理解しています。
そのため、構造が不明瞭だと重要なページが見落とされたり、評価されにくくなることがあります。
以下のような点を意識して構築することが効果的です。
- ディレクトリ構成を整理する
トップページ → カテゴリ → 詳細ページという階層構造を明確にすることで、情報の位置関係を理解しやすくする。 - パンくずリストを設置する
現在の閲覧位置を示すことで、ユーザーの利便性を高め、内部リンクの最適化にもつながる。 - ナビゲーションメニューをシンプルにする
主要な情報にすぐアクセスできる設計にする。
このように情報の階層構造を整理することでクローラーの巡回効率が上がり、ユーザーの離脱率を下げることにもつながります。
特にBtoBサイトやECサイトでは、カテゴリ構造とURL設計の明確化がSEOの基礎です。
「インデックスされる」とはどういうこと?
「インデックス」とは、検索エンジンがページを認識・登録し、検索結果に表示できる状態を指します。
どんなに高品質なコンテンツを作ってもインデックスされていなければ検索結果に表示されず、SEO効果はゼロです。
以下のチェックポイントを押さえましょう。
- noindexタグの誤設定を防ぐ
意図せず除外設定をしていると検索に表示されない - Googleサーチコンソールで状況確認
インデックス状況を定期的に確認し、必要に応じて「インデックス登録をリクエスト」する - 重複ページを正規化する
canonicalタグで主要ページを指定し、評価の分散を防ぐ
サイトが正しくクロール・インデックスされているかを確認することは、SEOの基礎的かつ最重要項目です。
無料で使えるチェックツールを紹介
テクニカルSEOの改善には、現状を正確に把握することが第一歩です。
無料で利用できる高品質なツールを活用すれば、初心者でも簡単にサイトの健康状態を確認できます。
- Googleサーチコンソール:https://search.google.com/search-console/
ページのインデックス状況やクロールエラーを確認できるGoogle公式ツール。 - PageSpeed Insights:https://pagespeed.web.dev/
表示速度をスコア化し、改善すべき項目を具体的に提示。 - Mobile-Friendly Test:https://search.google.com/test/mobile-friendly
スマートフォン表示の最適化状況を確認できる。モバイルファーストインデックス対応に必須。 - Screaming Frog SEO Spider(無料版あり):https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
サイト全体をクロールし、リンク切れ、重複タイトル、メタ情報の欠落などを一覧化。
これらを定期的に活用することで、低品質な要因を早期発見し効率的に改善を進められます。
専門的な対策が必要な場合の考え方
テクニカルSEOの中には、専門的な知識を要する分野もあります。
CMS(WordPressなど)のテンプレート調整やサーバー設定、構造化データの記述などは、HTMLやJavaScriptの理解が必要になる場合があります。
- JavaScriptやCSSの最適化
不要なコード削除や読み込み順の調整で表示スピードを改善 - 構造化データを使って検索結果を強化する
FAQ・レビュー・イベント情報などをリッチリザルト表示させる - XMLサイトマップを自動生成・送信する
全ページの構造を検索エンジンに正しく伝える
対応が難しい場合は、SEOコンサルティング会社や制作担当者に相談するのも有効です。
ただし、外注する際は「費用」「対応範囲」「改善指標」を明確に確認し、結果を測定できる体制を整えましょう。
テクニカルSEOは目に見えない部分の整備ですが、検索順位やインデックス速度、ページ評価に直結する重要な施策です。
定期的なチェックと継続的な改善こそが、長期的に検索エンジンから信頼されるサイトを作るための最適な手段です。
最新のGoogle動向とSEOに与える影響とは?

SEO対策は、Googleの評価基準(アルゴリズム)が変化するたびに見直す必要があります。
Googleは検索利用者にとって「より正確で役立つ情報」を届けるため、日々システムの改善を行っています。
したがって順位の変動は自然な現象であり、安定した成果を維持するには最新の動向を定期的にチェックすることが欠かせません。
2025年現在、AIコンテンツの普及やE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の重要性強化など、SEOの基準はこれまで以上に「実体験と信頼性」を重視する方向へと進化しています。
Googleはどんな基準で順位を決めている?
Googleは「ユーザーが求める情報に素早くたどり着けるか」を最も重視しています。
そのため、単にキーワードを含むだけでなく、ページ全体の構成や読みやすさ、ユーザーエクスペリエンス(UX)の質が大きく影響します。
主な評価項目は以下の通りです。
- ページ内容の関連性
検索クエリと一致しているか、回答が的確か - 専門性・信頼性
運営者や著者が誰か、情報源が明示されているか - モバイル対応・表示速度
スマートフォンでも快適に閲覧できるか - ユーザーエクスペリエンス
レイアウト・内部リンク・導線が整理されているか
これらはすべて「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」の一環であり、各要素を高水準で満たすほど上位表示が期待できます。
コアアップデートとは?影響を受ける理由
Googleが年に数回行う大規模なアルゴリズム更新を「コアアップデート」と呼びます。
これは検索全体の品質を改善するための更新であり、サイト単位ではなくWeb全体に影響します。
- 順位が急に変動する
今まで上位だったページが下がることがある - 低品質コンテンツの影響
薄い内容や重複記事は評価が低下しやすい - 被リンク・サイテーションの影響
外部からの評価が高いサイトは信頼性を維持しやすい - 一次情報・独自性の強化
体験談や専門的視点を含む内容が評価されやすい
Googleはコアアップデートの詳細を公開していませんが、Google検索セントラルなどでガイドラインやヒントを発信しています。
順位変動の要因を分析する際は、アクセス解析やGoogle Search Consoleで流入データを確認し、改善の方向性を明確にすることが大切です。
直近で話題になった変更点まとめ
近年のGoogleアップデートでは、「ユーザーに役立つコンテンツ」を重視する方向性がより明確になっています。
特に以下の更新は、SEO担当者に大きな影響を与えました。
- 「ヘルプフルコンテンツアップデート」
検索意図を満たさないコンテンツや、AI生成による低品質ページの評価が下がるように調整。ユーザーが「役立った」と感じる内容が重視されます。 - 「E-E-A-T」強化
Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)に加え、Experience(経験)が加わり、実際の体験や一次情報を含む記事が評価されやすくなりました。 - AIコンテンツの扱い
GoogleはAI生成自体を否定していませんが、「品質と検証」を重視しています。
人の確認が入っていない文章や曖昧な情報は順位が下がりやすくなっています。 - ページエクスペリエンスシグナル
表示速度、インタラクティブ性、レイアウトの安定性などがユーザー満足度の指標として導入されました。
これらの変更は、単なるテキスト評価ではなく「ユーザーが本当に満足できる体験」を軸にしているのが特徴です。
そのため、SEO施策を行う際には技術・構造・内容の3方向からの最適化が欠かせません。
アルゴリズムに対応するにはどうすればいい?
アルゴリズムの変化に一喜一憂するよりも、「本質的に価値のある情報を提供すること」が最も効果的です。
以下の点を意識すれば、コアアップデートにも強いサイトを作ることができます。
- 情報の質を高める
一般論ではなく、一次データや実際の事例を含めて独自性を出す。 - 定期的に記事を見直す
古い情報やリンク切れを放置せず、最新情報に更新する。 - 構成とテキストを最適化する
h2・h3の階層構造を明確にし、読みやすい文を意識する。 - 検索意図を理解する
ビッグキーワードだけでなく、ロングテールキーワードを活用して具体的な課題に応える。 - 内部・外部施策の連携
内部リンクを整え、被リンクやサイテーションの獲得も並行して進める。
Googleは短期的な順位操作よりも、継続的にユーザーの満足度を高めるサイトを評価する傾向を強めています。
SEOは「検索エンジンのため」ではなく、「ユーザーのため」に改善を続けることが最も確実な対策です。
これからSEO対策を始める方へ:効果を上げるためのチェックリスト

最初に準備しておくべきもの
SEOを始める前に、分析や改善を行うための環境を整えることが重要です。
準備が不十分なままだと、どの施策が効果的だったのか、どこに問題があるのかが判断できません。
以下の項目を確認しておきましょう。
- Googleサーチコンソールの登録
公式ページから無料でアカウントを作成し、インデックス状況や検索クエリ、クリック率などを確認できるようにします。 - Google アナリティクスの導入
Google アナリティクスを導入しユーザーの流入経路や滞在時間、離脱率などを分析して改善につなげます。
GA4対応が標準になっているため、旧バージョンから移行済みかを確認しておきましょう。 - SSL(https)対応
安心できる通信環境を整えることで、検索エンジンからの信頼性が高まり、ユーザーにも安心感を与えます。 - XMLサイトマップの設置
サイトの階層構造を検索エンジンに伝えるための基本ファイルです。
Google サーチコンソールに送信することでクロールの効率が上がります。 - robots.txtファイルの確認
クロールを許可・拒否するページを明示し、不要なページがインデックスされないように管理します。
これらはどれもSEOの初期設定として必須項目です。
準備が整っていれば、効果測定・リライト・改善のサイクルを正しく回せるようになります。
キーワードの選び方と使い方
SEOの中心は「ユーザーがどんな言葉で検索するか」を把握することです。
適切なキーワード選定は、コンテンツの方向性や集客の質を大きく左右します。
キーワードには次の2種類があります。
- ビッグキーワード
検索ボリュームが大きく、競合も多い単語(例:SEO、ダイエット) - ロングテールキーワード
検索ボリュームは少ないが、具体的で意図が明確な複合語(例:SEO 無料ツール 初心者)
初心者が成果を上げやすいのはロングテールキーワードです。
競合が少なく、ユーザーの検索意図が明確なため、アクセスが成果につながりやすくなります。
Google Search ConsoleやGoogleキーワードプランナーを使って検索ボリュームを分析し、ターゲットを明確化することがポイントです。
また、ページ内ではキーワードを不自然に詰め込みすぎず、関連語や共起語も自然に含めることで文章の品質と検索エンジン評価を高められます。
定期的な見直しで成果を維持する
SEOは継続して改善を行うことで効果を発揮します。
一度上位表示されたページでも、競合サイトの更新やGoogleアルゴリズムの変更で順位が下がることがあります。
定期的なチェックと改善を怠らないようにしましょう。
- アクセス数や検索順位を定期的にチェックする
Google サーチコンソールの「検索パフォーマンス」レポートでクリック数・表示回数・平均掲載順位をチェック。 - 古くなった情報を更新する
仕様変更・サービス終了・統計データなど、古い情報を放置せずにリライトで最新化する。 - クリック率や直帰率を分析する
タイトルやメタディスクリプション、導入文を見直してCTRを高める。 - 新しいキーワードを調査して追加する
トレンドや季節要因、ユーザーの検索意図の変化に合わせて新しいテーマを取り入れる。
SEOは短期的なテクニックではなく、「継続的な改善の積み重ね」が最も重要です。
ユーザーにとって価値のある情報を定期的に更新し、検索意図を満たすサイトを育てていくことが、順位の安定と自然流入の増加につながります。
まとめ
SEO対策は、検索エンジンで上位に表示されるようにWebサイトを整える取り組みです。
広告のように費用がかかることなく、長く安定した集客が見込めるのが特徴です。
ただし、すぐに結果が出ないことや、やるべきことが多いことから、最初は戸惑う方も多いかもしれません。
対策は「内部対策(サイト内の構成や文章)」「外部対策(他のサイトからの評価)」「テクニカル対策(ページの構造や仕組み)」の3つに大きく分かれます。それぞれが違う役割を持っていて、バランスよく取り組むことが大切です。
記事を作成する際は、検索意図に沿った内容であるか、読みやすく整理された文章になっているかを常に意識しましょう。
タイトルや見出し、段落構成、テキスト量といった細部の最適化も、検索順位に大きく影響します。
また、SEOは一度対策を行って終わるものではなく、定期的な見直しと改善を継続することが欠かせません。
検索アルゴリズムの変化や競合の動きを踏まえて調整を続けることで、長期的な成果を維持できます。
もし社内で対応が難しい場合は、専門のSEOコンサルティングやWebマーケティング会社に相談するのも有効です。
焦らず、正しい方向で少しずつ積み重ねていくことが、最終的に大きな成果へとつながります。
SEOの権威性を高めるための方法については下記で詳しく紹介しています。