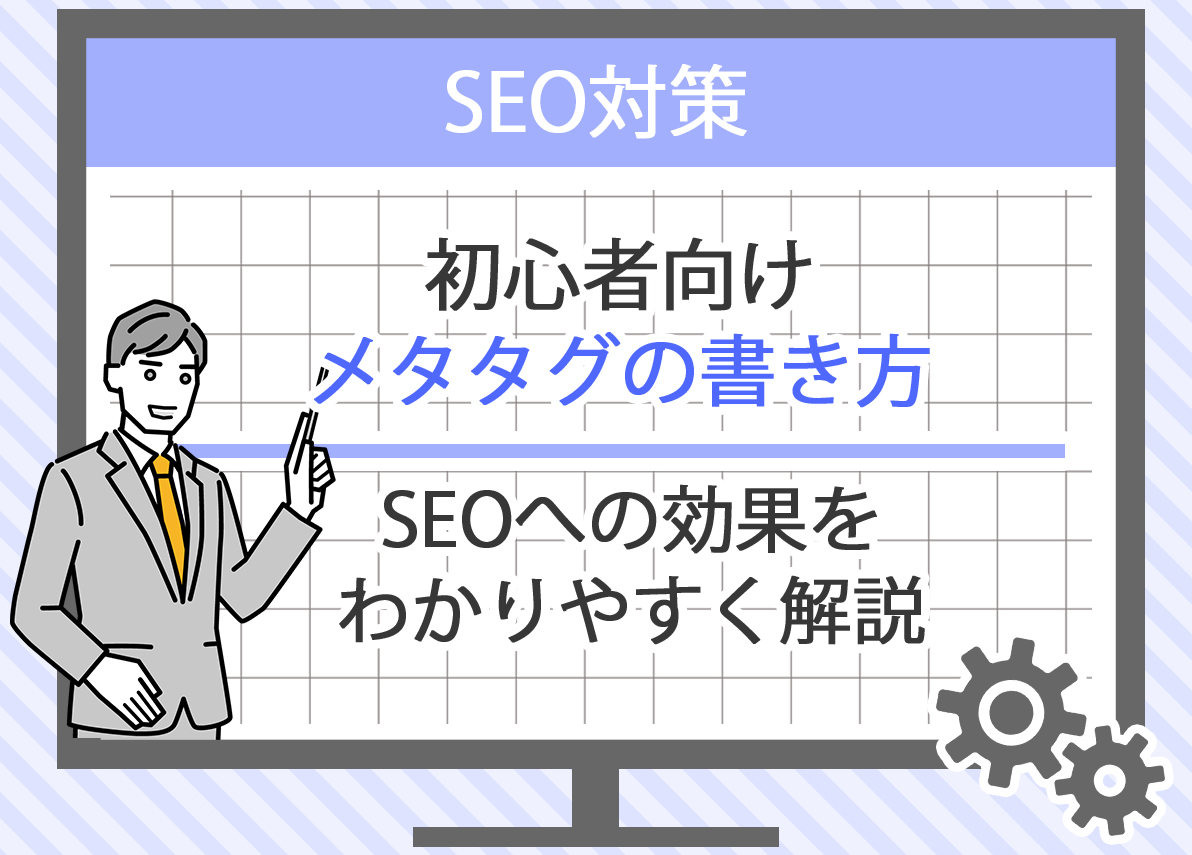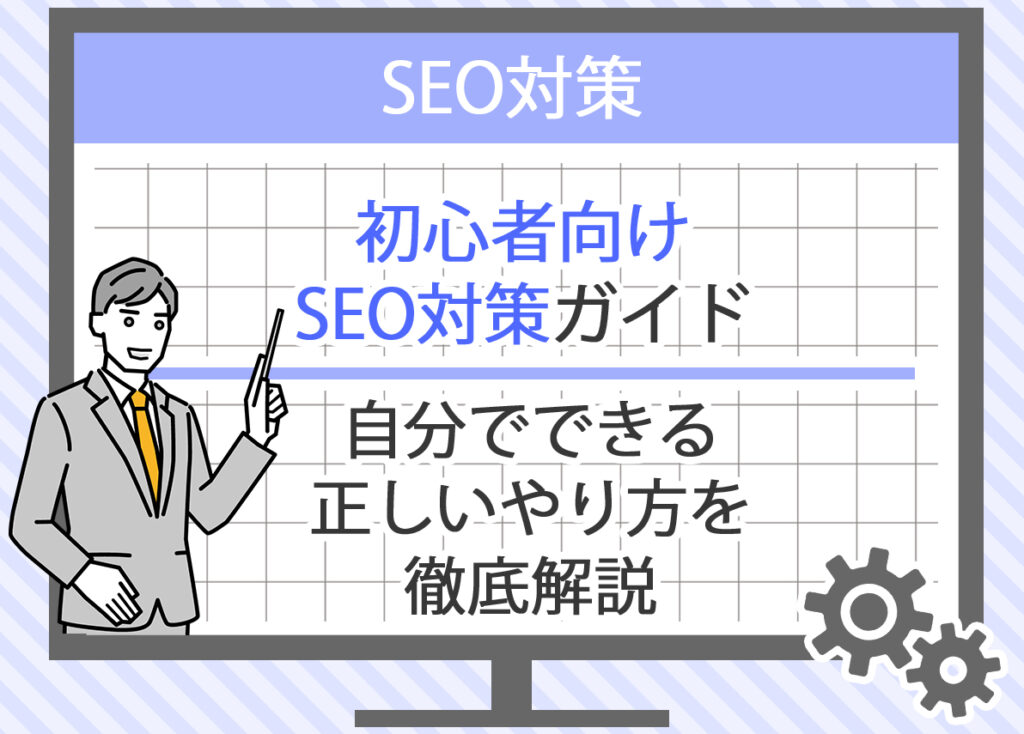
Webサイトを公開したのに「アクセスが思ったより伸びない」と感じていませんか。
主な原因の一つは、検索結果に表示されにくい状態にあることです。
これを解消する方法として注目されているのが、検索エンジン最適化とも呼ばれるSEO対策です。
SEO対策は、Googleなどの検索エンジンがページを評価する仕組みに合わせて構造や文章を整え、関連性の高いキーワードで上位表示を目指す施策を指します。
基本的なポイントを押さえれば、初心者でも自分で実践しながらサイト運営に役立てられます。
この記事では2025年現在の最新動向や具体的な進め方をわかりやすく紹介します。
Google Search Consoleなどの無料ツールを活用しながら、検索から訪れるユーザーを増やす第一歩としてぜひ参考にしてください。
そもそもSEO対策とは?初心者向けに基礎から解説

SEOってなに?検索結果に出やすくする仕組み
SEO(Search Engine Optimization、検索エンジン最適化)は、検索エンジンで自分のWebサイトを上位に表示させるための一連の改善作業を指します。
たとえばGoogleで「カフェ 東京」と検索すると多くのページが表示されますが、上位にあるほどクリック率が高くなります。
検索エンジンはクローラーと呼ばれるロボットがWeb上のページを巡回し、HTML構造やURLを解析して関連性や品質を判断します。
SEO対策ではこの仕組みを理解し、コンテンツ設計や文章を基本的なポイントに沿って整えることが重要です。
SEOは次の二つを意味します。
- 検索で上位に表示されること
- そのために行う具体的な対策
たとえば料理ブログが「簡単レシピ 時短」で上位表示を狙ったり、企業が「地域名+サービス名」で見つけやすくする施策は代表的な例です。
Google Search Consoleなどの無料ツールを活用して状況を確認しながら進めると、実践しやすく成果を出しやすくなります。
SEO対策でできること
SEO対策を行うことで、次のような効果が期待できます。
- 検索からのアクセス数を増やし広告費を抑えられる
- 興味を持つユーザーに情報を伝えやすくなる
- Googleに良質なサイトと認識され、信頼性を高められる
Web広告と異なりクリック料金が不要なため、中長期的に安定した集客が可能です。
ただし成果が出るまでには時間がかかるため、継続的な見直しと改善が欠かせません。
検索エンジンの基本
検索エンジンは次の流れで情報を整理します。
- インターネット上のページを集める(クロール)
- ページ内容を理解しインデックス化する
- 検索意図に合わせて順位付けして表示する
Google、Bing、Yahoo!などがありますが、日本ではGoogleが大きなシェアを持ちます。
SEO対策では、検索エンジンがどのように情報を発見し評価するかを把握することが欠かせません。
なぜSEO対策が必要なのか
デザインや内容が優れていても、検索で見つけてもらえなければ訪問者は増えません。
SEOを行わないと以下のような問題が起こりやすくなります。
- サイトを公開しても閲覧者が増えない
- 記事を更新してもアクセス数が伸びない
- 商品やサービスへの問い合わせが少ない
キーワードを含むタイトル設定や定期的な更新を行ったサイトは、ユーザーエクスペリエンスの向上とともに検索順位を上げる例が多くあります。
Googleも「役立つコンテンツを上位にしたい」と明言しており、閲覧者の意図を踏まえた改善こそが効果的なSEO対策です。
なぜ今SEO対策が重要なのか?最新動向

2024年から2025年への主な変化
2024年以降、検索エンジンの評価基準は大きく進化しました。
特に注目されるのがGoogleによる「E-E-A-T」評価の強化です。
(Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性、Experience:体験)
誰が執筆したのか、実際の経験や専門知識があるかが重要視され、匿名記事や出典が不明な資料は評価されにくくなりました。
医療・金融など信頼性が求められる分野では、著者情報の公開や根拠を示すことが欠かせません。
最新のSEOでは、サイト運営側が発信する体験や実績を明確に示すことがポイントになります。
新たに重視されるポイント
- AIコンテンツの品質確認
自動生成記事が急増したことで、Googleはクローラー(ロボット)がHTMLやURLを分析し、低品質な文章や情報量の少ないページは評価を下げる傾向を強めています。 - 役立つコンテンツアップデート
検索者の疑問を具体的に解決できるか、深く網羅された内容かどうかがより重要になりました。 - Webサイト全体の一貫性
テーマを整理し内部リンクを適切に設計すると、クロールの効率が高まり評価向上につながります。
Googleはアルゴリズムを頻繁に更新しており、事前通知のない変更も多いため、Google Search Consoleを活用して最新情報や指標を定期的に確認することが不可欠です。
モバイル対応と表示速度の重要性
スマートフォンからのアクセスは日本でも約7割に達しています。
Googleはモバイルファーストインデックスを導入し、スマホ表示の利便性が検索順位に直結します。
さらに、ページの読み込みが3秒を超えると離脱率が高まり、ユーザーエクスペリエンスを損ないます。
画像サイズの最適化や不要スクリプト削除、サーバー応答改善を行い、PageSpeed Insightsで速度を定期的に計測して改善することが重要です。
2025年以降に求められるユーザー目線
これからのSEOでは、検索者が「何を知りたいか」を中心に考えたコンテンツ設計が欠かせません。
- 検索意図に沿った具体的な答えを提供する
- 体験談や日付、出典を明示して信頼性を高める
- 見出しや段落を整理し、視覚的に理解しやすいレイアウトにする
- ロングテールキーワードを活用したページ作成を実践する
自分でできるSEO対策|始める前に知っておくべきこと
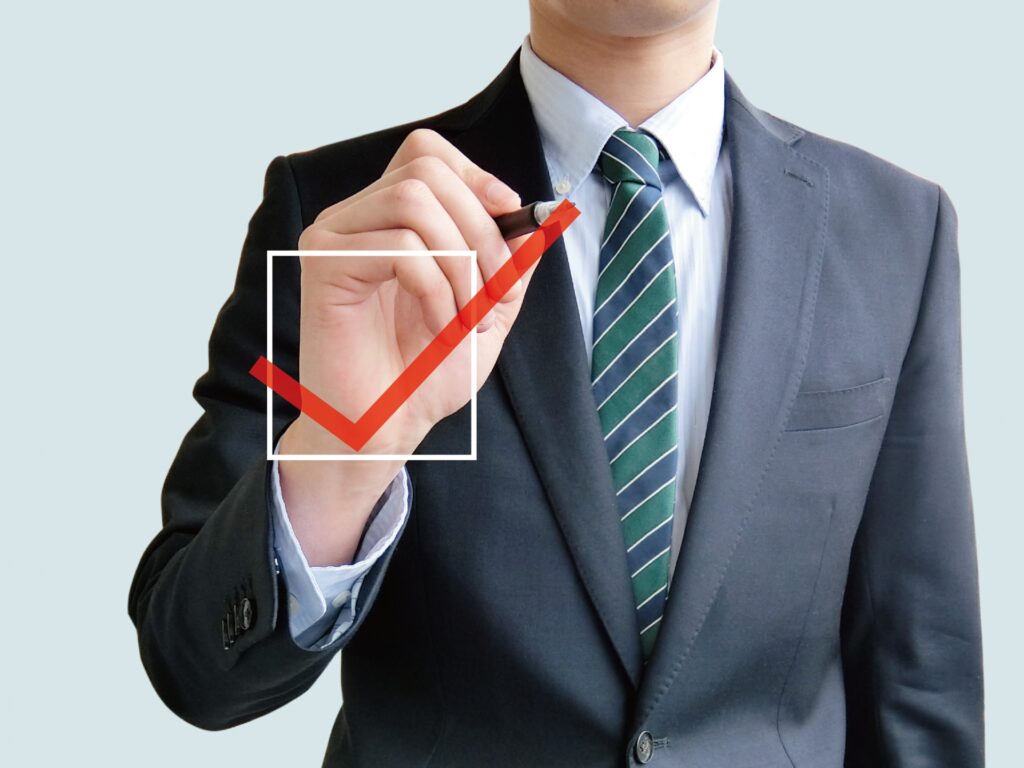
SEO対策にお金はかかる?自分でやるならどこまで可能?
SEO対策は、自分で行えば初期費用をほとんどかけずに始められます。
ただし、施策内容によっては有料サービスを活用する場合もあります。
自分で取り組みやすい主な施策は次の通りです。
- タイトルや見出しをわかりやすく書き直す
- 記事内に検索されやすいキーワードを自然に含める
- 画像にalt属性を設定する
- スマホでも見やすいレイアウトに調整する
- サイト全体の構成やメニューを整理する
これらは無料で行えますが、より詳しい分析や競合調査をする場合は、有料SEOツールの使用や外部制作会社への依頼、SEO対応テンプレートの購入などで費用が発生することもあります。
Google Search Consoleは無料で利用でき、クローラーによるURL検出状況や検索ボリューム、指標の確認に欠かせない基本的ツールです。
自分でやるメリットと注意点
自分でSEO対策を行うメリットは次の通りです。
- 費用を抑えられる:外注費用が不要
- サイト構造や検索エンジンの仕組みを実際に理解できる
- 修正や更新を即座に行えるスピード感がある
一方で注意すべき点もあります。
- 調査やライティングに時間がかかる
- 古い手法を行い逆効果になるリスクがある
- 結果が出るまでに時間が必要
進める際はGoogleのガイドラインを確認し、Google アナリティクスやGoogle Search Consoleを活用して状況を把握しましょう。
「短期間で順位を上げる」とうたう業者への依頼は慎重に検討してください。
必要な時間と作業のイメージ
SEOは一度で完了するものではなく、継続的な見直しと改善が不可欠です。
自分で行う場合の主な作業は次の通りです。
- キーワードを調べる
検索ボリュームが多く関連性の高い言葉を発見 - 記事を書く
検索意図に沿った具体的で役立つ内容にする - タイトルや見出しを工夫する
クリック率を上げる構成にする - 画像の設定
alt属性の追加やファイルサイズの調整 - サイト内リンクを設定する
関連ページを適切につなぐ - 表示速度の改善
不要なスクリプト削除や画像圧縮 - 定期的な見直し
古い情報の更新や不要ページの削除
1記事あたり数時間から数日かかることもあり、サイト全体の構造や内部リンク整理にはさらに時間が必要です。
まず何から始めればいいか
初めて取り組む場合は以下を参考にすると進めやすくなります。
- キーワード調査
Google キーワードプランナーやラッコキーワードで検索数や難易度を確認 - タイトルの見直し
ビッグキーワードとロングテールキーワードを組み合わせる - 記事内容の充実
読みやすく役に立つ情報を提供しユーザーエクスペリエンスを向上 - 画像のalt属性設定
検索エンジンに内容を正確に伝える - スマホ表示確認
端末ごとの表示崩れを防ぐ
SEOは小さな改善を積み重ねることで効果が現れます。
資料や事例を参考にしながら、具体的施策をコツコツ実践することが検索順位を上げる確実な方法です。
SEO対策の具体的なやり方と手順【内部編】

タイトルタグと見出しの書き方のポイント
タイトルタグは検索結果に表示されるページタイトルで、閲覧者が最初に目にする重要な要素です。
わかりやすく、クリックしたくなる表現にすると検索順位だけでなくクリック率の向上も期待できます。
見出しも同様に、ページ内の情報を整理して検索エンジンや閲覧者に構造を伝える役割があります。
- タイトルタグには検索意図に合うキーワードを自然に含める
- h1→h2→h3の階層で構成し、要点を簡潔に示す
- ロングテールキーワードを適切に使い、関連性を高める
Google Search Consoleを活用すれば、どのキーワードで表示されているかや検索ボリュームを確認でき、改善に役立ちます。
特に2025年現在は、検索エンジン最適化を意識した明確な見出し設計が重要です。
キーワードの入れ方とその考え方
キーワードはページのテーマを示す中心的な要素ですが、詰め込みすぎは逆効果になります。
- ページの主題に沿った言葉を選び、文章中に自然に使用
- タイトル・見出し・導入文・画像のalt属性などにバランスよく配置
- 言い換えや関連語も活用し、不自然な繰り返しを避ける
たとえば「SEO対策 自分で行う 方法」など具体的な検索語を組み合わせると、検索エンジンのクローラーが関連性を正しく判断しやすくなります。
ページの読み込み速度を速くする方法
表示スピードはSEOとユーザーエクスペリエンスの双方に影響します。
3秒以上かかると離脱率が上がるため、以下の作業が欠かせません。
- 画像をWebPなど軽量形式にしサイズを最適化
- 不要なスクリプトを削除または遅延読み込み
- ブラウザキャッシュを使用して再訪問時の速度を上げる
- 外部読み込みコンテンツを減らす
PageSpeed Insightsで現状のスコアや改善指標を確認し、提案された手順を実践すると効率的です。
これらの調整はサイト運営の品質評価にも直結します。
スマホ対応を確認する
スマートフォン利用者が増えた現在、モバイル表示の最適化は必須です。
- 文字サイズを大きめに設定し横スクロール不要にする
- ボタンやリンクは指でタップしやすい位置に配置する
- 画像や表がスマホでも崩れないか確認する
GoogleのモバイルフレンドリーテストでURLを入力すると、クローラー視点で問題箇所を発見できます。
モバイル対応はユーザーエクスペリエンスの向上と検索順位の安定に欠かせません。
サイトマップを作る重要性
サイトマップはWebサイト内のページを一覧化して検索エンジンに伝えるXMLファイルで、クローラーに正確な構造を知らせる役割を持ちます。
- ページの存在を正しく通知し登録漏れを防ぐ
- 更新や新規公開を素早く反映させる
- 階層が深いページでも巡回対象にできる
WordPressなら「XML Sitemap & Google News」などのプラグインで簡単に作成可能です。
作成後はGoogle Search Consoleに送信しておくことで、内部施策としてのSEO効果を高め、検索順位を上げるための基本的かつ効果的な手順となります。
外部対策とは?リンクや関連サイトとのつながりを理解

「被リンク」とは何か、その効果
被リンクとは、自分のWebページが他サイトからリンクされることを指します。
たとえば他のブログ記事で「詳しくはこちら」と自サイトが紹介される場合がそれにあたります。
検索エンジンのクローラーはURLやHTML構造を巡回し、他サイトからリンクを受けたページを「関連性が高く役立つ可能性がある」と評価します。
被リンクを受けることで得られる主な効果は次の通りです。
- 検索順位が上がりやすくなる
- Googleに「信頼されている」と認識されやすい
- 紹介元サイトからの訪問者が増え、アクセス数を増やしやすい
- サイト名やブランドの認知度が広がる
ただし、質の低いサイトから大量にリンクを受けると評価が下がるリスクがあるため、自然で信頼できるリンクが重要です。
信頼されているサイトからのリンクが大事な理由
検索エンジンは被リンクの「数」よりも「質」を重視します。
- 教育機関や業界団体など、信頼度の高いドメインからのリンクは価値が高い
- 自サイトと内容が近いテーマのサイトからのリンクは関連性が高く有効
- 購入したリンクや不自然な相互リンクはペナルティの対象
Googleはアルゴリズムを頻繁に更新しているため、自然な形で得た被リンクこそが最適な評価につながります。
被リンク獲得の過程を記録した資料や事例を社内で共有すると、今後の改善や進め方の参考になります。
SNSでのシェアも外部対策になる?
X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSでページがシェアされることも外部対策の一部です。
検索順位に直接影響するとは限りませんが、以下のメリットがあります。
- ページが拡散され被リンクの機会が増える
- SNSから直接アクセスが増え、流入状況を把握しやすくなる
- ブランド名やサイト名が広まり、検索される可能性が高まる
SNSでの話題性は検索エンジンが「注目されているページ」と判断する材料にもなり、SEOに間接的な効果を与えます。
自分でできる外部対策のアイデア
外部対策は他人任せにせず、自分で進める工夫も可能です。
- お役立ち情報を積極的に発信し、自然に紹介される可能性を高める
- 他サイトとコラボして対談・インタビュー・共同企画など相互リンクの機会を作る
- 自社のSNSアカウントで継続的に記事を発信し、公開直後から見つけてもらうチャンスを増やす
- Q&Aサイトやフォーラムで回答しながら自サイトを紹介(Yahoo!知恵袋やteratailなど)
- 地域メディアや業界団体にアプローチし、地域イベントや活動紹介として取り上げてもらう
これらを行う際はGoogle Search Consoleで被リンク状況や品質指標を定期的に確認し、関連性や質を維持することが重要です。
単に被リンクを増やすのではなく、紹介したくなる魅力的なページを作ることが外部対策を成功へ導く基本的な進め方です。
無料で使えるSEOツールを活用して効果を高めよう

自分のサイトの順位を調べるには
SEO対策を行った後は、自分のページが検索結果でどの順位に表示されているかを把握することが重要です。
順位を知ることで、改善が順調かどうかや見直しが必要かを判断できます。
手動で検索して確認する方法もありますが、検索履歴や地域差によって結果が変わり正確な順位をつかみにくい場合があります。
そこで役立つのがSEO用の無料ツールです。
これらのツールは特定キーワードの順位や状況を客観的に確認でき、定期的な変化の記録や複数キーワードの一括チェックにも対応します。
Google Search Consoleを使えば、クローラーが検出したURLの状態や検索ボリュームなどの指標を実際のデータとして把握でき、改善を進めやすくなります。
よく使われている無料ツール
初心者でも使いやすく実用的なツールを以下にまとめます。
- Googleサーチコンソール
Google公式の検索管理ツール。どのキーワードで表示されているか、クリック数や表示回数、指標の推移など詳細データを確認できます。
公式 https://search.google.com/search-console/about - Googleキーワードプランナー
Google広告アカウントがあれば無料で利用可能。検索回数が多いキーワードや関連語、月間検索ボリュームを調査できます。 - ラッコキーワード
1つの単語に対して一緒に検索される関連語を一覧で発見でき、記事構成やライティングの設計に便利。
公式 https://related-keywords.com/ - Ubersuggest(無料版)
順位確認や競合分析、キーワード調査まで対応(有料版あり)
公式 https://neilpatel.com/ubersuggest/ - PageSpeed Insights
ページの表示速度やHTMLの最適化状況を分析し、改善点を具体的に示します。
公式 https://pagespeed.web.dev/?hl=ja
複数のツールを組み合わせると、より詳細で関連性の高いデータを集められ、SEO施策の精度が上がります。
ツールを使って改善点を見つけよう
SEOツールは単に順位を知るだけではなく、「どこを直せば検索順位が上がるか」を見つけるための指標を提供します。
以下のような改善点を確認しましょう。
- クリック数が少ないページ
タイトルや説明文を見直す - 表示されているのにクリックされないキーワード
検索意図と記事内容のズレを解決 - アクセス減少ページ
競合の更新や古い情報を最新化 - 表示速度が遅いページ
画像やスクリプトを最適化 - スマホ表示に不具合があるページ
モバイル対応を改善
気づいた点は小さなことでも積極的に修正することが大切です。
修正を重ねることでユーザーエクスペリエンスが向上し、検索順位の上昇につながります。
SEOは一度きりでは終わらないため、資料や事例を参考にしながら定期的に見直しを行うことが効果を上げる基本的な方法です。
SEO対策でやりがちなNGポイントと注意点
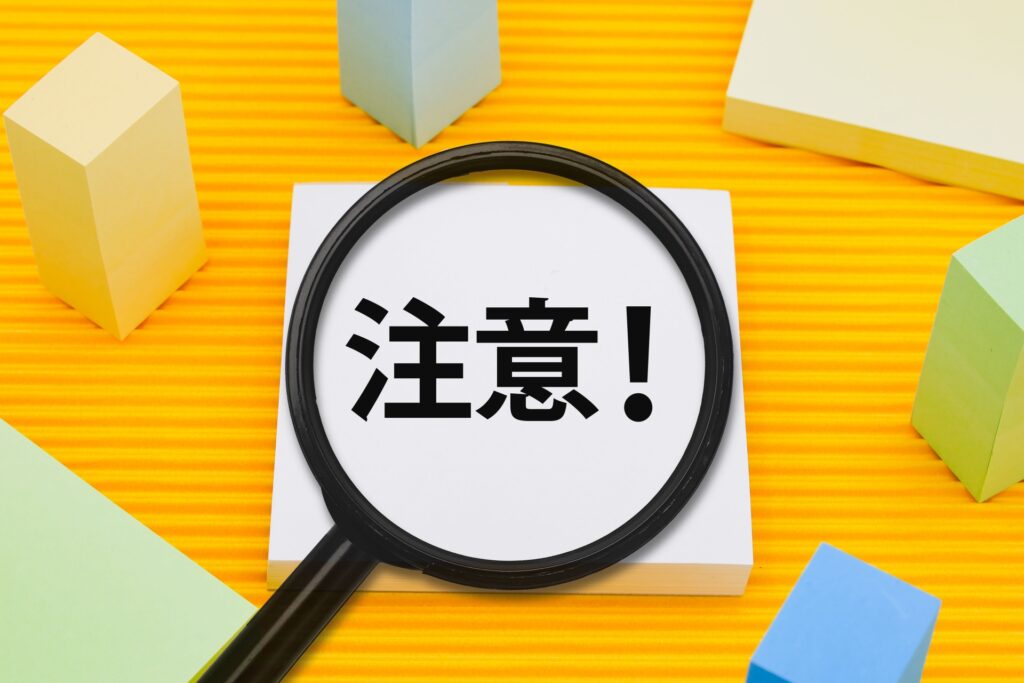
他のサイトから文章をコピーするとどうなる?
他のWebサイトから文章をそのままコピーして使うと、SEOでは大きなマイナス評価を受けます。
Googleはネット上の重複コンテンツを検知し、どれがオリジナルかを判断してコピーコンテンツを評価対象外にします。
- コピーコンテンツは重複とみなされる
検索エンジンは内容の独自性を重視している - 元のサイトの評価を下げることもある
悪質と判断されればペナルティを受ける可能性もある - 信頼性を失う
閲覧者にとっても、他のサイトと同じ文章では読む価値を感じにくい
情報を参考にする場合は、自分の言葉に置き換えてオリジナル性を高めましょう。
引用するときは出典を明記し、引用部分が全体の主体にならないようにします。
内容が薄いページは評価されにくい?
ページの文字数が多くても役に立つ情報が少ないと評価は下がります。
- 一般的な説明だけで独自性がない
- 実例やデータ、体験談が不足している
- 検索意図に沿った具体的な解決策がない
Googleの「役に立つコンテンツアップデート」では、具体的で独自性のある情報が求められます。
資料や事例、実際の体験を交えて深掘りし、検索意図に合う解決策を示すことが重要です。
見出しや構成をおろそかにしない
検索エンジンはページ構造を解析して内容を判断します。
hタグを正しく使うことで、クローラーがURLとHTMLを正確に認識します。
- h1タグは1ページ1回のみ
- h2タグで大きなテーマを区切り、h3で細分化
- 構造は階層的にh2→h3→h4の順に整理
見出しだけを読んでも流れがわかるようにすると、閲覧者の理解度も上がり、滞在時間が伸びやすくなります。
1ページ1テーマを守る
1ページに複数テーマを詰め込むと、検索エンジンが焦点を判断しづらくなります。
- 1ページで1つの悩みや疑問にしっかり答える
- 検索キーワードを1テーマに絞り、関連性を高める
- ロングテールキーワードで具体的な検索意図に対応
テーマを絞ることで、ページの関連性が高まり評価が上がります。
読みやすい文章と構成のコツ
Web文章は流し読みを前提に構成すると効果的です。
- 結論を先に書く
- 1〜3行で改行し視認性を上げる
- 箇条書きや表を使い情報を整理
- やさしい言葉を用いて専門用語を避ける
長文では目次を設けると、閲覧者が知りたい部分へすぐに移動でき、ユーザーエクスペリエンスが向上します。
画像や見出しもコンテンツの一部
画像や見出しは文章と同じくらい重要です。
- 画像で内容を補足し視覚的に伝える
- 画像にはalt属性を設定して検索エンジンに内容を伝える
- 見出しにロングテールキーワードを自然に入れる
画像を選ぶときは自分で撮影したものや著作権フリー素材を使用します。
ファイルサイズが大きい場合はページ表示が遅くなり、ユーザーエクスペリエンスを下げる原因になるため、圧縮してから使うのがおすすめです。
まとめ
SEO対策は、検索結果で自分のサイトを上位に表示させるための取り組みです。
難しく感じるかもしれませんが、基本を押さえれば初心者でも少しずつ自分で始められます。
重要なのは、検索している人にとってわかりやすく役立つページを作ることです。
ページのタイトルや見出しには、検索されやすいキーワードを自然に含めることが大切ですが、入れすぎは逆効果になるため注意しましょう。
読みやすい構成やスマホでも見やすいレイアウト、表示速度の向上も検索エンジンに評価されます。
さらに、他のサイトから紹介される被リンクやSNSでのシェアも、検索順位を押し上げる要素となります。
これらは発信する内容に価値があれば自然と増えていくものです。
Google Search Consoleなどの無料ツールを活用すれば、自分のサイトがどの検索キーワードで表示されているかや改善点を把握できます。
まずは「誰に」「何を」届けたいかを明確にし、少しずつ見直しと改善を重ねていくことが、SEOを継続して強化する基本的な方法です。
初心者向けメタタグの書き方とSEOへの効果については下記で詳しく紹介しています。