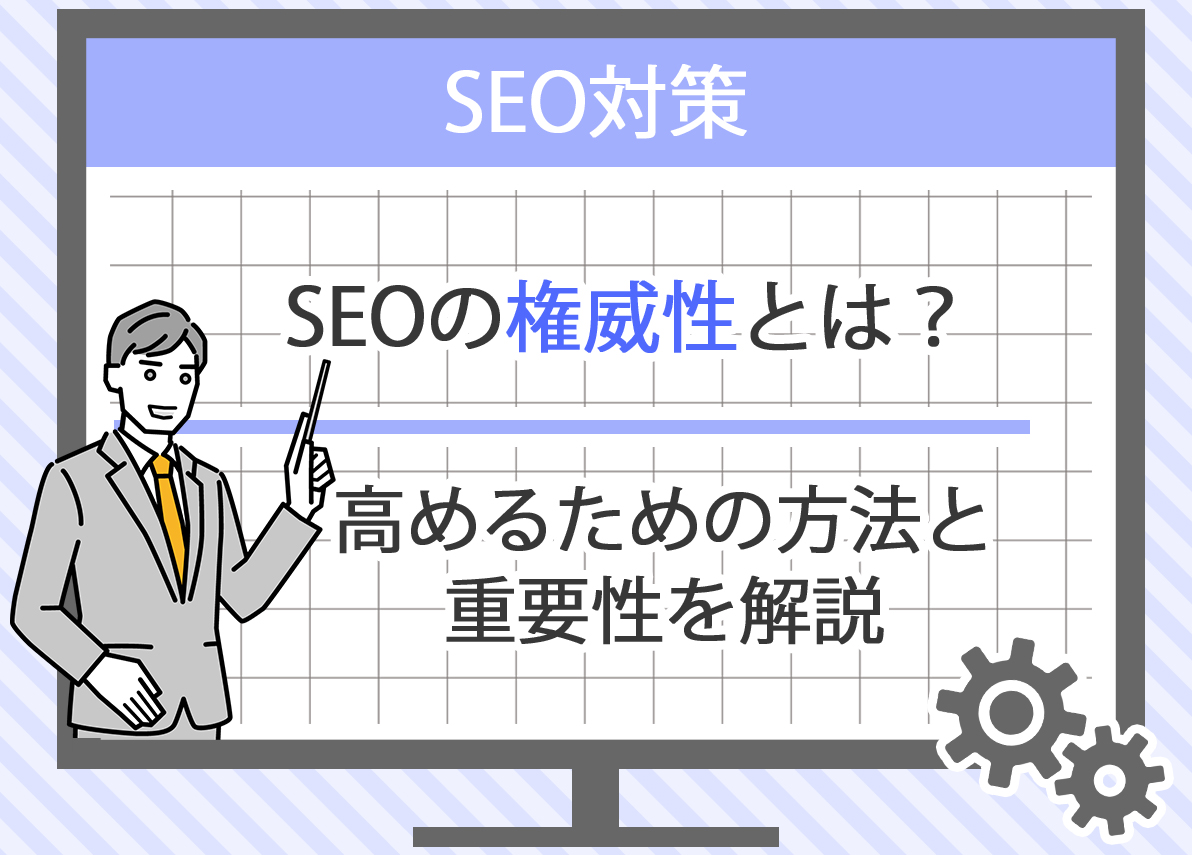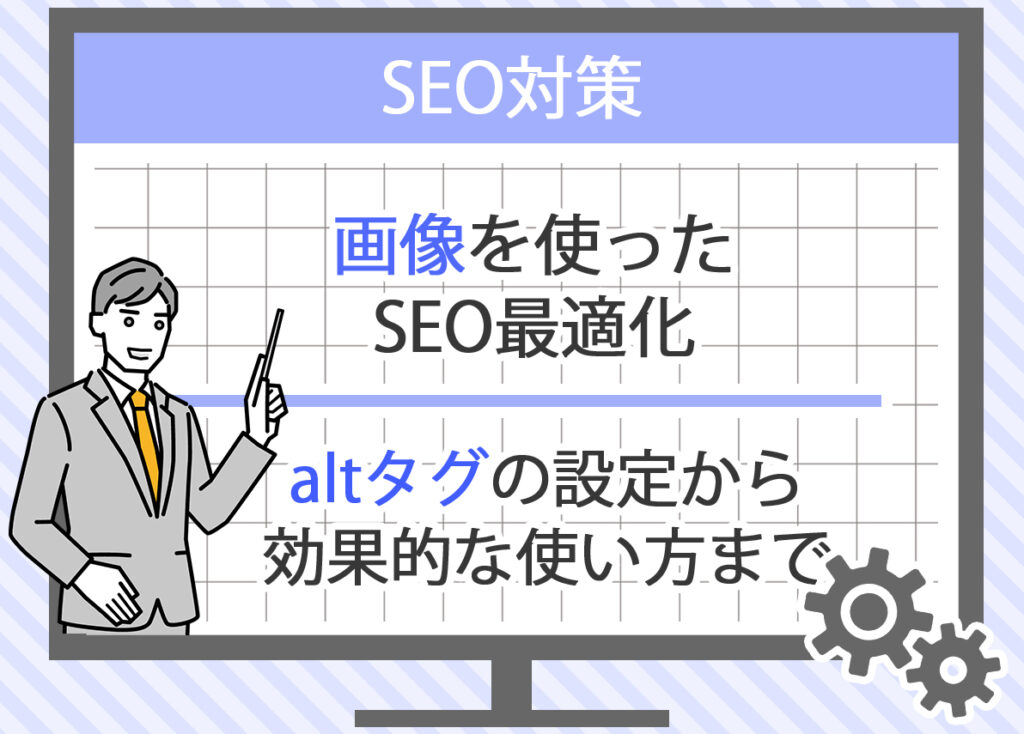
SEOにおいて、画像は単なる装飾ではなく、Webページの検索順位やユーザーエクスペリエンスに大きな影響を与える重要な要素です。
特にGoogleでは、画像の最適化状況が検索結果に直接的な影響を及ぼすこともあり、画像SEOは避けては通れない対策のひとつになっています。
もし画像を適切に活用できていない場合、どれほど高品質なコンテンツを用意していても、検索エンジンからの評価が十分に得られず、上位表示を逃す可能性があります。
画像のファイル形式やAlt属性、サイズ、読み込み速度、配置などの要因は、SEOアルゴリズム上で無視できない項目となっているため、しっかりと対策を講じることが求められます。
この記事では、SEOにおいて画像が果たす役割やオリジナル画像の重要性、効果的なAlt属性(Altタグ)の設定方法、さらには表示速度の改善や容量の圧縮といった画像最適化の手法について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
検索順位を上げるための基本を理解し、Webページ全体の品質向上を目指す一歩として、ぜひ参考になさってください。
SEOにおける画像の役割と効果

画像が検索結果に影響する理由
画像が検索結果に影響を与えるのは、検索エンジンがページ内のテキスト情報だけでなく、画像そのものや関連する情報も評価の対象にしているためです。
Googleなどの検索エンジンは、画像に設定されたAlt属性やファイル名、さらに画像が含まれる文脈(周囲のテキストやセクション)を読み取り、それぞれの関連性を判断しています。
特にGoogle画像検索は、通常のWeb検索とは異なるトラフィックをもたらす可能性があります。
画像を最適化しておくことで、search結果ページやGoogleの「画像」タブからの訪問数を上げることができ、サイト全体のトラフィック増加につながります。
また、Google Search ConsoleやPageSpeed Insightsなどのツールでも、画像に関する最適化の重要性が示されています。
以下のような要素が、画像がSEOにおいて評価される仕組みと関係しています。
- Altタグ
Altタグ(Alt属性)は、画像の内容を検索エンジンに伝えるためのテキストです。
画像が表示されないときに代替表示される役割もあり、SEO上でも高く評価されるポイントです。
Alt属性には、ページと関連するキーワードや文脈を自然に含めることで、上位表示の可能性を高めることができます。 - ファイル名
ファイル名も、検索エンジンが画像の内容を理解するための重要な情報源です。
たとえば「SEO_tips.png」と命名された画像は、「img1234.png」よりも内容が明確で、画像とコンテンツの関連性が高いと判断されやすくなります。
ファイル名にキーワードを含めることで、画像検索への露出機会も広がります。 - 画像の周辺テキスト
画像の近くにある本文テキストやキャプションに、画像と関連する情報が含まれていると、検索エンジンはその画像の意味をより正確に理解できます。
これにより、評価されやすくなるだけでなく、ユーザーにとってもわかりやすいページ構成となります。
ユーザーにとって画像が持つ重要性
画像は検索エンジンの評価に限らず、ユーザーにとっても理解と関心を高めるための手段として非常に有効です。
特にWebページや記事では、単なるテキストだけでなく、画像を交えた表現により、情報が直感的に伝わるようになります。
以下のような利点があります。
- 注意を引く
ユーザーはページを開いたときにまず視覚情報を確認します。
インパクトのある画像を配置することで、閲覧者の興味を引き、サイト内に長く滞在してもらいやすくなります。 - コンテンツの理解を促進
テキストでは伝えきれない内容も、画像があれば一目で分かることがあります。
たとえば、商品の使用例や手順を図解すると、閲覧者は直感的に内容を把握しやすくなります。 - ユーザーエクスペリエンス(UX)を向上
適切に配置された画像は、ページ全体のデザインと調和し、快適な閲覧体験を提供します。
特に、属性の異なるユーザー(たとえば高齢者や視覚に負荷がある方)にとっても、画像の配置や説明文が丁寧なWebページは理解しやすくなります。
画像がサイトの表示速度に与える影響
サイトの表示速度は、ユーザーエクスペリエンスだけでなくSEOにも大きな影響を与える指標です。
画像の容量が大きすぎると、読み込み時間が長くなり、結果的に離脱率(直帰率)を高めてしまう恐れがあります。
Googleのアルゴリズムでは、表示速度も評価要因のひとつとして含まれており、パフォーマンスの最適化は欠かせません。
- 画像の最適化
適切なファイル形式(JPEG、WebPなど)や解像度に調整することで、容量を抑えながら画質を保つことができます。
画像のリサイズや圧縮によって、読み込み速度を向上させることが可能です。 - 画像の遅延読み込み(Lazy Loading)
Lazy Loadingの仕組みを取り入れると、ユーザーがスクロールしたときに必要な画像だけを読み込むようになります。
初期表示速度の改善につながり、モバイル環境でのストレスを軽減できます。 - レスポンシブデザイン
画面サイズに応じた画像を表示するレスポンシブ設計により、無駄なデータ転送を避けられます。
これはユーザーにとって快適で、デバイスごとのUX向上にも貢献します。
画像の最適化ツール
画像最適化には、信頼性のあるツールを活用することで、効率よく圧縮や形式変更が行えます。
- TinyPNG
PNGやJPEG形式の画像を、視覚的な劣化を最小限に抑えながら圧縮できます。特にWebコンテンツ向けに最適です。 - ImageOptim
Macユーザー向けのローカル圧縮ツールで、メタデータの削除や容量の削減に適しています。 - Squoosh
Googleが提供する無料の画像圧縮ツールで、WebPやAVIFなどの形式にも対応しており、ブラウザ上で簡単に操作できます。
PageSpeed Insightsと併用することで、最適な設定のヒントも得られます。
これらのツールを活用することで、画像の最適化がスムーズに進み、Webサイト全体のパフォーマンス向上と上位表示の可能性アップに貢献できます。
特に検索トラフィックを意識するWebメディアでは、こうした取り組みが日常的な作業となっており、見落としのないよう継続的にチェックすることが大切です。
Altタグの設定ポイントと注意点

Altタグを正しく設定する方法
Altタグとは、画像にどのような意味や内容があるのかを検索エンジンやスクリーンリーダーに伝えるための属性(Alt属性)です。
視覚に制限のあるユーザーがスクリーンリーダーを使ってWebページを閲覧する際にも、Altタグの内容が読み上げられることで画像の情報を理解できます。
さらに、検索エンジンにとっても、画像の意味を把握する重要な要素となっており、正しく設定することでSEO効果が期待できます。
画像の情報が検索エンジンに伝わらないと、いくら高品質な画像を用意しても評価されにくくなります。
画像の属性を丁寧に整備することは、単なるマナーではなく、上位表示を目指す上で欠かせない要素のひとつです。
次のような点を意識して設定しましょう。
- 画像の内容を簡潔に説明する
Altタグは、画像が何を示しているかを分かりやすく短く記述します。
たとえば製品の写真であれば「赤いTシャツ」や「ノートパソコン」など、読み手がひと目で理解できる説明が理想です。
これは検索エンジンに対しても、画像と周囲の文脈の整合性を明示する意味があります。 - 適切なキーワードを含める
Altタグには、対象ページのテーマやキーワードと関係のある語句を自然な形で盛り込むと効果的です。
ここで大切なのは、キーワードの「詰め込み」ではなく、自然な文の流れを保つことです。
Altタグは短文ながらも、文脈に沿って読み手に意図が伝わるように設計する必要があります。 - コンテキストに合った内容を記述
同じ画像でも使われる場所や目的によって意味合いは異なります。
画像がページ上でどんな役割を担っているかを考慮し、説明文を調整しましょう。
たとえば、製品ページに使われる画像と、ブログ記事内で使われる画像では、注目すべきポイントや補足内容が異なります。
Altタグ設定で避けるべきミス
Altタグを設定する際には、よくある誤りを避けることが大切です。
誤った記述をしてしまうと、かえってSEOに悪影響を与えたり、読み手に誤解を与える原因になります。
以下に代表的なミスを紹介します。
- キーワードの詰め込み
過剰にキーワードを詰め込むと、検索エンジンにスパムと判断されるおそれがあります。
たとえば「赤いTシャツ、赤いTシャツ通販、赤いTシャツ安い」など、同じ語句を無理に連ねるのは避けましょう。
Altタグはあくまで読みやすく、有効な情報で構成する必要があります。 - 空のAltタグ
Altタグが未記入のままだと、画像がどのような内容なのか判断できません。
特に情報を伝える目的で使用されている画像の場合は、空白のままにせず、適切な説明を追加してください。
ただし、純粋な装飾素材などの場合は例外となることがあります(詳細は後述)。 - 無関係な説明
実際の画像とAltタグの説明が一致していないと、ユーザーと検索エンジン双方に混乱を与えます。
たとえば、風景の写真に「期間限定セール中」と書かれていた場合、内容とのズレが生じてしまいます。Altタグは、画像の意味や目的と一致していることが前提です。 - 長すぎる説明
Altタグは簡潔な表現が求められます。
目安としては80文字以内が理想的です。
長すぎるタグはユーザーにも検索エンジンにも読みづらく、内容がぼやけてしまいます。読み手が一読で把握できる長さにとどめるよう心がけてください。
Altタグの設定を最適化するポイント
Altタグを最適化するには、単に書けばよいというわけではありません。
以下のポイントを押さえると、効果的なAltタグの設計が可能です。
- 具体的であること
たとえば「花」という表現よりも、「黄色いバラのブーケ」と記述したほうが、画像の内容が明確に伝わります。
これは画像検索において、関連性の高いマッチングを生むためにも有効です。 - 適切なキーワードを使用
Altタグは、文脈の中で自然にキーワードを取り入れることが求められます。
SEOに関する記事であれば、「SEOに役立つ画像最適化のポイント」など、ページのテーマと整合性のある表現を使うとよいでしょう。 - 装飾的な画像には空のAltタグを設定
単なる背景や罫線など、情報伝達の必要がない画像には、検索エンジンに「この画像は評価しなくてよい」と伝えるため、空のAltタグを使用します。
これはアクセシビリティの観点でも重要です。
HTMLでは以下のように記述します。<img src="decorative-image.png" alt="">
このような空タグを使用することは、不要な混乱を避け、読み上げツールの負担を減らすうえでも有効です。
Altタグの設定例
以下に、さまざまなシーンにおけるAltタグの設定例をご紹介します。
- 製品写真:赤いTシャツの商品画像の場合:「赤いTシャツ メンズ 夏用」
- サービス説明:ウェブデザインサービスの紹介画像の場合:「モバイル対応のウェブデザイン例」
- コンテンツの補足:SEOの手順を説明する図の場合:「SEOのステップを示すフローチャート」
このように、文脈や意図に合わせてAltタグを調整し、チェックしながら記述することで、検索エンジンへの訴求力が高まります。
2025年現在では、AIによる画像解析が進化しているため、Altタグの精度や文脈の整合性も評価要因として考慮されやすくなっています。
機械的なルールではなく、閲覧者にとって意味のある表現を心がけることが求められています。
検索エンジンに最適化された画像の作成方法

画像のファイルサイズを小さくする方法
画像のファイルサイズが大きすぎると、Webページの読み込み速度が遅くなり、ユーザーがページを離れてしまう原因になります。
特にモバイル端末での表示では、通信容量の消費や表示遅延がストレスとなるため、軽量な画像の使用がとても重要です。
ファイルの読み込みが速くなると、SEO評価やトラフィックにも良い影響を与える可能性があります。
以下の方法で、画像の容量を効率的に減らすことができます。
- 圧縮ツールを使用する
TinyPNGやSquooshなどのオンライン圧縮ツールを使うと、画質をほとんど落とさずにファイルサイズを縮小できます。
特にSquooshは、Googleが開発したsearch対応の高機能圧縮ツールで、AVIF形式やWebP形式にも対応してます。 - 適切な解像度を選ぶ
Webページでの表示には72dpi程度の解像度が標準です。
高すぎる解像度はファイルサイズ増加の要因となります。
記事やブログなどでは、必要以上に大きな数値を使わず、実際の表示サイズに合わせて調整するのが基本です。 - 不要なメタデータを削除する
画像には、カメラの設定や撮影日といったメタ情報が含まれる場合があります。
これらの情報は表示にもSEOにも関係しないため、容量削減のために削除しましょう。MacユーザーにはImageOptimが便利で、バッチ処理にも対応しています。 - 保存形式に注意する
gif形式はアニメーションや透過用途で使われますが、用途を誤るとファイルサイズが大きくなる傾向があります。
シンプルな静止画であればJPEGやWebPを選ぶほうが効率的です。
画像形式の選び方(JPEG, PNG, WebPなど)
画像形式は、ファイルサイズ・表示の鮮明さ・透過の有無などによって使い分けが必要です。
以下は、代表的な画像形式の特徴です。
- JPEG
写真など多くの色数を扱う画像に適しています。
高い圧縮率で容量を抑えつつ画質を保ちやすいため、特にブログや商品紹介ページにおすすめです。
ただし、透過には対応していません。 - PNG
背景の透過が必要な場合や、ロゴ・アイコンなどにはPNGが向いています。
画質が鮮明な反面、ファイルサイズが大きくなる傾向があるため、内容に応じて選択しましょう。 - WebP
Googleが開発した次世代形式で、JPEGやPNGよりも圧縮率が高く、同等の画質でもファイルサイズを大幅に削減できます。
現在では多くの主要ブラウザで対応しています。AVIFと並び主流のフォーマットとして注目されています。 - AVIF(補足)
AVIFはWebPよりもさらに高圧縮かつ高画質を実現できる新しい画像形式です。
ただし、対応ブラウザが限定的なため、WebPとの併用設計が望まれます。
適切なファイル名の付け方
画像のファイル名も、検索エンジンが画像を認識するうえで非常に重要です。
意味のあるファイル名を設定することで、画像が検索対象として扱われる可能性が上がり、ページ全体の評価向上にもつながります。
- 説明的であること
「img001.jpg」のようなファイル名よりも、「seo-ranking-report.jpg」など、内容を説明する名前にするほうが適切です。
これは検索アルゴリズムが内容を理解するための文脈の一部として評価する要素です。 - キーワードを含める
画像ファイル名にページのキーワードを盛り込むことで、画像が検索対象になる確率が上がります。
無理な詰め込みではなく、自然な語句を意識しましょう。
たとえば、「seo_画像最適化_例.jpg」といった形です。 - スペースや特殊文字を避ける
ファイル名には、スペースや記号などの特殊文字を使用しないようにしましょう。
ハイフン(-)で単語を区切る形式が主流です。たとえば「seo画像.png」よりも「seo-image.png」のほうが推奨されます。 - ファイル構成のチェック
同一の画像名が別のファイルで重複しないように管理することも大切です。
CMSで画像管理する場合、incディレクトリやmediaフォルダなど保存先の設計によっては自動的に変更されることがあります。
これらのガイドラインを参考にしながら、ファイル名・形式・容量を整えた画像を用意することで、searchエンジンでの評価を高め、上位表示の可能性を引き上げられます。
効果的な画像配置のポイント
画像の配置場所や方法によって、SEO効果や読者の理解度が大きく変わります。
以下の配置方法を活用することで、記事の読みやすさや検索エンジンからの評価を同時に向上させることができます。
- 記事の冒頭に目立つ画像を配置する
記事の上部に強いインパクトのある画像を配置することで、読者の注意を引くことができます。
検索結果で表示されるサムネイル画像になるケースもあるため、コンテンツの代表として適した画像を選ぶのが理想です。 - 段落ごとに画像を挿入する
長文コンテンツでは、適度に画像を差し込むことで視線の流れをリセットできます。
特にフローチャートや図解素材などは、難しい内容を直感的に理解しやすくする効果があります。 - 余白を活かした配置
画像とテキストが詰まりすぎていると読みにくくなるため、適度な余白設計が求められます。
特にモバイルでの表示においては、画像の周辺に余裕を持たせた設計が推奨されます。
このように、画像の選び方や設置方法にも気を配ることで、SEOとユーザーエクスペリエンスの両方を意識したWebページを構築できます。
画像は視覚情報としてだけでなく、ページの評価や滞在時間、検索結果のクリック率といったSEOに関連する多くの要因と関係しています。
検索エンジンと読者の両方にとってわかりやすい設計を心がけていくことが、効果的な画像活用の第一歩となります。
サイト掲載画像の品質を高めるポイント

高画質の画像を使うべき理由
高画質の画像は、Webページにおける信頼感や印象に大きな影響を与える重要な要素です。
画像が粗かったり、解像度が低かったりすると、コンテンツ全体の品質が低く見られてしまう可能性があり、ユーザーの離脱要因にもつながります。
現在では、Googleのランキング要因において、ページの構成要素としての画像品質やオリジナル画像の有無が注目されており、AIによる画像生成や識別も進化しているため、使う画像のクオリティは以前より厳しく評価されている傾向にあります。
以下のような視覚的な影響が期待できます。
- 視覚的な訴求力
鮮明な画像は、ユーザーの視線を引きつける力があります。
特に商品紹介ページやサービス紹介では、細部までくっきり表示できる画像を使用することで、内容への関心を長く維持する効果が期待できます。 - ブランドイメージの向上
統一感があり高解像度で構成された画像を使うと、ブランド全体の印象がプロフェッショナルなものになり、訪問者に信頼感を与えることができます。
他社と差別化したい場合には、素材の選定や画像スタイルの設計にもこだわりましょう。 - 情報の正確な伝達
画像が高精細であればあるほど、製品のディテールやサービスの特徴などが正確に伝わりやすくなります。
文章だけでは伝わらない情報を補足できるため、ユーザーの理解を深め、購買や問い合わせといった行動につなげることができます。
サイト全体のデザインと画像の調和
画像は、単体での品質だけでなく、ページ全体のデザインや文脈にどれだけ自然に溶け込んでいるかも評価対象になります。
統一感のない画像配置や色味は、ユーザーの集中力を妨げたり、情報伝達を妨げる原因になってしまいます。
- 統一されたビジュアルスタイル
全体のデザインに一貫性を持たせることが大切です。
画像の色調や明るさ、縦横比などをそろえることで、訪問者に「整っている」印象を与えることができます。
ファーストビューの印象や信頼性にも関わってくるポイントです。 - テキストと画像のバランス
テキストと画像の情報量に極端な差が出ると、読む人の注意が散漫になるおそれがあります。
画像が本文を補足するように設計し、文中の情報を視覚的に補完する役割を意識しましょう。
表現が重複しすぎる場合には、別の視点や要素を盛り込む工夫も必要です。 - 効果的な余白の利用
画像の周囲に十分な余白を設けることで、ページが詰まった印象を避けることができます。
余白によって視線の誘導が自然になり、重要な要素がより際立ちます。
特に情報量が多いページでは、余白の使い方が読みやすさを左右します。 - シンプルさを保つ
情報を詰め込みすぎると、かえって印象が弱くなる場合があります。
目的に合わせて、強調したい画像だけを選び、見せたい内容を明確にするよう意識しましょう。
とくに人気の高いLPやサービス紹介ページでは、画像の数を絞ることが成果につながるケースもあります。
画像の使い方を適切に設計・最適化することで、ユーザーにとって見やすく、理解しやすいページを提供できます。
また、検索エンジンにとっても画像品質はコンテンツ評価の一部です。
高品質な画像と適切なチェック・設計は、SEOとUXの両面からも欠かせない取り組みです。
まとめ
画像は、SEO対策において単なる装飾ではなく、コンテンツ全体の品質を左右する重要な要素のひとつです。
特にGoogleでは、画像が含まれる文脈や属性の整合性、ファイル名やAlt属性の内容まで評価対象となっており、画像SEOに取り組むことは上位表示を目指す上で欠かせない対応といえます。
高画質かつ適切に生成された画像を使うことで、Webページの視認性が向上し、訪問者が情報をスムーズに受け取れるようになります。
また、画像のファイルサイズを調整して読み込み速度を上げることは、UXの向上だけでなく、searchエンジン側からの評価を高める結果にもつながります。
さらに、全体のデザインや構成との調和を図り、色調やスタイルに一貫性を持たせることで、視覚的に安心感のあるサイト設計が可能になります。
これは、訪問者の離脱を防ぐだけでなく、トラフィックの増加や滞在時間の上昇にも寄与します。
最後に、Altタグやファイル名といった画像の付帯情報についても、細部までチェックを行い、検索エンジンが正しく内容を読み取れるようにしておくことが大切です。
これらの設定を丁寧に整えることで、画像そのものがSEOに貢献する要素となり、結果として全体のページ評価を押し上げることにもつながります。
画像はテキスト以外の「伝える力」を持った素材です。
情報の補完や印象づけを目的に効果的に活用しながら、検索エンジンとユーザーの両者にとって有益なWebページを設計していくことが、これからのSEO施策ではますます求められていくでしょう。
SEOの権威性を高めるための方法については下記で詳しく紹介しています。