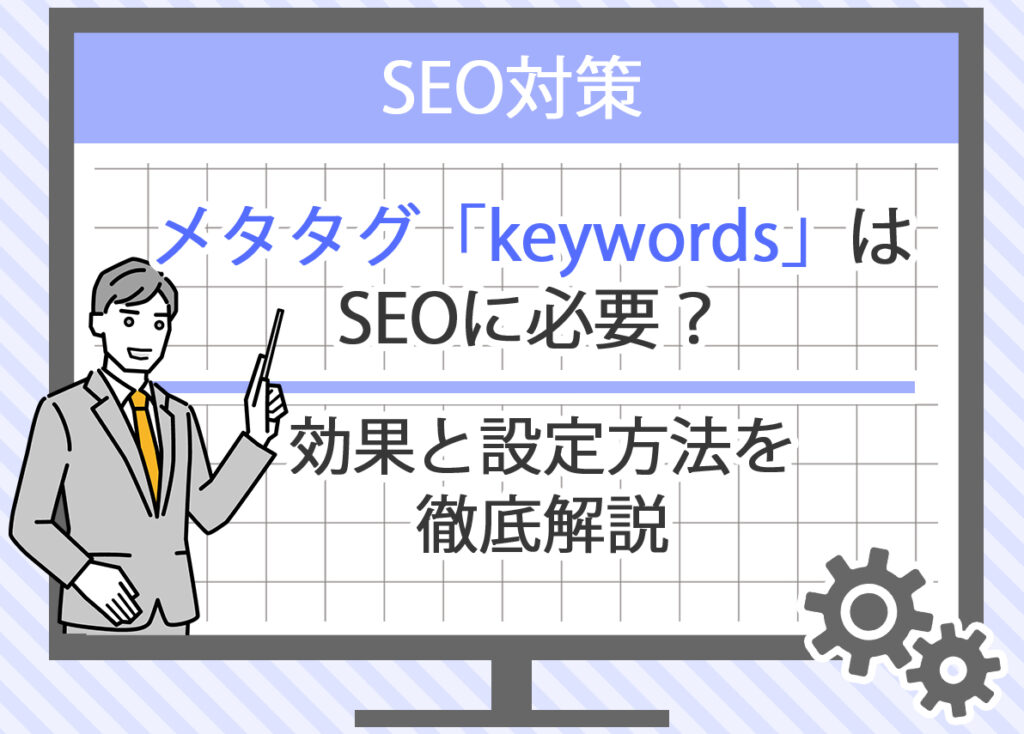
「meta keywords(メタキーワード)」という言葉を聞いたことはあるけれど、どんな意味があるのか、今のSEO対策に必要なのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
特にWebサイトを初めて作る方や、ページの設定をするときに「この項目って書くべきなの?」と迷うこともあるかと思います。
この記事では、そんな疑問をお持ちの方に向けて、meta keywordsタグの基本的な意味や、現在のGoogleの評価、実際に使うべきかどうかの判断基準までをわかりやすくご紹介します。
専門用語をできるだけ使わずに解説していますので、Webのことがあまり詳しくない方でも安心して読める内容になっています。
メタタグ「keywords」とは?意味とSEOとの関係を解説

メタタグってそもそも何?
メタタグとは、Webページの内容を検索エンジンなどに伝えるために使われるHTMLのタグの一種です。
ページの見た目には表示されず、ページの裏側にある情報(ソースコード)として書かれています。
これによって、検索エンジンはそのページがどんな情報を持っているかを判断しやすくなります。
メタタグにはいくつかの種類があり、それぞれに役割があります。
たとえば、検索結果に表示される説明文を指定するdescriptionタグや、ページの文字コードを伝えるcharsetタグなどがあります。keywordsタグはその中の一つで、主にそのページに関連するキーワードを検索エンジンに伝えるために使用されてきたものです。
keywordsタグの役割とは
keywordsタグは、Webページがどんなテーマやトピックを扱っているかをキーワードで指定するために使われます。
HTMLのソースコード内に以下のような形で記述されます。
<meta name="keywords" content="SEO, メタタグ, キーワード, Webマーケティング">
このように、カンマで区切った言葉を並べて、検索エンジンに「このページはこういったキーワードに関連しています」と伝える役割を持っていました。
以前は検索エンジンがこの情報を参考にしてページの内容を判断していたため、多くのWebサイトがこのタグを活用していました。
SEOとメタタグのつながり
SEO(検索エンジン最適化)では、検索結果で上位に表示されるために検索エンジンに正しくページ内容を伝えることが大切です。
メタタグはその手段の一つとして長く使われてきました。
特にkeywordsタグは、Webサイト運営者が意図するキーワードを明示的に検索エンジンへ伝えられる方法として注目されていました。
しかし、検索エンジンの技術が進化するにつれて、その重要性は大きく変化していきました。
現在では、検索エンジンはページ内の実際のテキストや構造、ユーザーの行動など多くの情報を分析するようになったため、keywordsタグに記載されている内容はほとんど評価されなくなっています。
なぜ検索エンジンに関係しているのか
keywordsタグは、検索エンジンが「どんなページか」を知るための情報源として一時期とても重要でした。
特にGoogleが普及する前の検索エンジンは、ページの内容を機械的に判断するのが難しかったため、Webサイト運営者が用意したメタ情報を強く参考にしていたのです。
そのため、運営者はページの内容に関連するビッグキーワードやロングテールキーワードをkeywordsタグに入力することで、検索結果での表示順位を上げようとしていました。
ところが、検索エンジンの利用が広がるにつれて、この仕組みを悪用するケースが増えてしまいました。
たとえば、ページの内容に関係のない人気キーワードを大量に入れてアクセスを集めようとする「キーワードスパム」が横行したのです。
これに対抗するために、Googleなどの検索エンジンはkeywordsタグの評価をやめ、現在では完全に無視するようになっています。
この変更により、現在ではSEOの効果を期待してこのタグを使用する意味はほとんどなくなりました。
ほかのメタタグとの違い
keywordsタグとよく比較されるのが、descriptionタグです。
どちらもメタタグの一種で、ページの情報を検索エンジンに伝える目的で使われますが、役割はまったく異なります。
keywordsタグ:ページに関連するキーワードを指定するために使う。現在はGoogleなどの検索エンジンでは無視されている。descriptionタグ:検索結果に表示されるページの説明文を指定する。現在でも使われており、クリック率に影響する可能性がある。
また、titleタグも重要なメタ情報の一つです。これはブラウザのタブや検索結果のタイトル部分に表示されるもので、ページの内容を短く正確に表現する役割があります。
SEOにおいては今でも強い影響力を持っており、適切なキーワードを自然に盛り込んだタイトルにすることが効果的とされています。
そのため、現在のSEOではkeywordsタグを使うよりも、タイトルや見出し、ページ全体の内容に自然な形でキーワードを入れることが重視されています。
さらに最近では、検索エンジンがユーザーエクスペリエンス(UX)やコンテンツの品質を重視するようになっており、単純にキーワードを入れるだけでは評価されにくくなっています。
keywordsタグは現在のSEO対策では重要視されていないものの、過去の流れを知ることで、なぜ今のSEOが「内容重視」になったのかを理解しやすくなります。
タグの使い方に迷ったときは、ページの目的と訪問者の視点を第一に考えて設定することが大切です。
かつては重要?meta keywordsが使われていた理由

昔はSEO対策の定番だった
Webサイトが検索結果で目立つためには、検索エンジンに自分のページがどんな内容なのかを伝える必要があります。
現在のようにAIが文章を読み解く技術がなかったころは、ページの表面的な情報をもとに検索順位を決めていました。
その中でもmeta keywordsタグは、検索エンジンにキーワードを伝えるための重要な手段として、多くのWebサイトで使われていました。
サイト制作者は、ページ内容に関連する言葉をこのタグに入れておくことで、「このページは〇〇について書いています」と検索エンジンに伝えていたのです。
たとえば、料理レシピサイトであれば、「レシピ, 簡単, 時短, 夕食」などのキーワードを記述することで、そうした言葉を検索した人の目に留まりやすくなることを期待していました。
検索順位に直接影響していた時代
今では考えられないかもしれませんが、かつてはkeywordsタグに入力した言葉が検索結果の順位にそのまま影響することがありました。
検索エンジンは、Webページの構造や文章を深く理解する力が弱かったため、こうしたタグの情報に大きく頼っていたのです。
そのため、多くのWeb担当者が競ってこのタグにビッグキーワードやロングテールキーワードを大量に入れるようになりました。
タグの中に人気の言葉を入れておけば、たとえその言葉が実際のページに出てこなかったとしても、検索結果で上位に表示される可能性があったからです。
この仕組みをうまく活用すれば、文章の内容よりもタグの工夫だけでアクセス数を増やすことが可能でした。
どうして使われなくなったのか
Googleは現在、meta keywordsタグの内容を検索順位の評価対象として使用していません。
これはGoogleの公式ブログでも明言されており、SEO対策としてこのタグを設定しても意味がないというのが一般的な認識です。
keywordsタグが使われなくなった理由は、その機能が過剰に利用されすぎたことと、検索エンジン側の進化にあります。
まず、多くのサイトが本来の内容と関係ない人気ワードを詰め込み、検索結果が実際の内容と合わないページで溢れるようになってしまいました。
ユーザーが求めている情報にたどり着けない状況が増え、検索エンジンの品質が下がってしまったのです。
そこで検索エンジン各社は、より正確にページの内容を判断できるような仕組みを開発していきました。
現在では、実際の文章や見出しの構成、内部リンクの流れ、ユーザーエクスペリエンスなど、ページ全体の構造や内容の「中身」を重視するようになっています。
その結果、meta keywordsタグの情報は検索順位にまったく影響しなくなり、今ではGoogleも公式に「無視しています」と明言しています。
スパム対策としての背景
meta keywordsタグの廃止には、スパム対策という大きな背景があります。
このタグを使って、本来関係のないキーワードを大量に書き込むことで、不正にアクセスを集める行為が多発しました。
たとえば、まったくスポーツと関係ないページに「サッカー, オリンピック, 野球」などのキーワードを入れて、検索からの訪問者を集めようとするようなケースです。
こうした手法はキーワードスパムと呼ばれ、検索結果の質を著しく下げる原因となっていました。
検索エンジンはそのような行為を見つけるたびに対策を強化してきましたが、いたちごっこのように続くこともあり、最終的にこのタグ自体を評価対象から外すという対応が取られました。
今では、検索結果の質を守るための取り組みの一環として、meta keywordsタグの無効化が常識となっています。
過去のSEOとの違い
現在のSEO対策は、過去とは大きく変わっています。
昔はキーワードを入れるだけで効果があったため、簡単に見える対策が主流でした。しかし今は、ページの構造・内容・ユーザーエクスペリエンス・外部からの評価など、さまざまな要素が組み合わさって評価されるようになっています。
以下のようなポイントが、過去と現在のSEOで異なる部分です。
- キーワードの使い方
昔はタグに書けばOKだったが、今は文章の自然な流れの中で使うことが大事 - 内容の質
昔は文字数やキーワードの数が重視されたが、今はユーザーのニーズに合った内容が評価される - 検索エンジンの見方
昔はタグ頼り、今はページ全体を理解して判断
そのため、meta keywordsタグを使うことに時間をかけるよりも、読みやすい構成で、訪問者の求めている情報をしっかりと届けるコンテンツ作りに注力した方が、結果的に検索でも見つけられやすくなります。
検索エンジンに評価されるには、技術的なタグの設定よりも、ページの質やわかりやすさが大切です。
今のSEOは、人が読んで納得できる内容をどう作るかに重点が置かれているのです。
ものの質を高めることや、ページの構成を整えることに時間を使った方が、検索エンジンにきちんと評価される近道となります。
meta keywordsタグの設定方法と書き方のポイント
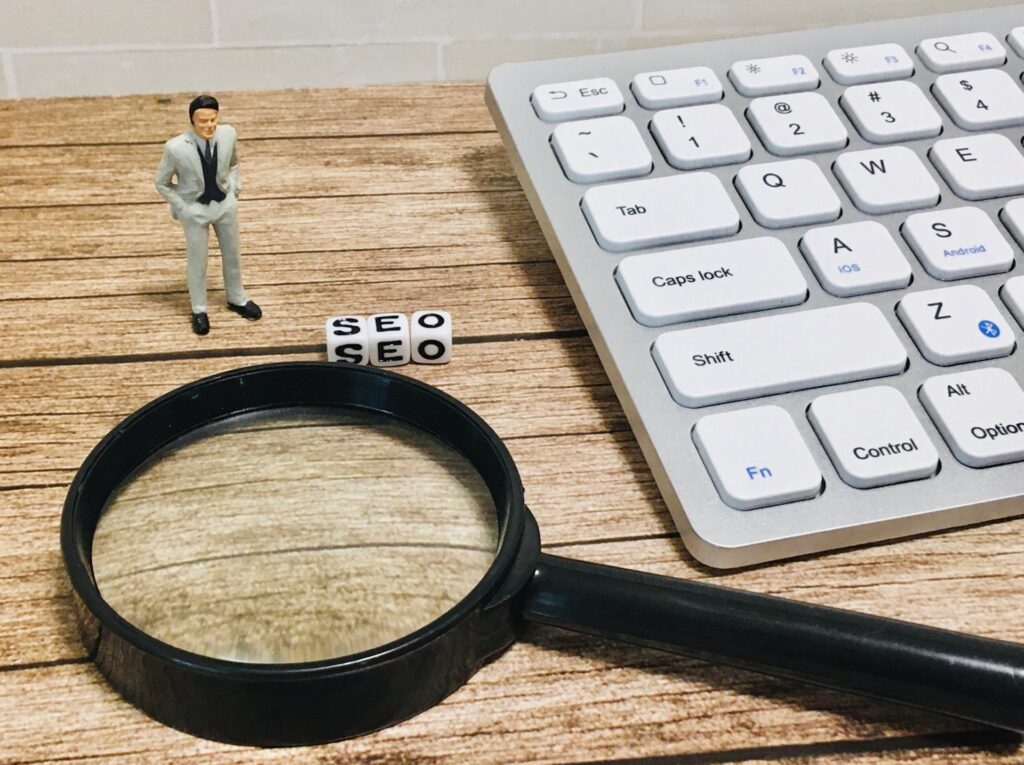
書き方の基本ルールとは?
現在では多くの検索エンジンがこのタグを無視していますが、記述する場合は正しい形で設定することが大切です。
基本的な記述方法は次の通りです。
<meta name="keywords" content="SEO, metaタグ, 設定, Webマーケティング">
このように、<meta>タグの中で「name」属性に”keywords”、「content」属性にカンマで区切ったキーワードを記載します。
キーワードの並びは自由ですが、ページ内容と関係のある言葉に限定することが原則です。
設定するときに使うタグの例
HTMLの構造に慣れていない方でも、meta keywordsタグの位置は比較的わかりやすいです。headタグの中に記述するのが基本です。
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>ページのタイトル</title>
<meta name="description" content="このページの簡単な説明文です。">
<meta name="keywords" content="SEO, metaタグ, 設定, Webマーケティング">
</head>
このように、タイトルやdescriptionと並んで設定されることが一般的です。
HTMLファイルの冒頭で記述されるため、設定ミスがあると全体の構文にも影響を与えることがあります。
閉じタグの抜けなどには注意が必要です。
どんな言葉を入れればいいの?
meta keywordsに入れる言葉は、そのページの内容に深く関連しているものに限るべきです。
具体的には、記事やページで実際に使っている用語、読者が検索する可能性のある言葉が適しています。
キーワードの選び方の考え方には以下のような基準があります。
- ページの主なトピックに関連していること
- ページ内に実際に含まれている言葉であること
- ビッグキーワードだけでなくロングテールキーワードも含めること
また、似たような言葉を無理に並べるのではなく、検索意図を意識したキーワードの組み合わせを意識すると、内部的な整理にも役立ちます。
たとえば「SEO対策」というページに以下のようなキーワードが考えられます。
- SEO
- 検索エンジン
- metaタグ
- コンテンツ制作
- 上位表示
- アクセス解析
ただし、現在ではmeta keywordsを見て順位を決める検索エンジンはほぼ存在しないため、過剰に詰め込む必要はありません。
キーワードの数や区切り方のコツ
meta keywordsに記述するキーワードの数には明確な上限はありませんが、一般的には5〜10個程度にとどめておくのが無難です。
あまりに多くのキーワードを詰め込みすぎると、スパムと見なされるリスクがあります。
区切りには「半角カンマ(,)」を使います。全角の「、」や空白では正しく認識されないことがあります。
以下は良い記述例です。
<meta name="keywords" content="Webマーケティング, SEO対策, コンテンツ制作, キーワード調査, metaタグ">
悪い記述例は以下のようなものです。
<meta name="keywords" content="SEO, SEO, SEO, 安い, 無料, おすすめ, クレジットカード, 車, 音楽">
このように無関係なワードを入れたり、同じキーワードを繰り返すのは避けてください。
書くときによくある間違い
meta keywordsタグを記述するとき、特に初心者の方が陥りやすいミスがあります。
以下に代表的なものを挙げます。
- 関係のないキーワードを入れてしまう
内容と無関係な語句は評価されないだけでなく、信頼性を損ねることがあります - ひとつのキーワードを何度も繰り返す
スパムと判断される可能性があります - タグの場所が間違っている
head内でない場所に記述するとHTMLのエラーになる可能性があります - 区切り方が誤っている
半角カンマを使用せず、空白や全角カンマを使うと正しく認識されません - キーワードが多すぎる
長くなりすぎると逆に逆効果になりやすく、検索エンジンにとっても読みづらい情報になります
以下のような記述は避けるようにしてください。
- キーワードの羅列:SEO, SEO, SEO, SEO
- 誘導目的の人気ワード混入:ダイエット, 音楽, 芸能人, 話題
meta keywordsタグをどうしても使う必要がある場合でも、設定は控えめに行い、過度なSEO対策をしないことが、現在のWeb制作では大切になっています。
内容と一致した自然な表現を選び、タグの記述に依存せずにページそのものの質を高めることが最も重要です。
まとめ
meta keywordsタグは、かつては検索エンジンにページの内容を伝えるための手段としてよく使われていました。
しかし、現在のGoogleなどの検索エンジンはこのタグをまったく評価に使っていないため、SEO対策としては効果がないと考えられています。
むしろ、関係のないキーワードを入れすぎると、スパムとみなされてサイトの信頼を下げる原因になることもあります。
もしどうしても使う必要がある場合でも、そのページに関係する言葉を簡潔にまとめて記述する程度にとどめるのが安心です。
たとえばCMSの仕様で入力が必須になっているときや、内部的な整理が目的のときなどには意味があります。
今のSEOでは、キーワードタグよりもページの文章や見出しがわかりやすいかどうか、訪問した人が読みやすく満足できるかなど、ページ全体の内容や使いやすさが評価されています。
meta keywordsの設定に時間をかけるよりも、読み手にとって役に立つコンテンツを作ることが何よりも大切です。
まずは訪問者のことを考えて、やさしく、わかりやすく情報を伝えることを意識しましょう。




