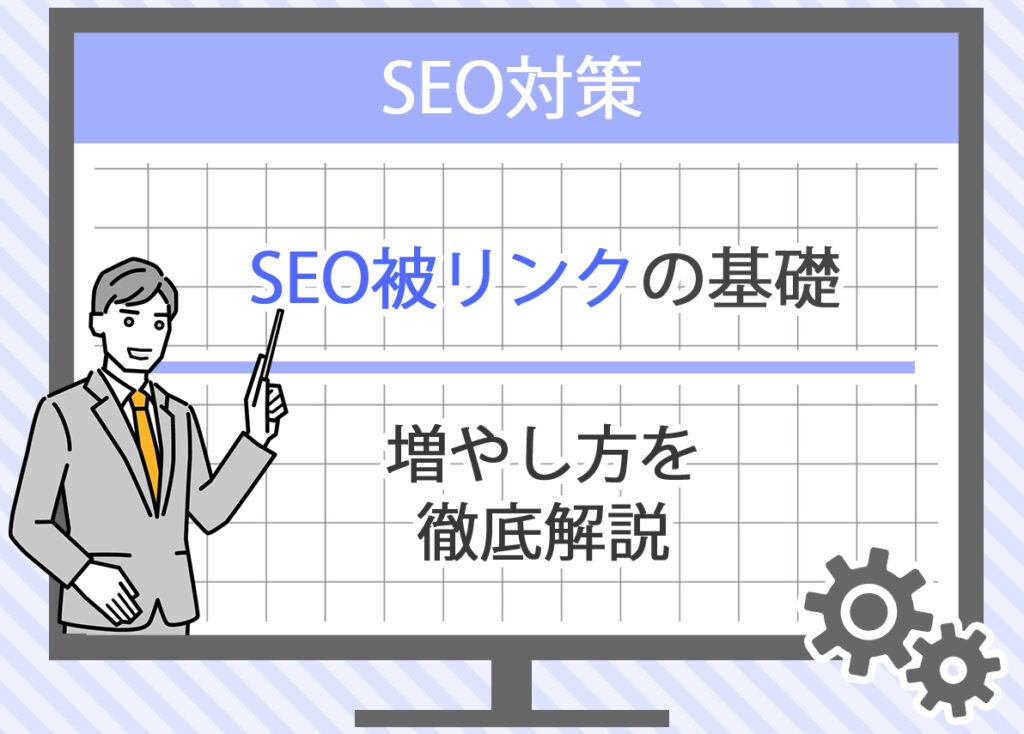
「検索で自分のサイトが上に出てこない…」そんな悩みをお持ちではありませんか?
実はその原因のひとつに「被リンク」というものが関係しています。
被リンクとは、他のサイトから自分のサイトへ向けて貼られたリンクのことです。
これは、検索エンジンが「このサイトは信頼されている」と判断するための大切なポイントのひとつ。
初心者向けに基礎から順を追ってご紹介していきます。
SEOにおける被リンクとは?基礎をわかりやすく解説

そもそもSEOってなに?
SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、日本語では検索エンジン最適化と呼ばれています。
これは、Googleなどの検索エンジンで自分のwebサイトをできるだけ上のほうに表示させるための工夫のことです。
SEOには大きく分けて2つの方向性があります。
- 内部対策:自分のサイトの中身を整理し、見やすく、わかりやすくすること
- 外部対策:他のサイトとのつながりや信頼を高めること
被リンクはこのうちの外部対策にあたります。
被リンクってどんなリンクのこと?
被リンクとは、他のサイトから自分のwebサイトに向けて貼られるリンクのことです。
たとえば、Aさんが書いたブログに「おすすめのお店はこちら」として、Bさんのお店のホームページへのリンクが貼られていた場合、このリンクはBさんのサイトにとって「被リンク」になります。
リンクを「もらう」側が“被”リンクと呼ばれるのがポイントです。
Googleは、このような被リンクを「他のサイトから推薦されている」と見なします。
つまり、たくさんのサイトからリンクされているページは「内容が役立つもの」と判断されやすくなるのです。
なぜ被リンクが検索順位に影響するの?
Googleなどの検索エンジンは、検索結果の順位を決めるときにさまざまな要素をチェックしています。
その中でも被リンクの数や質は、特に重視されている要素のひとつです。
検索エンジンは「このサイトはどれくらい他のサイトから評価されているか」を被リンクで見極めようとします。
リンクが多い=おすすめされていると考えるためです。
ただし、数だけを増やせば良いというわけではありません。
最近では、「質の低いサイトから大量にリンクされている」ような状況だと、逆にペナルティとして順位が下がることもあります。
以下のような特徴を持つリンクは、検索順位に良い影響を与えやすいです。
- 信頼できるサイトからのリンク
企業や公共機関、業界専門サイトなど - 関連性の高いサイトからのリンク
同じテーマやジャンルの中でのリンク - 自然に貼られたリンク
無理やり作られたのではなく、紹介や引用の中に自然にあるリンク
このように、どこから、どのようにリンクされているかがとても重要になります。
内部リンクとの違いもチェックしよう
被リンクと似た言葉に「内部リンク」がありますが、役割が異なります。
内部リンクとは、同じwebサイト内でページ同士をつなぐリンクのことです。
たとえば、トップページから商品紹介ページへリンクが貼ってある場合、それは内部リンクです。
両者の違いをまとめると次のようになります。
| 用語 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 被リンク | 他のサイトから自分のサイトに貼られるリンク | 「このブログで紹介されているサイトはこちら」など |
| 内部リンク | 同じサイト内のページ同士をつなぐリンク | 「詳しくはこちらのページをご覧ください」など |
内部リンクもSEO対策には大切な要素ですが、信頼や評価に直結しやすいのは被リンクです。
そのため、外からリンクされる機会を意識してコンテンツを作ることが大事です。
初心者でもわかる被リンクのイメージ
被リンクの仕組みを簡単にイメージすると、「他人から紹介されること」と考えるとわかりやすいです。
- SNSで誰かが自分の投稿をシェアしてくれる
- 友達が自分のことを別の人に紹介してくれる
これらと同じように、web上で他のサイトが自分のサイトをリンク付きで紹介してくれると、それが検索エンジンへの信号になるのです。
また、こうしたリンクが多ければ多いほど、「この人は信頼できる情報を出しているんだな」と検索エンジンに思ってもらえます。
ただし、質が低い紹介や無理やりなリンクは逆効果になるので注意が必要です。
被リンクは「数」と「質」のバランスがとても大切です。
しっかりと情報を届け、自然と紹介してもらえるような内容を意識することが、結果的に検索順位を上げる力になります。
被リンクの効果と検索順位への影響とは

被リンクがあるとどんなメリットがあるの?
被リンクがあることで得られるメリットは、検索エンジンからの評価が高まり、検索結果の上位に表示されやすくなることです。
検索順位が上がることで、より多くの人にサイトを見てもらえるようになります。
被リンクには、以下のようなメリットがあります。
- 検索順位の向上:他のサイトからのリンクは「このサイトは参考になる」と評価されている証と見なされる
- 訪問者数の増加:リンク元のサイトを見ている人がリンクをクリックして訪れてくれる
- サイトの信頼性アップ:権威のあるサイトからのリンクは、内容への信頼性も高めてくれる
- ページの広がり:紹介されることでSNSやブログなどにも拡散されやすくなる
検索エンジンにとって被リンクは、「他の人から推薦された印」として扱われるため、ただ自分で情報を発信するだけでは得られない価値が生まれます。
検索エンジンはリンクをどう評価する?
Googleをはじめとした検索エンジンは、リンクをただの移動手段として見ているわけではありません。
「どんなサイトからリンクされているか」「どんな文脈で貼られているか」など、細かく内容を見て評価しています。
評価のポイントには次のようなものがあります。
- リンク元の信頼性:有名メディアや業界団体など、信頼されているサイトからのリンクは評価が高い
- 関連性の高さ:自分のサイトとテーマやジャンルが近いサイトからのリンクはより効果的
- リンクの貼り方:自然な文章の中で紹介されているリンクは評価されやすい
- リンクの位置:ページの上部や本文中にあるリンクは評価が高く、フッターやコメント欄などは低いことが多い
- リンクテキスト(アンカーテキスト):リンクに使われる言葉が内容と合っていると評価されやすい
検索エンジンは、これらの要素を組み合わせてリンクの質や意図を判断し、検索順位に反映させています。
上位表示されやすくなるって本当?
被リンクの効果で検索順位が上がるというのは事実ですが、すべての被リンクが同じように効果があるわけではありません。
大切なのは「どこから、どうやってリンクされているか」です。
次のような特徴を持った被リンクがあると、上位表示されやすくなる傾向があります。
- 業界に関連するサイトからのリンク
たとえば飲食店のサイトなら、グルメブログや地域紹介サイトからのリンクが効果的 - 評価の高いサイトからのリンク
長く運営されていて、更新頻度も高く、閲覧者も多いサイトは評価も高い - ナチュラルリンク
紹介記事や引用の中に自然に貼られるリンクは信頼度が高い
ただし、上位表示にはコンテンツの内容・使いやすさ・ページ表示速度など、被リンク以外の要因も複合的に関わります。
関係のないリンクが悪影響になることも
一見すると、リンクが多いほうが良さそうに感じますが、無関係なサイトからの被リンクはマイナスになる可能性もあります。
たとえば、以下のようなリンクは評価が下がる要因になります。
- ギャンブルや成人向けなど、まったく関連性のないジャンルからのリンク
- リンクを販売しているだけのサイトやスパム的なサイトからのリンク
- 自動的に作られたリンク集など、明らかに不自然な場所からのリンク
このようなリンクは、Googleから「意図的に検索順位を上げようとしている」と見なされることがあり、検索結果からの除外や順位低下といったペナルティの対象になることもあります。
Googleは、リンクの評価を見直す「ペンギンアップデート」という仕組みを持っており、不正なリンク対策を厳しくチェックしています。
リンクが貼られたページの質も大切
被リンクの評価は、リンク元のサイトだけでなく、実際にリンクが貼られているページの質も重要な判断基準になります。
質の低いページとは、以下のような特徴を持つことがあります。
- 文字数が極端に少なく、内容が薄い
- 広告ばかりで読みづらい構成になっている
- コピーページ(他のサイトの内容をそのまま使っている)
- 更新が何年も止まっている古いページ
逆に、質の高いページは次のような点が評価されやすいです。
- 読者の疑問や悩みにしっかり答えている
- 画像や図解、箇条書きを活用してわかりやすく整理されている
- ページ内のリンク構造が整っていて、読みやすい
- 検索ユーザーが求めている内容が丁寧に書かれている
リンクを貼ってくれるページの中身が充実していないと、せっかくの被リンクもSEO効果が弱くなってしまいます。
そのため、リンクしてもらう側の自分のコンテンツにも、一定以上の質が求められます。
SEOに強いリンクの特徴を知ろう
検索エンジンに高く評価されやすい「SEOに強いリンク」には、いくつかの共通した特徴があります。
これらを意識することで、被リンクの質を見極める力がつきます。
- アンカーテキストが自然でわかりやすい
リンクに使われているテキストが「こちら」や「詳細」だけでなく、内容に合った言葉になっている - ページ内の目立つ場所にある
本文中や見出しの近くなど、ユーザーが目にしやすい位置にある - リンク先とのテーマが一致している
ジャンルや話題に共通点があり、読者も違和感なく読み進められる - ページのアクセス数やSNSでの反応が良い
リンク元ページに多くのユーザーが集まり、シェアされている
こうしたリンクは、SEO面でも効果があり、ユーザーにとっても自然でわかりやすいため、クリックされやすいという利点があります。
リンクを増やすことにばかり注目するのではなく、どのようなリンクが評価されるのかを理解して、質の高い被リンクを目指す視点が大切です。
被リンクを増やす方法と獲得手順を紹介
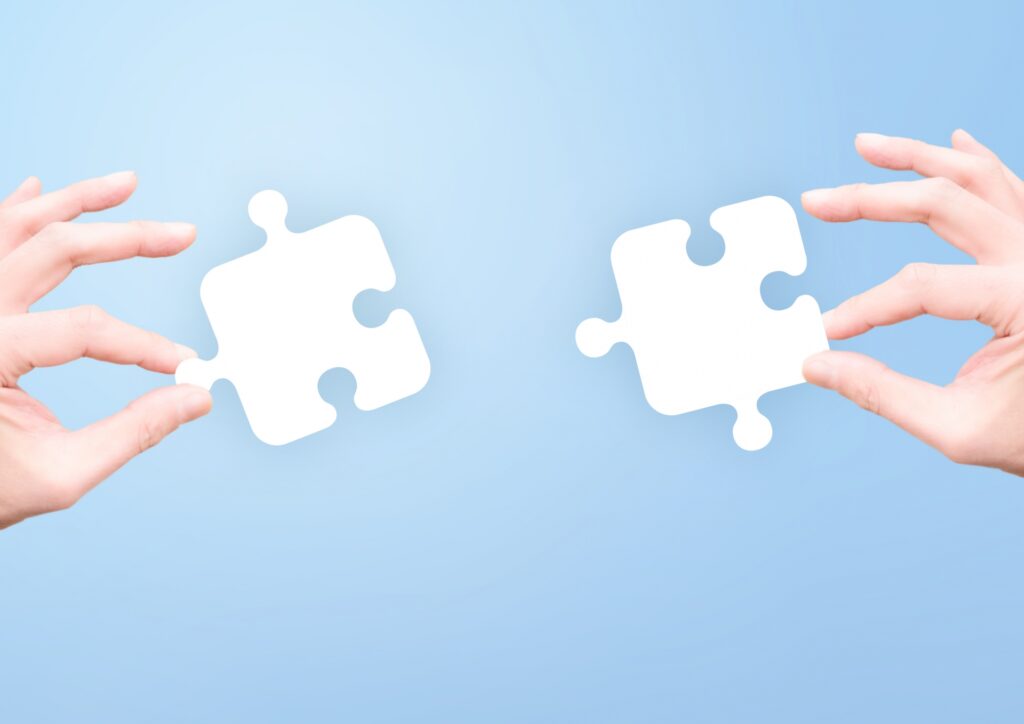
被リンクをもらいやすいページの作り方
ページ単体でリンクを得やすくするには、構成や設計段階でいくつかの工夫を加えておくことが効果的です。
以下は、被リンクを獲得しやすいページの特徴です。
- 検索されやすいテーマを選ぶ
ロングテールキーワードを意識して、具体的な悩みに答える構成にする - 情報に客観性がある
引用やデータ、調査結果を活用することで、信頼性が上がる - 読み終えた後に他人に共有したくなる構成になっている
要点がまとまっており、「この内容を誰かに伝えたい」と思わせる - 更新性がある内容にする
最新情報を盛り込むことで、検索にも強く、リンク先としての価値が長持ちする
「リンクを貼る価値がある」と自然に感じてもらえるページ設計が、被リンクの数と質に影響を与えます。
相互リンクの注意点と使い方
被リンクを増やす方法として「相互リンク」という考え方もあります。
これは、自分のサイトから相手にリンクを貼り、その相手からもリンクをもらうという仕組みです。
適切な相互リンクには効果がある場合もありますが、やり方によってはマイナスの評価を受けることもあるため、注意が必要です。
以下は相互リンクを行う際の注意点です。
- ジャンルや内容に共通点があるサイトを選ぶ
関連性のないサイトとのリンク交換は避ける - 不自然に大量のリンクを交換しない
数を稼ぐためだけのリンク交換はペナルティの対象になりやすい - リンク交換が目的のディレクトリサイトは使わない
スパム的とみなされる可能性が高い - 読者にとって有益な情報として自然にリンクする
無理に貼るのではなく、文脈の中で自然に紹介する
Googleも、意図的に順位を上げようとする相互リンクには厳しい目を向けています。
記事をシェアしてもらうための工夫
被リンクは、SNSなどでの「シェア」や「紹介」から自然に増えるケースも多くあります。
自分でリンクをお願いしなくても、多くの人に記事を知ってもらえる工夫をしておくことが大切です。
記事をシェアしてもらうためにできる工夫は次のとおりです。
- SNS用のタイトルや画像を設定しておく
XやFacebookなどでシェアされたときに目を引くデザインにする - シェアボタンを記事の上下に設置する
読者が気軽に投稿できるようにすることで拡散されやすくなる - 読者の声や体験談を取り入れる
共感されやすい内容はシェアされやすい - 記事内で明確な問いかけをする
「こんな体験、ありますか?」など読者との関係性を意識した文を入れる
SNSでのシェアは、一気にリンク数が増えるきっかけになることもあります。
特にテーマ性が強い記事や、旬な話題を扱っているコンテンツは、広がりやすいため意識して設計すると良いです。
被リンク対策で注意すべき5つのポイント

数だけを増やすのはNG
被リンクの数が多ければ良いという考えは、現在のSEO対策では間違いです。
確かに一昔前までは、リンクの数が多いほど検索順位が上がるとされていましたが、現在の検索エンジンはリンクの「数」よりも「質」を重視しています。
たくさんリンクがあるだけで中身が伴っていなければ、検索エンジンからの評価にはつながりません。
特に以下のような方法でリンクを無理に増やそうとするのは避けるべきです。
- 無関係なページから無作為にリンクを集める
検索エンジンは内容のつながりを重視するため、テーマが異なるリンクはマイナス評価の対象になる - 一度に大量のリンクを急増させる
自然な流れではないと判断され、不正な手法と見なされることがある - 自作自演のリンクを乱用する
複数の自分のサイトを使ってリンクを張り合うような手法は、ペナルティの対象になることがある
検索エンジンはユーザーにとって有益な情報を評価するよう設計されているため、リンクの「質」を高めることが重要です。
怪しいリンク交換には要注意
リンクの獲得方法として、相互リンクやリンク交換の依頼がありますが、過度なリンク交換や不自然な交換は危険です。
特に次のような状況には注意が必要です。
- SEO対策を目的としたリンク交換だけを目的とした依頼が届く
このような場合は、内容に関係がなかったり、リンク先が怪しいサイトであることが多い - 一部のディレクトリ登録型サイトへの大量登録
登録すれば簡単にリンクがもらえるようなサービスの多くは、現在では検索エンジンからマイナス評価を受けやすい - 報酬と引き換えにリンクを設置するような申し出
検索エンジンは「有料リンク」を厳しく取り締まっており、ペナルティの対象になります
Googleは明確に「検索結果を不正に操作しようとするリンク施策はルール違反」としています。
自然なリンクの構築を心がけ、リンク交換が必要な場合でも「ユーザーの役に立つ情報を共有する」ことが主目的であるかを判断基準にするべきです。
定期的にリンクの状態を見直そう
被リンクは一度得られたからといって、ずっとそのままにしておいて良いわけではありません。
時間が経つとリンク元のサイトの質が変わっていたり、不正リンクが追加されていたりすることもあります。
そのため、定期的にリンクの状態を確認し、必要に応じて対応する習慣が必要です。
リンクの確認に役立つツールは次のとおりです。
- Google Search Console
自分のサイトにどんなリンクがあるかを無料で確認できる公式ツール - ahrefsなどの外部SEOツール
より詳しく、リンク元の質や流入状況などをチェックできる - リンク否認ツール(Disavow Tool)
質の悪いリンクが発見された場合にGoogleに「このリンクは評価に含めないで」と伝えるためのツール
定期的にチェックすべきポイントは以下のとおりです。
- 知らないサイトからリンクされていないか
- 不自然なリンクテキストが使われていないか
- 同じページに過剰にリンクが集中していないか
検索エンジンにとって信頼され続けるサイトであるためには、被リンクのメンテナンスも大切な作業です。
リンクの数や表示順位に一喜一憂せず、地道な見直しと丁寧な管理を心がけることが、長期的なSEO対策につながります。
初心者でも簡単に使える便利機能とは
SEOツールの中には、初心者向けに設計された機能や表示が用意されているものもあります。
操作が直感的で、情報が視覚的にわかりやすく表示されるため、専門知識がなくても扱いやすいのが特徴です。
以下は初心者にやさしい機能がある代表的なツールです。
- Ubersuggestのダッシュボード
日本語対応で、画面の説明もわかりやすく、レポートをクリックするだけで重要な情報が表示される - MOZのスパムスコア表示
スパムっぽいリンク元を色付きで表示し、直感的にリスクを把握できる - Google Search Consoleのリンクレポート
表形式で簡潔に表示されており、不要な装飾がなく初心者に適している - おすすめの便利機能
- エクスポート機能:CSVやスプレッドシートで出力して管理がしやすくなる
- 履歴チェック機能:過去との比較でリンク数の推移を確認できる
- 通知機能:新しいリンクが発見されたときに知らせてくれる設定が可能なツールもある
ツール選びは操作性と表示のわかりやすさが重要です。
無理に高機能なものを選ばず、自分が使いこなせるものから始めることで、被リンク分析への理解が深まります。
最初のうちはGoogle Search ConsoleとUbersuggestの併用がとてもおすすめです。
まとめ
SEO対策において、被リンクはとても大切な要素のひとつです。
被リンクとは、他のサイトから自分のサイトへ向けて貼られたリンクのことで、検索エンジンはこれを「信頼されている証拠」として評価します。
ただし、リンクの数を増やせばよいという時代は終わっており、今は「質の高いリンク」が重視されています。
関連性のあるサイトから自然に貼られるリンクは、検索結果の順位を高める力になります。
一方で、無関係なサイトや信頼されていないページからのリンクは、評価を下げる原因になることもあるので注意が必要です。
また、自分のサイトがどこからリンクされているかを確認することも大切です。
Google Search Consoleなどの無料ツールを使えば簡単にチェックできるので、定期的に見直すようにしましょう。
質の低いリンクを見つけたら、削除や否認の対応も検討が必要です。
被リンクは、読みやすく役に立つコンテンツを作り、自然に紹介されるようにすることが基本です。
日々の発信やSNSでの共有も、リンクを増やす大きなきっかけになります。地道な積み重ねが、検索で上位に表示されるための近道になります。




