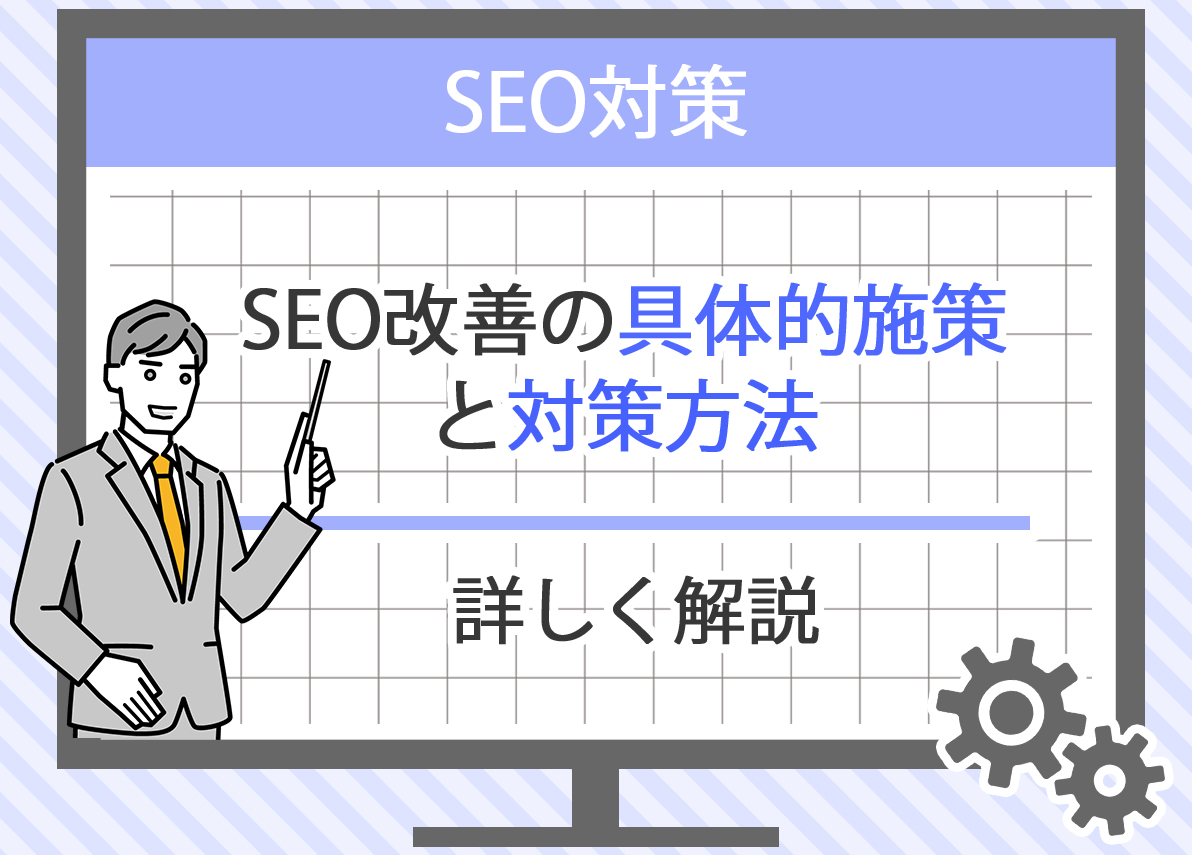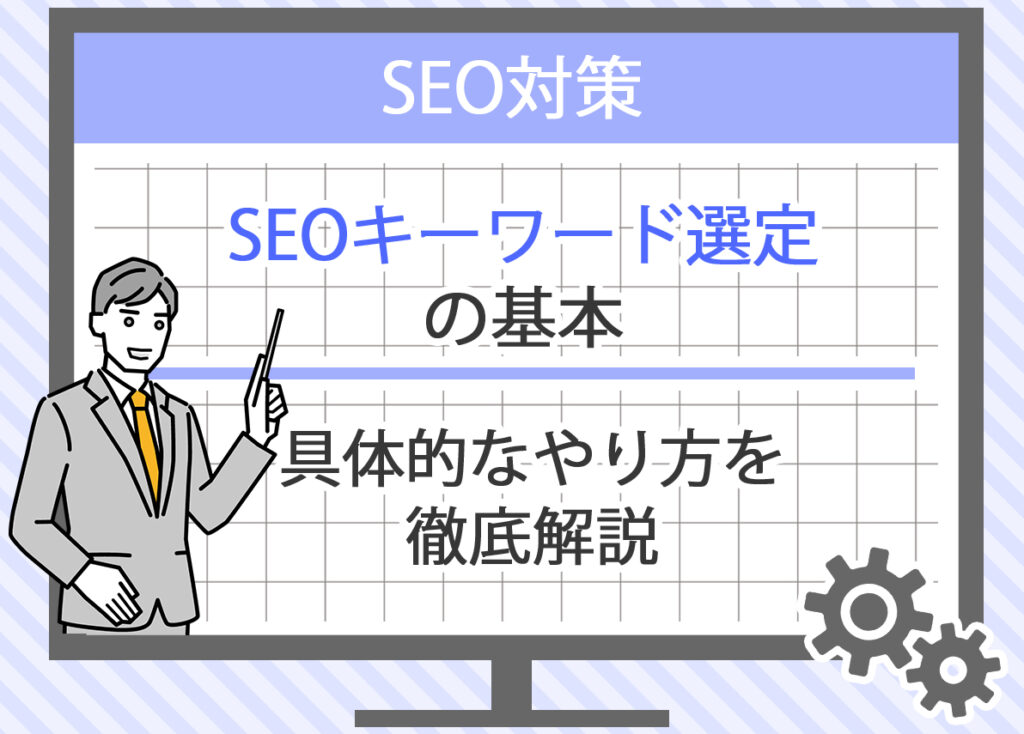
SEO対策を始めたいけれど「キーワードはどう選べば良いのか」と迷っていませんか。
この記事では、検索結果で上位を目指すために欠かせないキーワード選定の基本から、実際にコンテンツへ自然に入れる方法、注意すべきポイントまでを初心者にもわかりやすく解説します。
難しい専門用語はできるだけ避け、かみ砕いた言葉で説明するので、これからWebサイトやブログを運営したい方も安心して読めます。
検索されやすい言葉を知ることは、SEO対策の最初の一歩です。
読み進めることで、自分のサイトに適したキーワードの探し方や使い方を理解し、検索エンジンとユーザー双方に伝わる記事作りの基礎を身につけられます。
SEO対策におけるキーワードの重要性とは?
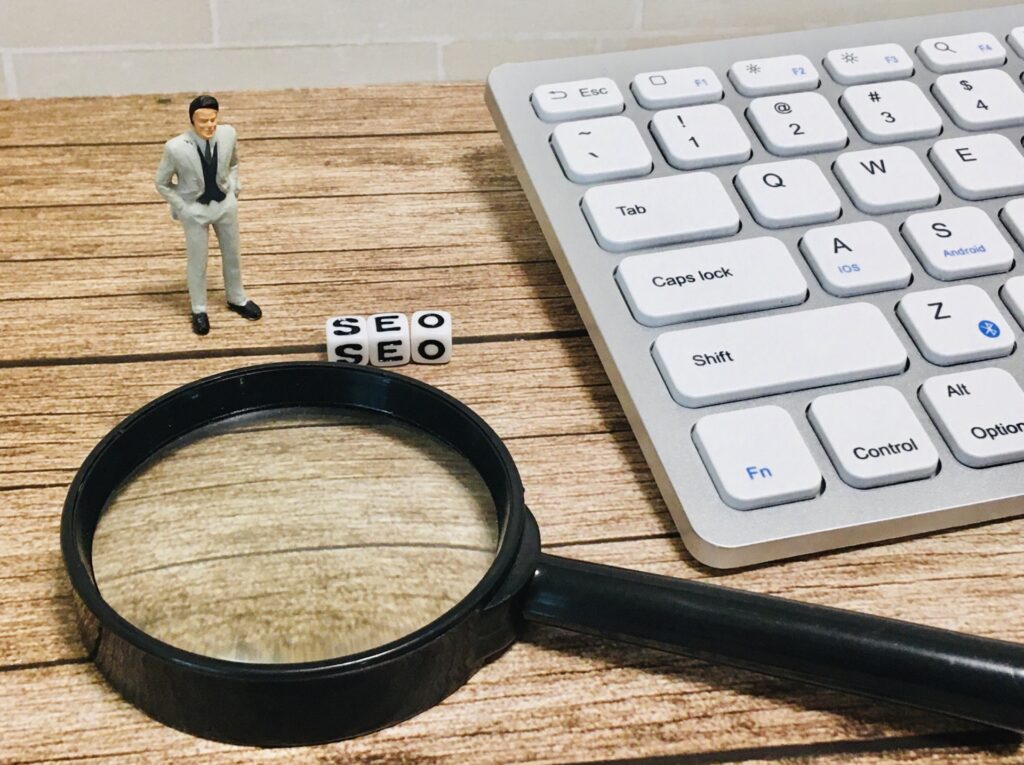
そもそもSEOってなに?
SEOは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、Googleなどの検索エンジンで自社サイトや記事を見つけてもらいやすくするための取り組みを指します。
たとえば「レモンケーキ レシピ」と検索した人に、あなたのレシピ記事が上位表示されれば、読まれる機会が増えます。
近年の検索は単語の一致だけでなく検索意図(インテント)や文脈も理解する傾向が強く、キーワード選定は「どんな人が、どんな状況で、何を解決したいか」を言語化する作業でもあります。
まずは検索されやすい言葉を選び、ページ内に自然な形で組み込み、読み手の課題に沿った情報構成にすることが基本です。
キーワードが検索結果に与える影響
検索エンジンはページの文字情報を解析し、「このページは何について書かれているか」を判断します。
判断材料にはタイトルタグ、見出し(h1〜h3)、本文、画像のalt、内部リンクのアンカーテキスト、メタディスクリプションなどが含まれます。
テーマが「手作りクッキーの作り方」であれば、以下のような語が自然に現れるはずです。
- クッキー 作り方
- 手作り クッキー レシピ
- クッキー 材料
こうした主語となるキーワードに加えて、関連語や共起語が文脈に沿って現れることで、ページの内容がより正確に伝わります。
逆に、関連の薄い語ばかりを散在させると「何のページか不明確」と判断され、上位表示が難しくなります。
なぜキーワード選びが成果のカギになるのか
良い記事を書いても、検索されない言葉だけを使っていれば見つけてもらえません。
いわば「看板のないお店」の状態です。
キーワード選びでは次の観点が重要です。
- 検索する人が実際に入力しそうな語(サジェストや検索クエリの実例)であること
- 競合性が過度に高すぎないこと(上位の面子やサイト規模を確認)
- 自分のページ内容との関連性が強いこと(検索意図との一致)
キーワードの種類も理解しておくと便利です。
- ビッグキーワード
検索回数が多い単語(例:カレー、旅行、ダイエット)。競合が非常に強い傾向があります。 - ミドルキーワード
2〜3語の組み合わせで適度な検索数(例:夜ご飯 カレー、旅行 夏 国内)。 - ロングテールキーワード
複数語で具体的な悩みや条件を含む(例:夜ご飯 カレー 簡単 レシピ、旅行 夏 国内 子連れ)。
検索数は控えめでも、意図が明確でコンバージョンにつながりやすい場合があります。
初心者の方は、まずロングテールキーワードから取り組むと、内容との親和性が高く、競合とも差別化しやすくなります。
検索ボリュームや競合性を見ながら、段階的にミドルへ広げる設計が現実的です。
よくある間違ったキーワードの使い方
キーワードは「入れれば良い」わけではありません。次のミスは避けましょう。
- キーワードの詰め込み(スタッフィング)
1文や1段落に不自然に繰り返すと読みづらく、ユーザーエクスペリエンスを損ねます。 - 検索意図とズレた語を使う
例:「安く海外旅行する方法」を求める人に「高級ホテル」の語ばかりを配置する。 - タイトルだけに入れて本文で触れない
本文や見出し、画像のaltなどにも自然に登場させることが大切です。 - 検索ボリュームが極端に少ない語だけを狙う
想定読者がほとんどいなければアクセスは伸びません。 - 流行語・一過性の話題に過度に依存する
短期間で需要が消えると、継続的な流入が見込みにくくなります。
キーワードは、読者の課題や文脈に沿って使うことで力を発揮します。
検索意図を起点に、タイトル・見出し・本文へ自然に配置していくことが、結果的に評価につながります。
検索キーワードの種類と分類を知ろう

検索キーワードは「どんな目的で検索しているか」によって分類できます。
検索意図を理解することで、記事の方向性や内容をより的確に決められます。
「今すぐ買いたい」検索と「調べたい」検索の違い
検索には、購入を前提とした「今すぐ買いたい」目的と、情報を集める「調べたい」目的があります。
例として「革靴 メンズ 安い」と検索する人は購入意欲が高く、「革靴 メンズ ブランド ランキング」と検索する人は比較検討中です。
- 今すぐ買いたい(購入目的)
「購入」「通販」「安い」「申し込み」「クーポン」などが含まれるキーワード。
行動にすぐ移す可能性が高い検索です。 - 調べたい(情報収集目的)
「比較」「おすすめ」「ランキング」「使い方」「違い」などが含まれるキーワード。
購入前に情報を集めている段階を示します。
検索意図を誤ると、ユーザーが求める情報と記事内容がずれて離脱につながります。
検索者がどの段階にいるのかを想定し、記事構成を調整することが大切です。
検索キーワードを3つのクエリタイプで理解する
ユーザーが検索を行う行動段階は、次の3つに大別できます。
- ナビゲーショナルクエリ
特定のサイトやブランドを直接探す検索
例:「ユニクロ 公式サイト」「Amazon ログイン」 - インフォメーショナルクエリ
知識や方法を知りたいときの検索
例:「パンケーキ 作り方」「SEOとは」 - トランザクショナルクエリ
購入・予約・申込みなどの行動を伴う検索
例:「宅配弁当 注文」「格安スマホ 比較」
ユーザーがどの段階にいるかを把握することで、どの情報をどの順序で提示すべきかが見えてきます。
特にインフォメーショナルクエリでは、過度な販売促進は避け、まず信頼を築く内容が効果的です。
よく見かける検索ワードのパターン
キーワードには頻出するパターンがあり、選定時に役立ちます。
- 「とは」型
意味を調べる検索(例:SEOとは、ロングテールキーワードとは) - 「方法」「やり方」型
具体的手順を求める検索(例:ブログ 書き方、パンの作り方) - 「おすすめ」型
比較・選び方を検討する検索(例:パソコン おすすめ、転職サイト おすすめ) - 「比較」「違い」型
どちらが良いかを知りたい検索(例:iPhone Android 違い) - 「安い」「格安」型
価格重視の検索(例:家具 安い 通販)
これらは検索ボリュームが安定しており、ユーザーのニーズが明確なため、ページ内容に沿って取り入れると効果的です。
ユーザーの気持ちを想像して分類する
キーワードを選ぶときは、検索者の背景や心理を想像することが欠かせません。
例えば「筋トレ メニュー 自宅 初心者」と入力する人を考えると、次のような状況が想定できます。
- ジムには通っていない
- 運動経験は少なめ
- 自宅でできる範囲の運動を知りたい
- 費用はかけたくない
- 続けられるか不安がある
このように検索語の裏側にある動機や状況を読み取ることで、ユーザーエクスペリエンスを高めた記事構成が可能になります。
意識しておきたいポイントは次の通りです。
- どんな状況でこの言葉を検索しているか
- 何に困っていて、どんな解決を求めているか
- 検索後にどんな行動を取りたいか
ユーザー心理を把握して作成された記事は、検索エンジンからの評価も上がりやすく、長期的に読まれるコンテンツにつながります。
適切なキーワードを選定する5つのポイント

検索で見つけてもらうためには「実際に検索されている言葉を選ぶ」ことが何より大切です。
ここでは2025年現在の最新動向も踏まえ、キーワード選びで意識したい5つの視点を紹介します。
検索されやすい言葉を選ぶ
自分が書きたいテーマだけを重視すると、検索結果に表示されないページになってしまいます。多くのユーザーは文法より気持ちを優先して検索するため、「スマホ 電池 早い」や「カレー 作り方 簡単」のように話し言葉に近いフレーズを意識しましょう。
検索されている語を調べるには以下の無料ツールが役立ちます。
- ラッコキーワード:公式 https://related-keywords.com/
- Google トレンド:公式 https://trends.google.co.jp/
関連語や検索回数、季節ごとのトレンドを確認して、実際の検索クエリに沿ったキーワードを選定します。
競合が強すぎるキーワードを避ける
「旅行」「ダイエット」「英語」など検索回数が非常に多いビッグキーワードは競争が激しく、上位表示は困難です。
初心者は次のように条件を絞ったロングテールキーワードを狙うと効果的です。
- 具体的な悩みに特化
「肩こり 解消 ストレッチ 30代 女性」 - 地域や目的を明確化
「脱毛 札幌 学生向け」
検索ボリュームが中程度(目安100〜1,000回/月)のキーワードは、競合が比較的少なく上位を狙いやすくなります。
自社らしさを反映させる
検索されやすい語だけに頼ると他サイトと似た内容になりがちです。
サービスや商品の特徴、ターゲットユーザー、地域性など自社ならではの強みをキーワードに盛り込むことで差別化できます。
- ターゲットを示す
「30代 子育てママ向け」「初心者歓迎」 - 特徴を伝える
「時短レシピ」「低価格で始められる」 - 地域を入れる
「福岡 オンライン英会話」「大阪 出張整体」
独自性を持つキーワードは、ユーザーの検索意図にも合いやすく、長期的な集客につながります。
検索ボリュームを確認する
「検索ボリューム」は1か月間にその語が何回検索されているかを示します。
多すぎると競合が激化し、少なすぎると流入が望めません。
以下のツールで調べるのがおすすめです。
- Google キーワードプランナー(Google広告アカウントで利用可)
- Ubersuggest:公式 https://neilpatel.com/jp/ubersuggest/
さらにGoogleトレンドで過去の推移を確認すると、季節性や一時的なブームも把握できます。
長く使えるキーワードか見極める
短期間で消える流行語より、長期的に検索されるロングライフキーワードを選びましょう。
- 一過性の流行語を避ける
「2025年 トレンド」などは寿命が短い - 日常的な悩みを狙う
「寝不足 解消」「肩こり ストレッチ」など - 特定企業やキャンペーン名への依存を避ける
継続的に検索される語を選ぶことで、記事が長く読まれ続け、検索エンジンからも安定して評価されます。
キーワード選びは、検索数だけでなく「誰に読んでもらい、どんな目的を果たすか」を明確にすることが基本です。
これら5つのポイントを押さえることで、ユーザーエクスペリエンスを高め、長く成果を生むSEO対策が可能になります。
無料で使えるキーワード調査ツール

キーワード選定を効率よく進めるには、信頼できるツールの活用が欠かせません。
ここではWeb初心者でも始めやすい無料ツールを中心に活用価値の高い方法をまとめました。
初心者にやさしい人気の無料ツール
無料で使えるキーワード調査ツールは、検索されやすい言葉を把握する第一歩として非常に便利です。
特に以下の2つは定番です。
「ラッコキーワード」でサジェストを調べる方法
「ラッコキーワード」は、ある言葉に関連する検索候補を一気に調べられる便利なツールです。
使い方はとても簡単で、初心者でもすぐに使えます。
使い方の流れは次のとおりです。
- ラッコキーワードのサイトを開く
- 調べたいキーワードを入力
- 検索ボタンをクリック
すると、以下のような情報が表示されます。
- サジェストキーワード:Googleサジェストに基づく関連ワード
- 共起語:検索結果の中で頻繁に一緒に使われている言葉
- Q&Aサイトの質問一覧:Yahoo!知恵袋などで実際に出ている質問文
サジェストにはユーザーのリアルな悩みが反映されているため、見出しや本文にそのまま活かすことができます。
また、有料プランに登録すると検索ボリュームや競合性も確認できますが、無料でも十分に役立つ情報が得られます。
Googleのツールで検索数をチェックする
Googleのキーワード関連ツールは、正確な検索ボリュームの把握に向いています。
代表的なツールとしては「Google キーワードプランナー」があり、広告用のアカウント(Google広告)を作成すれば、誰でも使うことができます。
使うことで以下のような情報がわかります。
- 月間検索数の目安:1か月あたりにどれくらい検索されているか
- 競合の強さ:そのキーワードを使っている広告主の多さ
- 関連キーワード一覧:似たような言葉や組み合わせも表示される
検索数が多いものは、ページを作っても多くの人に見つけてもらいやすいですが、競合も多くなる傾向があるため、ロングテールキーワードと併用するのが現実的です。
もうひとつのおすすめはGoogleサーチコンソールです。
こちらは、自分のWebサイトにどんなキーワードでアクセスされているかを分析できます。
公式サイト:https://search.google.com/search-console/
有料ツールと無料ツールの違いとは?
無料ツールでも多くの情報が得られますが、より詳しく、かつ効率的に調査したい場合には有料ツールが有利です。
無料ツールとの違いは次のとおりです。
- 表示されるデータの量と精度が違う:無料ではざっくりとした検索数しか見られないことが多いです。
- 競合サイトの詳しい分析ができる:他サイトの順位や被リンク、ドメインの強さなどもチェックできます。
- 効率化の機能が多い:キーワード分類、自動保存、検索トレンド分析など、業務の時短に役立ちます。
有名な有料ツールには以下があります。
- Ahrefs:公式 https://ahrefs.com/ja
- SEMRush:公式 https://ja.semrush.com/
- キーワードファインダー:公式 https://keywordfinder.jp/
初心者であれば、まずは無料ツールから始めて、必要になったら有料版を検討するのが現実的です。
どのツールを使えばいいか迷ったときの選び方
ツールを選ぶ際は、自分がどんな作業をしたいかに合わせて選ぶことが大切です。
キーワードの候補を探したいのか、検索数を見たいのか、競合を知りたいのかによって適したツールは変わります。
以下のような使い分けをすると判断しやすくなります。
- 候補をたくさん知りたいとき
→ ラッコキーワード、Googleサジェスト - 検索数や競合の強さを確認したいとき
→ Googleキーワードプランナー、Ubersuggest - トレンドを知りたいとき
→ Googleトレンド - 自サイトの現状を知りたいとき
→ Googleサーチコンソール
すべての作業を1つのツールで完結させようとせず、目的に応じて組み合わせて使うのがポイントです。
SEOキーワードをコンテンツに入れる方法と注意点

キーワードを効果的に入れることで検索エンジンに正しく内容を伝えられますが、使い方を誤ると読みにくくなったり評価が下がる可能性があります。
最新SEOの考え方を踏まえ、自然に取り入れるためのポイントをまとめました。
キーワードはタイトルに入れるのが基本
検索エンジンはまずページタイトルを確認して内容を判断します。
タイトルに主要キーワードがないと関連性が低いと見なされ、検索順位が下がる場合があります。
例:「SEO キーワード 選び方」を狙うなら、「初心者でもできるSEOキーワードの選び方」といった自然な形でタイトルに入れるのが効果的です。
ただし無理に詰め込むと不自然になり、クリック率の低下につながるため注意が必要です。
見出しと本文への配置
見出し(h2・h3)や本文にキーワードを含めることで、検索エンジンに記事構成を明確に伝えられます。
特に重要な見出しにはテーマに近いキーワードを、段落の導入にも自然に取り入れると、読み手にとっても内容がわかりやすくなります。
- h2 テーマに沿ったキーワード例「キーワード 選び方」「SEO ポイント」
- h3 補足的な内容例「ロングテールキーワードの探し方」
ページ全体にバランスよく配置することで、検索エンジンからの評価が高まりやすくなります。
無理な詰め込みは逆効果
キーワードを多く入れれば良いという考え方は古く、現在の検索エンジンは不自然な繰り返しを見抜きます。
以下の使い方は避けましょう。
- 同じキーワードを1文に何度も使用
- 文法が崩れるほど詰め込む
- 流れを無視してキーワードだけを散らす
これらはユーザーエクスペリエンスを損ない、離脱率の上昇や評価低下につながります。
自然に読める文章を心がけるには?
キーワードを取り入れる際は読者目線を優先します。
質問形式や言い換えを活用すると文章が自然になり、さまざまな関連語を盛り込みやすくなります。
- 質問形式にする
「SEO キーワードってどう選ぶ?」 - 言い換えを使って文脈に変化を出す
「キーワード選定」「検索語句の選び方」など - 見出しと本文で別の表現を使ってもOK
「調査」「分析」「探し方」などのバリエーションを活用
キーワードは主役ではなく、あくまで内容を補う要素として扱うことが重要です。
配置と使用回数の目安
明確なルールはありませんが、全体の3〜5%程度が自然とされます。以下の場所に分散させると効果的です。
- タイトル(titleタグ)
- ページ冒頭の導入文
- 見出し(h2・h3)
- 本文の各段落
- 画像のalt属性(画像の説明)
- メタディスクリプション
特定箇所に集中させるのではなく、ページ全体で無理のない配置を心がけましょう。
目的は検索にヒットさせることではなく、読者にわかりやすく情報を届けることです。
検索キーワードはそのサポートとして活用してください。
キーワード対策で成果を出すための改善方法

アクセス数や順位を確認する方法
キーワードを入れた記事を公開した後は、効果を確認しながら改善を重ねることが大切です。
検索順位やアクセス数を継続的に観察し、必要に応じて調整することで長期的な成果につながります。
- Google アナリティクス(GA4)
ページごとのアクセス数、平均閲覧時間、直帰率などを分析できます。
公式 https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ - Google サーチコンソール
検索クエリ別の表示回数・クリック数・平均順位を確認できます。
公式 https://search.google.com/search-console
これらを併用することで「どのキーワードで流入があるか」「順位がどの程度上がったか」を具体的に把握できます。
効果が出ない場合の見直しポイント
キーワード対策をしても成果が出ない場合は、以下を重点的に確認します。
- 選んだキーワードが検索意図と合っているか
- タイトルや見出しにキーワードが適切に含まれているか
- 情報が古くなっていないか、内容が浅くないか
- 競合記事の構成や情報量との差はないか
必要に応じて競合記事と比較し、見出しや具体例を補強していくと改善の方向性が見えます。
順位が下がったときの原因と対応
一度上位に表示されても、時間の経過や検索アルゴリズムの更新で順位が下がることがあります。
原因として多いのは次の通りです。
- コンテンツの鮮度不足(情報が古いまま)
- 競合サイトがより充実した記事を公開
- サイト内部のリンク切れや表示速度の低下
まずは記事の更新や最新情報の追加、内部リンクの見直しなど小さな改善から取り組みます。
定期的な改善で上位表示をキープ
SEOは一度で終わりではなく、継続的な改善が欠かせません。
次のような習慣を取り入れると、安定した成果が期待できます。
- 定期的に検索順位とアクセス数を確認する
- 新しい関連情報や事例を追加して鮮度を保つ
- 内部リンクや関連ページの導線を強化する
手を加え続けることで、検索エンジンから「更新されているサイト」と判断されやすくなるという効果もあります。
PDCAで継続的に強化
改善を効率的に回すにはPDCAサイクルが役立ちます。
- Plan(計画):狙うキーワードや記事構成を決定
- Do(実行):記事を作成・更新
- Check(確認):サーチコンソールやアナリティクスで成果を分析
- Act(改善):順位や流入状況に合わせて内容を修正
この流れを繰り返すことで、検索エンジンからの評価が少しずつ高まり、キーワード対策の成果を長期的に伸ばすことができます。
まとめ
SEO対策で何より重要なのは、検索する人の気持ちを理解し、役立つ情報を届けるページを作ることです。
キーワードはその出発点であり、どんな言葉が検索されているかを把握することが第一歩になります。
キーワード選定では検索数だけでなく、「その言葉を検索する人が何を知りたいのか」という意図を考えることが欠かせません。
具体的でニーズの高いロングテールキーワードを選ぶと、競合が少なく、読まれやすい記事作成につながります。
選んだキーワードは、タイトル・見出し・本文に自然に組み込むことで、検索エンジンにも読者にも内容が伝わりやすくなります。
ただし、無理に詰め込むと文章の流れが損なわれ逆効果になるため、読みやすさを重視しましょう。
さらに記事公開後は、アクセス数や検索順位を定期的に確認し、内容を更新しながら改善を重ねることが大切です。
継続的な見直しが検索エンジンからの評価向上につながります。
難しい専門用語を多用するよりも、「読者にとってわかりやすいか」という視点を持つことこそが、SEO対策で長く成果を得るための基本です。
SEOスコアを上げる方法については下記で詳しく紹介しています。
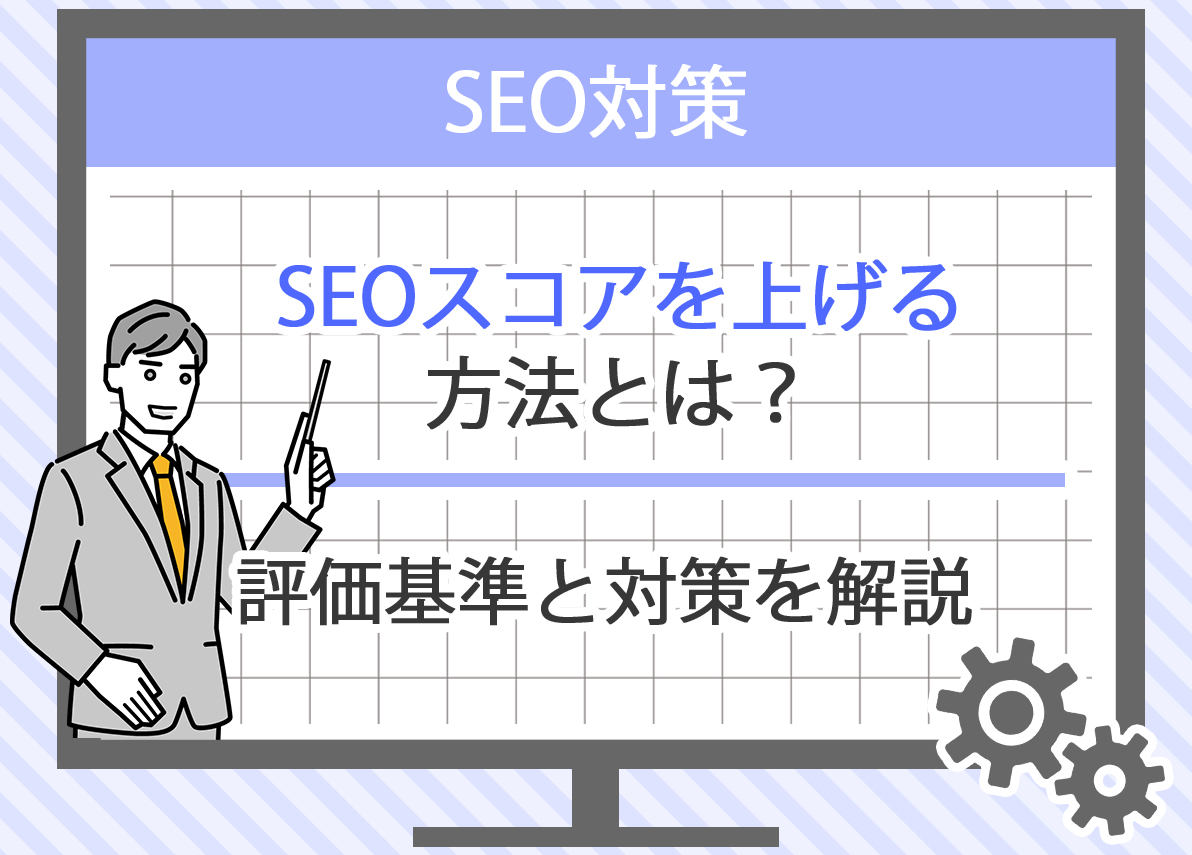
SEO改善の具体的施策と対策方法については下記で詳しく紹介しています。