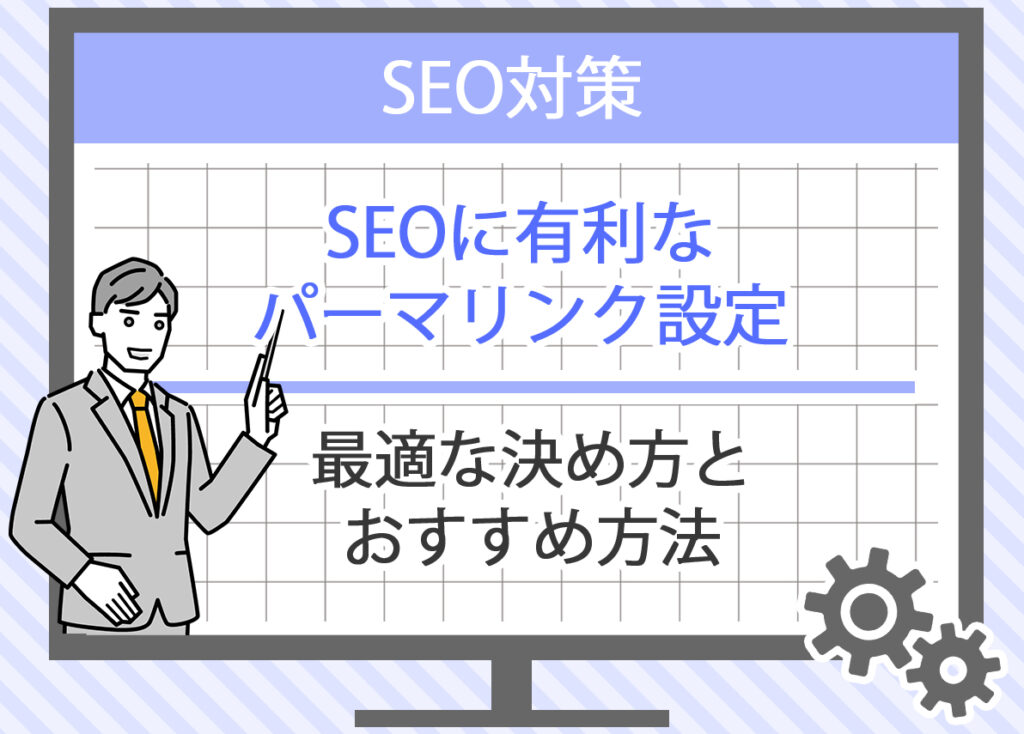
ブログやWebサイトを運営していると、「パーマリンク」という言葉を目にすることがあるかと思います。
なんとなく使っているけれど、どうやって決めたら良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
実はパーマリンクの設定は、検索エンジンの評価やユーザーの見やすさに関わる大切なポイントなのです。
特にWordPressを使って記事を書いている方にとって、最初にしっかり決めておくことがトラブル回避のコツになります。
この記事では、パーマリンクの意味から設定方法、SEOへの影響までを初心者の方でもわかりやすく丁寧に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
パーマリンクとは?基本の意味とSEOへの影響を解説

パーマリンクは「記事の住所」のようなもの
パーマリンクとは、Webサイトの各ページに割り当てられる固定のURL(アドレス)のことを指します。
「パーマネントリンク(Permanent Link)」の略で、文字通り恒久的なリンクという意味を持っています。
たとえば、ブログの記事やお知らせページなど、それぞれの内容に一つずつ住所のように割り当てられるのがパーマリンクです。
インターネット上のページには、見ている人がたどり着くための住所が必要になります。
その住所こそがURLであり、パーマリンクはそのページがどんな内容なのかを一目でわかりやすく伝える工夫が求められます。
パーマリンクが分かりにくいと、読んでいる人にも検索エンジンにも伝わりづらくなってしまうため、見た目や構造がとても重要になります。
なぜパーマリンクが検索順位に関係するのか
検索エンジンは、URLの中身もページの内容を判断する手がかりの一つとして見ています。
特に、GoogleではURL構造がページの評価基準のひとつになっています。
以下のような理由があります。
- URLに関連キーワードが含まれていると、検索エンジンがページ内容を理解しやすくなる
- シンプルで意味のあるURLは、ユーザーにも覚えてもらいやすく信頼されやすい
- 不必要に長く複雑なURLは、評価されにくくなることがある
たとえば「https://sample.com/p=123」というURLよりも、
「https://sample.com/blog/permalink-setting」のように意味のある単語で構成されたURLの方が、検索エンジンにもユーザーにも親切です。
また、SEO対策では、ビッグキーワードだけでなく、具体的でニッチなロングテールキーワードをURLに取り入れることで、より詳細な検索に対応できる可能性が高くなります。
パーマリンクの「見た目」がユーザーに与える印象
パーマリンクの構造は、ページの印象にもつながります。
URLは検索結果に表示される場合もあるため、わかりやすく、整理された印象を持たせることが大切です。
たとえば以下のようなURLを見比べてみてください。
- https://example.com/id=5687abc
- https://example.com/blog/seo-permalink-guide
前者はどのようなページか分かりませんが、後者はSEO関連のパーマリンク設定ガイドであることが一目で伝わります。
ユーザーは「自分が探している情報がここにあるかも」と感じてクリックしてくれますし、URLをSNSでシェアしたときにも内容の伝わりやすさが大きく変わります。
難しく考えなくてOK!まずは仕組みを知ろう
専門用語が多くて敬遠されがちなパーマリンクですが、実際に設定してみるとそれほど難しくありません。
WordPressでは、投稿画面や設定画面からクリックだけで簡単に変更できるようになっています。
ただし、すでに公開した記事のURLを後から変更すると、古いURLからのアクセスが途絶えてしまうことがあります。
ページの引っ越しのようなイメージで、新しいURLに案内(リダイレクト)を出す必要があります。
初めて設定するときは、以下の点を意識するとスムーズです。
- URLは短く、シンプルにする
- 英単語を使う(スペースや記号は使わない)
- 意味のある言葉を入れて、ページ内容が伝わるようにする
- 公開後はできるだけ変更しない
パーマリンクを正しく理解し、ページの住所を整えておくことで、検索エンジンにもユーザーにもわかりやすいWebサイトに近づけます。
少しずつ仕組みを知っていけば、自然に使いこなせるようになります。
WordPressにおけるパーマリンク設定の方法と初期状態

WordPressの初期パーマリンク設定はどうなっている?
WordPressをインストールした直後のパーマリンク設定は、初期状態で「?p=123」のような数字だけの形式になっています。
これは記事のIDを表しているだけで、ページの内容がまったくわかりません。
検索エンジンや訪問者にとって、どんな情報があるページなのかをURLだけで判断するのは難しくなります。
そのため、初期状態のままではなく、意味のあるURLに設定を変更することが推奨されています。
初期設定のまま記事を公開してしまうと、後から変更する際にトラブルが起こることがあります。
具体的には、URLを変更することで古いリンクが無効になったり、アクセスが減ったりするケースがあります。
最初にきちんと設定しておくことが大切です。
記事を公開する前に見直すべき設定画面の場所
WordPressでパーマリンクを変更するには、管理画面から簡単に設定できます。
パーマリンク設定画面へのアクセス方法は次のとおりです。
- WordPress管理画面にログイン
- 左側メニューの「設定」をクリック
- 「パーマリンク設定」を選択
この画面では、投稿ページや固定ページのURL構造を変更することができます。初期状態の「基本」以外に、いくつかの形式が用意されており、投稿名を使った形式がSEOや見た目の面で好まれる傾向があります。
選択肢の中から自分のサイトに合ったものを選び、必ず「変更を保存」ボタンをクリックすることで設定が反映されます。
URL構造を変える前に確認しておきたいこと
パーマリンクの変更はいつでも可能ですが、記事を公開した後の変更は注意が必要です。
すでに外部からリンクされていたり、SNSでシェアされていたりする場合、そのURLを変更するとリンク切れになってしまいます。
以下の点を確認してから変更するようにしましょう。
- 記事の公開前かどうか
公開前なら自由に変更可能 - 外部リンクやSNSでシェアしていないか
リンクが多い記事のURL変更は避けるのが無難 - 変更後にリダイレクトを設定するか
旧URLから新URLへ自動的に移動させる設定が必要
URLを途中で変更する際には、301リダイレクトを設定することで検索エンジンの評価を引き継ぐことができます。
プラグインを使えば簡単に設定できるものもあります。
初心者でも迷わない設定方法の手順を紹介
実際にWordPressでパーマリンクを変更する手順はとても簡単です。
特別な知識は必要なく、数回のクリックだけで設定できます。
- WordPressにログインする
- 左メニューの「設定」→「パーマリンク設定」を開く
- 「投稿名」を選択する
- 下の「変更を保存」ボタンをクリックする
これで、今後作成する記事やページのURLが、投稿名ベースのパーマリンクになります。
パーマリンクに使う単語は、英数字を基本とし、意味のある言葉を短くまとめることがポイントです。
また、単語と単語の間にはハイフン(-)を使うようにすると、読みやすくなります。
記事投稿画面では、URLスラッグの編集も可能です。
タイトルが長い場合は、スラッグを短く編集することで、URLの見た目を整えることができます。
例:
- タイトル:WordPressでパーマリンクを変更する方法とは?
- スラッグ:permalink-change
スラッグはタイトルとは別に、自由に設定できる部分なので、記事ごとにわかりやすく整理することで、管理のしやすさも高まります。
わかりやすいURL構造は、SEOだけでなく読者の信頼感にもつながります。
記事数が増える前に、しっかり整えておくのがおすすめです。
SEOに最適なパーマリンクの決め方と重要なポイント

検索エンジンに伝わりやすいURLの特徴とは
パーマリンクを考えるうえでまず意識したいのが、検索エンジンに正しく内容を伝えられるURLになっているかどうかです。
検索エンジンはページの内容を判断するために、URLの文字列にも注目しています。
特に重要とされているのが、URLに含まれる単語がページの内容と一致しているかどうかという点です。
検索エンジンに伝わりやすいURLの特徴には次のようなものがあります。
- 短く簡潔である
- 意味のある単語が使われている
- ページ内容を連想しやすい構造になっている
- 記号や複雑な数字が含まれていない
たとえば「/seo-tips」や「/web-marketing-guide」のようなURLは、どんなテーマのページかがひと目でわかり、検索エンジンにもユーザーにも好まれる傾向があります。
キーワードを入れるときの注意点
パーマリンクにキーワードを入れることで、そのページがどんな内容なのかを検索エンジンに伝えやすくなります。
ただし、無理にたくさんキーワードを詰め込むと逆効果になる場合があります。
キーワードを入れる際に気をつけたいポイントは次の通りです。
- 1ページにつき1つのキーワードを意識する
詰め込みすぎは不自然に見えます - 単語同士はハイフン(-)でつなぐ
読みやすさが向上します - ページの内容と合っている言葉を使う
クリック後の印象とズレると離脱されやすくなります - ロングテールキーワードを意識すると検索に強くなる
より具体的な検索ニーズに対応しやすくなります
例えば、Web広告についての記事なら「/web-ads-basics」など、誰が見ても想像しやすく、かつ検索エンジンにテーマが伝わる表現にすると良いです。
日本語よりも英語?どの表記がいいのか解説
WordPressでは、記事タイトルをもとにパーマリンクを自動生成する機能がありますが、日本語タイトルの場合、そのまま日本語URLが生成されることがあります。
日本語を含むURLは見た目がそのまま表示されることもありますが、多くのブラウザやSNSではエンコードされてしまい
「%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%AD%E3%81%93 」
のような文字列になる場合があります。
これでは人間にも検索エンジンにもわかりづらくなってしまいます。
そのため、以下のような配慮が推奨されています。
- 英語で意味を表す単語に置き換える
- ローマ字でなく、英単語を使用する(例:/yamaneko ではなく /wildcat)
- ロングテールキーワードを活かすとSEO効果も高まる
日本語タイトルのまま公開すること自体は問題ではありませんが、パーマリンクだけは英語で整えておく方が管理しやすく、URLとしても整って見えます。
無駄な単語や記号を避けるコツ
パーマリンクを作成する際には、必要以上に長くなってしまうのを避けるために、無駄な単語や記号を省くことが大切です。
余計な情報が含まれていると、SEOにもユーザーエクスペリエンスにも悪影響を与える可能性があります。
避けるべき例としては以下のようなものがあります。
- 「and」「the」「with」などの意味を持たない英単語
- スペース、アンダースコア(_)、記号(!, ?など)
- 関係ないカテゴリ名やタグを含める
特に、URLに記号やスペースが含まれているとエンコードが発生し、URLが長く複雑な文字列に変換されてしまうことがあります。
やってはいけないパーマリンクの書き方と注意点

長すぎるURLがよくない理由
URLが長すぎると、次のような問題が起こります。
- 見た目がごちゃごちゃしていて読みづらい
- SNSやメールでシェアすると途中で切れてしまう場合がある
- スマホなどの小さな画面では全部表示されない
- 意図が伝わらず、ユーザーの不信感につながる
特にロングテールキーワードを入れたい場合でも、必要以上に単語を詰め込みすぎないよう注意が必要です。
以下のようなURLは避けた方が良いとされています。
- /this-is-a-very-long-url-that-contains-too-many-unnecessary-words
- /カテゴリー名/投稿名/サブカテゴリ/日付/タグ/作者名/記事タイトルの一部
目安としては、単語3〜5個程度に収めると読みやすく、ユーザーエクスペリエンスにもプラスになります。
日付やカテゴリを含めるのはアリ?ナシ?
WordPressでは、パーマリンクに日付やカテゴリを自動で含める設定も可能です。
しかし、これにはいくつかの注意点があります。
- 日付入りのURL:古く見えるリスクがある
- カテゴリ入りのURL:カテゴリ名を変えたときにURLも変わってしまう
たとえば、以下のようなURLは管理上のリスクが高くなります。
- /2022/07/10/permalink-guide
- /blog/seo/permalink-guide
こうした形式は、コンテンツがいつ書かれたかを強調したいメディア記事などには向いていますが、長期間読まれる記事(いわゆるストック型コンテンツ)には不向きです。
カテゴリ名を含める形式を使う場合は、カテゴリ構造を途中で変えないことが前提になります。
カテゴリの変更でURLが変わると、リダイレクトやSEO評価への影響が出ることがあります。
日付やカテゴリをどうしても使いたい場合は、プラグインやカスタム設定でリダイレクト処理を入れておくなどの工夫が必要です。
意味のない文字列を使うと起こる問題
WordPressの初期設定では「?p=123」や「archives/357」など、内容をまったく表していないURLが設定されることがあります。これをそのまま使ってしまうと、以下のような問題が起きやすくなります。
- 検索エンジンにページの内容が伝わらない
- ユーザーがクリックする前にどんな情報か判断できない
- SNSなどでシェアされても興味を持たれにくい
- サイト内リンクの管理が難しくなる
特にSEOの観点では、URL内に使われる単語は検索対象になる要素のひとつなので、何も意味を持たない記号や数字だけでは検索結果に影響を与えづらくなります。
避けるべき文字列には次のようなものがあります。
- /?id=98765
- /abc123xyz
- /archives/456
そのかわりに、記事の内容を表すキーワードを英単語で簡潔に入れることを心がけましょう。意味が明確なURLは検索エンジンだけでなく、訪問者にもやさしい設計になります。
初心者がやりがちなミスとその防ぎ方
パーマリンクの設定は一見簡単に見えますが、初心者がついやってしまいやすいミスも多く存在します。
以下の点に気をつけることで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
- URLに日本語をそのまま使ってしまう
文字化けや長くなる原因になります - 意味のない記号や数字を使ってしまう
内容が伝わらずSEOにも弱くなります - 公開後にURLを変更してしまう
アクセスや評価が下がる恐れがあります - 長すぎるURLになってしまう
シェアしづらくなり、印象も悪くなります - カテゴリを変えるときにURLの変化に気づかない
リダイレクト設定を忘れるとリンク切れになります
こうしたミスを避けるためには、記事を書く前にパーマリンクのルールをあらかじめ決めておくことが大切です。
可能であればサイト全体で共通のパターンを定めておくと、管理が格段に楽になります。
変更時にやっておくべき対処とは
どうしてもURLを変更しなければならない場合は、いくつかの対処をしっかり行う必要があります。
特に以下の対策は最低限行うようにしましょう。
- 301リダイレクトを設定する
旧URLから新URLへ自動的に転送させる処理 - サイトマップを再生成・再送信する
検索エンジンに新しい構造を正しく伝えるため - 内部リンクの見直しを行う
自分のサイト内に古いURLが残っていないか確認する - Google アナリティクスやサーチコンソールで動作確認する
アクセス状況の変化をチェックするため
WordPressを使っている場合、「Redirection」などの無料プラグインを活用することで、リダイレクト処理も簡単に管理できます。
プラグインを使わずに.htaccessファイルを編集する方法もありますが、誤操作するとサイトが表示されなくなる可能性があるため、自信のない方は避けた方が安心です。
後から後悔しないために決めておくべきこと
パーマリンクはあとから簡単に変更できるように見えますが、一度公開してしまうと修正が難しくなる項目のひとつです。
後悔しないためには、事前に次のようなポイントを整理しておくと良いでしょう。
- サイト全体で統一したルールを作る
投稿名ベースにするのか、カテゴリを含めるのかなどをあらかじめ決めておく - 記事ごとのスラッグ(URL末尾)にルールを設ける
キーワードの入れ方や語順などを揃える - 公開前に必ずURLを確認する
タイトル変更の影響などでスラッグが自動生成されていることもあるためチェックが必要 - 記事タイトルに頼らず、スラッグは自分で編集する
長すぎるときは短く調整する
一度でもURLを変更したことで検索評価やアクセス数に影響が出た経験をすると、その重要性がよくわかります。
設定はシンプルでも、事前に考えて決めることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
パーマリンクを変更する際のリダイレクト設定と301対応

「リダイレクト」ってなに?初心者向けに解説
Webサイトのページを引っ越したときや、パーマリンク(URL)を変更したときに、古いURLのままアクセスしてくるユーザーや検索エンジンを自動で新しいURLに案内する仕組みを「リダイレクト」と呼びます。
たとえば、以下のような状況でリダイレクトが役立ちます。
- ページのURLをわかりやすいものに変更した
- 古い記事を統合して新しいページにした
- サイト全体の構造を整理してカテゴリを変更した
リダイレクトがないと、古いURLにアクセスしてきた人は「ページが見つかりません」と表示されるエラーページに誘導されてしまいます。
閲覧者にも不親切で、検索エンジンの評価も失いやすくなるため、設定は必須です。
301リダイレクトの意味と使い方
リダイレクトにはいくつかの種類がありますが、パーマリンクの変更に使うのは「301リダイレクト」です。
これは、「このページは引っ越しました。今後は新しいURLを使ってください」という指示をサーバーから出す仕組みです。
301という数字はステータスコードと呼ばれるもので、「恒久的に移動した」という意味を持ちます。
Googleなどの検索エンジンはこの信号を読み取り、新しいURLにページ評価を引き継ぐよう対応します。
使い方としては、旧URLと新URLをペアで指定し、次のような形式で設定されます(.htaccessファイルなどで直接記述する場合)。
Redirect 301 /old-page https://example.com/new-page
ただし、この方法は少し専門的なので、WordPressを使っている方にはプラグインでの設定がおすすめです。
旧URLから新URLへ正しく誘導する方法
リダイレクトの設定では、どのページがどのページに変わったのかを正しく対応させることが重要です。
特に記事数が多い場合や、カテゴリーを一括で変更した場合には、抜け漏れなくすべての旧URLに対して新URLを用意する必要があります。
設定ミスや対応漏れがあると、検索エンジンからの評価を逃すだけでなく、ユーザーも目的の情報にたどり着けず、ユーザーエクスペリエンスが損なわれてしまいます。
以下のような作業がポイントになります。
- 新旧URLの一覧をエクセルやスプレッドシートで整理する
- 記事内容が異なるURLに飛ばすのは避ける
- 不要なページはリダイレクトではなく削除(404)扱いにすることも検討する
一部の記事だけパーマリンクを修正した場合でも、リダイレクトの確認は必ず実施するようにしましょう。
リダイレクトの設定がSEOに与える影響
パーマリンクを変更した際にリダイレクトを正しく設定しないと、検索エンジンは「新しいページとは別物」と判断するため、それまで蓄積されていたSEO評価がゼロになってしまうリスクがあります。
301リダイレクトを適切に使えば、以下のような効果が期待できます。
- 旧URLの評価をできるだけ新URLに引き継げる
- リンク切れを防ぎ、閲覧者の離脱を抑えられる
- サイト内の構造整理やリニューアルにも対応しやすくなる
ただし、リダイレクトの重複や連続設定(チェーンリダイレクト)は避けるべきです。
たとえばA→B→Cと転送されるような場合、検索エンジンもユーザーも混乱しやすくなります。
リダイレクト先が複数に分かれていると、評価が分散してしまう恐れがあるため、できるだけ一回のリダイレクトで完結するように設計することが大切です。
プラグインを使って簡単に設定するには?
WordPressでパーマリンクを変更した場合、リダイレクトの設定を自動化・簡素化できるプラグインが便利です。
代表的なプラグインには次のようなものがあります。
- Redirection:定番の無料プラグイン。UIがわかりやすく、複雑な設定なしで301リダイレクトが可能
- Rank Math:SEO機能が豊富なプラグインで、リダイレクト管理も含まれている
- All in One SEO Pack:SEO設定と合わせてリダイレクト管理ができる総合ツール
これらのプラグインは、以下のような操作で設定できます。
- 管理画面で「旧URL」と「新URL」を入力するだけ
- 301か302などの転送タイプを選ぶ(通常は301)
- 保存すればすぐに反映され、動作確認も可能
また、Redirectionプラグインでは自動的にURLの変更履歴を検出して、自動でリダイレクト設定を提案してくれる機能もあります。
初めてリダイレクトを設定する方にとっては、プラグインを使うことで安全かつ確実に移行処理を行えるようになるため、とても便利です。
手動での設定に不安がある場合は積極的に活用しましょう。
canonicalタグとの違いと正しい使い分け方

canonicalタグって何のためにあるの?
canonical(カノニカル)タグは、検索エンジンに対して「このページが本来のオリジナルです」と伝えるためのタグです。
Webサイトには、見た目や内容がほぼ同じでもURLが違うページが複数存在することがあります。
canonicalタグを使うことで、「このURLを評価してください」と優先的に評価してほしいページを明示することができます。
次のような状況でcanonicalタグは役立ちます。
- URLの末尾にパラメータ(?utm_source=など)がついているページが複数存在する
- 同じ記事を複数のカテゴリやタグで公開している
- 印刷用ページやスマホ向けのページが別URLになっている
canonicalタグはHTMLのheadタグ内に次のような記述をします。
<link rel="canonical" href="https://example.com/sample-page">
これによって、どのページが検索結果に表示されるべきかをGoogleに明確に伝えることが可能になります。
パーマリンクとどう関係してくるのか
パーマリンクとcanonicalタグは、どちらも検索エンジンとの「URLのやり取り」に関わる要素ですが、役割が異なります。
- パーマリンク:ユーザーや検索エンジンがアクセスする固定のURLそのものを決める設定
- canonicalタグ:同じ内容を持つページの中で、どれを「本物」として評価してもらうかを指定する仕組み
たとえば、同じ記事が以下の2つのURLで公開されている場合を考えてみます。
- https://example.com/blog/sample
- https://example.com/category/sample
どちらも同じ内容なら、canonicalタグを「https://example.com/blog/sample」に設定しておくことで、検索エンジンにとっては「このURLを正しく評価してね」と伝えることができます。
パーマリンクでURL構造を整えることは大前提ですが、運用上どうしても同じ内容が複数のURLで公開される場合に、canonicalタグで対応するのが理想的な使い分けです。
初心者が混同しやすいポイントを整理
canonicalタグは便利な仕組みですが、使い方を間違えると逆に評価が落ちてしまうケースもあるため、次のような点に注意が必要です。
- すべてのページに同じcanonicalを設定してしまう
正しい評価がされなくなります - 内容が異なるページにcanonicalを貼る
Googleに不自然と判断されます - リダイレクトと混同して設定してしまう
canonicalはあくまで「評価の集中」のためであり、「ページを移動させる」役割はありません - 相互にcanonicalを貼り合う
2つのページでお互いに「本物だよ」と主張すると評価が分散します
canonicalは「移動させる仕組み」ではなく、「評価をひとつにまとめる仕組み」です。
まとめ
パーマリンクは、記事やページのURLを決める大切な設定です。
URLはインターネット上の住所のようなもので、わかりやすく整理されたパーマリンクにすることで、検索エンジンにもユーザーにも好まれやすくなります。
特に、英単語で短くまとめたURLにすることで、見た目の印象がよく、クリックされやすくなります。
WordPressでは、投稿名だけを使った形式が多く使われていて、シンプルで扱いやすくSEOにも効果的な形とされています。
また、パーマリンクを後から変更する際には、301リダイレクトを設定して、古いURLから新しいURLに正しく案内することが大切です。
これを忘れると、検索順位やアクセス数に悪い影響が出てしまうことがあります。
さらに、同じ内容のページが複数ある場合は、canonicalタグを使って、検索エンジンに「どのページが本物か」を伝えることが重要です。
これにより、評価が分散するのを防ぎ、1つのページに集めることができます。
パーマリンクは難しそうに見えますが、基本の考え方と注意点を知っておけば、誰でも安心して設定できる項目です。初めにしっかり整えておくことで、後からのトラブルも防ぎやすくなります。




