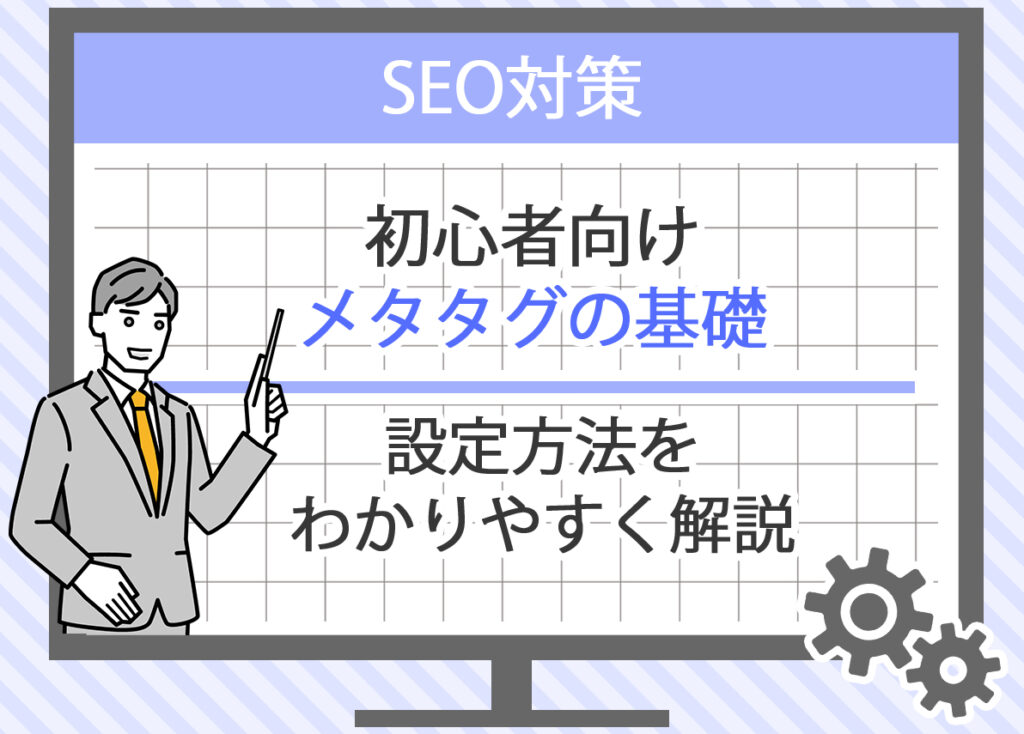
Webサイトを作ったり運営したりするとき、「メタタグ」という言葉を見かけることがあるかもしれません。
でも、「何のためにあるの?」「どこに使うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
メタタグは、検索エンジンやブラウザにページの情報を伝えるためのタグで、SEO対策にも関わるとても大切な要素です。
この記事では、初心者の方でも安心して理解できるように、メタタグの意味や種類、正しい書き方、そして設定する際のポイントをわかりやすくやさしい言葉で解説していきます。
メタタグとは?基礎からわかる重要な役割を解説

メタタグはWebページの「裏側メモ」
Webページは見た目だけでなく、見えない情報もたくさん含んでいます。
その中でも、メタタグはページの「裏側」にある情報を整理して伝えるためのタグです。
たとえば、ページの説明文や文字コード、検索エンジンに知らせたいキーワードなどを記述します。
メタタグの情報は、Webページを訪れたユーザーには直接表示されませんが、検索エンジンやSNSでの表示内容に影響を与える大切な要素です。
ちょうど、本の表紙を開いたときに出てくる「概要」のようなイメージを持つと理解しやすいかもしれません。
たとえば、Googleで何かを検索したときに、検索結果に表示されるページの説明文。
あの文章は、多くの場合、メタタグに書かれている「description(ディスクリプション)」という情報を元に作られています。
なぜメタタグがあると検索に強くなるのか?
メタタグがあることで、検索エンジンがそのページの内容をより正確に理解しやすくなります。
検索エンジンは、サイトの中身を「クローラー」と呼ばれるロボットのような仕組みで読み取っています。
そのときに、メタタグがあるとページの内容を効率よく把握できるため、検索結果で表示されやすくなる傾向があります。
また、meta descriptionは、クリック率にも関係してきます。
ユーザーは検索結果を見て、説明文が自分の探している内容に近ければ、よりクリックしやすくなります。
つまり、メタタグは検索順位だけでなく、ページへのアクセスにも影響を与えるのです。
以下のような要素が、検索エンジンに良い印象を与えることが知られています:
- 説明が簡潔で内容が伝わりやすい
余計な言葉を使わずに要点をまとめると効果的です - キーワードが自然に含まれている
無理に詰め込むのではなく、文の流れに沿って使います - ページごとに内容を変えている
すべて同じ説明だと検索エンジンの評価が下がることがあります
メタタグが使われる場所とその働き
メタタグは、HTMLファイルの中に記述されます。
ここは、見た目のデザインとは別に、Webページの設定や外部とのつながりを定義する重要な場所です。
以下は、主なメタタグの種類とそれぞれの役割です。
- meta charset:文字コードの指定(例:UTF-8)
- meta description:ページの説明文を設定
- meta keywords:ページに関連するキーワード(※現在は多くの検索エンジンで無視される傾向あり)
- meta robots:検索エンジンに対するページの扱い方を指示(例:index, follow など)
- meta viewport:スマートフォンなどでの表示方法を調整
これらのメタタグは、ユーザーエクスペリエンスの向上や検索対策、SNSでの見え方など、さまざまな場面で役立ちます。
たとえば、meta viewportを使えば、スマートフォンで表示したときの画面サイズを自動調整できます。
SNSでのシェア時に表示される画像や説明文も、Open Graph(OGP)というメタタグを使って制御できます。
FacebookやX(旧Twitter)などに適した内容を設定できるので、クリックされやすくなる工夫としても有効です。
HTMLにどんなふうに書かれているのかを見てみよう
実際のHTMLでは、メタタグは以下のように記述されます。
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="初心者向けにメタタグの役割や書き方を解説します。">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
このように、<meta>というタグに対して、nameやcontentなどの属性を指定することで、さまざまな情報を設定しています。
HTMLを書くのが初めての方でも、上記の例を参考にすれば、基本的なメタタグの設置はそれほど難しくありません。
コピペして編集するだけでも、立派なSEO対策につながる第一歩になります。
もし自分のサイトのメタタグがどうなっているか確認したいときは、ブラウザでページを開いて右クリック → 「ページのソースを表示」などを選ぶことで、HTMLの中身をチェックできます。
WordPressを使っている場合は、専用のプラグインを導入することで、コードを書かずにメタタグを管理することもできます。
たとえば「Yoast SEO」や「All in One SEO Pack」などが有名です。
どちらも無料版があり、初心者でも扱いやすい構成になっています。
SEOにおけるメタタグの効果と検索エンジンへの影響
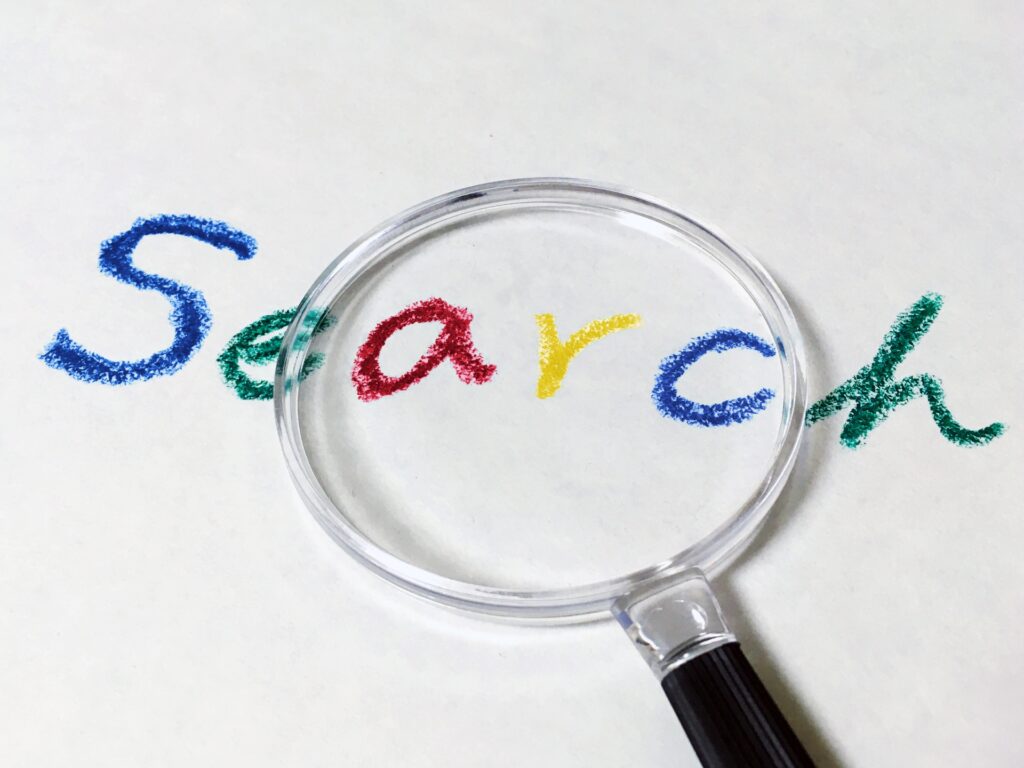
検索エンジンがメタタグから読み取る情報とは?
検索エンジンは、Webページの内容を判断する際にメタタグに記載された情報も参考にしています。
ページ全体を細かく読み込んで解析するのと同時に、最初に概要やヒントとなる情報があると理解しやすくなるからです。
特に以下のようなメタタグは、検索エンジンにとって重要な情報源とされています。
- description:ページの説明文を検索エンジンに伝える
- robots:ページを検索結果に載せるかどうかを伝える
- viewport:スマホやタブレットでの表示に関する設定
descriptionタグに記載された内容は、検索結果の画面にも表示されることがあるため、クリックされるかどうかに関わるポイントにもなります。
上位表示にどれくらい影響するの?
メタタグの中でも、直接順位に影響するタグと、間接的に影響を与えるタグがあります。
たとえば、descriptionタグ自体はGoogleのランキング要因には含まれていないとされていますが、それでもクリック率に影響を与えるため、結果的に検索順位に影響が出る可能性があります。
robotsタグはもっと直接的です。
たとえば、以下のように記述されたタグがあると、そのページは検索結果に表示されません。
<meta name="robots" content="noindex">
このように書くことで「このページは検索結果に載せないでください」と検索エンジンに伝えています。
設定を間違えると、意図しないページが表示されなくなるリスクもあります。
また、モバイル対応を知らせるviewportタグも、ユーザーエクスペリエンスの評価に影響する要素のひとつです。
スマホからの閲覧が多い現代では、モバイルでの使いやすさも検索順位に関係しています。
「クリックされやすい」ページになる理由
検索結果に表示されるページは、見た目も大事です。
特にdescriptionに書かれた内容は、ユーザーがそのページをクリックするかどうかを判断する材料になります。
クリックされやすいdescriptionの特徴としては、以下のような点が挙げられます。
- タイトルと内容に一貫性がある:ユーザーが求めている内容が明確に伝わる
- 読みやすく、長すぎない:検索結果の表示では約100文字前後が目安
- キーワードが自然に含まれている:不自然に詰め込まず、自然な文章にする
たとえば、ロングテールキーワードを意識したdescriptionにすると、特定のニーズを持ったユーザーに刺さりやすくなります。
検索結果に表示される文(スニペット)との関係
Googleの検索結果では、タイトルの下に表示される文を「スニペット」と呼びます。
これは、ページの中身から自動的に抜き出されることもありますが、descriptionメタタグに書かれた内容がそのまま表示されることもあります。
うまく設定されたスニペットは、ユーザーにとって「このページを見れば自分の疑問が解決しそう」と思わせる大きな要因になります。
一方で、descriptionタグが未設定だったり、内容が空欄だったりすると、Googleは自動で本文の一部を抜き出して表示します。
その結果、文脈が伝わりにくかったり、意図しない情報が表示されたりすることもあるため、自分で内容をコントロールできるように設定しておくほうが安心です。
descriptionメタタグの最適な文字数は、おおよそ90〜120文字程度とされています。
パソコンとスマホでは表示される文字数に違いがあるため、一文で大事なことが伝わるように意識して作成すると良いでしょう。
メタタグの種類とmeta属性の正しい記述ルール

よく使う代表的なメタタグを紹介
Webページの見た目には現れませんが、メタタグにはたくさんの種類があり、それぞれに異なる役割があります。
中でもよく使われている代表的なメタタグを紹介します。
- meta charset:ページの文字コードを指定します。日本語を正しく表示するために大切です。
- meta name=”description”:ページの説明文を設定します。検索結果に表示されることがあります。
- meta name=”keywords”:ページの内容に関するキーワードを設定します。ただし、現在は検索エンジンにほとんど使われていません。
- meta name=”viewport”:スマートフォンやタブレットで見やすく表示させるための設定です。
- meta name=”robots”:検索エンジンに対して「このページを表示していいか」「リンクをたどってよいか」などを伝える設定です。
これらのタグは、Webページが正しく動作するためだけでなく、検索エンジンやSNSでも情報が正確に伝わるようにするために必要です。
「description」や「keywords」って何のこと?
descriptionは、ページの「要約文」にあたるもので、検索エンジンの検索結果に表示されることがあります。
keywordsは、ページの内容に関連する単語をカンマ区切りで並べるメタタグです。
たとえば、ページが「Webマーケティング」について書かれているなら、「webマーケティング, 広告, 集客」などのキーワードを記載します。
ただし、Googleはこのタグを検索順位の参考にしていないと公表しているため、現在はほとんど使われていません。
descriptionタグの例:
<meta name="description" content="Web初心者向けにメタタグの意味や書き方をわかりやすく解説します。">
このように、content属性の中に、ページの内容を簡潔にまとめた文章を書きます。
長すぎると検索結果で途中までしか表示されないため、100文字前後を目安にするのが良いとされています。
書き方の基本ルール(コピペOKな形も紹介)
メタタグを書く場所は、HTML文書の中のheadタグの内側です。
headタグは、ページの構成や外部との連携に関わる情報をまとめて書く場所です。
基本的な構成は以下のようになります。
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="このページはWeb初心者向けにメタタグを説明しています。">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="robots" content="index, follow">
</head>
いずれのメタタグも、開閉タグが不要で「<meta … >」の形で記述されます。
記述ミスを避けるためにも、テンプレートとして使える基本形を保存しておくと便利です。
viewportタグを使うと、スマートフォンでの表示も見やすくなります。
画面サイズを自動調整するように指示できるため、モバイル対応を意識するサイトでは必須の設定といえるでしょう。
robotsタグには、以下のような指示を与えることができます:
- index:ページを検索エンジンに載せる
- noindex:検索結果に表示しない
- follow:ページ内のリンクをたどる
- nofollow:リンクをたどらない
たとえば、「noindex, nofollow」と指定すると、そのページは検索エンジンに載らず、リンクも無視されるようになります。
公開したくないページや限定ページに使うことが多いです。
必ず使いたいメタタグと、あまり使わないもの
必ず使っておきたい基本のメタタグはいくつかあります。
特に初心者がWebサイトを作るときは、以下のタグを最初に設定しておくとよいでしょう。
- meta charset:文字化けを防ぐために必須です
- meta description:検索結果でのクリック率に関係します
- meta viewport:スマホやタブレットでの見やすさを調整します
一方で、あまり使われなくなっているメタタグや、効果が限定的なものも存在します。
- meta keywords:かつては検索対策に使われていましたが、今ではほとんど無視されています
- meta author:ページの作成者名を記述しますが、SEOやユーザーエクスペリエンスには直接関係しません
- meta refresh:一定時間でページを自動で切り替えるものですが、ユーザーの混乱を招きやすいため避けられる傾向があります
メタタグを正しく使うには、「何を伝えたいのか」「誰に伝えるのか」を意識することが大切です。
ページごとに内容を変える、文字数に注意する、不必要なタグは避けるといった基本を押さえて、正確で読みやすいWebページを作るための土台としてメタタグを活用してみてください。
メタタグの書き方と設定方法を初心者向けに紹介

メタタグを設置する場所はどこ?
メタタグは、HTMLファイルの中でもhead(ヘッド)という部分に記述します。
このhead部分は、ページのタイトルや文字コード、外部ファイルの読み込みなど、Webページの基本情報をまとめる役割を持っています。
headの外にメタタグを書くと正しく認識されないので、必ずheadの中に記述するようにします。
以下のようなHTMLの構成の中に入れ込むのが基本です。
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<!-- メタタグはこの中に記述 -->
</head>
<body>
<!-- ページの見た目を作る部分 -->
</body>
</html>
headタグの中に書かれていることで、Webページを開く前に情報が読み込まれ、ページの設定が素早く反映されるようになります。
コピペで使える基本の書き方
メタタグは、基本的に「」というタグで記述します。閉じタグが必要ないため、1行で完結する書き方が多いのも特徴です。
以下に基本的なメタタグのテンプレートを紹介します。
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="このページはWeb初心者の方向けにメタタグについてわかりやすく紹介しています。">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="robots" content="index, follow">
このように、nameとcontentをセットで使い、どんな情報を伝えるかを指定するのが基本の形です。
- charsetは、文字の種類(エンコード)を指定します
- descriptionは、ページの説明を設定します
- viewportは、スマートフォンでも読みやすくするための設定です
- robotsは、検索エンジンに「このページは表示してよい」「リンクをたどってよい」と伝える指示です
設定に迷ったときは、これらをベースにして書き換えるだけでも、最低限のSEO対策ができます。
WordPressでの設定方法(初心者でもできる!)
HTMLファイルを自分で触らない場合でも、WordPressであれば管理画面からメタタグを設定できます。
WordPressにはプラグインと呼ばれる追加機能があり、コードを触らずに簡単に設定が可能です。
特に使いやすいのが、以下のようなプラグインです。
- All in One SEO:多機能で、初心者にも使いやすい
- Yoast SEO:SEOに関する設定項目がわかりやすく整理されている
- SEO SIMPLE PACK:日本語対応で、最低限の機能に絞られていてシンプル
使い方は以下の通りです。
- 管理画面の「プラグイン」から該当のSEOプラグインをインストールして有効化します
- 各投稿や固定ページの編集画面に、descriptionやtitleの入力欄が追加されます
- テキストを入力するだけで、HTMLのmetaタグが自動で挿入されます
どのプラグインも入力した内容がリアルタイムでプレビューされるため、初心者の方でも安心して使えます。
無料ツールやプラグインを使う方法
WordPressを使っていない場合でも、無料でメタタグを作成できるツールがいくつか存在します。
入力項目に必要な情報を入れるだけで、HTMLタグが生成される仕組みです。
便利な無料ツールの一例:
- Metatags.io:OGP対応のタグもまとめて作れる
- SEOptimer Meta Tag Generator:英語だがシンプルで使いやすい
これらのツールでは、ページタイトル、説明文、キーワードなどを入力すると、最適な形でタグを生成してくれます。コピーしてHTMLのhead部分に貼り付けるだけなので、HTMLに不慣れな方にもおすすめです。
また、Chrome拡張機能にも便利なツールがあり、自分のページがどう見えるかを確認したり、他サイトのメタタグを調べたりすることもできます。
- META SEO inspector:ページのメタ情報をまとめて確認できる
- SEO META in 1 CLICK:SNSでの表示内容や文字数チェックも可能
いずれも無料で使えるので、メタタグの設定後に確認するためのツールとしても活用できます。
実際に書いてみよう:例文つき解説
ここまでの内容をふまえて、実際にWebページに使えるメタタグを作成してみましょう。
ロングテールキーワードを意識して、descriptionやtitleに入れる内容を考えておくと、検索ニーズの高いページ作りに役立ちます。
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="Webマーケティング初心者向けに、metaタグの役割や正しい書き方を具体的に解説しています。">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="robots" content="index, follow">
</head>
descriptionの中には、ページの内容がひと目でわかる文章を入れることが大切です。
検索結果でスニペットとして表示されることがあるため、内容をわかりやすく、自然な言葉で伝えましょう。
ビッグキーワードを盛り込むよりも、読み手が探している具体的な内容を表すロングテールキーワードを入れるほうが、質の高いアクセスを集めやすくなります。
書き終えたら、実際の表示を確認することも忘れずに行いましょう。
head内に正しく記述されていれば、HTMLソース上で確認できますし、SEOチェックツールでも検出されます。
Google検索で上位を狙うためのキーワード対策のポイント

メタタグに入れるキーワードはどう選ぶ?
キーワードは、検索される言葉に合わせてページの内容を伝えるためのものです。
特にmeta descriptionやtitleタグに含めることで、検索エンジンにこのページが何を扱っているかを明確に伝えることができます。
どのキーワードを使うかを決める際は、次のような視点が大切です。
- 検索されている回数が多いか
- 自分のページの内容と合っているか
- 読み手が使いそうな自然な言葉かどうか
ロングテールキーワードを活用すると、より具体的な悩みを持つ人にアプローチできます。
たとえば、「メタタグ 記述方法 初心者」といった複数の言葉を組み合わせたキーワードは、検索数は少なくても確度が高いとされています。
次のような方法で、入れるべきキーワードを探すことができます。
- Googleの検索窓に言葉を入力したときに出るサジェスト(予測)をチェックする
- 関連キーワード取得ツール(例:ラッコキーワード)を使う
- 他の上位表示ページで使われているキーワードを参考にする
いずれの場合も、ユーザーがどんな言葉で検索しそうかを考えることが大切です。
「詰め込みすぎ」はNG!自然な書き方とは
キーワードをたくさん入れれば入れるほど効果がある、と思われがちですが、不自然なキーワードの詰め込みはかえって逆効果になることがあります。
検索エンジンは、キーワードが多すぎると「読みづらい」と判断し、評価を下げてしまうことがあります。
たとえば、以下のような文章は避けたほうがよいでしょう。
「メタタグ 記述方法 メタタグ seo メタタグ キーワード 書き方 メタタグとは」
このような書き方は、読み手にも検索エンジンにも不親切です。
自然な文章の流れの中にキーワードを含めるほうが、読みやすく内容も伝わりやすくなります。
検索エンジンは、キーワードだけでなく文全体の意味を理解する能力を持っています。
そのため、「正確に伝える」ことを第一に考えて書くことが重要です。
次のような点を意識すると、自然な文章になりやすくなります。
- タイトルにキーワードを1回だけ入れる
- descriptionにキーワードを自然に2回程度含める
- 長文ではなく1〜2文で完結させる
キーワードが目立つだけでなく、文章全体としての読みやすさやわかりやすさも評価されるポイントになります。
SEOで失敗しないための考え方
キーワード対策は、ただ単に「言葉を入れればいい」というものではなく、ユーザーエクスペリエンスを高めるための設計の一部として考えることが大切です。
次のような考え方を意識すると、SEOの失敗を減らすことができます。
- ユーザーが何を知りたいかを最優先にする
- メタタグは「読み手への案内文」として考える
- 上位表示よりも、内容の正確さと読みやすさを優先する
- 無理にキーワードを押し込まず、自然な文にする
Googleは、表面的なキーワードよりも、読者にとって役立つかどうかを重視する方針を強めています。
ユーザーの検索意図に合った内容を提供することが、結果的に検索順位の向上につながります。
また、コンテンツが更新されていないと評価が下がることもあるため、定期的にdescriptionやタイトルを見直すこともSEO対策として有効です。
メタタグ設定時に確認すべき注意点と避けたいミス

タグを重複して使っていないか?
メタタグは、ページの情報を正しく伝えるためのものですが、同じ種類のタグを複数回使ってしまうと、検索エンジンがどれを参考にすればよいか混乱してしまう可能性があります。
たとえば、descriptionタグが2つ以上あると、Googleはどちらを使うべきか判断しにくくなり、意図しない文が検索結果に表示されることもあります。
以下のような記述が重複していないか、ソースコードをチェックしてみてください。
- meta name=”description”が複数行入っていないか
- meta name=”robots”が別の設定で2回以上記載されていないか
- OGP(SNS表示用タグ)と混同して、同じ内容が繰り返されていないか
特に、テンプレートやCMS(WordPressなど)を使っている場合、自動で出力されるタグと自分で追加したタグが二重に記載されることがあります。
タグの整理は、最終的なHTMLを確認して行うことが重要です。
文字数が長すぎる・短すぎるとどうなる?
メタタグの中でも、descriptionやtitleは適切な文字数に収めることが重要です。
長すぎると途中で切れてしまい、伝えたいことが伝わらなかったり、短すぎると情報が不足して検索エンジンに十分な内容が伝わらなかったりします。
目安としては以下のとおりです。
- titleタグ:30〜40文字程度(全角換算)
- descriptionタグ:90〜120文字程度(全角換算)
文字数が多すぎると、検索結果のスニペットで末尾が「…」と省略され、ユーザーに文章の全体像が伝わりにくくなります。
一方、短すぎる場合は、検索エンジンがページ内の他の文を自動的に抜き出してスニペットとして表示することがあり、意図したメッセージが表示されない可能性もあります。
文字数のバランスを取るには、次のようなツールが便利です。
- Serposcope Meta Description Checker:文字数や表示幅のチェックができます
- Google Search Console:実際にどう表示されたかの履歴を確認できます
正しく設定されているかどうかは、検索結果の見え方を実際にシミュレーションしてみると確認しやすくなります。
「noindex」「nofollow」は要注意
metaタグの中でも特に注意が必要なのが、robotsタグに含まれる「noindex」や「nofollow」の設定です。
これは、検索エンジンに対してページを掲載するかどうか、リンクを追いかけるかどうかの指示を出すためのものです。
以下のような設定は誤って使うと、ページが検索結果に表示されなくなることがあります。
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
このタグがあると、そのページは検索エンジンに載らず、リンクも追跡されません。
意図して設定する場合(たとえば、限定公開の資料ページや管理者用の画面など)には有効ですが、通常の公開ページで設定してしまうとWeb上から見つけてもらえなくなる可能性が高くなります。
次のような誤設定がないか確認しておくことが大切です。
- テンプレート側で自動的に「noindex」が入っていないか
- パスワード制限と組み合わせてrobotsタグの意味が変わっていないか
- WordPressの「検索エンジンに表示しない」チェックボックスがONになっていないか
一度設定してしまうと、検索エンジンに再度認識してもらうのに時間がかかることがあるため、事前の確認が非常に重要です。
Googleがメタタグを無視する場合もある
すべてのメタタグが必ずその通りに扱われるとは限りません。
Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとって最適な情報を表示するために、タグの内容を無視する判断をする場合があります。
descriptionタグを例にすると、設定した文章が検索結果に表示されることもありますが、実際にはGoogleがページ内の文章から自動的に別の部分をスニペットとして抜き出すことも多いです。
これは、検索したキーワードと一致している文が本文にあった場合、そちらのほうが関連性が高いと判断されるためです。
また、titleタグも過剰な繰り返しやキーワードの詰め込みがあると、Google側で別のタイトルに書き換えられて表示されるケースがあります。
避けるべき記述の一例:
- 「メタタグとは|メタタグとは|SEOに強いメタタグとは」など、同じ単語の繰り返し
- 誇張的な表現だけで中身が薄いタイトル
- 単語だけの羅列で文章になっていないもの
検索エンジンは「ユーザーが読みやすいかどうか」を非常に重視しているため、わかりやすく自然な日本語で書くことが重要です。
設定後は必ずプレビューやチェックをしよう
メタタグは一度設定したら終わりではなく、設定後に内容が正しく表示されているか、実際の検索結果でどのように見えるかをチェックすることが大切です。
チェックに使える便利な方法をいくつか紹介します。
- Googleで実際に検索して表示を確認する(ただし反映には時間がかかる)
- Googleリッチリザルトテスト:構造化データの確認と同時にdescriptionなども確認可能
- SNSカードチェック(XやFacebookの開発者ツール):OGPやtitleの表示を確認可能
- Chromeの開発者ツール:ページ上で右クリック→「検証」→Elementsタブでhead内のmetaタグを確認
また、ページが多い場合は、Google Search Consoleを活用することで、全体の表示状況や問題点を一覧で把握できます。
エラーがあった場合には通知も届くため、継続的に見直す体制を整えると安心です。
一度設定しただけでは検索エンジンの対応や評価が変わってしまうこともあるため、定期的に表示状況を確認し、必要に応じて修正を行うことが大切です。
特にdescriptionやtitleは、キーワードやページの内容変更に応じて調整することで、ユーザーエクスペリエンスの向上につながります。
まとめ
メタタグはWebページの中では見えない部分にありますが、検索エンジンやSNSにページの情報を正しく伝えるためにとても大切なものです。
特にdescriptionやtitleなどのタグは、検索結果の見え方やクリックされやすさに大きく影響します。
文字数のバランスや、キーワードの自然な使い方を意識して書くことがポイントです。
また、間違ったタグの重複や「noindex」などの設定ミスがあると、せっかくのページが検索に出てこなくなることもあります。
必ず設定後には、表示や内容をチェックするようにしましょう。
HTMLに慣れていない方でも、WordPressのプラグインや無料のツールを使えば、コードを書かずに簡単に設定することができます。
まずは基本のタグから取り入れて、自分のサイトに合った形で使ってみてください。
少しの工夫で、ページの見え方も検索結果での評価も大きく変わってきます。
無理に難しいことをする必要はありませんが、少しずつでも正しい知識を身につけて活用していくことが、Webサイトの運営にはとても役立ちます。




