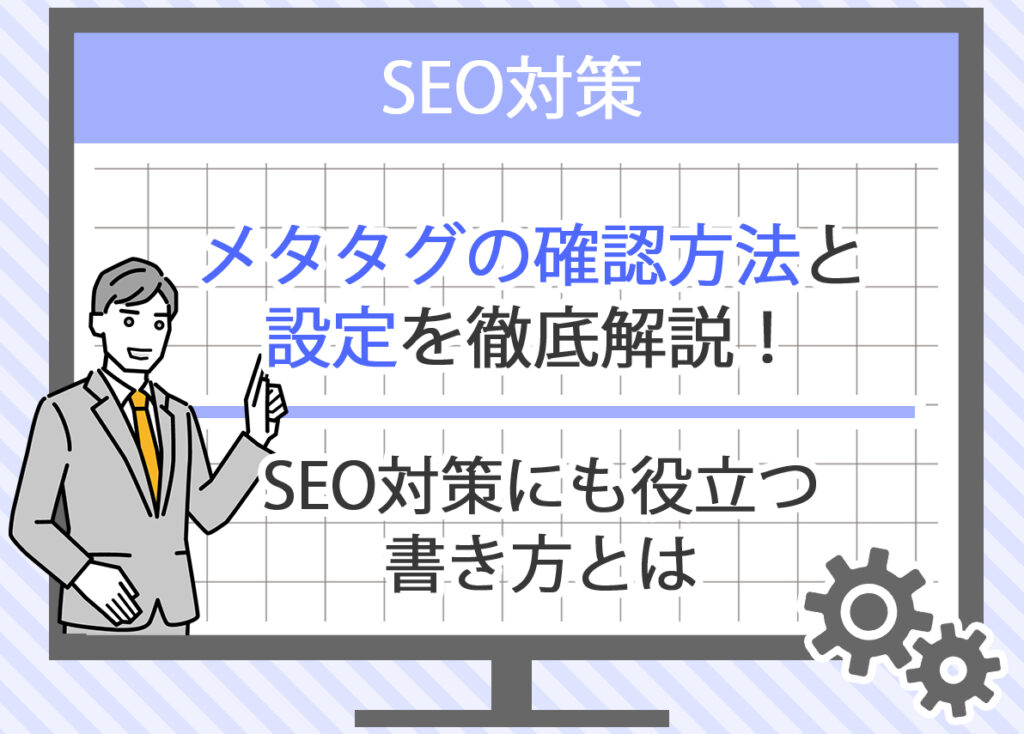
Webサイトを作ったり運営したりする中で、「メタタグ」という言葉を目にしたことはありませんか?
でも、なんだか専門的で難しそうに感じてしまいますよね。
メタタグとは、検索エンジンやSNSにページの情報を正しく伝えるための大切なしくみです。
たとえば、検索結果に表示される文章や、SNSでシェアされたときの見え方は、実はこのメタタグによって決まっています。
正しく設定することで、検索で見つけてもらいやすくなったり、クリックされやすくなったりするメリットがあります。
この記事では、初心者の方でも安心して読めるように、メタタグの意味や確認方法、設定のポイントなどをやさしく解説していきます。
そもそもメタタグとは?初心者向けに基礎から解説

メタタグは「見えない情報」を伝えるタグ
メタタグとは、Webページの中に含まれているユーザーには表示されない情報のことを指します。
これは画面上には見えませんが、検索エンジンやSNS、ブラウザなどがそのページを理解するための大切な役割を担っています。
たとえば、検索エンジンがページを読み取るときに、「このページは何について書かれているのか」「どんなキーワードに関連しているのか」といった判断をするために、メタタグの情報を参考にします。
メタタグが正しく設定されていると、Webサイトの評価や検索結果への掲載にも良い影響を与える可能性があります。
Webページの「説明書」のような役割
メタタグは、ページの内容や目的、表示方法などを裏側で伝える説明書のような役割を持っています。
Webサイトを作った人が、検索エンジンやブラウザに向けて「このページはこういう内容です」「こういう風に見せてください」と伝えるための手段なのです。
これは、たとえば商品に付いている成分表や使用説明書、映画で言えばジャンルやあらすじのようなもので、ページ自体が伝えたい情報を正しく届けるために欠かせないものです。
検索結果に表示される文章の元になる
Googleなどの検索エンジンで何かを検索したときに、表示される結果の中にタイトルと説明文があるのを見たことがあると思います。
この説明文の多くは、「meta description(メタディスクリプション)」と呼ばれるメタタグの内容が使われています。
たとえば「ホームページ 作り方」で検索すると、検索結果に「このページでは初心者でも簡単にできるホームページの作り方を紹介しています」といった説明が出てくることがあります。
これはページの中にあるmetaタグによって設定されているものです。
この文章がユーザーの興味を引くものであれば、クリックされやすくなり、アクセス数の増加にもつながります。
そのため、検索結果で表示されるこの部分はとても重要な要素のひとつです。
HTMLってなに?メタタグとどうつながる?
メタタグは「HTML(エイチティーエムエル)」という言語で書かれています。
HTMLとは、Webページの構造を作るための言語で、文字や画像、見出しやリンクなど、すべての要素がHTMLで定義されています。
メタタグはこのHTMLの中でも、ページの最初にある「head(ヘッド)」という部分に書かれます。
headは、見た目には出ない情報をまとめておく場所で、ここにmetaタグを書くことで、検索エンジンやSNSなどに向けて情報を伝えられるのです。
以下のようなコードが実際のmetaタグの一例です(初心者向けにシンプルな形式で紹介します):
<meta name="description" content="初心者向けにメタタグの基本を解説したページです。SEO対策にも役立ちます。">
このコードは、「このページはどんな内容か」を説明するもので、検索エンジンが理解しやすくなるよう手助けしています。
メタタグの正しい活用は、Webサイト全体の表示のされ方や信頼性にも関係してきます。
Web初心者でも、この仕組みを知ることで、少しずつページの品質や見え方を整えていくことができます。
必要なタグを適切に使うことで、検索エンジンからも正しく認識され、より多くの人に届くWebページに近づけることができます。
SEOにおけるメタタグの役割と重要性とは

SEOってなに?検索結果に出やすくするしくみ
SEOとは「Search Engine Optimization(サーチエンジン オプティマイゼーション)」の略で、検索エンジンで自分のWebページをできるだけ上位に表示させるための工夫のことを指します。
日本語では「検索エンジン最適化」と訳されることが多いです。
たとえば「おすすめ カフェ 渋谷」で検索したときに、上位に表示されているページのほうが、たくさんの人にクリックされやすくなります。
逆に3ページ目や4ページ目に表示されていると、なかなか見てもらえません。
SEOでは、Webページの内容そのものをよくすることはもちろん、検索エンジンに対して「このページはこういう内容です」と正しく伝えることがとても大切です。
そこで登場するのがメタタグです。
メタタグが検索順位に影響を与える理由
検索エンジンは、Webページの内容を自動で読み取り、どの検索キーワードに合っているかを判断しています。
そのときのヒントとして、メタタグの情報が使われます。
とくに以下のメタタグは検索結果に影響しやすいものです。
- descriptionタグ:検索結果に表示される説明文として使われる。クリック率に影響する。
- robotsタグ:検索エンジンにインデックスしてほしいかどうかを伝える。
- titleタグ(HTMLのtitle):ページのタイトルで、検索結果の見出しになる。
これらのタグがしっかり書かれていることで、検索エンジンがページを正しく理解し、検索結果にふさわしい位置に表示してくれる可能性が高まるのです。
たとえば「Webマーケティング 初心者」というロングテールキーワードで検索されたときに、その言葉がメタタグの中に入っていると、検索エンジンは「このページはその内容に関係している」と判断しやすくなります。
上位表示に関わる「情報の伝え方」
Webページの内容が良くても、検索エンジンがそれを正しく読み取れなければ、評価されません。
メタタグは、そうした「検索エンジンへの伝え方」をサポートする存在です。
メタタグの使い方を間違えると、検索エンジンに意図とは違う意味で理解されてしまい、表示されにくくなることもあります。
逆に、適切に情報をまとめて記述すれば、評価が上がる可能性があります。
以下のようなポイントが重要です。
- ページの主な内容を短く、わかりやすく表現する
- ターゲットユーザーが検索しそうな言葉を自然に含める
- 文字数を超えないようにしながら、内容が伝わるように書く
とくに、メタディスクリプションはクリック率に大きく関係します。
内容が魅力的だと、検索結果で上位に出ていなくてもクリックされることがあります。
クリックされることで、検索エンジンは「人気のあるページ」と判断し、上位に上がるケースもあります。
キーワードとの関係を知っておこう
メタタグは、キーワードとの関係がとても深いです。検索エンジンは、ページの中にどんな言葉が使われているかを分析して、「このページはどの検索キーワードに合っているか」を判断します。
とくに意識したいのが、以下のようなキーワードの考え方です。
- ビッグキーワード
たとえば「SEO」「ダイエット」「カフェ」など、よく検索されるけれど競争も激しいキーワード - ロングテールキーワード
たとえば「SEO メタタグ 初心者」「渋谷 カフェ 静か」など、検索数は少ないが、より具体的なニーズに対応したキーワード
ロングテールキーワードをうまくメタタグに入れることで、より具体的な検索ニーズに応えやすくなり、検索結果で見つけてもらいやすくなります。
また、titleタグやdescriptionタグにキーワードを不自然に入れすぎると、逆に評価が下がる可能性もあるため注意が必要です。
自然な文章の中にキーワードを無理なく取り入れることが大切です。
メタタグの主な種類と正しい設定方法を紹介

ページの説明文を伝える「description」
descriptionは、Webページの内容を短くわかりやすく要約して伝えるためのメタタグです。
検索エンジンはこの内容を参考にして、検索結果に表示する説明文を決めます。
たとえば、Googleで「ホームページ 作り方」と検索したときに表示される各サイトの説明文は、多くの場合このdescriptionタグに記述された内容が使われています。
魅力的で具体的な説明文を書くことで、クリックされやすくなります。
以下はdescriptionタグの記述例です:
<meta name="description" content="初心者向けにホームページの作り方をわかりやすく解説しています。HTMLや画像の使い方も紹介。">
descriptionを書くときのポイントは以下のとおりです。
- ページの内容を短く具体的にまとめる
- 長さは120文字程度が目安
- 誘導したいキーワードを自然に含める
- 内容とかけ離れた文章は避ける
キーワードを入れる「keywords」
keywordsタグは、そのページがどんな検索キーワードに関連しているかを伝えるためのタグです。
ただし、現在のGoogleはこのタグをランキング要素として使っていません。
それでも、ページのテーマを整理したり、他の検索エンジンに向けてヒントを示すという意味では一部のケースで使われることもあります。
実際の使用例は以下のとおりです。
<meta name="keywords" content="HTML, Web制作, 初心者, メタタグ">
使う場合の注意点として、関係ないキーワードを入れると検索エンジンから評価を下げられることがあります。
また、繰り返しやキーワードの詰め込みは避けるべきです。
メタタグ「keywords」はSEOに必要?効果と設定方法については下記で詳しく紹介しています。
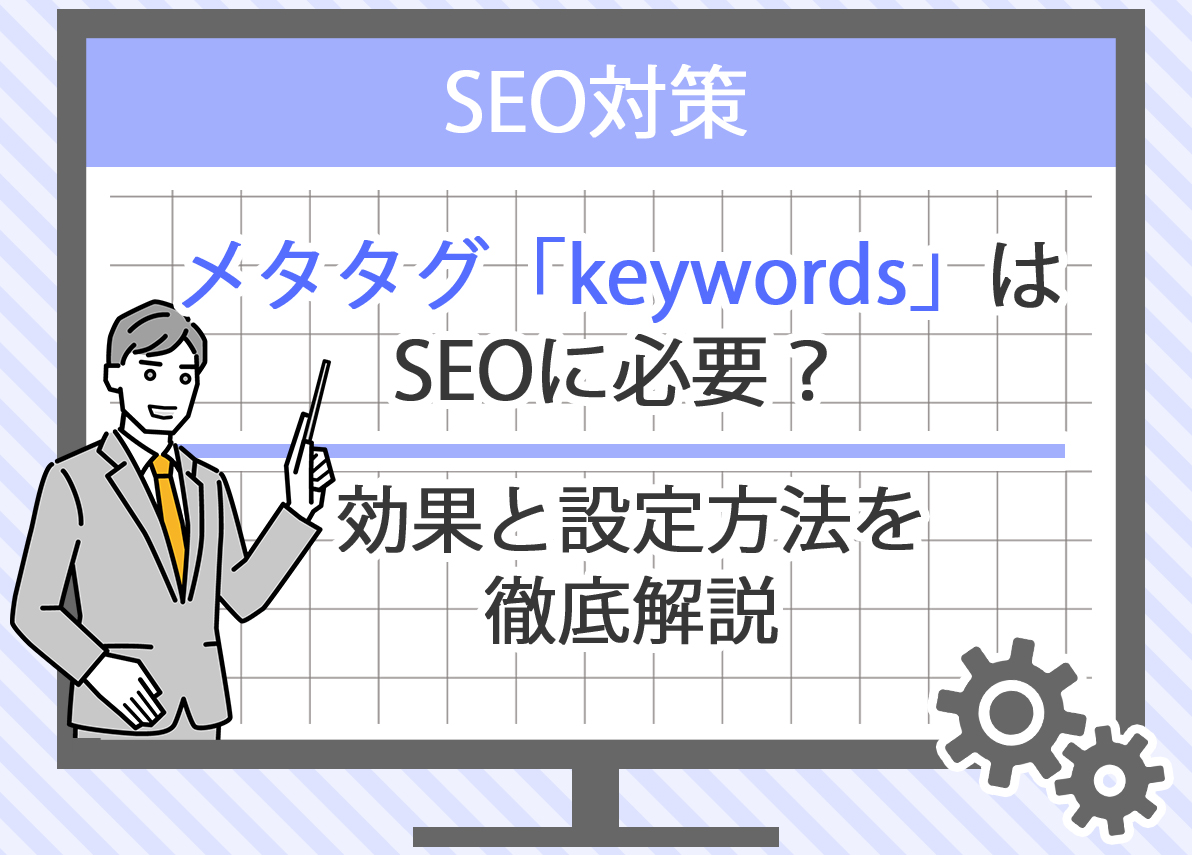
SNSと連携する「ogタグ(OGP)」とは
ogタグ(Open Graph Protocol)は、ページがSNSにシェアされたときの見え方をコントロールするタグです。FacebookやX(旧Twitter)などでURLを貼ったとき、タイトル・説明・画像が自動で表示されるのは、このタグが設定されているからです。
設定していないと、意図しない内容や画像が表示されることがあります。
よく使われるogタグは以下のようなものです。
<meta property="og:title" content="初心者向けホームページ作成ガイド">
<meta property="og:description" content="HTMLの基本から画像の使い方まで、わかりやすく解説。">
<meta property="og:image" content="https://example.com/images/ogp.jpg">
<meta property="og:url" content="https://example.com/homepage-guide">
- og:title:SNSに表示されるタイトル
- og:description:説明文
- og:image:サムネイル画像のURL
- og:url:ページの正確なURL
特に画像サイズは推奨があり、Facebookでは1200×630ピクセルが適しているとされています。
表示の調整に使う「viewportタグ」
スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でも見やすく表示されるようにするために使うのがviewportタグです。
このタグがないと、スマホで見たときに文字が小さすぎたり、画面が横にはみ出してしまうことがあります。
基本的な記述例は以下のようになります。
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
- width=device-width:画面サイズに合わせて幅を調整
- initial-scale=1.0:表示倍率を指定(標準サイズで表示)
このタグがあることで、どんなデバイスでも読みやすく整った表示が実現し、ユーザーエクスペリエンスの向上につながります。
タグの順番や並び方にも注意しよう
メタタグはHTMLファイルの内に書くのが基本です。
書く順番は厳密に決まっているわけではありませんが、検索エンジンやSNSが読み取りやすいように整えておくことが大切です。
以下のような順番で記述することが推奨されます。
- charset(文字コード)
- viewport
- title(ページタイトル)
- description
- keywords
- ogタグやtwitterタグなどSNS用タグ
- robotsやcanonicalなどの制御タグ
タグの中に同じ情報が複数あったり、設定が矛盾していると、検索エンジンが正しく認識できない原因になります。
たとえば、descriptionタグが2つあったり、metaタグとOGPで違う内容が設定されている場合などが該当します。
また、CMSやプラグインで自動的に追加されるメタタグと、自分で書いたタグが重複しないようにも注意が必要です。
見やすく整理されたメタタグは、HTMLファイル全体の印象もよくなり、管理や修正がしやすくなります。
検索エンジンにとっても、情報を正確に読み取りやすくなるため、設定時には丁寧に確認することが大切です。
メタタグを確認する方法と便利なツールの使い方

自分のページにメタタグがあるか確認したいとき
Webサイトにメタタグが正しく設定されているかどうかを確認することは、検索エンジン対策やユーザーエクスペリエンスの向上において重要です。
自分でHTMLを編集している場合はもちろん、CMSやホームページ作成ツールを使っている場合でも、意図しない設定ミスがあるかもしれません。
確認方法はいくつかありますが、どれも専門的な知識がなくても試せるものばかりです。
とくにページのtitleやdescription、OGPなどの情報は、検索結果やSNSでどのように表示されるかに関わる大切な部分ですので、定期的にチェックするようにしましょう。
Chromeでソースコードをチェックする方法
Google Chromeを使えば、ブラウザ上でページのソースコードを簡単に確認できます。
難しそうに感じるかもしれませんが、やってみると意外とシンプルです。
確認手順としては、以下の方法が基本になります。
- Webページ上で右クリック:メニューが表示されたら「ページのソースを表示」を選ぶ
- キーボードでショートカット:Windowsなら「Ctrl + U」、Macなら「Command + Option + U」で開けます
ソースコードが表示されたら、<head>タグの中を探します。
そこにmetaタグが記述されていれば、設定されていることが確認できます。
さらに絞り込みたい場合は、キーボードの「Ctrl + F」や「Command + F」で検索窓を表示し、「meta」や「description」「og」などのキーワードを入力して探すのが便利です。
拡張機能や無料ツールを使って簡単に見る
HTMLを直接見なくても、便利な無料ツールやブラウザ拡張機能を使えば視覚的にわかりやすくメタタグを確認できます。
操作も簡単で、初心者の方にとってもおすすめです。
主なツールと特徴は以下のとおりです。
- META SEO inspector:Google Chromeの拡張機能で、ページ内のmeta情報を一覧表示してくれる
- SEO META in 1 CLICK:title、description、OGPなどを一目で確認できる便利ツール
- Ahrefs SEO Toolbar:上級者向けながら無料でも一部機能が使える
こうしたツールを導入することで、わざわざソースコードを開かなくても、現在の設定や不足しているタグなどが簡単に確認できます。
Web制作ツールやCMSでも確認できる
WordPressやWixなどのCMSを使ってWebサイトを作っている場合、メタタグはテーマやプラグインによって自動的に生成されることが多いです。
特にWordPressでは、以下のようなプラグインを使えば簡単に確認・編集が可能です。
- Yoast SEO:descriptionやOGPの設定が可能で、検索エンジンの見え方もシミュレーションできる
- All in One SEO Pack:初心者にもわかりやすく、meta設定を一括で管理できる
CMSによっては、管理画面からmeta情報を編集できる機能が最初から備わっていることもあります。
使っているCMSにあわせて、管理メニューの「SEO設定」や「ページ設定」などをチェックしてみましょう。
間違いがないかチェックするコツ
見た目ではわからない問題がある場合もあるため、以下のようなチェックポイントを押さえておくと安心です。
- 記述ミスがないか:タグの綴り間違いや閉じタグの忘れがないか確認する
- 重複がないか:同じ種類のmetaタグが複数あると、検索エンジンが正しく読み取れない
- 内容が空になっていないか:descriptionやtitleが空欄になっていると、正しく表示されない
- 意図しない自動生成になっていないか:CMSやプラグインで自動で挿入された内容が適切か確認する
さらに、Googleが提供している「リッチリザルト テスト」や「モバイルフレンドリーテスト」なども活用すると、検索エンジン側から見たときの状態を確認できます。
Googleのリッチリザルトテスト
https://search.google.com/test/rich-results
こうした外部のチェックツールを活用することで、見落としがちなエラーや未設定箇所に気づきやすくなります。
地道な確認ですが、ページの品質や信頼性にもつながる作業ですので、ぜひ定期的に行うようにしてみてください。
メタタグが検索エンジンに与える効果と影響とは

正しく書けば検索結果に好影響がある
検索エンジンは、Webページの情報を読み取る際にメタタグを重要な参考資料のひとつとして扱っています。
特に、descriptionタグやtitleタグ、OGPタグなどは、検索順位や表示内容に大きく関わります。
メタタグを適切に書くことで得られる好影響には以下のようなものがあります。
- ページの内容が検索エンジンに正しく伝わる
テーマや目的がはっきり伝わると評価が安定しやすくなる - ロングテールキーワードを含めることで検索範囲が広がる
検索意図が具体的なユーザーにも届きやすくなる - ページの構成が明確になる
情報の整理がされていると判断され、クローラーにとって読みやすくなる
これらが積み重なることで、検索結果での上位表示につながる可能性があります。
ただし、順位そのものを直接操作できるわけではなく、あくまで補助的な役割としての効果です。
間違った書き方は「逆効果」になることも
メタタグの記述が適当だったり、設定ミスがあると、思わぬマイナスの影響を受けることがあります。
とくにdescriptionやrobotsなどのタグは注意が必要です。
- 内容の薄いdescription:検索結果に出てもクリックされにくくなる
- 重複するmeta情報:同じdescriptionが複数のページに使われていると、重複コンテンツとみなされることがある
- 不正確な内容:ユーザーが期待した内容と違って直帰率が上がる可能性がある
このようなケースでは、検索順位が下がったり、クリック率が下がってしまったりといった逆効果を引き起こします。
正しく使えば役立つメタタグですが、扱いを誤ると評価を落とすこともあるため、注意深く設定する必要があります。
クリック率やアクセス数にも関係する
検索順位とあわせて意識しておきたいのが「クリック率」です。
検索結果に表示された際に、ユーザーがどのページを選ぶかは、タイトルや説明文の内容に大きく左右されます。
descriptionタグやOGPタグを魅力的に書くことによって、ユーザーの興味を引き、クリック率を高めることができます。クリックされやすい文章には以下のような特徴があります。
- 明確なメリットが伝わる:読むことでどんな情報が得られるかがはっきりしている
- 興味を引く言葉が使われている:「初心者向け」「簡単にできる」「無料で使える」などの具体的なワード
- キーワードが自然に含まれている:検索した言葉がそのまま文章内にあると安心感がある
クリック率が上がると、Googleの評価にもよい影響を与える可能性があると言われています。
それは、「このページはユーザーにとって有益」と判断されやすくなるためです。
noindexタグやnofollowタグの注意点
noindexやnofollowといったメタタグは、検索エンジンに対してページの扱いを指示するために使われます。
しかし、使い方を間違えるとページが検索に出なくなる原因にもなります。
- noindex:このページを検索結果に表示しないように指示する
- nofollow:このページ内のリンクを評価対象にしないように指示する
以下のようなケースでは注意が必要です。
- 公開したいページにnoindexを入れてしまっている:検索結果に表示されなくなる
- 内部リンクにnofollowがついている:サイト内の評価の流れを断ち切ってしまう
特にCMSやプラグインで自動的に設定されていることがあり、意図せずページがインデックスされなくなることがあります。
Search Consoleなどを使って定期的に確認しておくと安心です。
SNSでの見え方(OGP)にも影響あり
OGP(Open Graph Protocol)タグは、SNS上でページをシェアしたときの見え方をコントロールするために使います。
適切に設定されていれば、タイトルや説明、サムネイル画像がきれいに表示されて、SNS経由のアクセスにも好影響があります。
たとえば以下のように記述します。
<meta property="og:title" content="初心者でもできるメタタグの基本ガイド">
<meta property="og:description" content="検索順位やSNS表示に影響するmetaタグの書き方をやさしく解説します。">
<meta property="og:image" content="https://example.com/ogp-image.jpg">
<meta property="og:url" content="https://example.com/meta-guide">
表示の崩れや情報の不足があると、SNSでの見た目が中途半端になり、ユーザーにとっても魅力が伝わりづらくなります。
以下のようなミスにも注意しましょう。
- 画像サイズが小さすぎる:推奨は1200×630ピクセル
- titleやdescriptionが空白:見出しや紹介文が何も表示されない
- URLが異なるページを指している:クリックした先が別のページになる
SNS経由でのアクセスが多い場合は、OGPの最適化がユーザーエクスペリエンスを左右する大きなポイントになります。
各SNSのデバッガーツール(Facebookのシェアデバッガーなど)を使って表示を確認するのも有効です。
メタタグ設定時によくある注意点と対策ポイント

同じ内容を複数ページで使わない
metaタグの中でも特にdescriptionやtitleがすべてのページで同じになっていると、検索エンジンからの評価が下がってしまうことがあります。
Googleはページごとの情報を個別に認識したいため、descriptionやtitleが重複していると、正しく内容を理解してもらえません。
たとえば、すべてのページに「株式会社○○の公式サイト」というdescriptionを設定していると、それぞれのページの目的や特徴が伝わらず、ロングテールキーワードにも対応しづらくなります。
重複を避けるための対策には以下のような工夫があります。
- 各ページの目的や内容に応じてdescriptionを変える
- 商品ページや記事ページでは、その内容を要約した文を入れる
- ページのターゲットキーワードを自然に含めておく
CMSを使っている場合は、自動生成されるdescriptionがあるかどうかを確認し、必要があれば手動で上書きするようにすると安心です。
キーワードの詰め込みすぎに注意
検索エンジンにページを見つけてもらいたい一心で、metaタグに過剰にキーワードを入れてしまうケースがあります。
しかし、キーワードの詰め込みは逆効果になることが多く、Googleのガイドラインにも違反する可能性があります。
以下は避けるべき書き方の例です。
<meta name="description" content="SEO、SEO対策、SEO初心者、SEO無料、SEO検索、SEOで上位表示、SEOで集客">
こうした記述は読みづらいだけでなく、ユーザーにとっても魅力がありません。
自然な日本語で、ページの内容をやさしく説明するほうが、ユーザーエクスペリエンスにもつながります。
- 伝えたい内容を一文でまとめる
- 無理なくキーワードを1〜2個程度含める
- 同じ単語を繰り返さない
Google公式のアドバイスとしても、ユーザーにとって有益な説明を心がけるよう案内されています。
スマホやタブレットにも対応できているか
metaタグの一部であるviewportタグが正しく設定されていないと、スマートフォンやタブレットでの表示が崩れたり、読みづらくなったりします。
特に現在ではモバイル端末からのアクセスが非常に多く、モバイル対応は基本的な条件のひとつです。
一般的に使用されるviewportの設定は以下のようになります。
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
この設定によって、画面のサイズにあわせてWebページが自動で調整されます。対応が不十分だと、モバイルユーザーがすぐにページを離れてしまう原因になります。
以下のチェックポイントも参考にしてください。
- 横スクロールが必要な表示になっていないか
- 文字やボタンが小さすぎないか
- PC向けの画面がそのまま縮小されていないか
日本語が文字化けしないように設定を確認
metaタグの中には文字コード(エンコーディング)を指定するものがあります。
これが正しく設定されていないと、日本語の部分が記号や別の文字になってしまう文字化けの原因になります。
もっとも一般的な文字コードは「UTF-8」です。
HTMLのhead内に以下のような記述がされているか確認しておくと安心です。
<meta charset="UTF-8">
CMSやエディターによっては、自動的に違う文字コードで保存されてしまうこともあるため、ファイル保存時の設定も確認しておきましょう。
文字化けが発生すると、descriptionやOGPなどの表示に不具合が起き、ユーザーにも不信感を与える恐れがあります。
項目の抜けや記述ミスを見直す
metaタグは、見た目には影響が出にくい分、設定漏れやタイプミスに気づきにくい特徴があります。
特に以下のような点に注意しておくと、トラブルを未然に防ぎやすくなります。
- descriptionタグがまったく記述されていない:検索エンジンに自動生成された文が表示される
- titleタグが空白になっている:ブラウザのタブにサイト名が出ない
- og:imageのURLが間違っている:SNSシェア時に画像が表示されない
特にCMSを使っている場合、テーマやプラグインの設定で自動的にmetaタグが挿入されることもあるため、自分の意図した通りになっているかを目視で確認することが大切です。
小さなミスも見逃さないよう、構造や表示も一緒にチェックしておきましょう。
まとめ
メタタグは、Webページの内容を検索エンジンやSNSに正しく伝えるための大切な情報です。
ユーザーには見えない部分ですが、検索結果での見え方やクリック率、そしてページの評価にも関わってきます。
たとえば、descriptionタグは検索結果に表示される説明文となり、興味を持ってもらえるかどうかに影響します。また、OGPタグを使えばSNSでのシェア時の表示も整えることができます。
メタタグの設定では、同じ内容を複数のページで使わないこと、キーワードを詰め込みすぎないことなどに注意が必要です。
さらに、スマホやタブレットにも対応できるようviewportタグを使ったり、日本語が文字化けしないよう文字コードをUTF-8に設定したりすることも大切です。
こうした細かいポイントを押さえておくことで、検索エンジンからの評価も安定し、ページを見つけてもらいやすくなります。
初心者の方でも、1つずつ丁寧に設定を見直すことで、Webページの印象や見え方が大きく変わることを実感できると思います。
まずはできる範囲からメタタグを意識してみるのがおすすめです。




