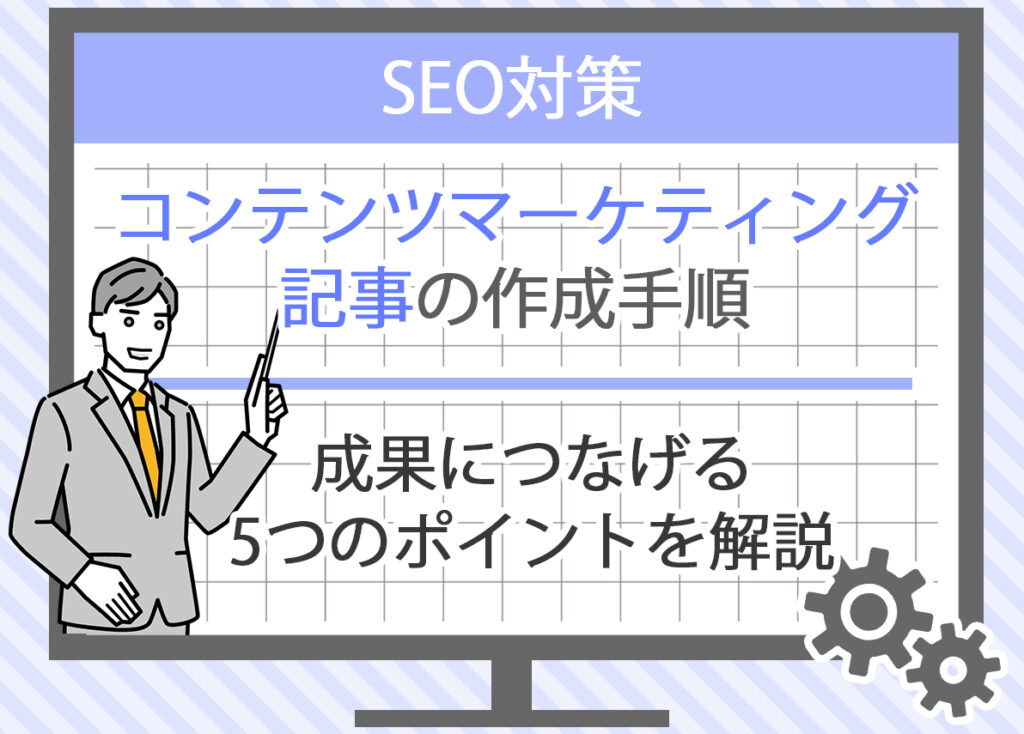
コンテンツマーケティングの記事作成に取り組みたいけれど、何から始めればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
特にWeb初心者の方にとっては専門用語や文章の書き方、SEOなど、聞きなれない言葉がたくさん出てきて戸惑ってしまうこともあると思います。
この記事ではそんな方でも安心して読み進められるように、記事作成の手順やコツをやさしく丁寧にご紹介します。
コンテンツマーケティングとは?基本と重要性をわかりやすく解説

コンテンツマーケティングってどういう意味?
コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって役立つ情報や読み物を発信することで、信頼を築き、商品やサービスに興味を持ってもらう方法です。
たとえば「○○の選び方」や「○○の始め方」といった解説記事や、使い方を紹介するブログ記事などがこれにあたります。
広告のように「買ってください」と直接呼びかけるのではなく、ユーザーが知りたい情報をコンテンツ(文章・画像・動画など)として提供し、読者との関係性を深めていく方法です。
このような取り組みにより、自然に読者との接点を作ることができ、結果的に商品の購入やサービスの利用につながる可能性が高くなります。
なぜ今、記事での情報発信が注目されているのか
スマホやパソコンで検索するのが当たり前の今、ユーザーは「自分の悩みや疑問を自分で調べたい」と考えています。そのため、必要な情報をすぐに読める「記事」はとても便利な手段です。
特に、検索エンジンで上位に表示されると、多くの人に読まれるチャンスが増えます。
記事は広告費をかけずに集客ができる点も大きな特徴です。
さらに、情報を蓄積できる点も魅力です。
一度書いた記事が検索エンジンに表示され続ければ、長期的にユーザーを呼び込む効果が期待できます。
ユーザーは次のようなタイミングで記事を探します。
- 新しい知識を身につけたいとき
- 商品やサービスを比較・検討しているとき
- 問題を解決したいとき
こうしたニーズに合わせた記事を用意することで、企業はより自然なかたちでユーザーとつながることができます。
従来の広告との違いとは
従来の広告は、テレビCMやバナー広告などのように短い時間やスペースで強く訴えるスタイルが主流でした。
一方で、コンテンツマーケティングは「役に立つ内容を届ける」ことを重視しています。
従来広告の特徴
- 広告としてすぐにわかる
- 一方的なメッセージが多い
- 広告を止めれば効果も止まる
コンテンツマーケティングの特徴
- ユーザーにとって自然な形で届く
- 興味を引いたあとで商品紹介につなげられる
- 一度作成したコンテンツが繰り返し見られる
このように、情報収集が日常的になった今のユーザーには、コンテンツを通じて興味を持ってもらう方法の方が受け入れられやすくなっています。
たとえば「おすすめのコーヒーメーカー5選」という記事の中で、自社の商品を紹介すれば、読者の流れを止めることなく自然に情報を届けることができます。
初心者でも始めやすい理由
コンテンツマーケティングは、専門的な知識がなくても少しずつ始められるのが魅力です。
以下のような点が、初心者でも取り組みやすい理由としてあげられます。
- 書くテーマは自社の商品や業界に関することでOK
特別なスキルがなくても、自分たちが普段扱っている内容なら書きやすいです。 - 無料で始められる
ブログやSNSを使えば、コストをかけずに情報発信が可能です。 - 長く使える資産になる
一度公開した記事が、検索され続けることで効果が持続します。
また、読みやすい文章の構成や見出しの付け方なども、テンプレートを使えば簡単に覚えられます。
このように、記事作成を通じて読者に価値ある情報を届けることで、検索エンジンからのアクセスも期待でき、結果として自社サービスへの問い合わせや資料請求につながるケースも増えています。
特に、読者の目線に立った内容を意識することで、より多くの人に読まれる記事づくりが可能になります。
成果を出すために重要な記事作成のステップと流れ

まずは「目的」をしっかり決めることが大切
記事を書く前に、最初に考えておきたいのが「この文章を通して何を達成したいのか」という目的です。
目的がはっきりしていないと、内容にブレが出てしまい、読み手に伝えたいことがうまく届かなくなってしまいます。
目的にはいくつかの種類があります。
- 問い合わせや資料請求につなげたい
- 商品やサービスに興味を持ってもらいたい
- 自社の専門性や信頼性を伝えたい
- 検索結果に表示させてアクセスを集めたい
目的がはっきりすると、誰に向けて書くか(ターゲットユーザー)や、どういった内容が必要かも自然と見えてきます。
たとえば「資料請求を増やしたい」なら、サービスの魅力だけでなく、他社との違いや導入事例なども伝える必要があります。
「検索からのアクセスを増やしたい」なら、キーワードの選び方やSEO対策が大切になります。
読み手の立場を意識して、どんな行動を促したいのかを考えることが、質の高い記事作成の第一歩です。
記事全体の設計図(構成)を作る
文章をいきなり書き始めるのではなく、まずは全体の設計図を考えることで、読みやすくて内容にムダのない記事が作りやすくなります。
構成を考えるときは、以下のような順番を意識すると効果的です。
- 導入文:読み手の興味を引く内容や、この記事で得られることを簡単に伝える
- 本文:見出しごとに話を分けて、読みやすく整理する
- まとめ:内容をふりかえり、次の行動につなげる案内を入れる
また、構成を決める際は、検索エンジンからの流入も考慮して、ロングテールキーワードやビッグキーワードを見出しに入れる工夫も効果的です。
キーワードの候補がうまく見つからない場合は、「ラッコキーワード」(https://related-keywords.com/)などの無料ツールを使うと便利です。
見出しごとに話を分けると、読み手が一目で内容を理解しやすくなり、途中で読むのをやめてしまう可能性も減らせます。
見出しや文章の書き方の流れ
構成が決まったら、見出しと本文を書いていきます。
このときに大切なのは、「読みやすさ」と「わかりやすさ」を意識することです。
以下のポイントを参考にすると、初心者でもスムーズに書けるようになります。
- 一文を短く区切る:読み手の負担を減らせる
- 難しい言葉は使わない:専門用語はかんたんな言葉で言い換える
- 箇条書きや表を使う:情報が整理されて理解しやすい
特に重要なのが見出しの使い方です。
見出しを上手に使うと、読者は自分に必要な情報だけを素早く見つけられるようになります。
見出しのコツ
- 「○○の方法」「○○のポイント」のように具体的にする
- 質問形にして、読者の疑問に答える形にする
- キーワードを自然に含めて検索でも見つけられやすくする
文章のトーンや言葉の選び方は、ターゲットに合わせて調整しましょう。
たとえば、初心者向けなら「〜しましょう」などの柔らかい言い回しを使うと、読み手に安心感を与えられます。
公開後のチェックや見直しも重要
記事を公開したら終わりではなく、見直しや修正作業がとても重要です。
誤字脱字や表現のゆれをチェックするだけでなく、実際に読んでくれるユーザーの立場に立って読み返してみることが大切です。
見直しの際に気をつけたいポイント
- 誤字や脱字、漢字の間違いがないか
- 内容に古い情報や間違いがないか
- 見出しや小見出しの流れが自然かどうか
- 読んでいて意味が伝わりにくい部分がないか
また、画像がある場合は、表示が乱れていないか、スマホでもきちんと見えるかなども確認しておくと安心です。
公開直後は、文章の修正や追加がしやすいタイミングなので、なるべく早めに見直しを行いましょう。
継続的な改善で成果が出やすくなる
記事は一度書いて終わりではなく、定期的に見直して改善することで、より良い結果につながっていきます。
たとえば、アクセス数が少ない場合は、タイトルや見出しの表現を変えてみたり、内容を追加したりすると変化が見られることもあります。
Google アナリティクスやアクセス解析ツールを使って、読まれている部分や離脱されやすい箇所を確認してみましょう。
改善のヒントになるチェック項目
- どの見出しで読者が離脱しているか
- 記事の平均読了時間はどれくらいか
- 検索から流入しているキーワードは何か
- 「問い合わせ」などの行動につながっているかどうか
これらのデータを見ながら、小さな改善を積み重ねることが、質の高い記事を作り続けるコツです。
また、季節や流行にあわせて見直すことで、読者の関心とタイミングをとらえることもできます。
記事は「書いて終わり」ではなく、「育てていくもの」という意識が、継続的な集客につながります。
ブログ記事やオウンドメディアに適した構成と書き方のコツ

見出しと段落でスッキリ読みやすく
文章の内容が良くても、見た目が読みづらいと途中で読むのをやめてしまう人もいます。
そのためには、見出しと段落を適切に使い分けて、読みやすいレイアウトを意識することが大切です。
文章をスッキリさせる工夫
- 一段落ごとの文章は3〜4行程度におさえる
長文が続くと視線が追いにくくなる - ひとつの話題に見出しをつける
読みながら内容を整理しやすくなる - 箇条書きを活用する
情報の整理や比較がしやすくなる
読み手は、画面をスクロールしながら情報を拾っていくため、視覚的にパッと見て把握できる構成がとても重要です。
スマホユーザーが多い現在では、特にこのポイントが大きな差を生みます。
専門用語はやさしく言い換えるのがコツ
Webやマーケティングの記事には専門用語が多く出てきますが、すべての読者がそれを理解しているとは限りません。
理解しづらい言葉が連続すると、読者は読み進める気をなくしてしまう可能性があります。
やさしく伝えるための言い換えの工夫
- 初出の専門用語にはカッコで説明を添える
たとえば「SEO(検索結果で上位表示を狙う工夫)」など - よく知られていない略語はフルで説明する
「GTM」ではなく「Googleタグマネージャー(タグの管理を行うツール)」と書く - 同じ用語を何度も使う場合は、場面に合わせて言い換える
「アクセス解析」→「どれくらい見られているかを分析すること」
読者が置いてけぼりにならないように、情報のわかりやすさを最優先に考えることが大切です。
やさしく伝える工夫こそが、記事全体の質を高める要素になります。
最後まで読んでもらうためのまとめ方
記事の最後まで読んでもらうためには、しっかりとした「締め」が必要です。
内容を振り返りながら、読者に「読んでよかった」と感じてもらえるようなまとめ方を意識しましょう。
効果的なまとめ方のコツ
- 記事全体のポイントを簡潔にふりかえる
- 読んだあとに行動したくなる一言を加える
「気になる方はまず1記事から始めてみましょう」など - リンクや資料への案内をわかりやすく提示する
とくにオウンドメディアでは、記事を読んだ人に次のページを見てもらう、問い合わせをしてもらうなど、読後のアクションを意識した書き方が効果的です。
たとえば、サービス紹介ページや関連記事へのリンクを記事の終わりに配置することで、自然な流れで次のページに進んでもらいやすくなります。
読者の記憶に残りやすくするには、最後まで読みやすく、理解しやすいまとめが欠かせません。
記事の冒頭で約束した内容を丁寧に振り返ることで、読み手の満足感も高まります。
SEOを意識した記事作成に欠かせないキーワードの選定方法

SEOってなに?検索されやすくなるしくみ
SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジンで上位に表示されやすくするための工夫を意味します。
検索エンジンとは、GoogleやYahoo!などのことを指し、ユーザーが入力したキーワードに関連する情報を表示します。
たとえば「ブログ 記事 書き方」と検索したとき、上のほうに表示された記事は、SEOの工夫がしっかりされている可能性が高いです。
検索結果の上位に表示されると、多くの人の目に触れる機会が増え、読まれる確率も高まります。
SEOのしくみは完全には公開されていませんが、以下のような要素が影響しているといわれています。
- キーワードが記事タイトルや見出しに入っているか
- 読者の疑問にしっかり答えている内容になっているか
- ページの表示速度やスマホでの見やすさ
- 他のサイトからリンクされているかどうか
検索エンジンは、ユーザーにとって役立つページを上位に表示しようとするしくみを持っています。
つまり、SEOを意識するということは、ユーザーエクスペリエンスを考えた記事づくりにもつながります。
キーワードはどうやって選べばいい?
キーワードを選ぶ際には、まず「読者がどんな言葉で検索しているか」を考えることが大切です。
ただし、よく使われる短くて人気の言葉(ビッグキーワード)だけを狙っても、競合が多すぎて上位表示されにくい場合があります。
そこで、より具体的な検索語句であるロングテールキーワードも組み合わせることがポイントです。
- 読者の疑問や悩みから連想する
- 自社の商品やサービスと関連性が高いワードを考える
- ツールを活用して関連キーワードを調べる
無料で使えるキーワード調査ツール
- ラッコキーワード(https://related-keywords.com/)
- Googleキーワードプランナー(Google広告に登録すると利用可能)
たとえば「記事作成」というビッグキーワードに対して、「記事作成 方法」「記事作成 コツ」「記事作成 外注」などのような具体的なキーワードを探すことで、検索意図により近い記事を作りやすくなります。
タイトルや見出しに入れると良い理由
検索エンジンは、ページの中でもタイトルや見出しに含まれているキーワードを重視する傾向があります。
これは、検索エンジンにとって「この記事は何について書いているのか」を判断するうえで、タイトルや見出しが手がかりになるからです。
- 記事タイトルに主要なキーワードを自然に含める
- 見出しにも関連キーワードを入れて内容を補足する
- 文脈に合った表現にすることで読者にも読みやすくなる
ただし、機械的に入れすぎると文章が読みにくくなってしまいます。
あくまで読みやすさを第一に考えたうえで、自然な形でキーワードを盛り込むことが大切です。
見出しで工夫したいポイント
- 「○○の書き方」など具体的な形にする
- 読者が「自分に関係ありそう」と思える言葉を使う
- 一目で話題がわかるように構成する
たとえば「キーワードの選び方」というよりも、「SEOに強いキーワードの選び方」のようにすると、検索エンジンと読者の両方に伝わりやすくなります。
無理に詰め込むと逆効果になることも
キーワードを多く使えばいいというものではありません。あまりに同じ言葉を繰り返し使いすぎると、検索エンジンから「不自然」と判断されてしまい、評価が下がってしまうこともあります。
また、読者にとっても読みづらくなり、内容が頭に入ってこなくなるため、過剰なキーワードの詰め込みは逆効果になります。
- 同じ言葉を何度も繰り返す
- 読みにくい文章にしてまでキーワードを入れる
- 文脈に合わないキーワードを無理やり差し込む
キーワードの使い方は「質」と「バランス」が大切です。
必要な場面で、自然に登場させる程度で十分に効果があります。
読者が快適に読める文章であることが、結果的にSEOにも良い影響を与えます。
読者の検索意図を想像しよう
SEOにおいて最も大切なのは、検索した人がどんな情報を求めているのかを想像することです。
ただキーワードを入れるだけではなく、その言葉の裏にある「意図」まで考えることが大切です。
検索意図には、次のような種類があります。
- 情報収集をしたい:「○○とは」「○○の意味」など
- 比較や検討をしたい:「○○ 比較」「○○ メリット デメリット」など
- 行動につなげたい:「○○ 申し込み」「○○ ダウンロード」など
キーワードを選ぶ際は、その言葉を検索した人がどんな状況で、何を知りたいのかを想像しながら記事の内容や構成を考えると、読者とのズレを防げます。
また、検索意図に合わせた構成にすると、読者がページ内をスムーズに読み進められるようになり、ユーザーエクスペリエンスの向上にもつながります。
検索意図を考えるヒント
- 検索結果に出てくる他の記事をざっと見る
- サジェスト(検索欄に表示される関連ワード)をチェックする
- 読者がどのような悩みや目的を持っているかを整理する
SEO対策の第一歩は、読者の気持ちに寄り添ったキーワード選びです。
単なる言葉として扱うのではなく、読者との接点として丁寧に考えることが、結果的に記事の価値を高めることにつながります。
コンテンツ制作時によくある失敗とその改善ポイント

誰に向けた記事かがあいまい
コンテンツ制作において最も多い失敗のひとつが、「誰に読んでほしいのか」が明確でないまま書き始めてしまうことです。
ターゲットがあいまいだと、内容がぼんやりしてしまい、誰にも刺さらない文章になってしまうことがあります。
読者像を具体的にするには、以下の点を意識すると効果的です。
- 年齢や職業、関心ごとなどをイメージする
- その人が抱えていそうな悩みや疑問を考える
- どんな情報を求めているのかを想像する
このように読者像(ペルソナ)を設定しておくと、文章のトーンや使う言葉、扱うテーマも自然に決まってきます。
たとえば「ホームページを作りたいけど何から始めればいいか分からない初心者」がターゲットなら、専門用語はなるべく使わず、やさしい表現で一歩ずつ説明していく必要があります。
文章が長すぎて途中で離脱される
長い文章は情報量が多くて良さそうに見えますが、読者が読み切る前に途中でページを閉じてしまう「離脱」の原因になることがあります。
離脱されにくくするための工夫
- 1段落を3〜4行以内におさえる
- 長文の中に見出しや箇条書きを適切に入れる
- スマホでも読みやすいレイアウトにする
とくにスマホで読むユーザーが多い現在では、見た目のスッキリ感が非常に大切です。
長い文を続けると視線の移動距離が増え、読み手が疲れてしまいます。
内容は大切ですが、伝えたいことをシンプルに分けて書くことで、読者の集中力を保つことができます。
また、ひとつの話題が長くなりすぎないように、適度に話題を区切ることで、理解もしやすくなります。
情報が古くなっていて信頼されない
Webの記事は、一度公開したら終わりではありません。
内容が古くなると、読者からの信頼を失うだけでなく、検索エンジンからの評価も下がる可能性があります。
よくある古い情報のまま放置されがちな部分
- 料金やサービスの内容
- 外部サイトのリンク先や引用元
- 表記している年数や数値
とくに技術やトレンドの変化が早いテーマでは、数か月で情報が古くなってしまうこともあります。
更新が必要かどうかをチェックする方法
- アクセス解析ツールで閲覧数が下がっていないかを確認する
- 他の検索結果と比較して内容が古くないか調べる
- 書いた時点から半年以上経っていないか確認する
情報の鮮度を保つためには、定期的な見直しと更新作業が不可欠です。
更新のタイミングで新しい事例やデータを加えると、より価値のある記事にすることもできます。
改善するにはどうすればいい?
制作後の改善を怠ると、せっかく書いた記事が読まれないまま終わってしまうこともあります。
記事は「育てるもの」と捉えることが大切です。
改善のために役立つチェックポイント
- アクセス解析で読まれている部分、読まれていない部分を確認する
- 離脱率が高い見出しや段落を見直す
- 問い合わせや資料請求などのアクションにつながっているかチェックする
- 類似キーワードや検索意図に応じて新しい内容を加える
改善に役立つ無料ツール
- Google アナリティクス:https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
- ヒートマップツール(たとえばUser Heatなど)
改善は一度で終わるものではなく、少しずつ修正と追加を繰り返していくことが重要です。
ときには、まったく別の視点からの見直しも必要になります。
ユーザーエクスペリエンスを意識しながら、読み手の満足度を上げていくことで、結果的に検索でも評価されやすくなります。見直しと改善は、地味ですがとても効果のある作業です。
外注か自社か?記事制作の依頼先を選ぶ際の比較と注意点

外注のメリットとデメリット
記事制作を外部に依頼する、いわゆる「外注」には多くのメリットがありますが、同時に注意すべきポイントもあります。
メリットとデメリットの両面を知っておくことで、依頼するかどうかの判断がしやすくなります。
外注の主なメリット
- 専門的な知識や技術を活かせる:Webライターや編集プロダクションは、SEOや構成に慣れている
- 社内の時間とリソースを節約できる:記事作成にかける手間を減らすことができる
- 納期や品質が安定しやすい:プロに依頼すれば、一定の品質とスケジュールが見込める
外注の主なデメリット
- 社内の意図や細かいニュアンスが伝わりにくい:企画の方向性がズレてしまう可能性がある
- コストがかかる:品質や経験値によって金額に差が出やすい
- 修正に時間がかかることがある:外部とのやりとりが必要なためスピード感が落ちる場合がある
外注する際は、「誰に依頼するか」「どこまで任せるか」「確認フローはどうするか」などをあらかじめ整理しておくと、スムーズに進めやすくなります。
自社で書く場合に気をつけること
社内で記事を作成する場合、コストは抑えられますが、そのぶん注意すべき点もあります。
特に記事作成に不慣れな場合や専任の担当者がいない場合には、クオリティのばらつきが出やすくなります。
自社で制作する際の注意点
- 専門用語の多用に注意する:読み手がわかる言葉を使うように意識する
- ユーザーエクスペリエンスを意識した構成を考える:自己満足な記事にならないように読者目線を持つ
- 執筆にかかる時間を見積もる:本来の業務に支障が出ないように調整する
- 社内レビュー体制を作る:誤字脱字や内容のズレを防ぐためにチェック工程を組み込む
自社で書くメリットとしては、商品やサービスについて詳しい人が文章を担当することで、より深い内容を盛り込めるという点があります。
ただし、それが読み手にとって分かりにくくならないよう、文章構成や見出しに配慮することが求められます。
どんな会社に依頼すればいいの?
外注先を選ぶときに重視したいのは、「自社に合ったパートナーであるかどうか」という視点です。
記事制作会社やWeb制作会社、個人ライターなど、依頼先はさまざまです。
- 編集プロダクション:企画から構成、執筆、校正まで一括対応してくれることが多い
- 個人のライター:費用を抑えやすく、柔軟に対応してもらいやすい
- Web制作会社やSEO支援会社:マーケティング視点を含めた提案が可能
信頼できるかどうかを見極めるには、過去の実績やサンプル記事、対応スピードなどもチェックすることが重要です。
また、初回からいきなり大きな案件を任せるのではなく、小さな案件でお互いの相性を確かめる方法もあります。
契約前に確認しておきたいポイント
外注に失敗しないためには、契約前のすり合わせが欠かせません。
トラブルを避けるためにも、書面や共有ドキュメントなどで細かく条件をまとめておくことが大切です。
契約前に確認したいポイント
- 記事の納品形式と文字数:Word形式かGoogleドキュメントか、画像の有無など
- 修正の回数と対応範囲:何回まで修正してもらえるか、料金が発生するラインはどこか
- SEOや構成の対応有無:キーワード選定や見出しの作成を任せられるかどうか
- 納期と連絡手段:スケジュールが無理のないものか、やりとりがスムーズか
見積もり段階でこれらの条件を共有し、合意しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、外注先とのやりとりをスムーズにするために、社内での担当者や確認体制を明確にしておくと、意思疎通もしやすくなります。
予算と品質のバランスをどう取るか
費用を抑えたい一方で、一定以上の品質を保ちたいという場面はよくあります。
その場合には、記事の目的と必要な品質レベルをあらかじめはっきりさせることがポイントです。
予算と品質のバランスを考えるときの視点
- 単価よりも「内容の質」が大事な場面:サービス紹介や専門知識を扱う記事など
- ボリュームを重視する場面:定期更新するブログや商品紹介記事など
- 一部だけ外注し、他は社内で対応:構成だけ外注して執筆は社内で行うなどの使い分け
また、外注費が限られている場合は、SEOや構成案の相談だけをお願いし、実際の執筆は自社で担当するというハイブリッド型の対応もおすすめです。
予算と品質はトレードオフになりがちですが、依頼内容を明確にすることと、長く付き合えるパートナーを見つけることが、コストを抑えつつ効果的な運用を行うコツになります。
費用だけで判断せず、「伝えたいことが読者にちゃんと届くか」を基準に外注先を選ぶことが大切です。
読者のニーズを捉えるペルソナ設計と企画の立て方

「誰に向けた記事か」をはっきりさせよう
記事を作成する際にまず重要なのは、「誰に向けて書くのか」を明確にすることです。
これがあいまいなままだと、伝えたいことがぼやけてしまい、読者の心に届きにくくなります。
記事のターゲットが明確であれば、言葉の使い方、伝え方、構成すべてが読み手に合わせたものになりやすく、共感されやすくなります。
特にWebでは必要な情報だけを短時間で知りたいというニーズが強いため、読み手の視点を持つことが非常に重要です。
ターゲットを絞るための基本的な考え方
- 読んでほしい人の年齢・性別・職業はどんなものか
- どんな悩みや課題を持っているか
- どのような情報を求めているのか
ターゲットが明確になると、文章のトーンや使う単語、書き方の選択も自然と決まりやすくなります。
ペルソナってなに?具体例で解説
ペルソナとは、「読者像を具体的に設定した人物モデル」のことです。ターゲットを「30代の主婦」といった大まかな設定にとどめるのではなく、まるで実在する人物のように細かくイメージする手法です。
ペルソナを設定することで、文章の内容や構成が読者に寄り添ったものになり、ユーザーエクスペリエンスの質が上がります。
ペルソナの例
- 名前:田中 美咲さん
- 年齢:34歳
- 職業:育休中の会社員
- 家族構成:夫と2歳の子ども
- 課題:時間が限られていて、効率よく情報を得たい
- 興味関心:子育てしながら在宅で始められる仕事を探している
- よく使うSNS:Instagram、YouTube
このように細かく想像しておくと、「どんな表現が響きやすいか」「どんな情報があれば助かるか」が自然に浮かび上がってきます。
ペルソナ設定で得られる効果
- 内容のブレを防げる
- 文章のトーンを統一しやすい
- 読者の立場に立った表現がしやすくなる
ペルソナは一度作って終わりではなく、記事の種類や目的に合わせて何パターンか持っておくと、企画の精度も上がります。
事前に調べておくと企画がスムーズに
思いつきだけで記事を書き始めると、途中で行き詰まってしまうことがあります。
事前の情報収集がしっかりできていると、企画も構成もスムーズに進みます。
企画前に調べておきたいこと
- 同じテーマで書かれた他の記事:検索上位にある記事を参考に構成を考える
- 関連キーワードや読者の疑問:検索サジェストやQ&Aサイトが役立つ
- ペルソナに関係しそうなSNSの投稿:XやInstagramのタグ検索を活用
調査した情報をノートやツールにまとめておくことで、記事作成に取りかかったときに迷いにくくなります。
また、同じテーマでも他サイトにはない切り口を見つけるヒントにもなります。
あらかじめ下調べをしておくと、ライターや編集者との認識のズレも少なくなり、記事の品質を安定させやすくなります。
丁寧な準備が、読みやすく、信頼される記事を作る基盤になります。
おすすめのツールで効率的に記事を作成する方法
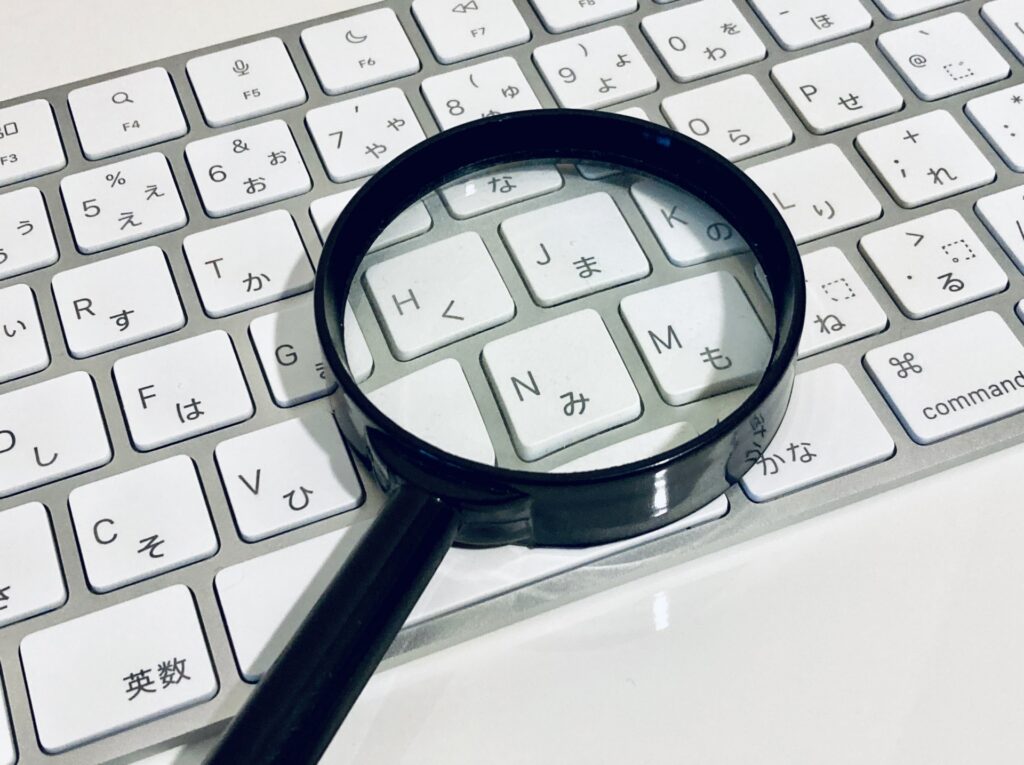
無料で使える便利なツール紹介
記事作成は、何もないところから始めると時間がかかりやすく、途中で手が止まってしまうこともあります。
そんなときに役立つのが、無料で使えるWebツールです。
ツールを使うことで、下調べや構成、書き出しがスムーズになり、作業の効率がぐっと上がります。
特に初心者でも使いやすく、記事制作の助けになるツールは以下の通りです。
- Googleドキュメント:https://docs.google.com
オンラインで使える文章作成ツール。自動保存されるので、データが消える心配がありません。共有やコメント機能もあるので、チームでの作業にも便利です。 - ラッコキーワード:https://related-keywords.com
検索キーワードを探すための無料ツール。ロングテールキーワードを見つけたいときに役立ちます。 - Canva:https://www.canva.com
アイキャッチ画像やグラフなど、記事に必要なビジュアル素材をかんたんに作成できます。テンプレートも豊富です。 - Notion:https://www.notion.so
記事の構成やメモ、進捗の管理に便利なノートツール。ライティング以外にも活用できます。
これらのツールは、登録も無料で手軽に使えるため、Webに不慣れな方でも安心して利用できます。
書いた文章のチェックツールとは?
文章を書いたあとに、誤字脱字や読みづらい部分を直す「チェック作業」も欠かせません。
チェック作業をサポートしてくれるツールを使えば、ミスを減らし、読みやすい文章に仕上げやすくなります。
文章チェックに役立つツール:
- Enno(https://enno.jp/):日本語の誤字脱字や表記の揺れをチェックしてくれる無料ツール
- 日本語校正サポート(https://www.japaneseproofreading.com/):文法チェックや、文章の難しさなどを確認可能
- Microsoft Word:スペルチェック機能が標準でついており、Word形式で納品する場合には特に便利
書いた文章はできれば時間をおいて読み返すこともおすすめです。
頭がリセットされた状態で読むことで、見落としていたミスに気づきやすくなります。
また、声に出して読むと、文のリズムや言葉のつながりの不自然さが見えやすくなります。
まとめ
コンテンツマーケティングの記事作成では、まず「誰に向けて書くか」を明確にすることがとても大切です。
その上で、読者の悩みや知りたいことを想像しながら、伝わりやすい構成と書き方を考えていきます。
見出しを使って読みやすくしたり、専門用語をやさしい言葉に言いかえたりする工夫も効果的です。
また、検索で見つけてもらうためにはキーワード選びも欠かせません。
記事を書いた後は、誤字や内容のズレがないかしっかり見直すことが信頼につながります。
さらに、記事を公開したあとも、定期的に情報を更新したり改善をくり返すことで、より読まれるコンテンツになります。
外部に依頼する場合は、目的や予算に合わせて信頼できる相手を選ぶことがポイントです。
自社で書くときも、ツールやテンプレートを活用すれば、無理なく続けることができます。
一つひとつの作業を丁寧に進めていけば、読み手にとって役立つ記事を作ることができます。
焦らず、少しずつ取り組んでいくことが大切です。




