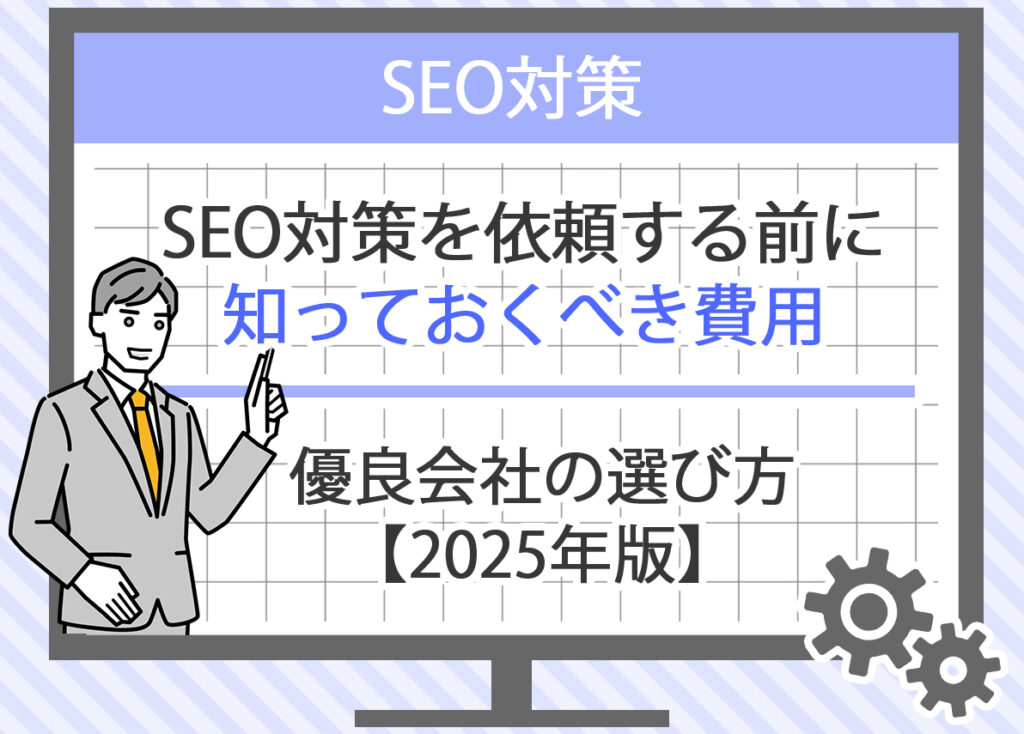
「ホームページを作ったのに全然アクセスが来ない…」「ネット検索で自社のサイトが出てこない…」そんなお悩みはありませんか?
それを解決する方法が「SEO対策」です。
とはいえ、「SEOって何?」「どこに頼めばいいの?」とわからないことだらけの方も多いはずです。
この記事では、SEO対策を専門の会社に依頼する際の流れや費用、選び方のポイントまで、初心者でも理解しやすいようにやさしく解説しています。
2025年の最新情報にも対応しているので、これからSEOを始めたい方や、外注を検討中の方にも役立つ内容です。
後悔しない依頼のために、まずは基本をしっかりおさえていきましょう。
SEOを外注するメリットとデメリットを解説

プロに任せることで得られるメリット
SEOの外注とは、検索結果で上位に表示されるようにするための対策を、専門の会社や業者に任せることです。
自分たちだけでは対応が難しい施策を、専門知識を持った人に任せられるため、さまざまなメリットがあります。
主なメリットは以下の通りです:
- 専門的な知識と経験がある
Google アナリティクスや検索エンジンのアルゴリズム、内部・外部対策など、SEOには複雑な要素が多くあります。外注先はそれらを理解し、的確な施策を実施できます。 - 最新の検索ルールに対応できる
Googleの検索アルゴリズムは頻繁に更新されます。
外注先はその変化を常にチェックし、最適な対策を提案してくれます。 - 社内の時間とリソースを節約できる
SEOは一度やれば終わりというものではなく、長期的に継続する作業が必要です。
これを社内で全てこなすのは負担が大きくなります。 - 客観的な視点から改善提案をもらえる
自社のサービスに慣れてしまうと見落としがちな問題にも、外部の目線から新しい気づきを与えてもらえます。 - コンテンツ制作やライティングも一括で任せられる
SEOに強い外注先では、検索されやすい記事(ロングテールキーワードなどを含む)をユーザーエクスペリエンスを考慮して構成・執筆してくれる場合もあります。
これらのメリットにより、SEOの専門性を社内で持たずとも、一定の効果を狙える点が外注の魅力です。
外注のデメリットとは?失敗を避けるために
一方で、SEOを外注する際には注意すべきデメリットも存在します。
特に、業者選びを間違えると費用が無駄になるだけでなく、逆にサイトの評価を落としてしまうリスクもあるため慎重さが求められます。
主なデメリットは以下の通りです:
- 社内に知識が蓄積されにくい
外注している間は、自社でSEOのノウハウが育ちにくいため、将来的に内製化を目指す場合には不利になることがあります。 - 成果が出るまで時間がかかる
SEOは即効性のある施策ではありません。
数ヶ月単位で見ていく必要があり、外注すればすぐ効果が出るというわけではありません。 - 契約内容が不透明なこともある
中には「成果が出る保証なし」としながらも、高額な契約を結ばせる業者も存在します。
契約前には作業内容・期間・成果物の範囲などを明確に確認することが重要です。 - 悪質な手法でペナルティを受けるリスク
質の低いリンクを大量に設置するなど、検索エンジンのガイドラインに反する手法で一時的な順位上昇を狙う業者もいます。
このような対策は長期的には逆効果です。
悪質なSEO業者を避けるためには、実績の提示、明確な提案内容、説明のわかりやすさなどを重視し、複数の業者を比較・検討することが大切です。
自社でやるより費用対効果が高い理由
外注はコストがかかる印象がありますが、場合によっては社内で運用するよりも費用対効果が高いケースもあります。
その理由は、成果を出すまでのスピードと精度が違うためです。
自社内でSEOを始めるには、以下の準備が必要です:
- 専門知識を持った人材の確保
- ツールの導入(Google アナリティクスや分析ツールなど)
- コンテンツ作成体制の構築
- 定期的な分析・改善の時間確保
これらをすべて用意するには時間も費用も大きくかかります。
特にWebに不慣れな会社では、方向性を誤ってしまい、かえって遠回りになる可能性も高くなります。
一方、実績のある外注先であれば、すでにノウハウとツールを持っており、最初から効率的な施策を展開できます。
その結果、少ない手間と早いスピードで集客の成果が見えやすくなるのです。
また、外注費用も月額10万円前後から成果報酬型まで幅広い料金プランが存在しているため、社内の人件費と比較しても割高とは限りません。
外注すべきか判断するためのチェックポイント
SEOの外注が向いているかどうかを見極めるには、以下のようなポイントをチェックしてみてください。
- Web担当者が1人しかいない、または兼任している
リソースが不足している場合、SEOを社内で回すのは困難になりがちです。 - SEOに詳しい人が社内にいない
基本的な知識がなければ、方向性を見失い、無駄な施策に時間を費やすことになりかねません。 - すでに広告などで集客しているがコストが高い
Web広告と比べてSEOは中長期的に費用を抑えられる施策です。
継続的な集客ルートを作りたいときにおすすめです。 - コンテンツの制作が追いつかない
記事作成や構成、ライティングまで任せたい場合は外注の方が適しています。 - 競合他社が上位に表示されている
検索結果で競合ばかりが目立つ場合、早めに対策しないと埋もれてしまう可能性があります。
このような状況に当てはまる場合、信頼できる外注先を見つけることが課題解決の近道となります。
比較サイトなどを活用して、複数社の提案を受けてみるのも良いでしょう。
SEO会社へ依頼する際の流れと準備しておくこと

依頼前に整理すべき「目的」と「目標」
SEO対策を会社に依頼する際に、最初に整理しておきたいのが「目的」と「目標」です。
これがあいまいだと、相手から最適な提案を受けられず、作業の方向性がずれてしまう可能性があります。
「目的」と「目標」は次のように分けて考えます:
- 目的:なぜSEOをやりたいのか(アクセスを増やしたい、問い合わせ数を増やしたいなど)
- 目標:どのくらいの結果を目指すのか(毎月の訪問者数1.5倍、資料請求数20件/月など)
たとえば、「サイトへのアクセスが少ない」という課題があれば、「月1,000人の訪問者を目指す」といった目標設定が有効です。
このように、目的は大きな方向性、目標は具体的な数値で設定することがポイントです。
また、目標はGoogle アナリティクスなどのツールで定量的に測定できるものを選びましょう。
設定した目標が明確であればあるほど、外注先も提案しやすくなり、施策がブレにくくなります。
打ち合わせ前に準備しておきたい情報
打ち合わせの前に、以下の情報を社内で整理しておくと、相談がスムーズに進み、具体的な提案を受けやすくなります。
- 現在のサイトURLや構成:ホームページのアドレスと、どんなページがあるかの一覧。
- 更新の頻度や体制:更新を担当している人が社内にいるか、外部に任せているか。
- 過去の対策歴:これまでにSEO対策やWeb広告など、どんな集客を行ってきたか。
- 狙いたいキーワード:どういった言葉で検索されたときに自社サイトが出てきてほしいか。
- 現在の課題:問い合わせが少ない、検索順位が上がらない、などの困りごと。
これらの情報があるだけで、SEO会社は施策の方向性や費用感をより具体的に伝えることができます。
また、CMS(WordPressなど)を使っている場合はその情報も伝えておきましょう。
どのツールでサイトを管理しているかによって、対策方法や必要な作業が異なるからです。
どんな資料があるとスムーズ?
SEO会社に依頼する際は、「資料」として準備しておくとやり取りが円滑になるものがいくつかあります。
- 現状のアクセスデータ
Google アナリティクスやサーチコンソールのデータ。
ない場合は「導入したい」という意向だけでもOKです。 - 過去に発注したWeb制作会社の仕様書やレポート
これまでの施策やサイトの構成が分かる資料があると便利です。 - 自社の強み・サービス内容がわかるパンフレットや営業資料
SEO会社はこれを見て、どのキーワードでアプローチすべきか判断しやすくなります。 - 競合サイトの情報
検索でよく見かけるライバル会社があれば、それも共有しておきましょう。
資料が揃っていない場合でも、最低限「現在のホームページのURL」と「やりたいこと」があればスタートできます。
また、紙ではなくPDFやスプレッドシートなどの形式で渡せると、やり取りがスムーズです。
初回相談でよく聞かれる内容とは
初回の相談では、SEO会社からいくつかの質問がされることがほとんどです。
準備しておくことで回答に困らず、スムーズに進行できます。
- 自社の事業内容と提供している商品・サービスは何か
- どんなユーザーに自社のサイトを見てもらいたいか
- 現在のWebサイトの課題や悩みは何か
- SEO以外に実施している集客施策があるか(Web広告、SNS、紙媒体など)
- 目指したいキーワードはあるか
- 社内に更新や修正作業を行えるスタッフがいるか
- SEO対策にかけられる予算の目安
これらの質問は、すべてどのような施策が最適かを判断するための材料になります。
正直に現状を伝えることが、良い提案を受けるための近道です。
また、「まだよくわかっていない」「予算は未定」などの状況でも、そのまま伝えて問題ありません。
信頼できる会社であれば、無理に高額な提案をすることはありません。
依頼先を選ぶポイントとは?信頼できる業者の特徴

信頼できるSEO会社の見分け方
SEOを外注する際に最も重要なのが信頼できる業者かどうかの見極めです。
見た目のよさや価格だけで判断すると、あとから「思っていた内容と違った」と後悔することにもつながります。
信頼できる会社かどうかを見極めるポイントは次のような点です。
- 実際の施策内容を丁寧に説明してくれる
専門用語を使わずに、内容や流れをわかりやすく説明してくれる業者は信頼しやすいです。 - 「すぐに上位表示できます」など、極端なことを言わない
SEOは長期的な取り組みです。すぐに結果が出ると強調する業者は注意が必要です。 - 継続的な改善提案をしてくれる
一度対策して終わりではなく、継続的にレポートを出し、改善を繰り返す体制があるかを確認しましょう。 - 透明性がある
「何を、いつ、どのようにやるか」をきちんと説明し、レポートで確認できる体制があることが重要です。 - 契約内容が明確で柔軟
途中解約が可能か、月額費用の内訳が明確かなども確認しましょう。
初回の打ち合わせ時の受け答えや資料の作り方、説明の丁寧さなどが信頼性のバロメーターになります。
実績があるかどうかのチェック方法
SEO会社の信頼性を測るうえで、過去の実績をどのように公開しているかは重要な判断材料になります。
ただし、実績の見せ方や表現方法には違いがあるため、内容をしっかり確認する必要があります。
実績のチェックポイントは以下の通りです。
- 事例紹介があるか
どんな業種のクライアントと取り組んできたかがわかるかどうか。
多業種での実績がある会社は応用力が期待できます。 - 数値の改善内容を示しているか
アクセス数や問い合わせ数など、施策によってどんな変化があったかを具体的に示しているかを見ましょう。 - 第三者メディアや公的資料に掲載されたことがあるか
メディア掲載やコンテスト受賞歴などがあれば、社外からの評価を得ている証拠になります。 - クライアントの声があるか
実名でコメントが掲載されている場合、実際の評価がより信頼できる情報として参考になります。
単に「実績多数」と書いてあるだけではなく、具体的な数値や施策内容がセットで紹介されているかをチェックしましょう。
提案内容で見る「プロらしさ」
見積もりと一緒に出される提案資料は、その業者がどれだけ自社のことを理解しているか、どの程度SEOに精通しているかを確認する重要な材料です。
プロらしい提案かどうかを見分けるポイントには次のようなものがあります。
- 自社の課題に合わせた内容になっている
テンプレートのような内容ではなく、自社のサイトの特徴や悩みに応じた施策が書かれているかを確認します。 - キーワードの選定根拠がある
狙うべきキーワードについて、ビッグキーワードやロングテールキーワードをどう組み合わせて対策するかの考えが示されているか。 - ユーザーエクスペリエンスを重視した施策が含まれている
コンテンツの充実やサイトの使いやすさを含む提案がされていれば、ユーザー目線の施策を重視している証拠です。 - 検索エンジンのガイドラインに則った内容である
Googleの公式ガイドラインに反していないこと、不自然なリンク購入などの提案がないこともチェックポイントです。
表面上の資料のきれいさよりも、「中身に納得感があるか」「信頼性のある根拠があるか」を重視してください。
契約前に確認したい5つのこと
契約を結ぶ前には、あとでトラブルにならないように、以下のような内容をしっかり確認しておくことが大切です。
- 契約期間の縛り
契約が1年など長期固定でないか、途中解約ができるかを確認しましょう。 - レポート提出の頻度と内容
何をどのくらいの頻度で報告してくれるのか。
順位だけでなくアクセス数やコンバージョンの変化も含まれているかをチェックします。 - 作業内容の具体性
SEO対策の「内容」があいまいでないか、タイトルや見出しの修正、内部リンクの設置など具体的に記載があるか確認します。 - 費用に含まれる範囲
初期費用・月額費用・成果報酬など、見積もりの内訳が明記されているかをチェックしましょう。 - 修正依頼や質問への対応体制
質問への対応が早いか、社内担当者が相談しやすい体制になっているかも重要です。
契約は一度結ぶと簡単に変更できないため、不明な点や気になる部分は、遠慮なく質問してクリアにするようにしてください。
SEO対策会社の費用相場と見積もりの考え方

SEOにかかる費用はどのくらい?
SEOの外注を検討するとき、最初に気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか」という点です。
SEO対策の費用は、会社や施策の内容によって大きく異なりますが、おおよその相場感を知っておくことが重要です。
主な価格帯は次のように分かれています。
- 月額5万円〜10万円
中小企業向けの基本的な対策が中心。
キーワード選定、内部対策のアドバイス、月1回のレポートなどが含まれることが多い。 - 月額10万円〜30万円
中規模〜大規模サイト向け。コンテンツの設計や記事制作、リンク構築など幅広い施策が組み込まれる。 - 月額30万円以上
競合の多い業界や全国展開を狙うケースに多く、綿密な分析と戦略的な対策が含まれる。
単発での施策(サイトの初期SEO設計など)では、30万円〜50万円程度の一括料金になることもあります。
記事制作代行やアクセス解析、コンテンツリライトなどを含む場合、オプションとして追加費用が発生することもあります。
費用はあくまで「サービスの中身」によって変動するため、金額の大小だけで判断せず、何が含まれているかを必ず確認するようにしましょう。
安すぎる会社には注意が必要
SEO対策の中には、相場と比べて極端に安い価格設定をしている会社も存在します。
一見するとコストを抑えられてお得に感じられますが、注意しないとむしろ損をする可能性があります。
価格が安すぎる場合にありがちなリスクは以下のとおりです。
- 作業内容が不明確
何をしてくれるのかが曖昧で、成果が出ないまま契約だけ続く。 - 自動ツールでの対策のみ
人の手による分析や改善提案がないため、サイトの本質的な改善にはつながらない。 - ブラックハットSEOの使用
ガイドラインに反した対策を行い、検索順位が一時的に上がっても後にペナルティを受けて順位が落ちるリスクがある。 - 実績やレポートがない
何の成果も見えないまま契約期間が終了してしまうことも。
安さだけに飛びつくと、費用対効果が悪くなるだけでなく、長期的には「信頼性のあるSEO会社に依頼し直すコスト」が追加でかかることにもなりかねません。
SEOは短期的な施策ではなく、継続的な運用と改善を前提とした取り組みです。
そのため、価格とサービス内容のバランスがとれた業者を選ぶことが大切です。
月額制・成果報酬制の違いとは
SEOサービスの費用体系には主に「月額制」と「成果報酬制」の2つがあります。
それぞれにメリットと注意点があるため、自社の目的や状況に合った選択が必要です。
月額制の特徴
- 毎月決まった金額を支払う形式
- サービス内容があらかじめ決まっており、継続的なサポートが受けられる
- アクセス解析や改善提案、レポート提出が含まれている場合が多い
- 長期的な施策向けで、安定した運用と戦略設計に適している
成果報酬制の特徴
- 「特定のキーワードで上位に入ったら支払い発生」など、結果に応じた報酬を支払う仕組み
- 初期コストを抑えられる場合があるが、条件や成果の定義が不明確なことがある
- 一部のキーワードだけに偏った施策になる可能性がある
- ロングテールキーワードでは成果対象外になることもあるため、注意が必要
費用だけでなく、自社のリソースや目標に合わせて「どちらが合っているか」を見極めることがポイントです。
見積書でチェックするべきポイント
SEO会社から見積書をもらった際には、金額の大小だけでなく、「何にどのくらいの費用がかかるのか」をきちんと確認する必要があります。
見積書で確認すべきポイントは次の通りです。
- 施策ごとの作業内容が記載されているか
ページタイトルの修正、構成案の提出、内部リンクの調整など、具体的な作業が書かれているかを確認します。 - キーワード選定やコンテンツ制作の範囲
対象となるキーワード数や、月何本の記事を制作するかなど、作業範囲を明確にすることで後のトラブルを防げます。 - 成果レポートの頻度と内容
順位の変化だけでなく、アクセス数、問い合わせ数など、施策の効果をどう可視化するかが重要です。 - オプション費用の有無
コンテンツ追加、サイト修正などが月額費用に含まれるのか、それとも別料金なのかも必ずチェックしましょう。 - 契約期間と解約条件
最低契約期間や途中解約の可否について明記があるかも重要です。
不明点があればその場で質問し、納得してから契約することが後悔を避けるコツです。
価格だけでなく、サービスの質と対応の丁寧さにも目を向けましょう。
SEO施策の主な内容と成果が出るまでの期間

SEO施策にはどんな種類がある?
SEO対策にはさまざまな方法がありますが、基本的には検索エンジンに「このページは役立つ情報だ」と伝えるための工夫のことを指します。
施策は大きく分けて、サイト内部の対策(内部施策)と外部からの評価を高めるための対策(外部施策)に分類されます。
主なSEO施策の種類
- 内部施策:サイト内の構成や情報の書き方を見直すことで、検索エンジンが内容を正しく理解しやすくする施策。
- 外部施策:他のサイトから自分のサイトへのリンクを増やすなど、外からの信頼性を高める施策。
- コンテンツSEO:検索ユーザーが求める情報を分かりやすく伝えるための記事やページを作成すること。
- テクニカルSEO:表示スピードの改善やモバイル対応、サイト構造の最適化など、サイト全体の使いやすさや見え方に関する改善。
どの施策も単独では不十分で、複数の施策を組み合わせて行うことが基本です。
検索エンジンは、ページの内容だけでなく、その使いやすさや信頼性、他サイトからの評価などを総合的に判断して表示順位を決めています。
コンテンツ作成・リンク対策とは?
SEO施策の中でもとくに重要とされるのが、コンテンツ作成とリンク対策です。
コンテンツ作成は、検索されやすいテーマに基づいたページや記事を作り、検索ユーザーの悩みや疑問をわかりやすく解決する内容にすることが目的です。
よく使われるコンテンツSEOのポイント
- ロングテールキーワードを活用して細かなニーズに対応する
- ユーザーエクスペリエンスを意識し、見やすく、読みやすい構成にする
- 信頼性のあるデータや実例を盛り込むことで説得力を高める
一方のリンク対策は、他の信頼性の高いサイトから、自分のサイトへリンクを貼ってもらうことです。
これにより、検索エンジンから「評価されているページ」として認識されやすくなります。
リンク対策で注意すべきこと
- 自然なかたちでリンクを得ることが重要
- 無理にリンクを購入するような手法(いわゆるブラックハットSEO)は、Googleのガイドライン違反にあたる
- コンテンツの質が高ければ、自然と他のサイトに紹介される可能性も高まる
リンクは「外からの推薦状」のようなものと考えられており、コンテンツの信頼性を裏付ける材料として重要な役割を果たします。
結果が出るまでの目安期間
SEOは即効性のある対策ではなく、施策をしてから成果が出るまでには一定の時間がかかります。
これは、検索エンジン側の評価や、コンテンツがインデックスされるまでの処理に時間がかかるためです。
成果が出るまでの目安
- 内部施策のみの場合:2〜3ヶ月程度で順位の変化が見られるケースもある
- コンテンツを新規で追加した場合:3ヶ月〜半年でアクセス増加が見られることが多い
- 競合が多いビッグキーワードを狙う場合:6ヶ月以上かかる場合がほとんど
対策を始めてすぐに結果が見えないと不安に感じることもありますが、SEOは「じっくり育てるもの」と考える必要があります。
また、更新頻度や対策の質、競合状況などによっても変動するため、あくまで目安として捉えておくことが重要です。
効果が出るかを判断する方法
SEOの効果が出ているかどうかを判断するには、アクセス数や検索順位など、いくつかの指標を組み合わせて見ていく必要があります。
感覚や印象だけではなく、データをもとに判断することが大切です。
効果測定で見るべき指標
- 検索順位の変化:狙っているキーワードでの順位が上がっているか
- アクセス数の増加:Google アナリティクスなどで訪問者数が増えているか
- コンバージョン数:問い合わせ、資料請求、購入などのアクションが増えているか
- ページの滞在時間や直帰率:ユーザーがページ内の情報をしっかり読んでいるかどうかの判断材料になる
SEO会社に外注している場合、月に1回程度のレポートでこれらの情報を確認できることが多いです。
また、コンテンツSEOの場合は、「よく読まれているページ」「検索されているキーワード」などをもとに、今後の改善方針も立てやすくなります。
見える成果だけでなく、改善の余地があるか、次にどんな手を打てばいいかという視点も含めて評価することで、SEO施策の精度を高めることができます。
「効果が出ない」と感じたときの見直し方法
SEO対策は数ヶ月〜半年かかる施策が多いため、すぐに結果が出ないこと自体は異常ではありません。
しかし、「何も変わらない」「改善が見えない」と感じる場合は、以下のような見直しが必要です。
見直しのための行動
- 月ごとの順位やアクセス推移を再確認
本当に変化がないのかをデータで確認する - 想定ターゲットとキーワードがズレていないか
検索意図とコンテンツ内容のギャップがないかを見直す - 施策の優先順位が適切か
テクニカルな改善ばかりに偏っていないか、コンテンツが薄くないかを見極める - 内部と外部の対策バランス
内部リンクやコンテンツばかりに偏りすぎていないか、外部評価の獲得もできているか - 業者に相談しやすい環境か
「今のままで問題ないのか?」と質問したときに、納得できる回答があるかどうか
SEOは長期施策ではありますが、少なくとも3ヶ月前後で小さな変化(順位の改善、クリック数の微増など)は現れ始めることが一般的です。
その兆しすらない場合は、業者の方針そのものを見直すことも検討すべきです。
自社運用と外注の比較|どちらが最適か?
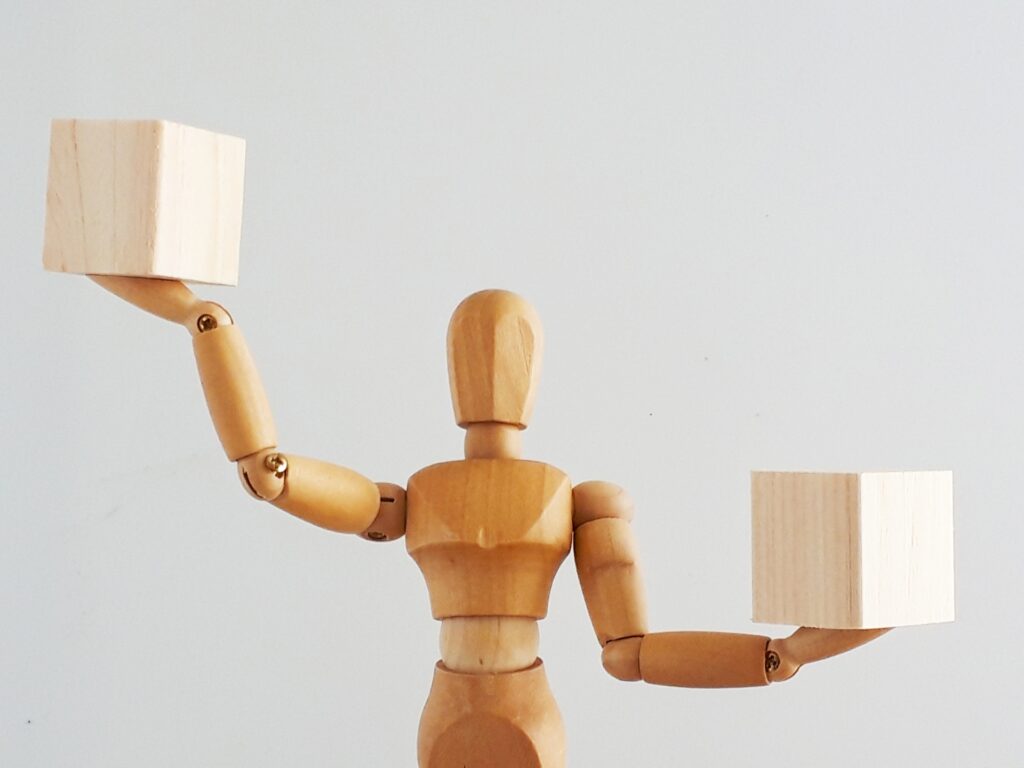
自社でやる場合に必要なスキルとリソース
SEOを自社内で運用する場合、費用を抑えられる反面、知識や人手が必要になります。
とくに、継続的な対応と情報のアップデートを欠かさない体制が求められます。
必要なスキルとリソースの例
- SEOに関する基本知識
検索エンジンの仕組みや評価基準を理解している - キーワード調査力
ビッグキーワードやロングテールキーワードを選定し、検索意図に合った記事作成を行える - ライティングと構成力
わかりやすく、読みやすく、ユーザーエクスペリエンスを意識した文章が書ける - Google アナリティクスやサーチコンソールの操作スキル
アクセス数や検索順位を分析できる - HTMLやCMSの編集スキル
サイトの構造を調整したり、内部リンクを設置できる - 更新の時間と人的リソース
月数本の記事更新やレポートのチェックなど、継続的な作業を担う人材と時間が必要
これらが社内に整っていないと、SEO対策を継続的に行うのは難しくなります。
また、担当者が1人に偏ると、他業務との兼任によって施策が後回しになることもあります。
まとめ
SEO対策を外注するか、自社で対応するかを考えるとき、まず大切なのは「自社の目的や体制に合っているか」をしっかり見極めることです。
ただ安いから、早く効果が出ると聞いたからという理由だけで業者を選ぶと、思ったような成果が出なかったり、費用が無駄になったりすることがあります。
信頼できる業者は、専門用語を使わずに丁寧に説明してくれることが多く、作業内容や費用についてもしっかり情報を開示してくれます。
逆に、「すぐに上がります」といった根拠のない話や、契約期間が極端に長い提案をしてくる会社には注意が必要です。
外注する場合でも、自社である程度の理解やチェックができると、施策の内容や効果を判断しやすくなります。
そのためには、基本的な知識を少しずつでも身につけることがとても重要です。
SEOは一度やれば終わりではなく、検索される内容や競合状況の変化に合わせて、地道に改善を続けていく作業です。
焦らず、わからないことは確認しながら、信頼できるパートナーと二人三脚で進めていくことが、よい結果につながるポイントです。




